

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「彼/彼女たちはなぜ書くのか?」(編集者 松岡 弘城)
2024年10月09日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「彼/彼女たちはなぜ書くのか?」(編集者 松岡 弘城)
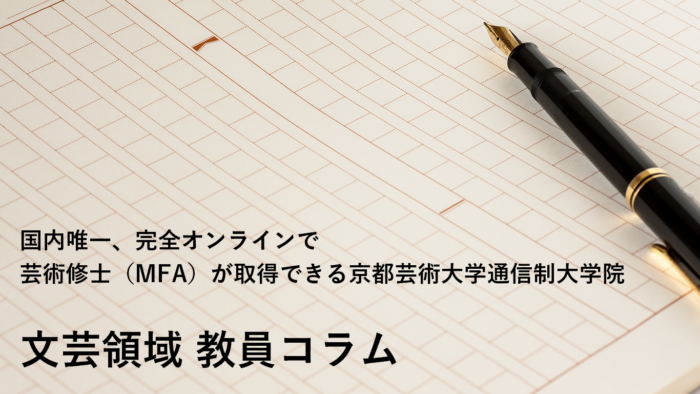
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は編集者松岡 弘城さんのコラムをご紹介します。

【松岡 弘城】(まつおか ひろき)
1991年、京都大学法学部卒業、日本経済新聞社に入社。新聞記者として勤務。文化部で書評欄の運営、作家の取材、連載小説の編集作業に携わる。2005年に退職。出版社勤務を経て、現在はフリーランスで小説の編集やコラム執筆を手がけている。2006年から朝日カルチャーセンターで創作教室の講師(現任)。
京都芸術大学大学院文芸領域・小説ゼミ2副担当。
「彼/彼女たちはなぜ書くのか?」
八月に開催された前期の「各ゼミ成果発表会」について、プログラムを振り返るところから始めてみましょう。
本学の文芸領域には、「小説ゼミ1」「小説ゼミ2」「クリティカル・ライティングゼミ」と、三つのゼミがございます。前期と後期、年に二度の「各ゼミ成果発表会」では、例えば、今回のM1(修士一年次)なら、各ゼミから四人の学生が発表者として立ち、自身の前期課題を対象にプレゼンテーションします。続いて、主に自分が属していないゼミの先生方から、コメントが寄せられます。各ゼミに一講時(八十分)が割り振られていますので、一人あたりの持ち時間は十五分ちょっと。このやりとりがめっぽう面白いのです。
ひとつには、真剣勝負の場ならではの緊張感があるせいでしょう。各ゼミは、小説ゼミ1が純文学系、小説ゼミ2がエンターテインメント系、クリティカル・ライティングゼミが編集・制作系と色分けされていますが、この日は、言わば〝異種格闘技〟編です。各ゼミの講師が顔を揃えるのも、この発表会だけ。書き手当人も気づかなかったような、意外性に富んだ意見が飛び出してきます。日頃、言葉を扱うプロによる批評ですから、何より言葉のひとつひとつに重みがある。私自身も勉強になります。
「ここはこうしたほうがいいんじゃないか」「ここはチャームポイントだから、もっと書いていい」等、ベクトルが常に作品と書き手を育てる方に向かっているので、発表者にとっても、針のむしろに立つような気にはならないでしょう。オンラインなので、演台がないのもプラスに働くのかもしれません。
藤野先生は、発表会の場で「小説について語り合うのは本当に楽しい」とおっしゃいました。それは、各人の作品が潜在的な可能性をおおいに秘めているせいでしょう。しかも、驚くべきは、一年次であれば、ほとんどの発表者が、初めて書いた小説であり、批評文であり、レポートだったという点です。発表会は、学生も講師も、新たな書き手、新たな作品と出会う場所として機能しているのです。
もうひとつの愉しみは、書き手自身によるプレゼンテーションです。形式は問いません――レジュメやパワーポイントの資料を用意する発表者もいれば、とつとつと語る人もいます。なぜ、この作品が生まれたのか? 書き手の人となりと、どうつながっているのか? ゼミ外では、恐らく初めて明かされる初期衝動は、発表会の最大の魅力と呼んでもいいかもしれません。アイデア、ほんのひとかけらの思い付きや気づき、時にメッセージが、どういうプロセスで物語として立ち現われたのか、本人の口から語られるのですから。
こうした印象には長い長い伏線があります。私と小説とのかかわりが激変したのは、新聞記者時代、念願の文化部への異動が叶い、文芸を担当するよう命じられてからでした。文化部と他の部署の仕事で異なるのは、作家に原稿を依頼して、受け取る編集者の職能がある点で、それが今日に至る原点とも言えるのですが、そこは端折ります。
当時、インタビュー記事を書くのは得意なほうだと思っていました。例えば、ある作家の新刊が出たので、インタビューに行く。文壇のいわゆる大御所クラスは編集委員やベテラン記者が担当していて、駆け出しはもっぱら若手の作家に相対します。礼儀として、当該作品以前に書かれた小説にも可能な限り目を通すのは当たり前ですが、ほとんどが初対面のインタビューはこちらも緊張するし、作家も慣れていないケースが多い。何件か仕事をこなしていくうちに、ある不文律に気づきました。作家に訊いてはいけない質問がある。
「あなたは、この作品にどういうメッセージを込めましたか?」
数百枚、時に千枚を超えるような新作を、一年間、あるいは何年もかけて書き上げた、それがほんの一言で表現できるわけはないし、答はすべて作品の中にある。笑い話で、「そんなアホなこと訊くんやない!」と作家から面罵された覚えもありませんが、夢で冷や汗をかいたりします。ましてや、「あなたはなぜ、小説を書くんですか?」なんて、「私の履歴書」クラスの長期連載でもなければ、聞くのもはばかられる/おこがましい問いでしょう。
それでも、さらに年を重ねた今では、意見を異にするようになりました。「あなたはなぜ?」と訊くべきではなかったか、と。
「どれも一次も通らず、書くのをやめてしまいました。というのも、大阪文学学校で知り合った人たちの中には、小説を書くことで何とか生き延びているような人がいて。その人たちを見ていると、自分の不純さに気づいてしまったんです。自分は誰かにすごいなって褒められたくて、自分を大きくみせるために小説を書いてるんじゃないかなって。そんな奴に小説を書く才能があるわけないって思いました。新人賞の落選がダメ押しになって、そこから学校に通うのもやめ、4年間なにも書きませんでした」
(HP「好書好日」掲載の、太宰賞受賞作家・市街地ギャオ氏のインタビューより)
この若き作家は、四年後、三十歳にして、小説を「ただ書きたい」という境地に至ったと明かしています。
皆様には、この初期騒動を是非、大切にしてほしい。本学はそれを育てて物語にするツールを用意して、お待ちしております。
——————————————————
説明会情報
【2024年10月16日(水)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(1) 小説ゼミ編(第一部)
「普遍的な物語を書くために――物語の「技術」を学ぶ場――」
たとえ紙媒体が衰退し、本が読まれなくなっても、「物語」なるものは人類にとって普遍的な価値をもち、きっといつの時代にも、ひとびとのこころを惹きつける何かであり続けます。
“いつか自分の手で、自分にしか書けない「物語」を書いてみたい。けれど、何をどうすればよいのかわからない”。
こうした思いが、「自分にも書ける」という確信に変わる場が、この大学院文芸領域にはあります。「物語」創作の最前線について、そしてその明るい展望について、以下の登壇者がお伝えします。
登壇者一覧)
■小説ゼミ2(主としてエンタテインメント小説ジャンル)指導担当者
*松岡弘城(編集者)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*藍銅ツバメ(作家)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月7日(木)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)
「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」
この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。
しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。
気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。
登壇者一覧)
■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者
*池田雄一(文芸評論家)
*藤野可織(作家)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月20日(水)19:00~20:30】
芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編
「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」
ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。
エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。
登壇者一覧)
■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者
*田中尚史(編集者)
*野上千夏(編集者)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
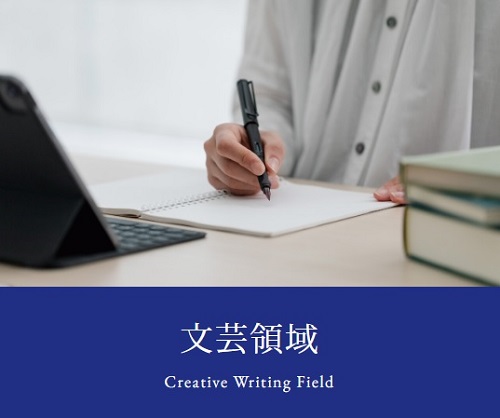
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事
-
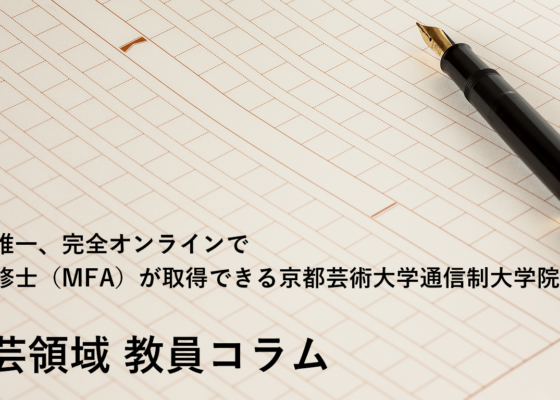
通信制大学院
2024年10月07日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「うそでありうそでなく、苦しくて楽しいほんとうの」(作家・編集者 岡 英里奈)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家、編集者の岡 英里奈さんのコラムをご紹介し…
-
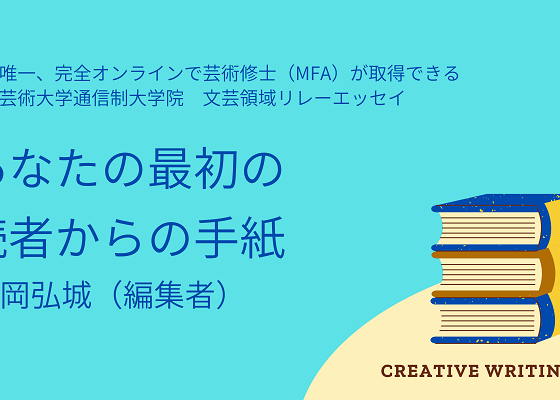
通信制大学院
2022年08月22日
【通信制大学院】あなたの最初の読者からの手紙(編集者・松岡弘城)―文芸領域リレーエッセイ②
2023年度に新設する文芸領域への入学を検討する「作家志望者」「制作志望者」へのエールとして、作家、編集者、評論家の方がリレーエッセイとしてお届けします。 今回…
-

通信制大学院
2022年10月16日
【通信制大学院】小説を書く理由とは?―文芸領域イベントレポート
2023年に開設する通信制大学院文芸領域では「創作現場のリアル」と題して、藤野可織先生、池田雄一先生、辻井南青紀先生が登壇し、小説の過去を振り返り…






























