

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読まれる恐怖の先にあるもの」(作家 藍銅ツバメ)
2024年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読まれる恐怖の先にあるもの」(作家 藍銅ツバメ)
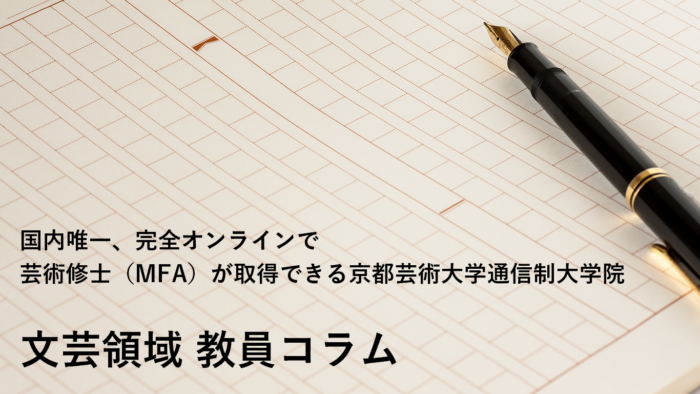
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は作家の藍銅ツバメさんのコラムをご紹介します。

【藍銅ツバメ】
1995年、大阪生まれ。徳島大学人間文化学科卒業。『鯉姫婚姻譚』で日本ファンタジーノベル大賞2021大賞受賞。近作に「Niraya」(小説すばる2022年4月号掲載)、「春荒襖絡繰」(小説新潮6月号掲載)、『鯉姫婚姻譚』(新潮社)、「青蝋百物語」(小説新潮12月号掲載)「ぬっぺっぽうに愛をこめて」(NOVA2023年夏号収録)、連載「馬鹿化かし」など(小説すばる2024年2月号から10月号まで掲載)。京都芸術大学通信制大学院文芸領域・非常勤講師。
「読まれる恐怖の先にあるもの」
自分の書いた文章を人に見せるというのはとても勇気のいることです。少なくとも私にとってはそうでした。始めは近しい友人や母親くらいにしか見せず、次に気の合う職場の同僚に見せ、やがて小説の講座に通って多くの知り合いに読んでもらうようになりました。そうして褒めてもらったり、こうした方が良いと助言を貰ったり、まったくダメだと酷評されたりします。そのたびに喜んだり、助言通りに修正するか決めたり、落ち込んだりします。その繰り返しでした。
今では作家として活動し、本を出したり連載をしたりしています。そうして顔も知らない人々が、私の書いた小説を読んでいます。それを思うと嬉しい反面、未だに恐ろしい気持ちになります。自分の書いた文章は自分だけのものだと、閉じ込めて独り占めしてしまいたい気持ちが今でもあるのです。とはいえ、見せないと何も始まりません。少しでも分かってほしいなら、面白いと思ってほしいなら読んでもらわないといけません。自分をさらけ出す恐怖を乗り越えた先に、読んでもらえる喜びがあります。
この京都芸術大学大学院の非常勤講師としてゼミの生徒の皆さんが書いた作品を読むようになり、書くこと、読まれることについて更に強く意識するようになりました。思い付き、書き始め、書き終わり、読んでもらうために提出する。それはとても凄いことです。一作品読み終わるごとに、その労苦を思って感動します。どの作品も個性があり、かならず際立って良い所があります。冒頭はもっとこうした方が良い、設定のここが矛盾している、と講師としてアドバイスすることもありますが、それができるのも作品を見せてもらえたからです。自分の心を込めた作品を人に見せるのは怖いことですが、その先に必ず発展するものがあります。
作家を目指すうえでまず大事なことは、書き始めること、人に見せるということだと思います。それは簡単なようで恐ろしく、それでいてやってみればあっけなく道が開けたりするのかもしれない。今の時代、人目に触れさせるのは難しくありません。インターネットで発表する、賞に応募する、同人誌の形にして頒布するなど、方法はいくらでもあります。紙に印刷して知り合いに配るというのでも構いません。もちろん、講師に見せるというのでもいい。本大学文芸領域の講師陣は皆、自分の文章を読まれるということについて考えてきた人のはずですから、真摯な答えを返してくれるでしょう。ぜひ、各々ができる方法で一歩踏み出してください。
——————————————————
説明会情報
【2024年11月7日(木)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)
「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」
この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。
しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。
気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。
登壇者一覧)
■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者
*池田雄一(文芸評論家)
*藤野可織(作家)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月20日(水)19:00~20:30】
芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編
「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」
ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。
エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。
登壇者一覧)
■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者
*田中尚史(編集者)
*野上千夏(編集者)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
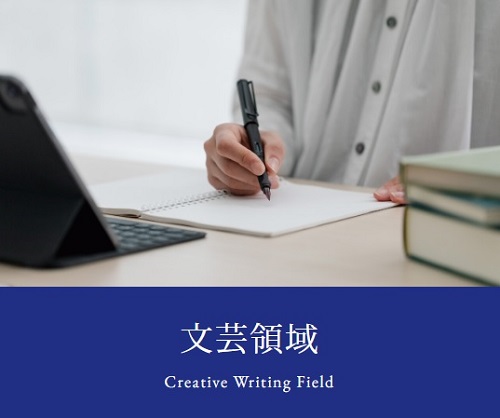
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事
-
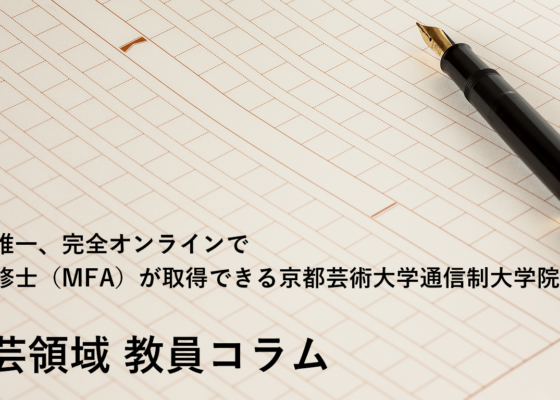
通信制大学院
2024年10月07日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「うそでありうそでなく、苦しくて楽しいほんとうの」(作家・編集者 岡 英里奈)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家、編集者の岡 英里奈さんのコラムをご紹介し…
- 記事がありませんでした
-
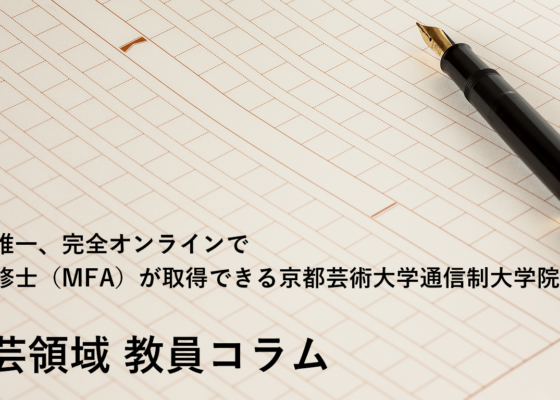
通信制大学院
2024年10月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「私が書いて私を知る」(作家 佐藤 述人)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家佐藤 述人さんのコラムをご紹介します。 【…






























