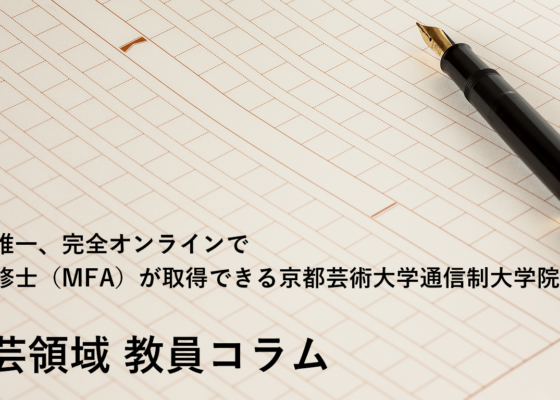通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読み手——書き手にとって不可欠なもの」(文学研究者 久村亮介)
2024年11月06日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読み手——書き手にとって不可欠なもの」(文学研究者 久村亮介)
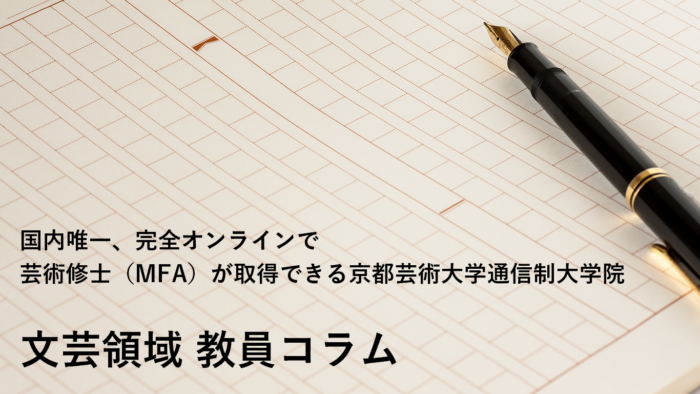
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は文学研究者の久村亮介さんのコラムをご紹介します。
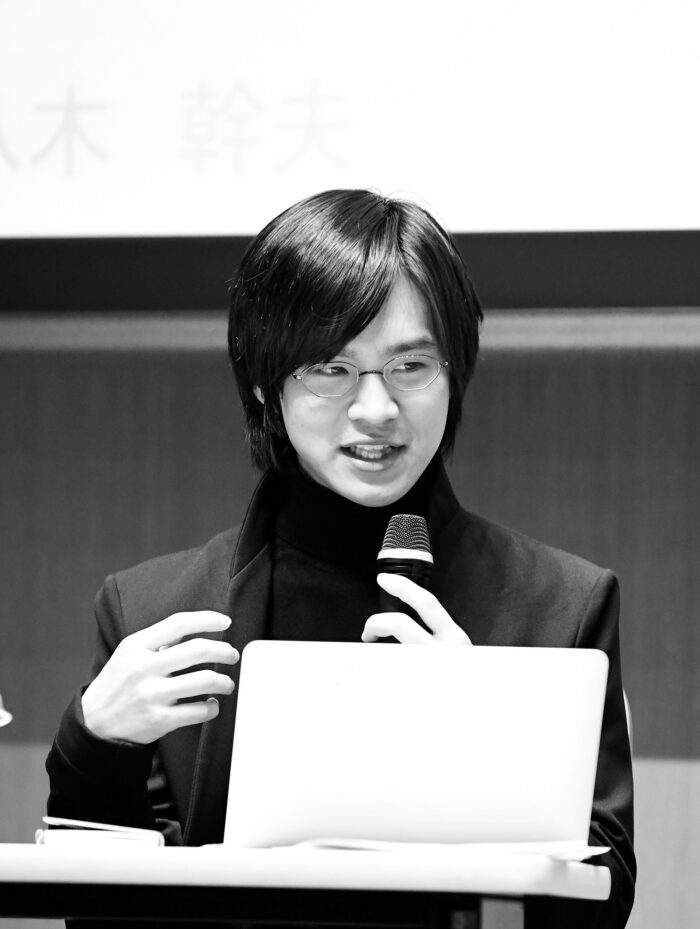
©西村義次
【久村 亮介】(ひさむら・りょうすけ)
東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程在籍。「西脇順三郎研究をはじめるまえに」(『Booklet 30 没後40年 西脇順三郎──無限の過去、無限の未来』慶應義塾大学アートセンター、2023年)など。京都芸術大学通信制大学院文芸領域・非常勤講師。
読み手——書き手にとって不可欠なもの
書き手にとって必要なものとは何か。
いきなり大きすぎるサイズの質問になりますが、こういう機会でもないと考えることもないでしょうから、ぜひ一緒に考えてみてください。
どうにも大喜利みたいなことを考えてみたくなってきますが、せっかくなのでここはあえて大真面目に、私なりの答えをぶつけてみたいと思います。書き手にとって必要なもの、それは「読み手」です。
その作品がどれほど優れているのか、いや、その作品が存在することでさえも、すべては読み手ありきである——とまあ、ここまでくると極論ですが、とはいえこうした考え方が、まったくもって無意味でないことは、おそらく納得してもらえるでしょう。ものを書いたことがある人であれば、一度はこのようなことを考えてみたことがあるはずです。
単純に「より多くの人に読んでもらったほうがいい」という話ではなく、そもそも読み手というのは、まず書き手にとって必要不可欠な存在なのだ、ということです。
しかし、この読み手の問題というのは、何を、どうやって書くのかという問題とは、かなり勝手が違っているように思えます。後者はいってみれば、創作における能動的な問題とでもいえそうなものです。能動的ゆえ、書き手の側でいろいろと思案のしようがあります。
いっぽう読み手の問題とは、どのように読まれるのかという、いわば受動的な問題です。もちろん、受け身の問題だからといって、まったく能動的に考えられないものではないでしょう。どのように読者に読ませようか、というかたちで、ある程度までは積極的に取り組むことができます。とはいえ、究極的には、書き手がそのすべてをコントロールすることはできません。
どのように読まれるのかという問題は、実際に他人に読まれる経験の積み重ねていくなかで、ようやくいくらかの想定ができるようになる、そういう種類のものだと思っています。(いままさに、このことを実感しながら書いています。)
こうした読み手の重要性を念頭においてみると、創作の実践というものの全体を、いくらか別の角度から考えてみたくなります。
つまり、作品を書き上げたところをゴールにするのではなく、書き上げたものを読んでもらい、フィードバックをもらって、さらにその意見を自分がどのように受け止めるべきか、これについてもじっくりと考える——このように、書き上げたあとの行程まで含めたものとして見るほうが、創作行為のより実際的な捉えかたであり、有効なものになっている気が、私はしています。
さて、そのための読み手を確保することが、実はなかなかに難しいことです。それも、とりあえず読んでくれるだけというのではなく、正面から真剣に自分が書いた作品と向き合ってくれたり、自分の書いたものに率直かつ的確な意見をくれたり、またそれなりの数の作品を読みこなしていたり、ましてや書き手としての技術に習熟していたり……そうした読み手ともなると、確保の難しさはなおさらです。この難問を解決する方法は、しかし、すでにおわかりかと思います。
自分のやる気に応えてくれるような環境は、残念ながら千載一遇の好運にでも恵まれない限り、自分一人で構築できるものではありません。このことに関する苦労と実感は、もちろん私自身もそのひとりですが、多くの人の身に刻まれているものでしょう。
この点についていえば、ここ大学院文芸領域で交わされているさまざまな意見を眺めていると、その多様さはもちろんながら、しかしある点についてはぴたりと一致していたりと、人に自分の作品が読まれるという体験の、純度の高いものがそこにあることを、しみじみと感じられます。
私自身も、少しでもより優れた読み手となるべく、日々研鑽を積みながらではありますが、とにかくすてきな作品に出逢えることを、心待ちにしております。
——————————————————
説明会情報
【2024年11月7日(木)19:00~20:30】
文芸領域 特別講義(2) 小説ゼミ編(第二部)
「物語の新しい可能性を問う――「マーケット」の影に隠れたもの――」
この数十年来、真摯に世界と向き合ってその意味を鋭く問い直す「純文学」や「現代文学」なるジャンルの作品は、一般的にあまり読まれなくなりつつある、ように見えます。
しかし、物語を通してこの世界のありようを確かめ、探求を続け、新たな道を模索することに、もう希望は見いだせないのか。それとも、いまだ省みられていない、新たな可能性の萌芽があるのか。
気鋭の文芸評論家、作家、書評家とともに、こうしたことを大学院という学びの場でいったいどれほど追求できるのか、その可能性を探ります。
登壇者一覧)
■小説ゼミ1(主として純文学ジャンル)指導担当者
*池田雄一(文芸評論家)
*藤野可織(作家)
ゲスト)
■非常勤講師(*学生作品評価添削担当)
*あわいゆき(書評家)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
【2024年11月20日(水)19:00~20:30】
芸領域 特別講義(3) クリティカル・ライティングゼミ編
「人の心を動かす文章とは――自ら発信する時代のライティングスキルーー」
ブログやSNSなど、いまや誰もが簡単に世界に向けて文章を発信できる時代。うまいだけではなく、もっと読みたいと思わせるにはどうしたらいいのか──。
エッセイ、書評、取材記事にコラム、あらゆる文章に対応するスキルは、誰にでも身につけられるもの。文章力なんてあとから付いてきます。人文書から実用書までさまざまなノンフィクションを手掛けてきたベテラン編集者2名が、伝わる文章の秘訣と当ゼミで学べることについてお話しします。
登壇者一覧)
■クリティカル・ライティングゼミ 指導担当者
*田中尚史(編集者)
*野上千夏(編集者)
司会進行)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
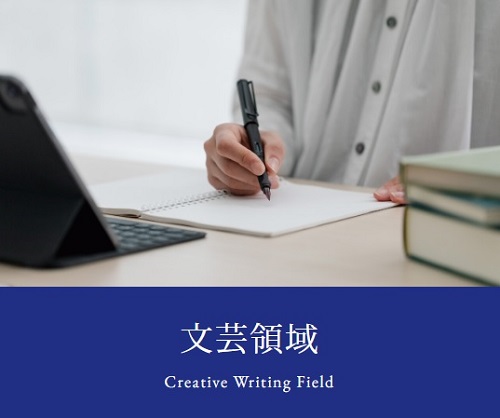
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事