

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「文章がうまくなりたい人に――クリティカルライティング・ゼミがお役に立てる理由があります」(編集者 野上千夏)
2024年11月18日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「文章がうまくなりたい人に――クリティカルライティング・ゼミがお役に立てる理由があります」(編集者 野上千夏)
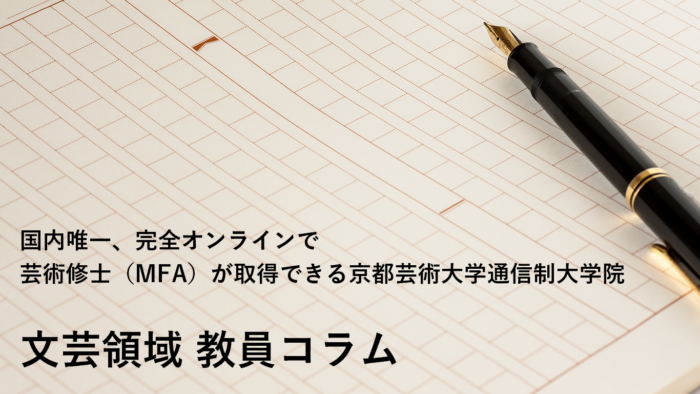
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は編集者の野上千夏さんのコラムをご紹介します。

【野上 千夏】(のがみ・ちか)
1964年山口県出身。1987年立教大学文学部日本文学科卒業。専攻は上代文学(日本書紀、古事記、万葉集)。趣味実用系の出版社を経て、2002年より大手出版社に編集者として勤務。主に趣味、生活ジャンルの実用系書籍を現在まで300冊以上手がけ、発行から10年以上版を重ねるロングセラーも多い。第4回料理レシピ本大賞に担当本が入賞。2024年定年退職し、現在はフリーランスとして編集や、出版プロデュースなどに携わる。京都芸術大学大学院文芸領域・クリティカル・ライティングゼミ副担当。
文章がうまくなりたい人に
――クリティカルライティング・ゼミがお役に立てる理由があります
ビジネス文書をスキルアップさせたい、取材記事を発信したい、共感を得られるエッセイを書きたい、など本ゼミを志望する人の動機や目的はさまざまですが、共通しているのは「文章がうまくなりたい」ということ。でも「うまい」文章って何? どうやって書くの? という疑問にお答えしましょう。
そもそも「うまい」文章って何?
本クリティカルライティング・ゼミはノンフィクションのライティングを教えています。エッセイ、インタビュー、レビューなど、ジャンルはさまざまありますが、目的は「読む人に自分の思いを伝えること」、そして「読んだ人の心を動かすこと」。あなたの書く文章を読んだ人が「知的好奇心を満たされた」「心が温かくなった」「困ったことが解決できた」などと思ってもらえたら、それが「伝わる文章」、イコール「うまい文章」であると私は考えています。
本ゼミには、プロの書き手になりたい人、SNSなどでエッセイを書きたい人や、zineを制作して社会に発信したい人もいます。目標はさまざまでも「伝わる文章」を書くということはすべての文章のベースです。
伝わる文章を作る3つのキーワード
とはいうものの、「普段文章を書いているけど、どうにもうまく伝わってない気がする」というあなた。伝わる文書にはコツがあるのです。基本的な3つのコツをここでご教授しましょう。
その1◆嘘偽りなく、誇張せず書くこと。
まず大切なのは、事実を書くことです。文章の信頼感を読み手に与えます。
その2◆短く、平易に書くこと。
1文が長いと、主語と述語が離れてしまい、読み手とっては何の話だかわからなくなることが。短く書くことが基本。すっと読めるようなるべくストレートに書きましょう。
その3◆観念的な表現、ふんわりぼんやりした表現をしないこと。
凝ったたとえや、詩的な表現を使うと、読み手は、はて? と思考をストップさせます。読み手に「わかる言葉」で書かないと伝わりません。それには一般的なワードを使いましょう。
とはいえ、実際に書いてみると、自分独りではどこを直せばよいのかわからす迷子になりがち。そこに本ゼミがお役に立ちます。
ゼミは講義形式ではなく、実践的な指導が中心。毎月課題を書き、教員が添削することで、明確にコツがつかめます。自分では気が付かない書きグセや、何度も使ってしまうお決まりの言葉も、個別指導で、毎月どんどん上達していきます。
実際、入学直後の4月にはアカ字(要修正箇所)で真っ赤になった原稿も、後期が始まる9月にはほとんどアカ字が入らなくなっています。
誰に伝えるか? ペルソナの設定が肝心
多くのゼミ生は入学時に「書きたい=伝えたい」テーマをもっています。でも「誰に読ませるか」を明確に想定している人は少ないもの。記事の「読み手」、すなわちターゲットを絞ることが「伝える文章」の第一歩です。
実際に企画書を書く課題では、「読者層」を必ず書いてもらいますが、「世代を問わず多くの人」と書く人のなんと多いことか。多くの人を想定すればするほど文章はぼんやりするもの。「ペルソナ」と呼ばれる読者の人物像をしっかり定めることが肝心です。
でも、自分独りの思考にのみ頼って書いた文章は、実際に読んでもらって感想をもらうことが少ないもの。ペルソナがなぜ必要なのかも実感できません。リアルな読み手を想定するには、他者に読んでもらって感想を得るのが近道でしょう。
本ゼミでは、教員が指導するだけでなく、ゼミの仲間が文章を読んで感想を述べたり、自分も他の人の文章を読むことができます。これがぐんと上達する秘訣! いちばん身近な読者が常に周囲にいるのは、確実なブラッシュアップにつながります。
現在、本ゼミでは、20代から60代までの男女が所属しており、そのキャリアはさまざま。ライティングの経験が無い人も多数です。すべてオンラインでの授業なので、日本全国だけにとどまらず、海外から受講している人も。普段の生活では出会うことがない人たちかもしれませんが、皆ライティングがうまくなりたいという「同好の士」。お互い刺激しあって、切磋琢磨できます。実際ゼミは、フレンドリーな雰囲気で毎回盛り上がっています。
伝わる文章を書くことは人生の武器
では実際ゼミではどのような学習をしているのでしょうか。
1年生は、毎月の共通課題である「本を勧める」というレポートに加え、月替わりの「バナナを売る」「手順書を書く」「写真や絵を表現する」などの課題をこなしつつ、前期末を目標に企画書作成から短い記事を作成します。後期では、インタビューの基本やDTP(組版)の基礎を学びながら、インタビュー記事を作成していきます。
2年生になると、独自の企画で取材やインタビューを重ねて、課題を制作していきます。
常に「広いフィールドで発信する記事」という観点で指導しているので、プロのライターとして活躍することも視野にいれつつ、さまざまな文章を発信する実践力が養えます。いずれ素晴らしい結果を出せる人が、このゼミから生まれるかしら、と、わくわくしながら私は授業を重ねています。
また相手にストレートに伝わる文章が書けるようになることは、身近な暮らしにも役立ちます。例えば、メール、仕事のレジュメ、スピーチ原稿などなど。インタビューの実習で「聞く力」を得られると、ふだんの会話もはずみやすくなり、コミュニケーション力をつけられます。実際私もふだん「よくそんなに人の話を続けられるね」と言われることが。知らずに取材体制になっているようです。これは誰にとっても一生役立つ大きな武器になることでしょう。
そんな役立つ文章を本気で学びたいあなたを、クリティカルライティング・ゼミでお待ちしています。
——————————————————
説明会情報
【2024年12月4日(水)19:00~20:30】
文芸領域 入学説明会
カリキュラム・学び方について教員が解説します。 参加者はカメラ・マイク不要の視聴型説明会です。
質疑応答コーナーでは、チャット機能で質問・相談ができます。
登壇者)
*辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
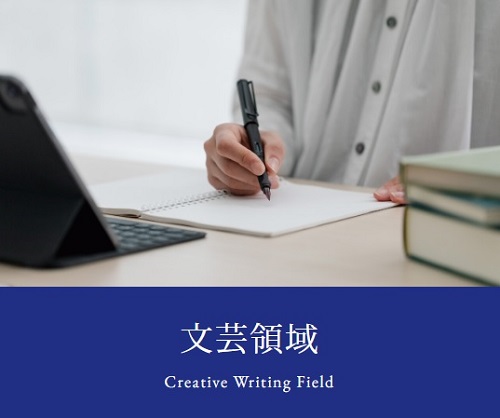
文芸領域では入学後、以下いずれかのゼミに分かれて研究・制作を進めます。
●小説創作ゼミ
小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。
●クリティカル・ライティングゼミ
企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。
おすすめ記事
-
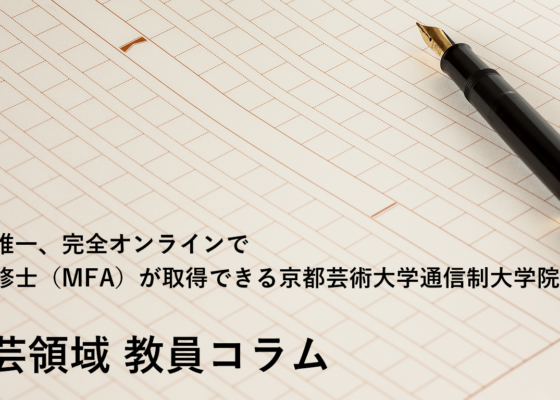
通信制大学院
2024年11月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「あなたの文章に読まれる価値はあるか」(編集者 田中尚史)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は編集者の田中尚史さんのコラムをご紹介します。 …
-
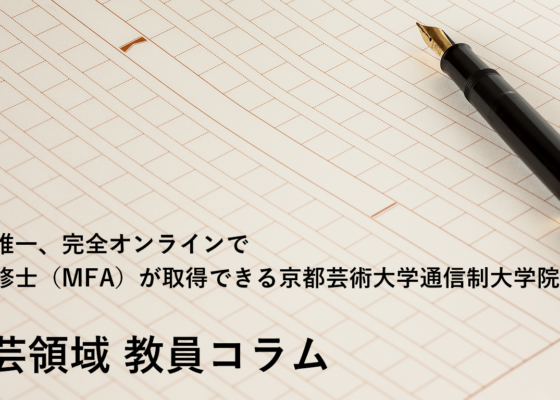
通信制大学院
2024年10月25日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「あらゆる創作活動に応用できる、概念の拡張とブラッシュアップについて」(文芸評論家 池田雄一)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は文芸評論家の池田雄一さんのコラムをご紹介します…
-
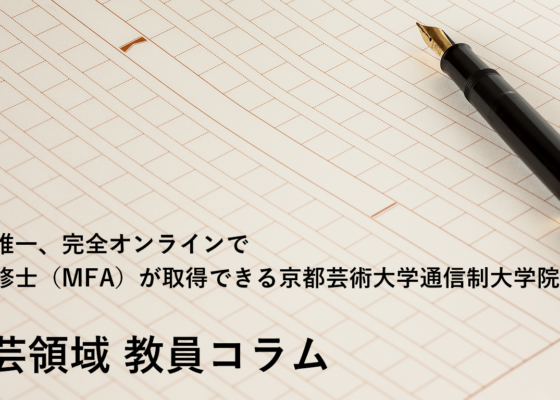
通信制大学院
2024年10月09日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「彼/彼女たちはなぜ書くのか?」(編集者 松岡 弘城)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は編集者松岡 弘城さんのコラムをご紹介します。 …






























