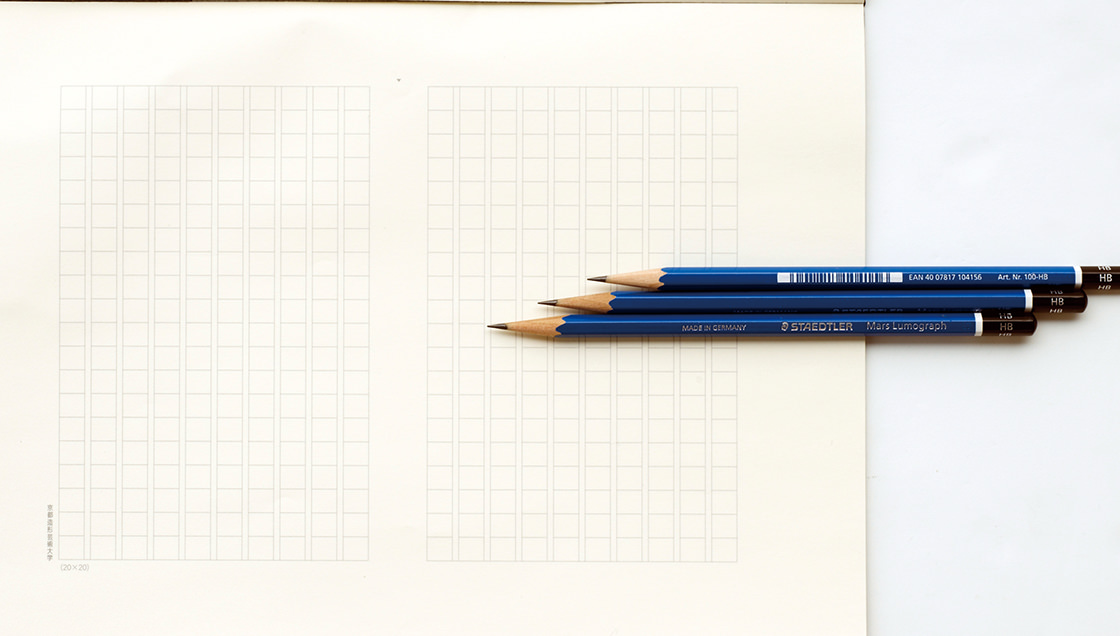

文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】大学は「習い事」か?
2024年12月23日
【文芸コース】大学は「習い事」か?
こんにちは。
文芸コース教員の中嶋優隆です。
突然ですが、みなさんは「大学は「習い事」か?」と問われたら、どう答えますか。今日はこの問いをみなさんと一緒に考えてみたいと思います。
この時期は大学入学や在学継続かを悩む方も多いと思います。
そんなとき、「大学は「習い事」だ。」と言われれば、なんだか心理的なハードルが下がるような気がします。私は大人になってからチェロを習い始めましたが、それは「なにか「習い事」をしたい!」という気持ちからでした。(写真は鴨川での練習中に撮影しました。)
 では、「大学は「習い事」だ。」と言い切ってよいか。どことなく、違和感を覚えます。いったいなぜでしょうか。
では、「大学は「習い事」だ。」と言い切ってよいか。どことなく、違和感を覚えます。いったいなぜでしょうか。
大学の教員っぽいことを言ってみましょう。この問いに答えるには、そもそも「大学」とはなんであり、「習い事」とはなんであるかを定義する必要があります。そうしないと、話がかみ合いませんね。だから、先ほどの問いは「そもそも、あなたは大学とはどのような場あるいは組織だと考え、また、「習い事」とはどのようなことを指すと考えるがゆえに、大学とは「習い事」だと判断するか否かを答えよ。」という意味になっているんです。ンー、ヤヤコシイ! でも、とりえず考えてみましょうよ。
まず、「習い事」をどう考えるか。たとえば子どもたちがピアノや水泳を「習う」とはどういうことか。旺文社の『国語辞典』(第十版、2006)によれば、「習う」とは「教えられた通りに繰り返し練習して知識や技術を身に付ける」とあります。すなわち、手本通りの知識や技術を身に付けること。であるからして、「習い事」とは、なんらかのスキルを手本通りに獲得することを目的とした行為だといえます。
これを踏まえると、先ほどの問いは「大学はスキルを手本通りに獲得することを目的とした場・組織か?」ということになりますよね。ンー、ドウダロウ…。なんだか直感的に違和感を覚えませんか。大学にはもっとこう大きな――そして不穏な――なにかを期待したいような。
そのある種の「不穏さ」は、「大学」という言葉に含まれているのデハ!
もう一度、旺文社の辞典を引いてみましょう。
【大学】学校教育法で規定された、学術研究・教育の最高機関である学校。最高学府。卒業すると学士の学位を得る。
へ~、ソウナンダ。引いては見たものの、答えには直結しないようです。でも、「学術研究・教育の最高機関である学校」というのはヒントになるのでは。ここには「学術研究」と「教育」が並置されていますね。再び旺文社の辞典からの引用してみます。2つの記述を比べてみましょう。
【教育】社会で生活するために必要な学問・知識・技能などが身につくよう、教え育てること。
【研究】物事をよく調べ考えること。真実・真理を求めて学問的に調べ考えること。
どうでしょう。アラ、オモシロイ! え、何が?
「教育」が目的とするのは、「社会で生活するために必要な(もの)が身につくよう」にすることですから、大学にはたしかに「習い事」の側面を認めることができるのです。しかし、「研究」はどうでしょう。「真実・真理を求めて…」。そう。「研究」では社会で生活するのに必要かどうかは問題ではないのです。もっと言えば、世の中が見過ごしているものに価値を見いだすことが「研究」という営みなのです。芸術大学では「研究」を「創作」や「表現」に置き換えてもいいでしょう。価値が認められている既存の芸術とは異なる方向を模索すること。それが大学のもうひとつの側面なのです。
これ、面白くないですか? 「習う」という既存の知識や技術を獲得する営みと、「創る」という既存のものからの革新を目指す営みと、正反対な2つの営みを同時に行うのが「大学」なのです。極論を言えば、たったいま講義で学んだことが、その直後に(いや講義の中ですら)覆ってしまう。それが「大学」なのです。
さらにさらに、「教育」と「研究」では、それぞれの行為の主体が違うではありませんか。「教育」は教員と学生のある種の上下関係が前提で、主体は教員です。「教え育てる」わけですから。一方、「研究」は大学に属する全員に開かれています。逆に言えば、「調べ考える」人ならだれでも大学にいていいわけです。教員と学生は、師弟関係でありながら「研究」(創作)者として対等でもある。
そう。「大学」とは、学ぶ内容の面でも、人間関係の面でも、「習う」以上のことが期待されている/できるわけです。これこそが、私たちが大学に求める「不穏さ」ではないでしょうか。それは、「社会」や「世の中」という凝り固まった価値観を疑い、教室に王政を敷く教員を論破する喜びです。もし、「大学は「習い事」である。」とするなら、それは大学の一面だけを切り取ったことになるでしょう。教員のコピーができあがるだけですから。
だから、先ほどの命題はこう書き直さねばなりません。「大学は「習い事」ではある。しかし、その内容および師弟関係を内側から破っていく場でもある。」と。素晴らしいと思いませんか。だって、こんな風に考えてきたところで、言葉のうえでは定義できていても、結局のところ、「大学」には安定した実体などないという答えにたどり着いたのですから。大学は根本的に〈空虚〉なのです。でも、それを裏返せば、私たちが〈わたし〉として、自由に輪郭を描くことが許されたもの、それが大学なのです。そして、この〈空虚〉さは、有用性(役立つこと)の追求に侵された現代社会のロジックを根本的に問い直すものにほかなりません。
大学のカリキュラムを達成することは「習い事」です。欠かしてはなりません。しかし、そのなかには無数の「不穏さ」が身を潜めています。その「不穏さ」を楽しむこと。それこそが、カリキュラムという単なる観光旅行的な「習い事」を、研究や創作という知的で独創的な冒険へと変えることになるでしょう。
ちなみに――ここで述べたことは芸道の「習い」の精神には備わっていたことかもしれません。千利休が残したという「利休百首」(「利休道歌」とも)の一首目と二首目は次のようなものです。
それを学ぼうと思った心が自分自身ながらの「師匠」である。そして、内容について批判をするには、まず「習う」ことが必要である。すべては「習う」ことから始まる。やっぱり、大学は「習い事」なのかも? ア、反転シチャッタ!
では、みなさまよいお年を。
文芸コース| 学科・コース紹介
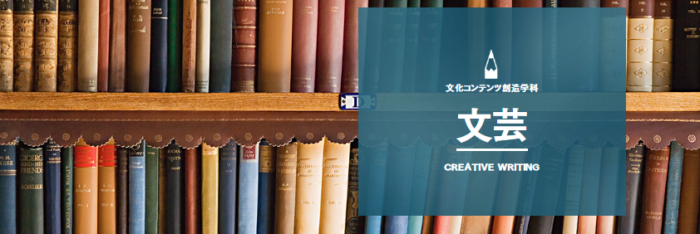
大学パンフレット資料請求はこちらから

文芸コース教員の中嶋優隆です。
突然ですが、みなさんは「大学は「習い事」か?」と問われたら、どう答えますか。今日はこの問いをみなさんと一緒に考えてみたいと思います。
この時期は大学入学や在学継続かを悩む方も多いと思います。
そんなとき、「大学は「習い事」だ。」と言われれば、なんだか心理的なハードルが下がるような気がします。私は大人になってからチェロを習い始めましたが、それは「なにか「習い事」をしたい!」という気持ちからでした。(写真は鴨川での練習中に撮影しました。)
 では、「大学は「習い事」だ。」と言い切ってよいか。どことなく、違和感を覚えます。いったいなぜでしょうか。
では、「大学は「習い事」だ。」と言い切ってよいか。どことなく、違和感を覚えます。いったいなぜでしょうか。大学の教員っぽいことを言ってみましょう。この問いに答えるには、そもそも「大学」とはなんであり、「習い事」とはなんであるかを定義する必要があります。そうしないと、話がかみ合いませんね。だから、先ほどの問いは「そもそも、あなたは大学とはどのような場あるいは組織だと考え、また、「習い事」とはどのようなことを指すと考えるがゆえに、大学とは「習い事」だと判断するか否かを答えよ。」という意味になっているんです。ンー、ヤヤコシイ! でも、とりえず考えてみましょうよ。
まず、「習い事」をどう考えるか。たとえば子どもたちがピアノや水泳を「習う」とはどういうことか。旺文社の『国語辞典』(第十版、2006)によれば、「習う」とは「教えられた通りに繰り返し練習して知識や技術を身に付ける」とあります。すなわち、手本通りの知識や技術を身に付けること。であるからして、「習い事」とは、なんらかのスキルを手本通りに獲得することを目的とした行為だといえます。
これを踏まえると、先ほどの問いは「大学はスキルを手本通りに獲得することを目的とした場・組織か?」ということになりますよね。ンー、ドウダロウ…。なんだか直感的に違和感を覚えませんか。大学にはもっとこう大きな――そして不穏な――なにかを期待したいような。
そのある種の「不穏さ」は、「大学」という言葉に含まれているのデハ!
もう一度、旺文社の辞典を引いてみましょう。
【大学】学校教育法で規定された、学術研究・教育の最高機関である学校。最高学府。卒業すると学士の学位を得る。
へ~、ソウナンダ。引いては見たものの、答えには直結しないようです。でも、「学術研究・教育の最高機関である学校」というのはヒントになるのでは。ここには「学術研究」と「教育」が並置されていますね。再び旺文社の辞典からの引用してみます。2つの記述を比べてみましょう。
【教育】社会で生活するために必要な学問・知識・技能などが身につくよう、教え育てること。
【研究】物事をよく調べ考えること。真実・真理を求めて学問的に調べ考えること。
どうでしょう。アラ、オモシロイ! え、何が?
「教育」が目的とするのは、「社会で生活するために必要な(もの)が身につくよう」にすることですから、大学にはたしかに「習い事」の側面を認めることができるのです。しかし、「研究」はどうでしょう。「真実・真理を求めて…」。そう。「研究」では社会で生活するのに必要かどうかは問題ではないのです。もっと言えば、世の中が見過ごしているものに価値を見いだすことが「研究」という営みなのです。芸術大学では「研究」を「創作」や「表現」に置き換えてもいいでしょう。価値が認められている既存の芸術とは異なる方向を模索すること。それが大学のもうひとつの側面なのです。
これ、面白くないですか? 「習う」という既存の知識や技術を獲得する営みと、「創る」という既存のものからの革新を目指す営みと、正反対な2つの営みを同時に行うのが「大学」なのです。極論を言えば、たったいま講義で学んだことが、その直後に(いや講義の中ですら)覆ってしまう。それが「大学」なのです。
さらにさらに、「教育」と「研究」では、それぞれの行為の主体が違うではありませんか。「教育」は教員と学生のある種の上下関係が前提で、主体は教員です。「教え育てる」わけですから。一方、「研究」は大学に属する全員に開かれています。逆に言えば、「調べ考える」人ならだれでも大学にいていいわけです。教員と学生は、師弟関係でありながら「研究」(創作)者として対等でもある。
そう。「大学」とは、学ぶ内容の面でも、人間関係の面でも、「習う」以上のことが期待されている/できるわけです。これこそが、私たちが大学に求める「不穏さ」ではないでしょうか。それは、「社会」や「世の中」という凝り固まった価値観を疑い、教室に王政を敷く教員を論破する喜びです。もし、「大学は「習い事」である。」とするなら、それは大学の一面だけを切り取ったことになるでしょう。教員のコピーができあがるだけですから。
だから、先ほどの命題はこう書き直さねばなりません。「大学は「習い事」ではある。しかし、その内容および師弟関係を内側から破っていく場でもある。」と。素晴らしいと思いませんか。だって、こんな風に考えてきたところで、言葉のうえでは定義できていても、結局のところ、「大学」には安定した実体などないという答えにたどり着いたのですから。大学は根本的に〈空虚〉なのです。でも、それを裏返せば、私たちが〈わたし〉として、自由に輪郭を描くことが許されたもの、それが大学なのです。そして、この〈空虚〉さは、有用性(役立つこと)の追求に侵された現代社会のロジックを根本的に問い直すものにほかなりません。
――ロラン・バルト『エッフェル塔』参照
大学のカリキュラムを達成することは「習い事」です。欠かしてはなりません。しかし、そのなかには無数の「不穏さ」が身を潜めています。その「不穏さ」を楽しむこと。それこそが、カリキュラムという単なる観光旅行的な「習い事」を、研究や創作という知的で独創的な冒険へと変えることになるでしょう。
ちなみに――ここで述べたことは芸道の「習い」の精神には備わっていたことかもしれません。千利休が残したという「利休百首」(「利休道歌」とも)の一首目と二首目は次のようなものです。
その道に入らんと思ふ心こそ我身ながらの師匠なりけれ
ならひつゝ見てこそ習へ習はずに良し悪し言ふは愚かなりけり
それを学ぼうと思った心が自分自身ながらの「師匠」である。そして、内容について批判をするには、まず「習う」ことが必要である。すべては「習う」ことから始まる。やっぱり、大学は「習い事」なのかも? ア、反転シチャッタ!
では、みなさまよいお年を。
中嶋
文芸コース| 学科・コース紹介
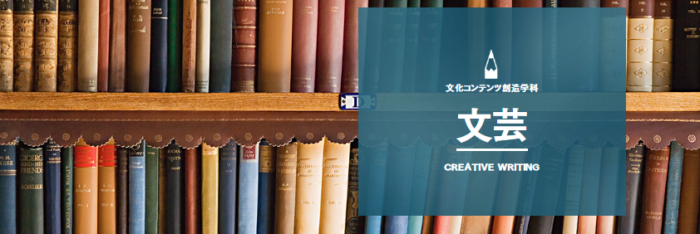
大学パンフレット資料請求はこちらから

おすすめ記事
-

文芸コース
2023年10月27日
【文芸コース】2024年度からの文芸コースでは「編集」を学ぶことができます。
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 今回のブログでは、文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方のために、新しい文芸コースの特…
-
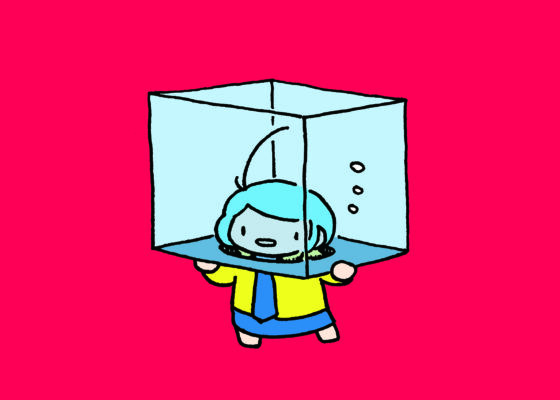
文芸コース
2024年01月13日
【文芸コース】「もの」になりきる文章術
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 最近、「どうすれば観察力は身につきますか?」とか「観察眼の重要性はわかったが、具体的な鍛え方がわからない」と…
-

文芸コース
2024年12月03日
【文芸コース】「書き直し」は肉体を意識しながらやってみよう
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 今年も残すところ一ヶ月となりましたが、文芸コースで今年最も多かった質問は、「書き直し」についてでした。方法論…






























