

陶芸コース
- 陶芸コース 記事一覧
- 【陶芸コース】粘土と水分、その状態について
2025年07月24日
【陶芸コース】粘土と水分、その状態について
みなさんこんにちは。
陶芸コースのかのうたかおです。
そろそろ梅雨も終わる感じでしょうか。と、書き始めたかったのですが、今年は早くも梅雨が明けましたね。京都は例年、祇園祭の巡行の頃に梅雨が明けて、暑い夏がやってくる、そんなイメージがあります。そしてやってくる夏本番!
その、夏がやってくると梅雨時のじっとりした空気とは違って、洗濯物も乾きやすく、カラッと気持ちのいい空気になります。(京都の夏は湿度も高めですが…)近年の暑さを考えると、熱中症やら夏バテやら、体調面でも色々と気にしなければならないことがありますよね。
陶芸においても“気をつけたいこと”があるんです。それが「粘土の乾燥」です。
制作したり、保管したり、どちらにせよ夏は乾燥がとても早いです。この「乾燥」というのが制作や保管をする上ではとても大きなポイントになってきます。そしてそれは同時に粘土の状態を理解して管理すること、とも言えます。ということで、今回は粘土についてのお話を。
 みなさん、粘土ってどんなイメージですか?硬くもあり、柔らかくもあり、少し冷やっとした触り心地の良いもの、そんな感じですよね。その粘土、作っているときは柔らかく、乾くと硬くなっていきますが、粘土は大きく分けて4つの状態で捉えると分かりやすいかな、と思っています。
みなさん、粘土ってどんなイメージですか?硬くもあり、柔らかくもあり、少し冷やっとした触り心地の良いもの、そんな感じですよね。その粘土、作っているときは柔らかく、乾くと硬くなっていきますが、粘土は大きく分けて4つの状態で捉えると分かりやすいかな、と思っています。
①泥状
②成形に適した柔らかさ
③少し硬くなり、削りやすい、加工しやすい状態
④乾いた状態
この違いは粘土が含んでいる水分の量によって決まります。
①の泥状が最も水分が多く、④に向かって少しずつ水分が抜けていくイメージですね。
①は泥状でかなりの水分量ですが、「ドベ」と呼んだりして粘土同士の接着に使ったりします。

②の成形に適した柔らかさがおおよそ20%〜25%程度の水分量だと考えられます。いわゆる「粘土」として想像できる硬さだと思います。これより水分が多いと柔らかすぎて扱いにくいですし、逆に少ないと可塑性がなくなり、成形しにくくなります。

③の「削りやすい状態」は約15%前後の水分量で、ある程度形が安定しており、高台を削ったり、表面を整えたり、把手や装飾をつけたりするのに適した硬さです。このとき、粘土同士を接着するために①の泥状の「ドベ」を使います。

成形が終わると、④の乾燥した状態にするのですが、ゆっくりと均一に乾燥させるのがとても重要になってきます。急に乾燥させると歪みやひび割れの原因になります。全体がバランスよく乾いていく(均一に収縮していく)ように何かで覆ってやったり、風が直接当たらないようにしたりと「養生」しながら全体を乾かしていきます。そしてしっかり乾かしてから、焼成します。

こんな風に水分の状態をどのようにしてやるのか、ということがとても大事になってきます。
乾燥の話と関連して、粘土の保管についての話も。「粘土の保管について、どのようにすればよいのでしょうか?」という質問をよくいただきます。ある程度の期間でしたら、写真のように厚手のビニールで二重に包むだけでも大丈夫です。
 また、陶芸家の多くは、工房の一角に「ムロ」と呼ばれるスペースを設けています。ムロは、いわゆる冷暗所とも呼べる空間で、あまり温度が高くなく、湿度も高い空間です。湿度を高めに保つために水を入れた容器を置いておいたりもします。そういった場所で成形途中の作品や粘土などを保管するのですが、流石にこんな場所を皆さんが用意するわけにはいかないと思います。ではどうすれば良いのか?
また、陶芸家の多くは、工房の一角に「ムロ」と呼ばれるスペースを設けています。ムロは、いわゆる冷暗所とも呼べる空間で、あまり温度が高くなく、湿度も高い空間です。湿度を高めに保つために水を入れた容器を置いておいたりもします。そういった場所で成形途中の作品や粘土などを保管するのですが、流石にこんな場所を皆さんが用意するわけにはいかないと思います。ではどうすれば良いのか?
ポイントになるのは湿度です。湿度がしっかりあって、温度変化が少ない環境が保管に適していると言えます。ですので、こんなふうにすると良いかと思います。
・まずは土を一つの塊にして、水を含ませてしぼったタオルなどで包む
・タオルで包まれた土を、厚めのビニールなどで包む(できれば二重程度)
・その状態で密閉できる容器に入れる
・その容器を冷暗所で保管する
こんな感じがお勧めです。
容器としては発泡スチロールや、密閉できる収納ボックスなんかが良いかな、と思います。
場所としては床下収納なんかは最適な場所と言えそうです。
こんな感じで保管して、時々タオルに水分を含ませてやるとある程度の長い期間、固くならずに、使用することができますよ。
こういった保管の方法も知っておくと、余った粘土が出ても心配することがなくなるはずです。
陶芸については、どうしても「成形をする」という工程が一番イメージできるものになってきますが、乾燥=水分のコントロールも成形するのと同じくとても大事な工程です。
暑い夏を迎えるにあたって、こんなことも知っておくと制作の助けになると思います。
それでは皆さん、またお会いしましょう!
陶芸コース| 学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
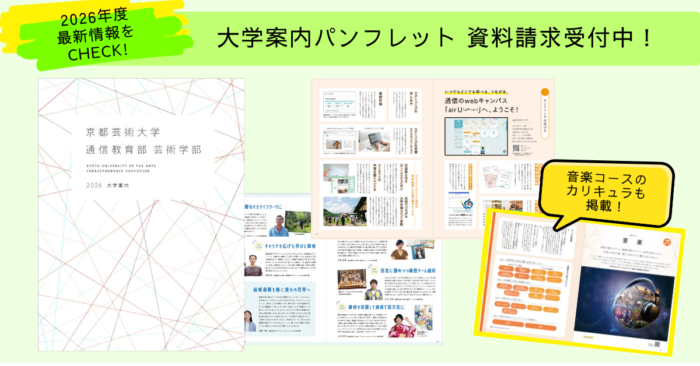
陶芸コースのかのうたかおです。
そろそろ梅雨も終わる感じでしょうか。と、書き始めたかったのですが、今年は早くも梅雨が明けましたね。京都は例年、祇園祭の巡行の頃に梅雨が明けて、暑い夏がやってくる、そんなイメージがあります。そしてやってくる夏本番!
その、夏がやってくると梅雨時のじっとりした空気とは違って、洗濯物も乾きやすく、カラッと気持ちのいい空気になります。(京都の夏は湿度も高めですが…)近年の暑さを考えると、熱中症やら夏バテやら、体調面でも色々と気にしなければならないことがありますよね。
陶芸においても“気をつけたいこと”があるんです。それが「粘土の乾燥」です。
制作したり、保管したり、どちらにせよ夏は乾燥がとても早いです。この「乾燥」というのが制作や保管をする上ではとても大きなポイントになってきます。そしてそれは同時に粘土の状態を理解して管理すること、とも言えます。ということで、今回は粘土についてのお話を。
 みなさん、粘土ってどんなイメージですか?硬くもあり、柔らかくもあり、少し冷やっとした触り心地の良いもの、そんな感じですよね。その粘土、作っているときは柔らかく、乾くと硬くなっていきますが、粘土は大きく分けて4つの状態で捉えると分かりやすいかな、と思っています。
みなさん、粘土ってどんなイメージですか?硬くもあり、柔らかくもあり、少し冷やっとした触り心地の良いもの、そんな感じですよね。その粘土、作っているときは柔らかく、乾くと硬くなっていきますが、粘土は大きく分けて4つの状態で捉えると分かりやすいかな、と思っています。①泥状
②成形に適した柔らかさ
③少し硬くなり、削りやすい、加工しやすい状態
④乾いた状態
この違いは粘土が含んでいる水分の量によって決まります。
①の泥状が最も水分が多く、④に向かって少しずつ水分が抜けていくイメージですね。
①は泥状でかなりの水分量ですが、「ドベ」と呼んだりして粘土同士の接着に使ったりします。

②の成形に適した柔らかさがおおよそ20%〜25%程度の水分量だと考えられます。いわゆる「粘土」として想像できる硬さだと思います。これより水分が多いと柔らかすぎて扱いにくいですし、逆に少ないと可塑性がなくなり、成形しにくくなります。

③の「削りやすい状態」は約15%前後の水分量で、ある程度形が安定しており、高台を削ったり、表面を整えたり、把手や装飾をつけたりするのに適した硬さです。このとき、粘土同士を接着するために①の泥状の「ドベ」を使います。

成形が終わると、④の乾燥した状態にするのですが、ゆっくりと均一に乾燥させるのがとても重要になってきます。急に乾燥させると歪みやひび割れの原因になります。全体がバランスよく乾いていく(均一に収縮していく)ように何かで覆ってやったり、風が直接当たらないようにしたりと「養生」しながら全体を乾かしていきます。そしてしっかり乾かしてから、焼成します。

こんな風に水分の状態をどのようにしてやるのか、ということがとても大事になってきます。
乾燥の話と関連して、粘土の保管についての話も。「粘土の保管について、どのようにすればよいのでしょうか?」という質問をよくいただきます。ある程度の期間でしたら、写真のように厚手のビニールで二重に包むだけでも大丈夫です。
 また、陶芸家の多くは、工房の一角に「ムロ」と呼ばれるスペースを設けています。ムロは、いわゆる冷暗所とも呼べる空間で、あまり温度が高くなく、湿度も高い空間です。湿度を高めに保つために水を入れた容器を置いておいたりもします。そういった場所で成形途中の作品や粘土などを保管するのですが、流石にこんな場所を皆さんが用意するわけにはいかないと思います。ではどうすれば良いのか?
また、陶芸家の多くは、工房の一角に「ムロ」と呼ばれるスペースを設けています。ムロは、いわゆる冷暗所とも呼べる空間で、あまり温度が高くなく、湿度も高い空間です。湿度を高めに保つために水を入れた容器を置いておいたりもします。そういった場所で成形途中の作品や粘土などを保管するのですが、流石にこんな場所を皆さんが用意するわけにはいかないと思います。ではどうすれば良いのか?ポイントになるのは湿度です。湿度がしっかりあって、温度変化が少ない環境が保管に適していると言えます。ですので、こんなふうにすると良いかと思います。
・まずは土を一つの塊にして、水を含ませてしぼったタオルなどで包む
・タオルで包まれた土を、厚めのビニールなどで包む(できれば二重程度)
・その状態で密閉できる容器に入れる
・その容器を冷暗所で保管する
こんな感じがお勧めです。
容器としては発泡スチロールや、密閉できる収納ボックスなんかが良いかな、と思います。
場所としては床下収納なんかは最適な場所と言えそうです。
こんな感じで保管して、時々タオルに水分を含ませてやるとある程度の長い期間、固くならずに、使用することができますよ。
こういった保管の方法も知っておくと、余った粘土が出ても心配することがなくなるはずです。
陶芸については、どうしても「成形をする」という工程が一番イメージできるものになってきますが、乾燥=水分のコントロールも成形するのと同じくとても大事な工程です。
暑い夏を迎えるにあたって、こんなことも知っておくと制作の助けになると思います。
それでは皆さん、またお会いしましょう!
陶芸コース| 学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから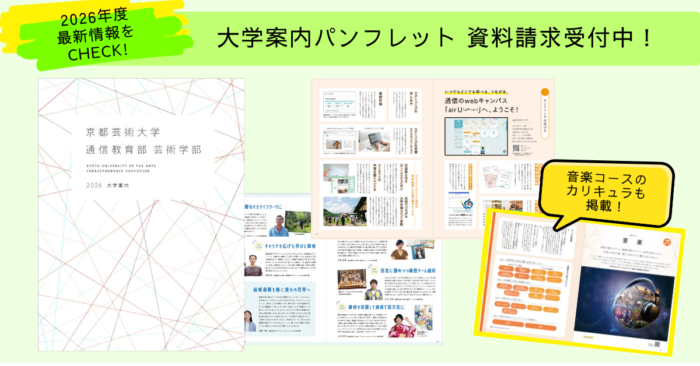
おすすめ記事
-

陶芸コース
2025年06月20日
【陶芸コース】2025年度卒業制作スクーリング、スタート!
こんにちは。 陶芸コース業務担当非常勤の伊賀上空見子(いがうえ くみこ)です。 今年も卒業制作スクーリングがはじまりました! 卒業制作スクーリングはプレゼンテー…
-

陶芸コース
2025年04月23日
【陶芸コース】2025年度が始まりました!ー陶芸コースでは何をどう学ぶの?
みなさんこんにちは。 陶芸コースのかのうたかおです。 春、ですね!新しいことの始まるこの季節はいつもワクワクします。 2025年度も多くの仲間をお迎えし、その期…
-

陶芸コース
2025年03月22日
【陶芸コース】コミュニケーションと知の場づくり=大学
こんにちは。陶芸コース業務担当非常勤講師の戸矢万葉(とや まは)です。 梅の花は、身を縮めていたかと思うと、あっという間に梅の香りは私たちの前を通り過ぎてしまっ…






























