

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「心地いい銭湯」(あわい ゆき)
2025年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「心地いい銭湯」(あわい ゆき)
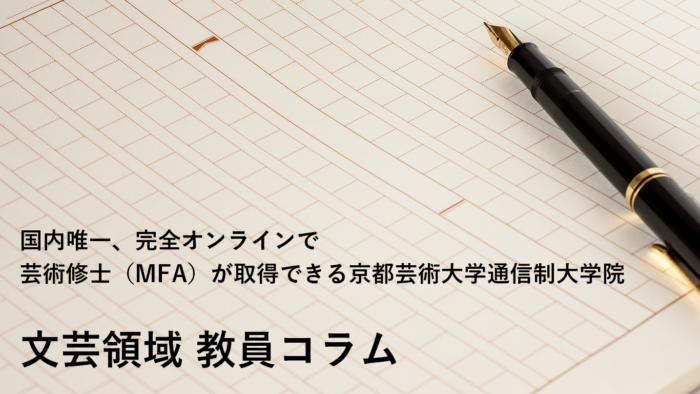
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は書評家、ライターのあわい・ゆきさんのコラムをご紹介します。

【あわい ゆき】(あわい・ゆき)
書評家、ライター。2000年生まれ。2022年に活動をはじめ、「小説現代」のほか、「文藝」「小説推理」「SFマガジン」「別冊文藝春秋」「産経新聞」「潮」などに寄稿。主に国内最新の純文学、大衆文学、SF、ミステリ、ライトノベル、児童小説を中心に幅広く読み、noteにも記事を公開している。
心地いい銭湯
最近、都内の銭湯をめぐっています。めぐっているといっても事前にスケジュールを立てて気になる銭湯に赴くのではなく、用事で外出して、少し時間が余ったときに近場の銭湯を調べてみるのです。ふらっと立ち入ると、リノベーションされて綺麗な銭湯、番台から脱衣所を覗けるようになっている古き良き銭湯など内装はさまざま。どの銭湯も独自にデザインされた空間が広がっていて、サウナの有無や立地によって客層もばらつきがあるので、どれだけ銭湯を訪れても飽きません。
そして私は銭湯を訪れ、ちゃぽりと湯船に浸かっていると、この場にいるみんなが同じ小説を読んでいるような奇妙な気持ちになるときがあります。それは言い換えれば、立場も目的も異なるのに、皆でくつろぐことができている奇妙な一体感ともいえるものです。あまたの銭湯には、たまたま気になった本を気楽に買うようなテンションで立ち寄る私に近い人もいれば、SNSの評判をみかけて訪れたひともいるかもしれません。あるいは好きな作家を追い続けるような態度で、何十年も通っているひともいるでしょう。それぞれ目的や立場が異なっても「銭湯」という事物を通じて心を通わせ、共生できている──それは「小説」が持ち得る力でもあるはずだと、思い出すのです。あらゆる人々を語っていき、分け隔てなく虜にできる力を、小説は秘めています。
また、小説を学べる「大学」という場も、これ以上なく銭湯的な空間であるように思います。大学は小中高よりも幅広い年齢までひらかれており、義務ではないので入学した動機も人それぞれ。しかし、興味関心のある「事物」を共有しているからこそ、隔たりをこえて共に学び合うことのできる、居心地のいい空間になっているのだ、と。
だから大学で小説を学ぶのは、銭湯にぽかぽか浸りながら、銭湯の極意を学ぶようなものである──のかもしれません。多くのひとに楽しんでもらえる銭湯のような小説を書くにはどうすればいいか、その技術を学べるのはもちろん、分け隔てなくくつろげる空間にもなってるのが大学の最もよいところでしょう。そう思っている私はいま、全国の大学をめぐりたくて仕方ありません。
──────────────────
説明会情報
【2025年10月29日 (木)19:00~20:30】
文芸領域「ことばの表現」の新しい可能性
「ことばの表現」ジャンルは、人類最古のものに見えてその実、SNS隆盛の現代においては、もっとも新しくラディカルな可能性を持った手立てとなりつつあります。この世のほとんどあらゆるものを、きわめて精確に表現しうる。人間社会を根底から揺り動かす絶大な力に満ちている。それでいて、そのほんとうの起源がいまだにわかっておらず、大きな謎も秘めています。
この神秘的で同時にきわめて現代的な「ことば」なるものの新たな可能性を掘り起こし、小説など広義の物語創造から、各種の評判、エッセイ、コラム、取材記事の執筆、そしてSNSにおける発信など、多種多様なジャンルにおける「ことばの表現」の近未来を展望します。登壇するのは、気鋭の文芸評論家、小説家、そしてフォロワー数83万人のコピーライター。どうぞふるってご参加ください。よろしくお願いいたします。
登壇者一覧)
■指導担当者
⁕池田雄一(文芸評論家)
⁕山本隆博(コピーライター)
司会進行)
⁕辻井南青紀(作家/文芸領域長)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
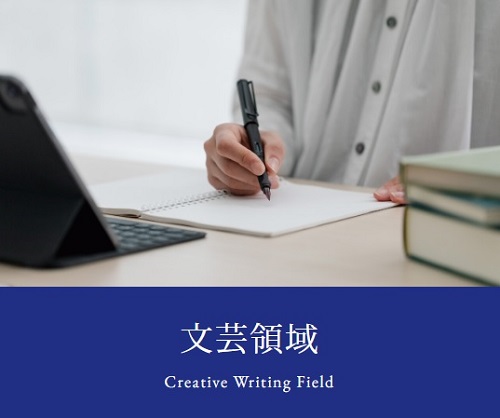
入学すると、一学年にひとつの「クリエイティブライティング・ゼミ」に入り、その中にある3つの専門性の高い指導グループのうちのどれかに所属します。
●クリエイティブライティング・ゼミ
小説などの物語創作や評論、エッセイ、コラムなどのテクスト、あるいは社会に向けて自身の思いを発信する活動など、さまざまなジャンルを横断的に学び、実践できる仕組みがあります。学びと創作の取り組みを可能な限り自由にするために、前期や後期など期ごとにゼミ内グループを移動することも出来ます。特定の分野やジャンルのみならず、大学院の二年間のうちにいろいろなことばの表現に触れ、実力をつけることが出来る機会があります。
おすすめ記事
-

通信制大学院
2022年11月24日
【通信制大学院】新文芸領域のPR短編映画『トンネルの先』『トンネルの中へ』について
新しい文芸大学院でこれから学ぶかもしれない方々と、おそらく同じ志を掲げ、同じ心意気で、映像による「物語」を作っている若い人たちがいます。 京都芸術大学芸術学…
-
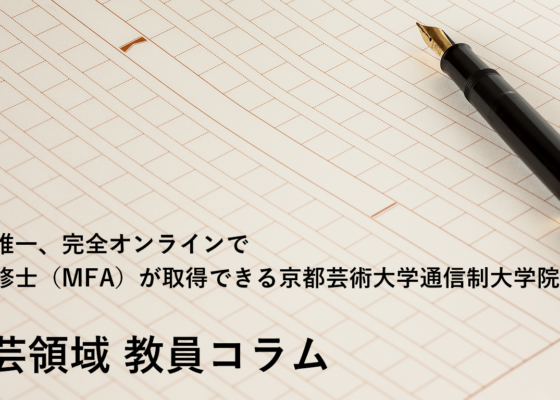
通信制大学院
2024年11月20日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「あの頃書いた小説」(作家 鳥山まこと)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家の鳥山まことさんのコラムをご紹介します。 …
-
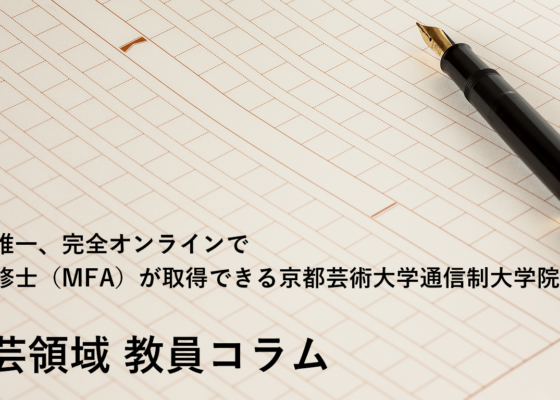
通信制大学院
2024年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読まれる恐怖の先にあるもの」(作家 藍銅ツバメ)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家の藍銅ツバメさんのコラムをご紹介します。 …






























