

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「なぜ『考察家』は定着しないのか?」(久村 亮介)
2025年11月25日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「なぜ『考察家』は定着しないのか?」(久村 亮介)
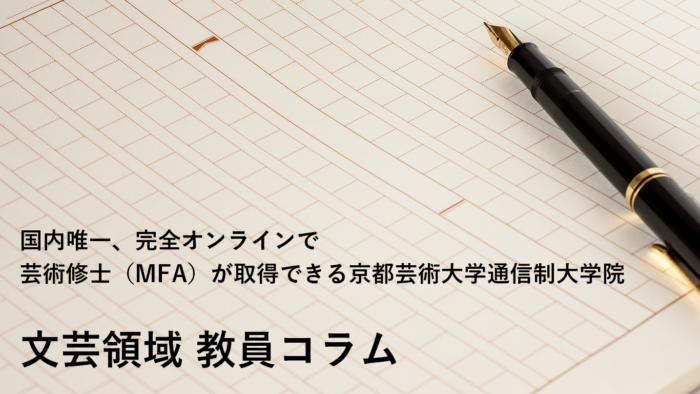
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は文学研究者の久村 亮介さんのコラムをご紹介します。
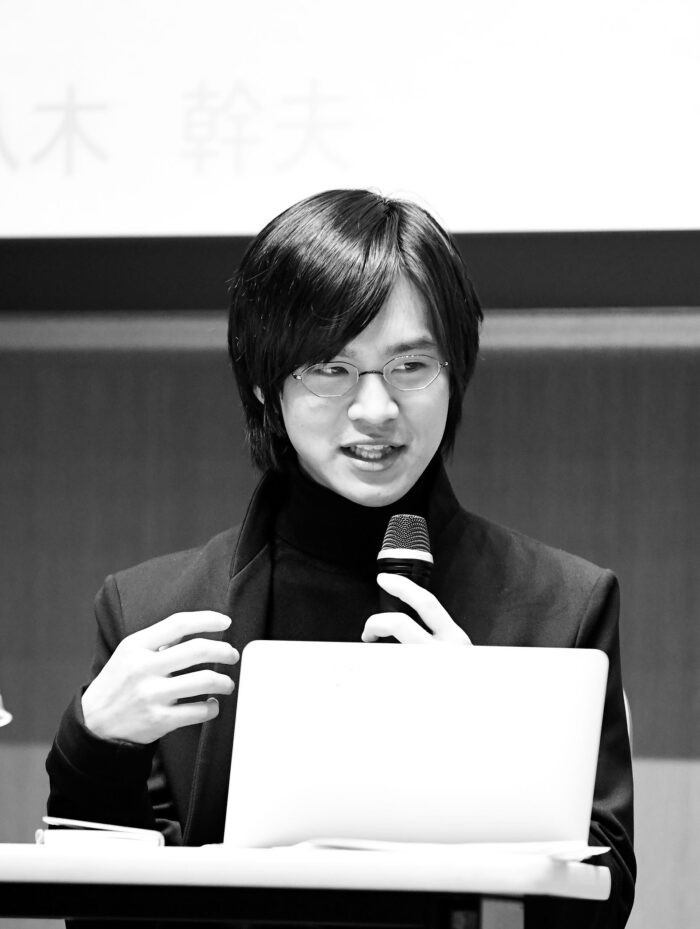
【久村 亮介】(ひさむら・りょうすけ)
文学研究者。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程在籍。「西脇順三郎研究をはじめるまえに」(『Booklet 30 没後40年 西脇順三郎──無限の過去、無限の未来』慶應義塾大学アートセンター、2023年)など。
なぜ『考察家』は定着しないのか?
最近、作品の読解を扱うコンテンツに「考察」ということばが入っているのをよく目にします。かつてであれば、ここに入ることばは「批評」であることが多かったように思います。ですが、ここ最近では「いま批評は存在できるのか」とまで言われるほどに批評は低調です。
本稿では、読解に関連する二つの語である「考察」「批評」を比較して、現代における作品の読まれ方について考えてみたいと思います。もちろん、この二つの語は年代によっても大いに印象が異なるはずです。できればこうした議論がさらに盛り上がって、いろんな意見が読めるようになることを望んでいます。本稿がその一助となれば、幸いです。
紙幅の都合でいきなり核心から入ってしまいますが、ここでは「考察家」という名称がいまだに定着をみていないことに注目してみましょう。対する批評においては、「批評家」という名称はごく自然なものです。この違いは、作品を論じるときの軸が作品にあるのか、それとも論じる人間にあるのか、という点に起因しているように思われます。
考察の中心にあるのは、主として作品中の事実(たとえば「実はこの台詞は……」というようなもの)です。一方で批評の中心は、それを語る論者自身が抱いた主張にあるように思われます。「批評とは竟に己の夢を懐疑的に語ることではないのか」という小林秀雄のことばを、まったく無視できる批評家はいないはずです。
では、こうした違いからどのような景色が見えてくるのでしょうか。それは、「この作品について自分はこう思う」という自分語り的な口調よりも、「実はこの作品はこうなんですよ」といったような正解めいた語り口のほうが受け入れられやすい、という風潮です。こうした風潮の要因としては、身を入れた意見を語ろうとすると「思想が強い」ということばで議論を避けられたり、批評がハイコンテクストなことばかり論じるために基本的な事実の確認を蔑ろにしていたり、作品のほうが消費的な態度を歓迎していたりと、いろいろなものが挙げられるでしょう。
もちろん、事実の確認は作品の読解において基本中の基本ですから、この部分がより丁寧になされるようになっていることは、かなり好ましい傾向だと思っています。しかしながら、考察コンテンツをいくつも漁っていると、そのうち「だから何なの?」という気持ちにもなってきます。「自分にとってこの作品を読むとはどういう意味があるのだろう」という問いが抜け落ちたまま、とめどなく細部の考察ばかりが生産されていき、果てにはちょっと陰謀論めいた無理が垣間に見えるようなことになっていることもしばしばです。
考察と批評の両方がなければ、もっとも楽しいはずの作品との深い対話ができないと私は思っています。先にあげたさまざまな外的要因についても考える必要がありますが、ひとまず本稿で述べてきたような姿勢を抜きにして、よりよい作品の読解はなされないのではないかと、今の私はそう考えています。さて、今のあなたから見て、考察と批評はどのようなものと映っているでしょうか?
──────────────────
第三回シンポジウム
【2025年12月17日(水) 19:00-20:30】
「“文学新人賞”ってなんだ?! ~自作を(社会の中で)発表するということ~」
毎年、小説創作を本気で志すひとの数は、年間およそ五万人、といわれています。このうちで、各種の文学新人賞などを獲得してプロ作家になるのは、ほんのひと握り。真剣に作家を目指そうとすればするほど、その事実上の登竜門となっている「文学新人賞」を獲得するために、いったい「何を」「どのように」書くべきなのか、思い悩んだ末に袋小路に入ってしまう、というひとも、決して少なくないようです。 今回のシンポジウムでは、昨今の文学賞なるもののありよう、そして今後どうなってゆくのかを、ともに考えます。新人賞出身作家や、新人賞の選考の専門家も集まって、その経験を語り、いかにすれば評価されうる作品が書かれうるのか模索を試みます。これからの世の中において、自らが構想し書き上げた作品をプロとして発表するということが持つ可能性を探究します。 また一方で、ネットやSNSなどの手立てが著しく発達した現在、どうすれば自作を今の世の中で発表できるのか、その具体的な方策についてもともに考えます。 もしかすると、これまでとは大きく違い、今後はこの「新人賞」なるものを経由せずとも、続々とプロ作家が誕生するような時代が到来する(*あるいはすでに到来している?)、のかもしれません。 完全オンラインで学べる「大学院文芸領域」のカリキュラムや学びの実際についてもご紹介しつつ、今、この時代に文芸創作なるものに取り組もうという志を持つすべての方のための、他ではなかなか触れることのない実践的な情報共有の場となるよう、力を尽くします。
登壇者一覧)
*池田雄一(文芸評論家/本領域教員、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*辻井南青紀(小説家/本領域長、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*山本隆博(コピーライター/本領域教員、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*岡英里奈(小説家・編集者/本領域非常勤教員)*佐藤述人(小説家/本領域非常勤教員)*久村亮介(文学研究者/本領域非常勤教員)
司会進行)
⁕辻井南青紀(作家・文芸領域長・「クリエイティブライティング」ゼミ指導教員)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
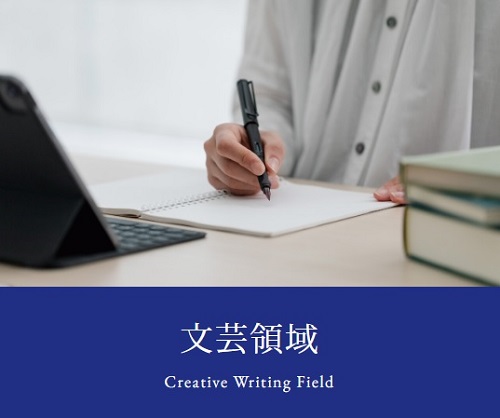
入学すると、一学年にひとつの「クリエイティブライティング・ゼミ」に入り、その中にある3つの専門性の高い指導グループのうちのどれかに所属します。
●クリエイティブライティング・ゼミ
小説などの物語創造や評論、エッセイ、コラムなどのテクスト、あるいは社会に向けて自身の思いを発信する活動など、さまざまなジャンルを横断的に学び、実践できる仕組みがあります。学びと創造の取り組みを可能な限り自由にするために、前期や後期など期ごとにゼミ内グループを移動することも出来ます。特定の分野やジャンルのみならず、大学院の二年間のうちいろいろな言葉の表現に触れ、実力をつけることが出来る機会があります。
おすすめ記事
-

通信制大学院
2025年11月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「ここにシャレあり」(新保 博久)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回はミステリー評論家の新保 博久さんのコラムをご紹…
-
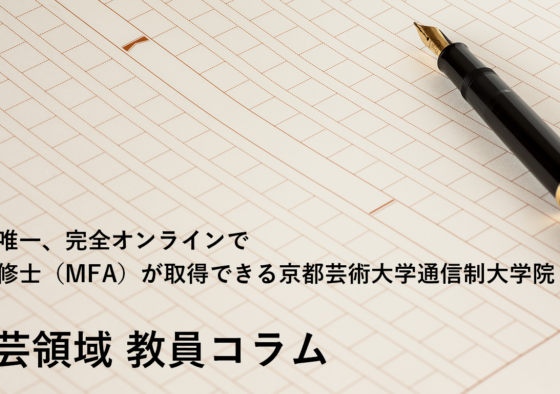
通信制大学院
2025年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「見失いがちなこと」(岡 英里奈)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家、編集者の岡 英里奈さんのコラムをご紹介し…
-

通信制大学院
2025年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「いまさら書こうとする人へ」(山本 隆博)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回はコピーライターの山本 隆博さんのコラムをご紹介…






























