

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「ここにシャレあり」(新保 博久)
2025年11月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「ここにシャレあり」(新保 博久)
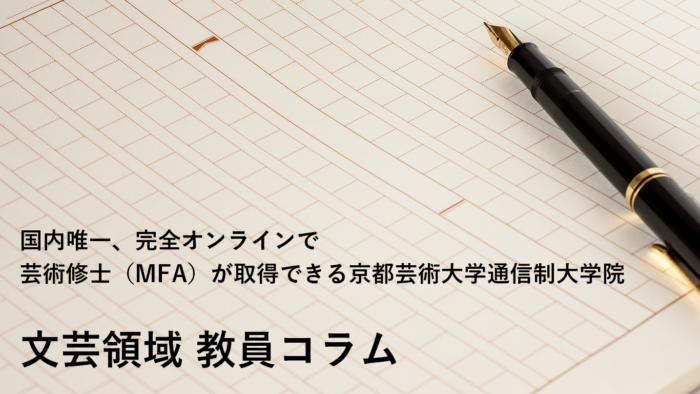
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回はミステリー評論家の新保 博久さんのコラムをご紹介します。

【新保 博久】(しんぽ・ひろひさ)
1953年、京都市生まれ。早大文学部卒。ミステリー評論家。江戸川乱歩賞、横溝正史賞、日本推理作家協会賞などの予選委員・本選委員を歴任。師事する権田萬治との共同監修書『日本ミステリー事典』で受賞した本格ミステリ大賞を、2025年に『死体置場で待ち合わせ 新保博久 法月綸太郎 往復書簡』で再度受賞したほか、『横溝正史自伝的随筆集』『シンポ教授の生活とミステリー』など編著書多数。近刊に『シンポ教授のマジカルミステリー劇場』(2026年1月文庫化予定)がある。京都芸術大学通信制大学院文芸領域・非常勤講師。
「ここのシャレあり」
所有者が書き込んで汚くなった古本は嫌われて当然だろう。よほど珍しくて、どんなに汚くても読みたいという読者しか欲しがるまいし、だいたい古書店主が買い取りを拒みそうだ。それでも、書き込みは喜ばれる場合がないとは限らない。
たとえば大学の教科書に指定された図書で、先輩が試験のヤマを張るのに重点箇所にアンダーラインを施してくれたりしていると、新本より役に立つ。時には「ここにシャレあり」と注記されている。教授の講義が教科書のその箇所にさしかかるとダジャレが飛んでくるので落シャレ注意という警告だ。その注記がある本来の印刷された記述から、どんなダジャレか事前予測もできるだろう。だが、どんなに寒くとも受講者が礼儀正しく笑ってあげないと、教授の機嫌をそこねかねず、ひいては成績に響く。十年一日、同じ箇所で飛ばしてきたダジャレを笑われては(いや、笑ってもらえなくては)教授のプライドが傷つく。
ところで「ここにシャレあり」というのが、そもそも「ここに幸(さち)あり」のモジリなのだ。若い人には「ここに幸あり」がわからないだろう。メロディくらい誰にも聞き覚えがありそうだが、結婚式でのお祝いソングとしてはすでにレッドリストに入っていいるのでは。長寿社会で、教える側と教わる側との世代差も広がっている。学ぼうとするかたがたのご協力を期待したい。
──────────────────
説明会情報
【2025年11月13日(木) 19:00-20:30】
「文芸領域=『クリエイティブ・ライティング』 ~その新しい可能性~」
大学院で、それも通信教育(完全オンライン)で、広義の「文芸」分野について、専門的に学び、創作や制作に深く打ち込める、本学大学院「文芸領域」。2023年度創設から現在に至るまで多くの優れた学生が学びと創作に打ち込み、昨年度、初の修了生を輩出しました。 これまでは、小説など物語創作、また編集制作など、ことばの表現の各ジャンルを専門的なレベルまで深めて学ぶという特性がありました。 次年度からは、既存の「文芸」ジャンルを今一度「ことばの表現」全般ととらえ直して、新しいゼミ指導体制、「クリエイティブ・ライティング」ゼミがスタートします。 従来の小説や物語の創作、編集制作といったわたしたちの専門ジャンルをより高め、深めるのみならず、専門性の「垣根」をなるべく取り払い、学生のみなさんが在学中に多様なジャンルに触れ、さまざまな学びと創作・制作を深化させられる新たな仕組みとなります。 非フィクション系の多様なテクストを社会に向け、SNSなどを通じて発信を行いたい、けれどそのために何をどうすればよいのか、とお悩みの方々にとっても、意義ある学びの場となるよう、力を尽くします。
登壇者一覧)
■指導担当者
⁕山本隆博(コピーライター・「クリエイティブライティング」ゼミ指導教員) ⁕あわいゆき(書評家・非常勤講師) ⁕新保博久(ミステリ評論家・非常勤講師)⁕石戸谷直紀(編集者・非常勤講師)
司会進行)
⁕辻井南青紀(作家・文芸領域長・「クリエイティブライティング」ゼミ指導教員)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
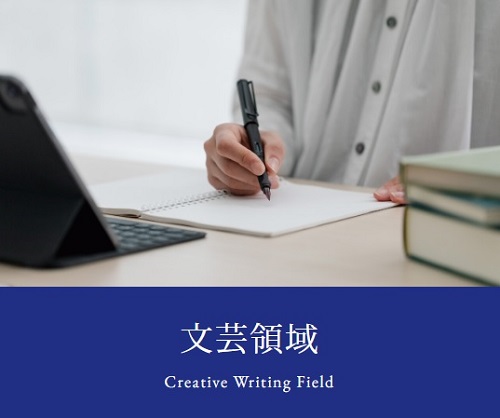
入学すると、一学年にひとつの「クリエイティブライティング・ゼミ」に入り、その中にある3つの専門性の高い指導グループのうちのどれかに所属します。
●クリエイティブライティング・ゼミ
小説などの物語創作や評論、エッセイ、コラムなどのテクスト、あるいは社会に向けて自身の思いを発信する活動など、さまざまなジャンルを横断的に学び、実践できる仕組みがあります。学びと創造の取り組みを可能な限り自由にするために、前期や後期など期ごとにゼミ内グループを移動することも出来ます。特定の分野やジャンルのみならず、大学院の二年間のうちにいろいろなことばの表現に触れ、実力をつけることが出来る機会があります。
おすすめ記事
-

通信制大学院
2022年11月24日
【通信制大学院】新文芸領域のPR短編映画『トンネルの先』『トンネルの中へ』について
新しい文芸大学院でこれから学ぶかもしれない方々と、おそらく同じ志を掲げ、同じ心意気で、映像による「物語」を作っている若い人たちがいます。 京都芸術大学芸術学…
-

通信制大学院
2025年11月04日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「円滑さから離れた贅沢な言葉へ」 (佐藤 述人)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家の佐藤 述人さんのコラムをご紹介します。 …
-

通信制大学院
2025年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「心地いい銭湯」(あわい ゆき)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は書評家、ライターのあわい・ゆきさんのコラムをご…






























