

通信制大学院
- 通信制大学院 記事一覧
- 【通信制大学院】文芸領域教員コラム「オープンダイアローグと〈創造の病〉」(池田 雄一)
2025年11月22日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「オープンダイアローグと〈創造の病〉」(池田 雄一)
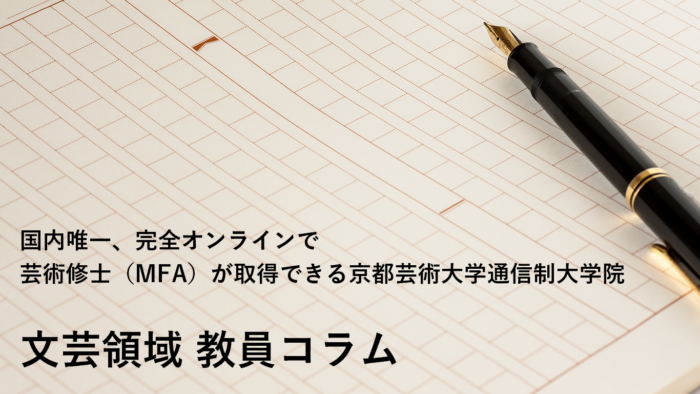
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。
今回は文芸評論家の池田 雄一さんのコラムをご紹介します。
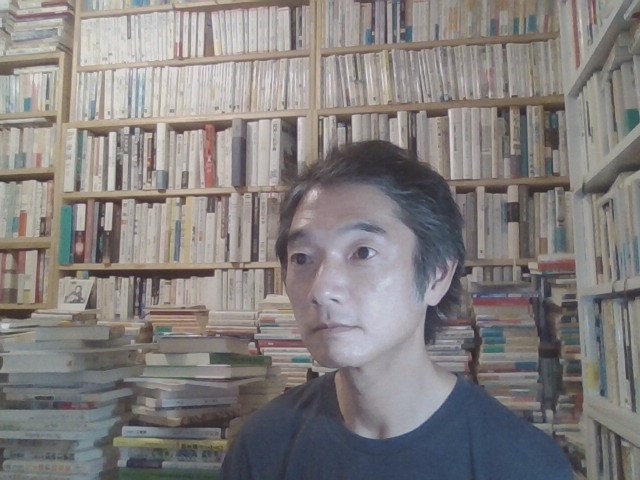
【池田 雄一】(いけだ・ゆういち)
1969 年、栃木県鹿沼市生まれ。 1994 年に「原形式に抗して」により、第 37 回『群像』新人文学賞の評論部門を受賞。文芸評論家として、批評、書評、文芸時評などを執筆。著書に『カントの哲学ーシニシズムに抗して』(河出書房新社)、『メガクリティック―ジャンルの闘争としての文学』(文藝春秋)がある。また共著に『思想としての 3.11』(河出書房新社)、『戦後思想の再審判―丸山眞男から柄谷行人まで』(法律文化社)などがある。これまでに早稲田大学、東京工業大学、東京大学、法政大学、武蔵野大学などで非常勤講師を、 2013 年から 2017 年にかけて東北芸術工科大学にて准教授をつとめる。現在は、京都芸術大学大学院にて特任教授をつとめている。
オープンダイアローグと〈創造の病〉
オープンダイアローグとは、1980年代のフィンランドで始められた、統合失調をはじめとした精神疾患の治療を目的とした、クライアントと治療者をふくめたチームのなかでの対話による方法である。最近はメディアにもとりあげられているので、この名称を聞いたことのある人もいるだろう。
フロイトからの精神分析の展開に詳しい人なら、統合失調症が対話などで治療できると聞いたら仰天するはずである。精神分析によって治療できるのは、強迫神経症、不安神経症など、いわゆる神経症に属する病である。統合失調症、躁うつ病、といった精神病系の病は、薬物による治療にたよる他ない。精神分析に関連する本には、例外なくそのようなことが書かれているからである。
さらに驚くことには、この方法は、デリダやフーコーやバフチンといった、いわゆる「現代思想」から影響を受けて開発されたのである。しかもこの方法は、すでに精神病の治療でエビデンスのある実績をあげているのである。
オープンダイアローグが採用している方法とは何なのか、かんたんにまとめてみよう。
●複数の治療者、クライアント、クライアントの家族などからなる「チーム」が編成される。場合によっては薬剤スタッフも入る。クライアントからの要請があったら、連絡を受けたものが24時間以内にチーム編成して、症状が安定するまで持続的に対話を実施する。
●対話の主体は「はい/いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、開かれた質問をこころがける。たとえば「あなたのお祖父さんがこの場にいたら、どのようなことを話すと思いますか」などである。
●治療者はクライアントの発信を妨げたり、分析したりしない。アドバイスもしない。妄想のような発言も受け入れる。
●本人のいないところで、クライアントの話をしない。
●あわてて診断しない。不確定な状況を受け入れる。
●治療の対象は、クライアント本人ではなく、治療者もふくめた、チーム全体である。
ここで注目したいのは、精神病で発現する「妄想」もまた、ここでは否定されたり修正されたりすることなく、チーム全体がそれを受け入れて積極的に聞き出すことが提唱されていることである。このような方法にかんして、わたしが即座に思いだしたのは、中井久夫『治療文化論』で紹介されている、天理教の教祖である「中山みき」のプロファイリングである。中井久夫は、江戸末期から明治初期にかけてという時代の転換期に、何人かの女性たちが新宗教の教祖となる事象についての考察を展開している。
女性たちはのきなみ、家族たちの困難を一身にひきうけて、不眠不休による超人的な労働力を発揮した後、覚醒し、開祖となる。こうした過程を、中井はエレンベルガーの言葉を採用して「創造の病」と呼んでいる。そのなかのひとり、中山みきは自らを「天理王命」と名のって、家族にも自分を天理王命としてあつかうように命じたのである。面白いことに、この家族は、みき当人を病人ではなく、「天理王命」として遇している。
最初に対話に入ったのは、みきの夫である。このことにより、中山みきが主体の「チーム」が編成されることになったのである。規模の違いはあるが、日本の近代初期には、新宗教の創立のほかにも、こうした事例があったはずである。新宗教の場合は、あらたなる世界認識が創造される。それとおなじく、小説などの芸術においても、あらたなる世界の認識枠組みが立ち上がる。こうしたことから、オープンダイアローグの方法を創造系のゼミで応用できないかと、画策しているところである。
──────────────────
第三回シンポジウム
【2025年12月17日(水) 19:00-20:30】
「“文学新人賞”ってなんだ?! ~自作を(社会の中で)発表するということ~」
毎年、小説創作を本気で志すひとの数は、年間およそ五万人、といわれています。このうちで、各種の文学新人賞などを獲得してプロ作家になるのは、ほんのひと握り。真剣に作家を目指そうとすればするほど、その事実上の登竜門となっている「文学新人賞」を獲得するために、いったい「何を」「どのように」書くべきなのか、思い悩んだ末に袋小路に入ってしまう、というひとも、決して少なくないようです。 今回のシンポジウムでは、昨今の文学賞なるもののありよう、そして今後どうなってゆくのかを、ともに考えます。新人賞出身作家や、新人賞の選考の専門家も集まって、その経験を語り、いかにすれば評価されうる作品が書かれうるのか模索を試みます。これからの世の中において、自らが構想し書き上げた作品をプロとして発表するということが持つ可能性を探究します。 また一方で、ネットやSNSなどの手立てが著しく発達した現在、どうすれば自作を今の世の中で発表できるのか、その具体的な方策についてもともに考えます。 もしかすると、これまでとは大きく違い、今後はこの「新人賞」なるものを経由せずとも、続々とプロ作家が誕生するような時代が到来する(*あるいはすでに到来している?)、のかもしれません。 完全オンラインで学べる「大学院文芸領域」のカリキュラムや学びの実際についてもご紹介しつつ、今、この時代に文芸創作なるものに取り組もうという志を持つすべての方のための、他ではなかなか触れることのない実践的な情報共有の場となるよう、力を尽くします。
登壇者一覧)
*池田雄一(文芸評論家/本領域教員、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*辻井南青紀(小説家/本領域長、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*山本隆博(コピーライター/本領域教員、「クリエイティブライティング・ゼミ」指導担当)*岡英里奈(小説家・編集者/本領域非常勤教員)*佐藤述人(小説家/本領域非常勤教員)*久村亮介(文学研究者/本領域非常勤教員)
司会進行)
⁕辻井南青紀(作家・文芸領域長・「クリエイティブライティング」ゼミ指導教員)
↓説明会の参加申し込みは文芸領域ページ内「説明会情報」から!
▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 文芸領域ページ
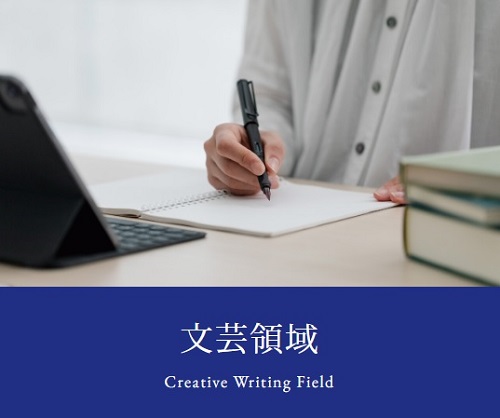 入学すると、一学年にひとつの「クリエイティブライティング・ゼミ」に入り、その中にある3つの専門性の高い指導グループのうちのどれかに所属します。
入学すると、一学年にひとつの「クリエイティブライティング・ゼミ」に入り、その中にある3つの専門性の高い指導グループのうちのどれかに所属します。●クリエイティブライティング・ゼミ
小説などの物語創作や評論、エッセイ、コラムなどのテクスト、あるいは社会に向けて自身の思いを発信する活動など、さまざまなジャンルを横断的に学び、実践できる仕組みがあります。学びと創作の取り組みを可能な限り自由にするために、前期や後期など期ごとにゼミ内グループを移動することも出来ます。特定の分野やジャンルのみならず、大学院の二年間のうちにいろいろなことばの表現に触れ、実力をつけることが出来る機会があります。
おすすめ記事
-

通信制大学院
2025年11月11日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「ここにシャレあり」(新保 博久)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回はミステリー評論家の新保 博久さんのコラムをご紹…
-
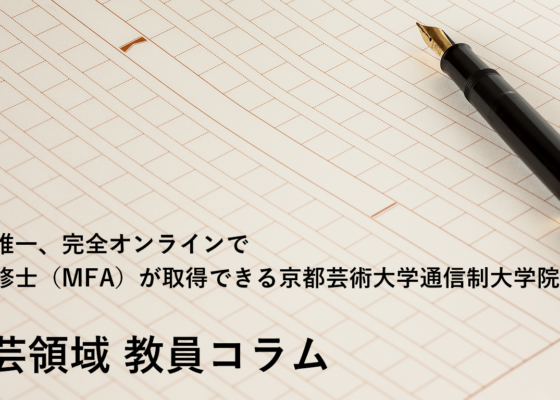
通信制大学院
2024年10月21日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「読まれる恐怖の先にあるもの」(作家 藍銅ツバメ)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は作家の藍銅ツバメさんのコラムをご紹介します。 …
-
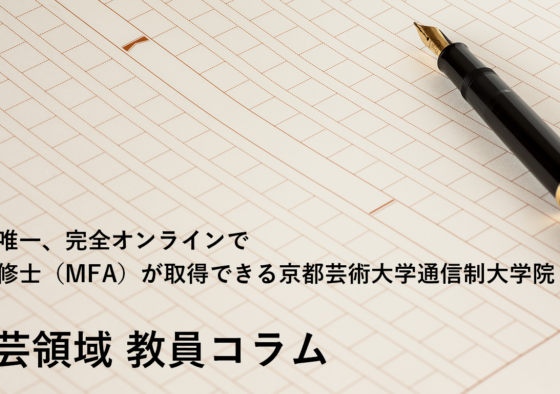
通信制大学院
2025年11月25日
【通信制大学院】文芸領域教員コラム「なぜ『考察家』は定着しないのか?」(久村 亮介)
文芸領域への入学を検討されている「作家志望者」「制作志望者」に向けて、本領域の教員がコラムをお届けします。 今回は文学研究者の久村 亮介さんのコラムをご紹介しま…






























