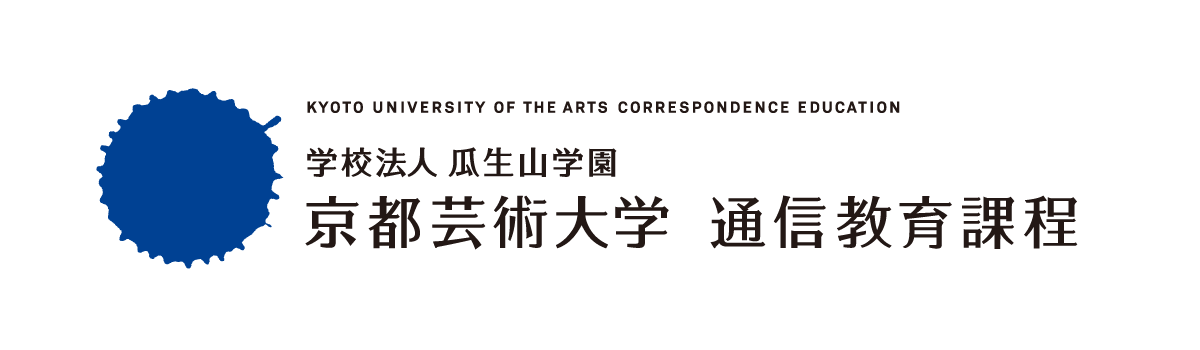アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「BBは倒錯的でも、反抗的でもなく、不道徳でもない。それだから道徳は彼女には通用しない」 ―― シモーヌ・ド・ボーヴォワール「ブリジット・バルドーとロリータ・シンドローム」1959年
2026年01月07日
【アートライティングコース】「BBは倒錯的でも、反抗的でもなく、不道徳でもない。それだから道徳は彼女には通用しない」 ―― シモーヌ・ド・ボーヴォワール「ブリジット・バルドーとロリータ・シンドローム」1959年
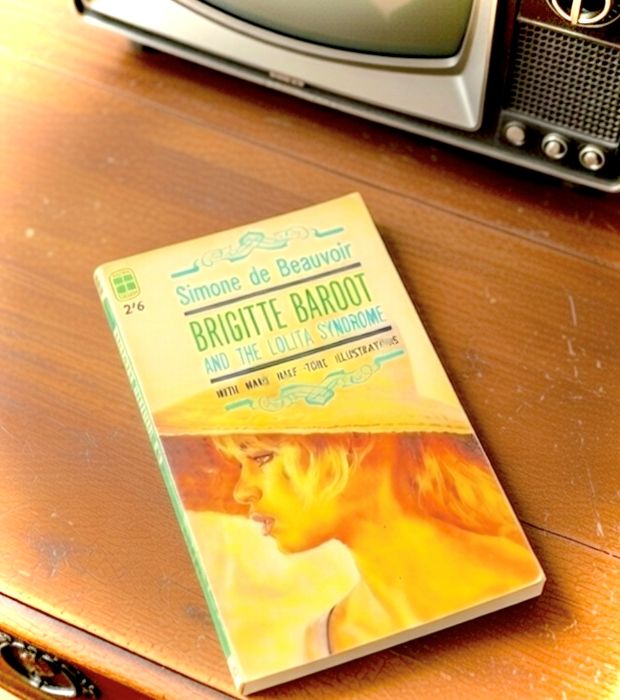
みなさま、明けましておめでとうございます。アートライティングコースの教員、上村です。みなさまはどのような年をお迎えになったでしょうか。
年々同じような正月ではありますが、年々同じようなことを繰り返せるというのはまことにありがたいことです。型通りのお参りや挨拶、紋切り型のお祝いの言葉や定番の食事など、何かと不安で行方も知れぬ世界でいつもどおりの暮らしを願うというのは切実なことです。人生行事や年中行事に限らず、紋切り型の振る舞いは日々の暮らしにおいても大事なもので、それは行為を自動化することによって、他事に煩わされることなく特定の仕事にかまけるための時間稼ぎをしてくれます。しかしまた、年々人も世の中も変わっていきますので、同じことのように見えて、完全に同じことは繰り返せません。繰り返すこと自体が目的化すると、やがて行事のありがたさは薄れ、日常の行為の意味も忘れられます。紋切り型もそらぞらしくなり、そうなると、あらためて時代にあった次の「型」が必要になります。日々の行為のなかには日々の認識行為も含まれます。月なみなものの見方、紋切り型の語り口が大雑把に世界を認識させてくれるからこそ、情報過多に陥らず、特定の対象に知覚を集中させることが可能になります。しかしまた、これは便利な反面で、その大雑把に習慣化された世界像だけにとどまってしまうおそれもあります。先入観、決めつけ、レッテル貼りは別に「パヨク」や「ネトウヨ」の得意技ということではありません。人間にとってはどうしても避けがたい宿業のようなもので、そうした紋切り型の像に囲まれることではじめて、切迫した生活のなかに安住の地を得ることができます。しかしその安住の地はそもそも現実ではなく、また移ろいやすい人の世にとっては永住の地でもありません。頼りがいある紋切り型ではありますが、そこからどこかで距離を置いておかないと、夢の中で他者を審判する愚に陥るでしょう。
(おそらく1958年の)大晦日の晩に、シモーヌ・ド・ボーヴォワールはテレビを前にしていました。といっても、この50歳の哲学者で、フェミニズムの理論家が観ていたのは、もちろん紅白歌合戦ではありません。テレビに映っていたのは、セーターを着てジーンズを身に着けたブリジット・バルドー(BB)です。このときBBは24歳、10代から雑誌モデルを務めたのち、女優となっていた彼女は、18歳で結婚した相手のロジェ・ヴァディムが監督した『素直な悪女』Et Dieu… créa la femmeで男性を翻弄する女性を演じて話題になります。そして私生活でもこの映画で知り合った俳優トランティニャンと不倫してキャンダルとなっていました。映画が評判になったのも、いろんな男性たちが彼女に惹かれたのも、彼女の美しい容貌や姿態が大きな要因です。しかしBBは単に魅力的な女性というだけではなかったようです。とりわけフランスでは人々から好かれているというより、顰蹙を買っていました。大晦日の晩、ボーヴォワールはテレビを前にして、BBがどうして悪評なのかを考えはじめます。ブリジットはソファーにくつろいでギターを爪弾いていました。ボーヴォワールはフランス人の視聴者の反応を想像してこう書きます。
「大したことはないわ」と女性たちは言った。「私だってそれぐらいできる。彼女は可愛くもない。女中のような顔をしてる。」男たちは彼女から貪欲に目を離せられないが、彼らもまたせせら笑った。観客が30人ほどなら、そのうちわずか2,3人が彼女を魅力的と考えた。彼女がクラッシクのダンスを披露すると、他の大勢は「彼女は踊ることもできるんだ」と渋々認めた。
スクリーンでは肉感的で危険な女性を演じ、実生活でも数々の男性たちと浮名を流したBBは、典型的なセックス・シンボル、男を堕落させる悪女という紋切り型で捉えられ、人目を集めはするものの、決して好意的な目で眺められていたわけではなかったようです。ボーヴォワールはそれに対して疑問を呈し、女性がなぜ、どのように評価されるのかを考察します。アメリカ合衆国の雑誌 Esquire に寄稿した(そのためフランスに比べ若干アメリカに好意的な表現が見られます)エッセイ「ブリジット・バルドーとロリータ・シンドローム」は、スクリーンで描かれる女性像についての分析にもなっています。昔のヴァンプ(吸血鬼のような女性)女優たちに取って代わり、1930〜40年代にかけて、友人のような女性像がもてはやされますが(例えばジーン・アーサー)、大戦後には再びエロティックな女性像が復活します。ただしかつてのヴァンプではなく、もっと直接に女性的な身体の曲線美を強調します。マリリン・モンロー、ソフィア・ローレン、ジーナ・ロロジリブーダといった女優が人気を博します。しかし映画界はそうした成熟した女性に代わって、さらに新たなタイプを生み出します。未成熟で、また大人から手の届かない距離を持つ「こどもとしての女性」femme-enfant がそれで、ナボコフの『ロリータ』が評判になったのも同時代です。ボーヴォワールはオードリー・ヘプバーン、レスリー・キャロンらと並んで、BBも「エロティックなおてんば娘」の典型として挙げます。この「こどもとしての女性」は「青い果実」と「運命の女」(ファンム・ファタール)を結合した「新しいエヴァ」です。「BBを背後から見ると、痩せており、筋肉質で、ダンサーの体つきで、ほとんど両性具有的である。女性らしさが勝ち誇っているのは、彼女のわくわくするような胸においてである。」こうした新しい女性像は、計算高く男性を魅惑する女性とは異なり、自然らしく、純粋に見えます。ボーヴォワールはここで大事な指摘を行います。BBに与えられた役柄には、ある面では慣習的な価値観が認められると。子どもとしての女性の自然さ、未熟さは、直され、矯正されることができるものとされています。幼く、無知な女性が過ちを犯し、常識はずれなこと、不謹慎なことをしたとしても、それは何かしら不幸な境遇のもたらした無思慮のせいであり、大人の男性は女性を許し、躾けることができる、というものです。しかし、ボーヴォワールはそうした既成の価値観は映画の観客はもう信じないとも言います。『素直な悪女』でBB演じるジュリエットは、模範的な妻や母にはなりようがありません。「無知や未経験は改善することができる」としても「BBは単に洗練されていないのではなく、危険なまでに真剣」なのです。BBは正すべき道徳的な欠陥があるのではありません。コケティッシュに計算高い悪女であれば、高潔な女性や男性たちはあっさり断罪するだけでしょう。しかし「悪」が純真な姿をとるなら、彼ら彼女たちは激昂します。そうした純真さ、無邪気さは自分たちの手に負えないからです。BBは正直に自分でいるだけです。冒頭に引用したとおり「BBは倒錯的でもなく、反抗的でもなく、不道徳でもない。それだから道徳は彼女には通用しない」のです。ボーヴォワールはエッセイのサブタイトルにある「ロリータ・シンドローム」を直接に説明してはいません。しかし、おそらくは、未熟で蠱惑的な少女を性的対象として追い求める男性の欲望だけを指しているのではないでしょう。そうした少女は、文化産業が新たな流行として作り出した女性像というより、従来の価値観にはそぐわない新たな女性の登場をも示しています。単に大人の言うことに従順な少女というのではなく、BBがまさに体現しているように、大人の規範から自由な存在です。「自由な女」は「軽い女」ではない、とボーヴォワールは書きます。性的に奔放だとしても、それは都合よく搾取されることではありません。BBは「恋愛のゲームにおいて獲物であると同時に狩人でもある」のです。「ロリータ」という語の指すものは、飼い馴らされる少女ではなく、むしろ自立した女性です(勿論、大人とは違うしかたで)。「ロリータ・シンドローム」とは、20世紀後半に男性たちがはじめて出くわした、蠱惑的でありながらも同時に理解不能で自分のものにすることのできない、自由な女性への複雑な欲求を指しているのでしょう。ボーヴォワールはもうすでに教科書的なフェミニズムの歴史に出てくる人物になったかもしれません。それまで自明のものとして与えられてきた女性の役割、男性中心の社会で従属的な存在として了解されてきた女性の立場の制度性を明らかにする、というと、今や誰しもできそうなことのように思えます。しかし彼女の書いたものをあらためて読んでみると、たとえばこのBBについてのエッセイでも、個々の演技や女優の肉体に向けられた具体的で犀利な観察眼に驚かされます。BBを単に肉体美を誇るセックス・シンボルとして危険視するのではなく、また彼女の純粋さを賞揚するのでもなく、はたまた男性の視線に迎合する女性として断罪するのでもなく、BBをとりまくスキャンダラスな噂、礼讃、非難に対し、社会の求めるさまざまな条件下で彼女がいかに行動したかを見定めます。知らず知らずに刷り込まれた紋切り型を見つめ直し、その枠にはまって思考することを反省するには、意志と知性が必要です。しかし、ボーヴォワールほどでなくても、少しの意志と知性で十分です。もっとも、それを使うには、やはり修練が要るでしょうけれど。
大晦日も近くなった晩、テレビを前にしていましたら、BBの訃報が流れてきました。正直なところ、まだ生きていたんだ、というのが最初の感想でした。しかし、女優としてほとんど関心を持っていなかったBBに興味を持つきっかけとなったボーヴォワールの文章を思い出し、この60年以上前のテキストをご紹介したいと思いました。機会があればBBの映画も見直したいものです。
* 添付の画像に写っている本は Simone de Beauvoir (translated by Bernard Fretchman), Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome, The New English Library, London, 1962。初出はアメリカの雑誌 Esquire, August 1, 1959、仏語版は Les Ecrits de Simone de Beauvoir, Gallimard, Paris, 1979 に所収。
おすすめ記事
-

アートライティングコース
2025年12月25日
【アートライティングコース】女が纏うタカラガイたちが語りかけてくるもの
こんにちは。アートライティングコース教員の大辻都です。 少し前ですが、国際芸術祭あいち2025「灰と薔薇のあいまに」を訪れました。芸術祭ということで一日ではまわ…
-

アートライティングコース
2025年11月18日
【アートライティングコース】「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」 ──『作り方を作る』佐藤雅彦
こんにちは。アートライティングコース非常勤講師の青木由美子です。 先日、横浜美術館で開催されていた『佐藤雅彦展』新しい×(作り方+分かり方)を観てきました。創作…
-
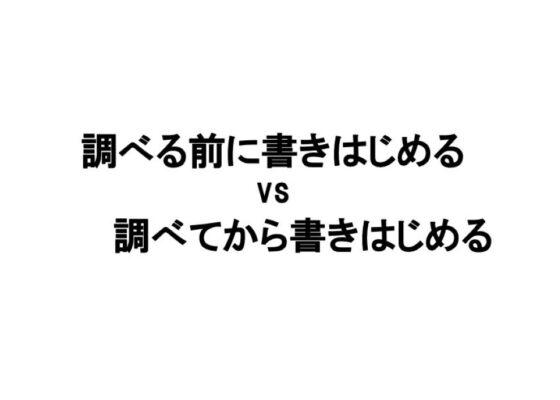
アートライティングコース
2025年10月03日
【アートライティングコース】調べる前に書きはじめるvs調べてから書きはじめる
こんにちは。教員の小柏裕俊です。 アートライティングとは「芸術や文化を対象として文章を書く行為、そのようにして生まれた文章」のことです。その対象は一つの芸術作品…