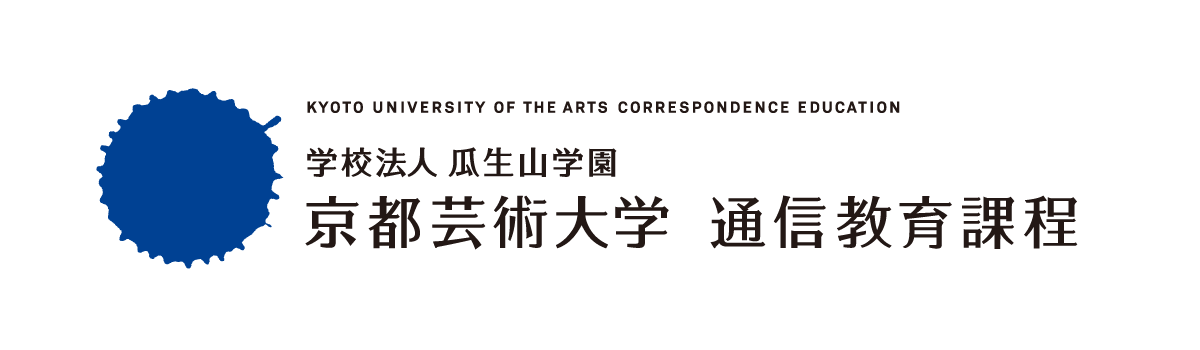文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】物語を通して、読者とイメージを共有する
2026年01月16日
【文芸コース】物語を通して、読者とイメージを共有する

文芸コースの麻宮ゆり子です。先日、20代前半くらいの男性から「どうして小説家になろうと思ったんですか?」という質問を受けました。その方は小説を読むのが好きで、将来は小説家になりたいと思っている、という青年でした。今回はそのときのやりとりをきっかけに、私自身があらためて考えたことについて書いてみたいと思います。
その方はいわゆる文豪といわれる人の小説からライトノベルまで、いろいろな本を読んでいるようでした。ただ、私とは二十以上歳が離れています。そんな彼に対して、どう答えればうまく伝わるだろうかと、私は少しの間考え込んでしまいました。そもそも「なぜ小説家になろうと思ったのか」なんて私にとっては、一言でいえるようなものではないからです。
私は二十年以上前に小説の新人賞を獲っていますが、それから今日まで小説家として順調にやってきた……というわけではありません。一度プロとしての名前が消え、再度「小説家になろう」と新人賞を獲る必要に迫られるなどの紆余曲折を経て、現在に至ります。しかしそんなことをまだ若い彼に言っても混乱するだけだろうと思い、ひとまず「自分の読みたい作品を誰も書いてくれなかったから、自分で書く方が早いと思ったんだと思うよ」と伝えました。
しかし彼の反応は「ふうん」という、どこか腑に落ちていない様子でした。そこで私はもう一つ付け加えてみました。「あと、自分の中に見える映像を、小説の中に描くことで、それを読者に伝えたいと思ったからかな」
すると彼はすぐに「だったら、最初から映像を作ればいいんじゃないですか」と返してきました。
そこで思わず私は、「おお……」と声を洩らしてしまいました。確かにそういうものの見方もできるからです。
実は、これらのやり取りの前に彼は「まだ自分の小説を最後まで書き上げたことがない」と話していました。さらに「自分の文章を読み返すのが苦手だ」とも言っていて、つまり自分で書いた小説を完成させ、他人に読んでもらった経験がないようでした。
彼はとても頭のいい青年です。自分の言葉で小説を書いて、それを他人に読んでもらうことの怖さを、すでにきちんと感じ取っている。だからこそ「自分の文章を読み返すのが苦手」と感じ、自ら「まだ他人に読ませることができない段階」に踏みとどまってる、と言えるのかもしれません。
かつての私も、彼と同じでした。それに今だって少しでも油断をすると「文章を書いて発表するのが怖い」という感覚に戻ってしまうことはあります。
そして今振り返ると、私が使った「映像」という言葉も、やや誤解を招きやすかったのかもしれません。むしろ「自分の中に見えたり聞こえたり、てざわりのようなものが感じられるイメージを、小説の中で表現し、それを読者と共有したいから」という言い方のほうが、より正確だった気がしています。
小説を書く際には物語の流れに沿って、人物の姿や、その人物が抱く心の風景、そして場面ごとの空気や景色などを読者に伝わるように描写する必要があります。この描写によって、読者は「その作品の場に立っているような感覚」を得ることができます。そのためには物語の流れも含め、作者自身がさまざまなイメージを明確に持ち、それを思い描きながら書くというのが大切です。
しかし学生の小説を読んでいて、たとえば、そういったものが「よく見えてこない」と感じることがあります。そのとき私は、「作者に見えていないものは、読者にも見えてこないんですよ」と学生には伝えています。この「見えていないもの」はやはり、はっきりとした「映像」というよりも、無数の点が関連し徐々に像を結んでいく「イメージ」に近いものです。
20代前半の彼はライトノベルをよく読むと言っていましたから、「映像」と聞いて、もしかしたらアニメーションのようなものを思い浮かべたのかもしれません。しかし純文学や中間小説などで作者が描こうとするのは、人物の目鼻立ちや小道具を細部まで固定した映像ではなく、あえて読者の想像が入り込む余地を残した「イメージ」なのだと思います。
するとそのイメージは読者に伝わって──そこで不思議なことが起こります。
作者のイメージを受け取った読者は、そこへ自分自身がつながる「個人的(集合的)な無意識の領域」にあるイメージを重ね、作品の世界をさらに広げてくれるのです。
たとえばAという場所を舞台にした、Bという人物が出てくる小説があるとします。読者は、「Bを演じるならこの俳優しか考えられない」と思ったり、「私は別の俳優を思い浮かべた」と感じたり、「Aはあの街がモデルだろう」「いや、別の街の方が近い気がする」とさまざまな想像をします。こういった作者の予想を超えた無数の「想像の声やイメージ」が作品に付与されていくのです。
だから小説が映像化されると、「この配役はイメージ通りだった」「うーん、何だか私の中のイメージと違う」という声が必ず発生します。映像作品が一つの像しか提示できないのに対し、小説に込められたイメージは、100人の読者に対し100通りの姿で受け取られ、広がっていく。そこに小説ならではの特性があるのでしょう。
ちなみに私の小説には、「斎木くん」という少し変わった人物が登場する物語があります。この、本になる前の原稿を読んだ編集者から「斎木さんは、こんなことはしないと思います」「やっぱりこういう言い方はしないのではないでしょうか?」と、はっきり指摘を受けたことがあり、私はとても驚いた経験があります。これなんて、まさにその好例ではないでしょうか。「斎木くん」を最初に創ったのは私です。しかし、作品が作者の手を離れた瞬間から、彼のイメージは読者一人ひとりの中で別々に育ち始め、そして最終的にはそれぞれの読者が抱く「斎木くん」になっていくのです。
こうした経験は、実際に小説を書き上げ、誰かに読んでもらった人にしか味わえないものです。なおこの現象は、大学に提出された学生の作品の中でも、確かに起こっています。
たとえばイメージがよく伝わってくる作品については、「読んでいたら、こんな絵が見えてきました」「主人公は、この俳優を思い浮かべながら読みました」と、私は自分が感じたことを学生にそのまま伝えています。するとたいていの学生は、「へえ……」と非常に驚いた表情を見せてくれます。
そう、学生の作品は、すでにそれを読んだ私の中で、「学生と私の共同作品」のように、新たなイメージの世界を育んでいるのです。
だからこそ20代前半の彼にも、いつか小説を書き上げる怖さを乗り越えて、できれば見知らぬ誰かに読んでもらい、その反応を受け取りながら、作品の世界が広がっていく驚きと楽しさを知ってほしいと思っています。
小説は基本的に一人で書くものです。けれど最終的には、読者と共有することで、まったく新たなイメージの形を獲得していく──そんな表現ができるのかもしれません。
文芸コース| 学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
おすすめ記事
-

文芸コース
2025年12月15日
【文芸コース】セザンヌの静物画のような文章を書きたい
セザンヌの描くリンゴを、私は私の言葉で書いてみたい。 このところ、強くそう思う。私が私自身の創作のために許す時間は、だいたい夜の10時以降。5歳の息子の寝かしつ…
-

文芸コース
2025年11月17日
【文芸コース】年末は100均で手帳を買おう!──長編小説を最後まで書き上げるために──
文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は「どうすれば長編小説を最後まで書き上げられるのか」というテーマでお話したいと思います。 ここでいう長編小説とは、400字詰原稿…
-

文芸コース
2025年10月17日
【文芸コース】文芸表現における「ポートフォリオ」って、どうつくればいいんだろう?
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 芸大生の就職活動に切っても切り離せない存在である「ポートフォリオ」。デザインやファインアートを学んだ方のもの…