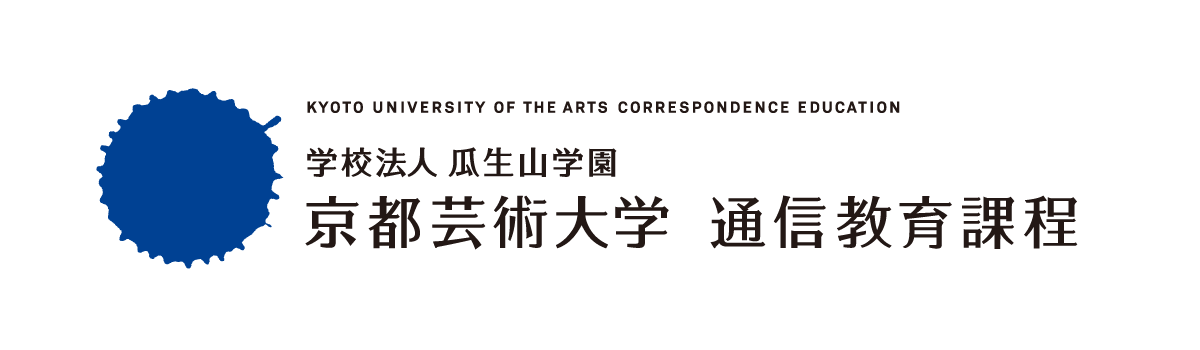文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」
2019年02月08日
【文芸コース】特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」
文芸コース主催の特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」が1月19日(土)の午後5時30分から、東京・外苑キャンパスで開かれました。講師は、作家で季刊総合誌『考える人』と月刊『芸術新潮』の元編集長だった松家仁之(まついえ・まさし)さんです。
会場となった203教室には、開演前からたくさんの人たちが集まり、満員の盛況となりました。

講義では、トルーマン・カポーティの『冷血』と、松家さんの短篇「眠る杓文字(しゃもじ)」(『文学界』2018年8月号掲載)の2作品を取り上げ、小説の具体的な創作方法などをお話ししました。
講義の前半は、『冷血』についてです。『冷血』は、米カンザス州の片田舎で起きた一家4人惨殺事件を題材にした作品で、幼なじみの作家ハーパー・リーの協力を得ながら精力的に取材を進め、5年あまりの歳月をかけて完成させたカポーティの代表作のひとつです。
松家さんは、映画『カポーティ』の映像(冒頭の13分間)も使い、カポーティ自身が<ノンフィクション・ノヴェル>とよんだ『冷血』がどのような経緯で書かれることになったのかをくわしく説明しました。

後半は、短篇「眠る杓文字」について語りました。
たまたま広島の平和記念資料館を訪れたときに、本館の下から発掘された黒焦げの「杓文字」の写真を見たことが構想のきっかけでした。
資料館の下の土の中に60年間にわたって眠りつづけてきた杓文字に触発された物語ができあがるまでの間、どのような取材をおこない、取材協力者にはどのような対応をしたのか。登場人物「先生」のモデルとなった建築家・丹下健三の話も盛り込みながら、作品完成までの経緯を具体的にお話しされました。
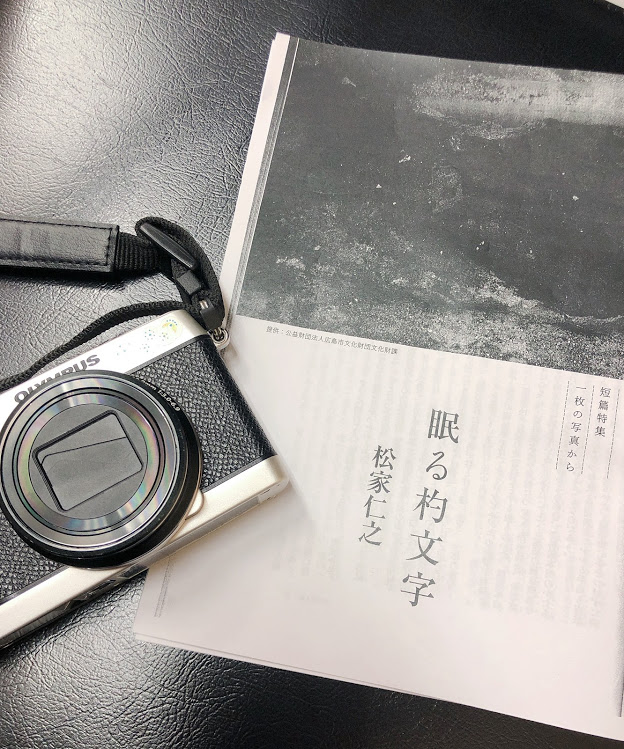
質問タイムも設けられ、参加者から最新長篇の『光の犬』(新潮社)の言葉の表記について、「<おもう>という言葉をひらがなにされていた。一か所だけ、<思う>と漢字のところがあった。ひらがなと漢字の使い分けはどのようにしているのか」という質問がありました。
これに対して、松家さんは「漢字だらけになるのが感覚的に好きではない。たとえば、<つよく>を漢字で<強く>と書いてしまうと、<つよく>という言葉のニュアンスを少し限定するような気がする」と答えていました。
文芸コース|学科・コース紹介

文芸コース コースサイト
会場となった203教室には、開演前からたくさんの人たちが集まり、満員の盛況となりました。

講義では、トルーマン・カポーティの『冷血』と、松家さんの短篇「眠る杓文字(しゃもじ)」(『文学界』2018年8月号掲載)の2作品を取り上げ、小説の具体的な創作方法などをお話ししました。
講義の前半は、『冷血』についてです。『冷血』は、米カンザス州の片田舎で起きた一家4人惨殺事件を題材にした作品で、幼なじみの作家ハーパー・リーの協力を得ながら精力的に取材を進め、5年あまりの歳月をかけて完成させたカポーティの代表作のひとつです。
松家さんは、映画『カポーティ』の映像(冒頭の13分間)も使い、カポーティ自身が<ノンフィクション・ノヴェル>とよんだ『冷血』がどのような経緯で書かれることになったのかをくわしく説明しました。

後半は、短篇「眠る杓文字」について語りました。
たまたま広島の平和記念資料館を訪れたときに、本館の下から発掘された黒焦げの「杓文字」の写真を見たことが構想のきっかけでした。
資料館の下の土の中に60年間にわたって眠りつづけてきた杓文字に触発された物語ができあがるまでの間、どのような取材をおこない、取材協力者にはどのような対応をしたのか。登場人物「先生」のモデルとなった建築家・丹下健三の話も盛り込みながら、作品完成までの経緯を具体的にお話しされました。
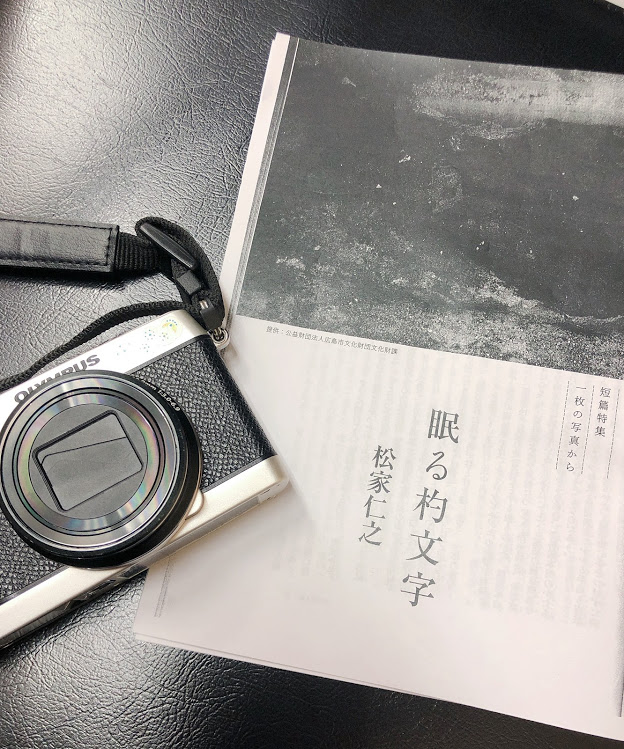
質問タイムも設けられ、参加者から最新長篇の『光の犬』(新潮社)の言葉の表記について、「<おもう>という言葉をひらがなにされていた。一か所だけ、<思う>と漢字のところがあった。ひらがなと漢字の使い分けはどのようにしているのか」という質問がありました。
これに対して、松家さんは「漢字だらけになるのが感覚的に好きではない。たとえば、<つよく>を漢字で<強く>と書いてしまうと、<つよく>という言葉のニュアンスを少し限定するような気がする」と答えていました。
文芸コース 伊藤譲治
文芸コース|学科・コース紹介

文芸コース コースサイト
おすすめ記事
-

文芸コース
2024年08月01日
【文芸コース】通信教育部マンガ 講評について
こんにちは、文芸コース主任の川崎です。 唐突ですがマンガを描いてみました。 通信教育における「講評」の意義とは何か、というテーマのマンガです。 文芸コース| 学…
-

文芸コース
2019年01月09日
【文芸コース】新しい年の初めに
新年明けましておめでとうございます。 今年も文芸コースのみなさんと一緒に、教職員ともども切磋琢磨していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申しあげます。 近年…
-

文芸コース
2021年10月26日
【文芸コース】見てから読むか!読んでから見るか!
皆さん、こんにちは。コロナ禍は少し落ち着きをみせてきていますが お元気でお過ごしでしょうか。文芸コース教員の安藤です。 前回の本欄でもご紹介させて…