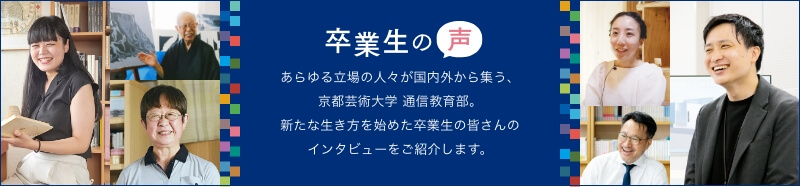| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 4年間 = 924,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(4年間) |
|
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 2年間 = 462,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(2年間) |
|
芸術学科
HISTORICAL HERITAGE
「幕末の京絵図 京都古地図復刻版」
伝えられてきた「もの」、守ってきた「こころ」。
過去から託されたものを確かに未来へと引き継ぐために、
いまある私たちの「文化遺産」をあらためて見つめ直します。
京都という地の利を生かし、現地を実際にあるいて重層する歴史を読み解く学外スクーリングを数多く実施。普段は入れない場所を訪れ、京文化の新たな一面を知ることも。
古文書、掛け軸、巻子、仏像などの実物に触れ、読み、調査する授業が豊富。膠や漆など伝統的な素材を使った修理作業も学べます。さまざまなほんものに触れることで、「知りたい」「読み解きたい」という意欲がわき、学習がすすみます。
歴史・美術史・文化財保存など。各分野から総合的に学ぶことで、「文化遺産」についての理解や考えを深められます。
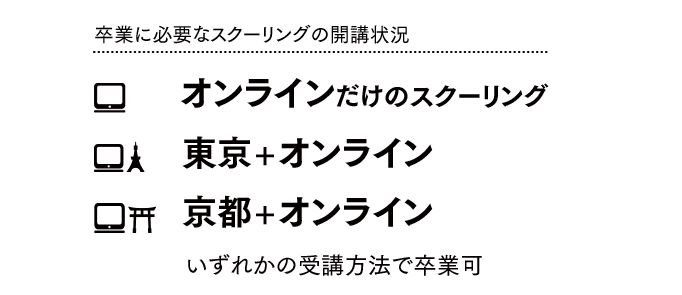

《学外授業の過年度例》
東寺、北野天満宮、比叡山延暦寺、建長寺、大原三千院、ほか。
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ◆ 京都の歴史 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 文献資料講読 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 京都学研修1 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 日本文化と東アジア | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 京都学入門 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 史料学基礎 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 史料講読基礎 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 歴史遺産学概論 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 歴史遺産学基礎講義 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 歴史遺産学Ⅰ-1 | レポート | 試験 | ||||||||||
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ◆ 京都の歴史 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 文献資料講読 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 論文研究基礎 | 1日間 | |||||||||||
| ◆ 論文研究特論 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 京都学研修1 | 2日間 | |||||||||||
| ◆ 京都学入門 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 史料学基礎 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 史料講読基礎 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ◆ 論文研究Ⅰ-1、2 | 2日間 | レポート | ||||||||||
| ◆ 論文研究Ⅱ-1、2 | 2日間 | レポート | ||||||||||
| ★ 歴史遺産学概論 | 2日間 | |||||||||||
| ★ 歴史遺産フィールドワーク1 | 1日間 | |||||||||||
| ★ 歴史遺産Ⅱ-1 | 1日間 | |||||||||||
| ★ 歴史遺産Ⅲ-1、3、5 | 2日間 | 1日間 | 2日間 | |||||||||
| ★ 歴史遺産学基礎講義 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 歴史遺産学Ⅰ-1、Ⅱ-1 | レポート | 試験 | レポート | 試験 | ||||||||
| ★ 古文書入門 | レポート | 試験 | ||||||||||
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 4年間 = 924,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(4年間) |
|
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 231,000円 × 2年間 = 462,000円 |
|
卒業までの合計金額の目安(2年間) |
|
大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)歴史遺産コースに3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。
また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。
書類審査
(大学等の卒業証明書など)
最短2年
3年次編入学の出願資格に
該当しない方は最短4年(1年次入学)
通信教育部
歴史遺産コース
書類審査
(指定提出物など)
最短2年
大学院
芸術学・文化遺産領域


お茶のイベントで外国の人々に会うときも、本コースでの学びが役立つという。「歴史を交えながら日本文化を紹介すると、より深く興味を持ってもらえます。自分の国の歴史をしっかり語れるって、いいですよね」。
「何百年も人の手で、伝えられてきた味なんですよ」。お茶の奥深さに魅了され、会社員でありながら中国茶や日本茶の講師も務める沼尻さん。「大好きなお茶の歴史について論文を書きたい」という一心で、本コースに飛びこんだ。もともと古いものに興味があり、先生の案内で京都の街を歩いたり、お寺にこもったりする実地の授業に感動。「座学でも、じかに鎌倉時代の仏像に触れ、本物の重みにハッとしました」。お寺、街並み、美術館など。これまで何気なく訪れていた場所も、ちゃんとした知識があれば、まるで感じ方が変わる。「歴史を学ぶと世界が広がる、と実感しました」。
こうして多彩なスクーリングを楽しむ一方、苦しんだのが目標にしていたはずのレポートや論文。「論文どころか、原稿用紙一枚を埋められなくて」。いくつかの課題をこなすうち、知識が自分の中でつながり、少しずつ筆がすすむようになったものの、今度は論文テーマに苦悩。「お茶の何を、どう研究するべきか」ギリギリまで悩み、ようやく先生から「それですよ、沼尻さん」と言われるものを発見した。
「出土した急須のカタチから、日本茶の飲み方の変化を探ることにしました」。やっとつかんだ重要なテーマ、しかし、だからこそ道は険しかった。まずは膨大な発掘資料を集め、自分なりに分類。その結果をもとに、独自の分析を繰り広げていく。「最後まで迷っていた結論を、じつは〝急須〞に教えてもらったんです」。たまたま出土品に間近でふれた瞬間、それまでの悩みが氷解し、自分なりの確信をつかめたという。「深く見つめれば、モノが歴史を語ってくれるんです」。卒業後は、さらに研究を深めるために大学院へ。「研究そのものは地道で大変だけど、お茶の歴史を少しでも明らかにすることで、文化の普及に貢献できたら」と話す沼尻さん。その手には、遠い昔から託された、文化の未来が握られている。

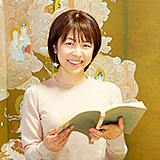
現在、大阪府高槻市にある「神峯山寺」の学芸員・広報として在職中。「私の提案した〝毘沙門不動ご祈願ろうそく〞が新たな授与品に。今後も、より広くお寺を知ってもらい、親しんでもらうための企画を考えたいです」。
「いま目の前にあるのが、千年も前につくられた像だなんて」。たまたま訪れた展覧会で、仏像の魅力に目覚めた中島さん。「もっと知りたい、できれば触れたい」という想いがつのり、本コースの学生に。「見るのが好き、という気持ちだけで入学して、最初は慣れないレポートに苦心しました」。先生から文献の集め方や引用方法を教わり、親子ほど歳の違うクラスメイトに励まされ、次第に学ぶ面白さを感じていった。「先生方の楽しい講義で、考古学やインド美術史など、未知の分野にもどんどん引き込まれて」。あらためて歴史を学ぶことで、仏像のもつ意味や背景など、より深い見方ができるようにもなったという。
「以前は〝美術品〞として鑑賞していただけでした。でも、祈る人や祀る人のさまざまな想いがあってこそ、世に生まれてくるんですね」。知れば知るほど、新たな興味がわいてくる。ある地方で出会った「被り阿弥陀」に衝撃を受け、卒業研究のテーマにしようと決心。「かぶる仏像なんて見たことなくて、なぜ?なんのために?と頭の中が疑問でいっぱいに。有名な仏像と違って研究者も少ないから、じゃあ自分で確かめよう未来につづく歴史と」。意気込んで調査をはじめたものの、扱える資料はごくわずか。様式などから造られた年代を検討するため、300体以上の仏像と細部を見比べていくことに。「最後の方は、向こうから来る人が仏像に見えるほど…でも苦労したからこそ、かつてない達成感を得られました」。
卒業と同時に学芸員資格を取得。やがて縁あって、歴史ある寺の広報として働くことになった中島さん。「ひとつひとつ迷いながらですけど…」。大学での知識に加え、参拝客としての目線を忘れず、寺を訪れる人が何を求めているか、それにどう応えられるかを模索している。「私の取り組みが、長い歴史のなかの〝点〞として刻まれるように」。中島さんの熱い視線は、いつの間にか、仏像と向き合う自身の未来に注がれていた。


じつはつい最近も、浄瑠璃寺の学術調査結果について発表がありました。つねに掘り起こされ、新たな発見が上書きされていくのも歴史の醍醐味。まだまだ現場から目が離せません!
幼い頃から母親に連れられ、しょっちゅうお寺めぐりをしていた。仏像も見慣れていた。なのに、本コースに入学してからは「見ること知ることすべてが新鮮で、興奮しどおしでした」と語る髙橋さん。その感動をあますことなくエネルギーに変え、フルタイムの仕事をこなしながらも学びに熱中。卒業研究では、先生をうならせる論文を書きあげた。
「生まれて初めて本物の仏像にふれたり、社寺や博物館の裏側を見学したり」。スクーリングでいろいろな体験をするたび、モノに向き合う心が磨かれていく。「たとえば、実際の史料を使って虫喰いの補修をする実習では、まず紙を貼る糊から炊くんです」。昔ながらの方法でつくられた糊は、再びはがすときにも素材を傷めない。100年後の再補修まで見すえたやり方に、伝承することの重みを感じた。
「入学前から、和紙などを使う修復には興味があったんです」という髙橋さんは、文具メーカーの開発担当者。「絵巻物に描かれた海や雲が、宗教的に何を表すか読み解くテキスト科目を受けてから、単純にキレイ!と絵柄を見るだけではなくなりました」。その観察眼が、後の卒業研究にも発揮された。「多種多様な学びが、思わぬところでつながるんです」。
研究のテーマに選んだのは、京都にある浄瑠璃寺の「九体阿弥陀如来坐像」。「図版で見たときはどれも同じ印象。でも実際に対面すると、あ、ここが違う、これは似てる、と思えてきました」。仕事のモットーでもある〝現場百回〞を実践し、何度もお堂に足を運んでは像に見入った。そして平日は、夜中まで書いていた原稿を、翌朝の通勤電車で読み返す日々。「もう、毎日が大忙し。なのに気がついたら大学院へ進学していました」。先生を感心させた着眼点を、さらに一歩掘り下げたくて、同じテーマで研究を深めているという。「文具の仕事でも、ここで教わったモノや形に対する想いを活かしたい」と話す髙橋さん。いにしえの学びは、いまと、これからの自分につながっていた。