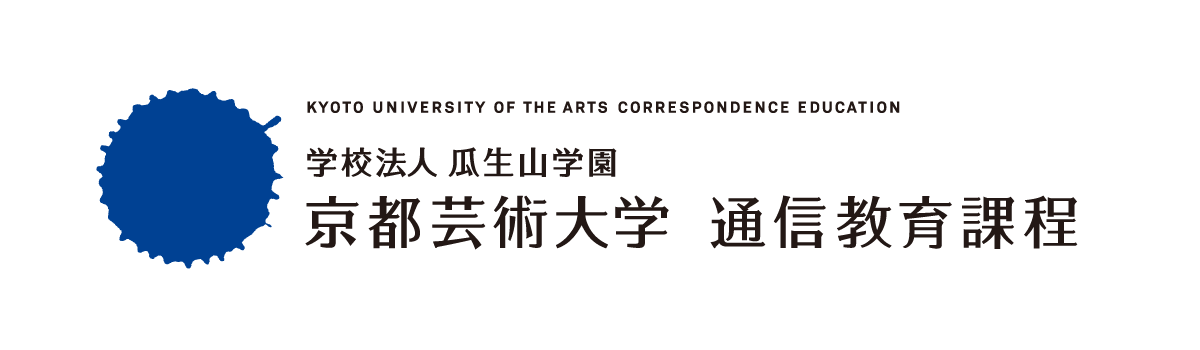アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「未完成でない建築は本当の意味で高貴なものとなりえない。」 (ジョン・ラスキン、1853)
2019年10月10日
【アートライティングコース】「未完成でない建築は本当の意味で高貴なものとなりえない。」 (ジョン・ラスキン、1853)

今年生誕200周年を迎えたイギリスの思想家ジョン・ラスキン(1819-1900)は、若い頃に大部の芸術論を出します。ラスキンの関心は芸術に留まらず、自然科学から社会問題まで実に幅広いのですが、彼は殷賑をきわめた19世紀イギリスにあって、一貫して産業化のもたらす諸問題や文明の平板化を鋭く批判しました。彼の芸術論も、作品の外面にかかわる審美的な記述というより、そもそもの人間の制作や労働のありかたを問うものとなっており、その点では、終生の主要テーマがすでに芸術論というかたちで現れていると考えることができます。
冒頭に掲げたラスキンの言葉は、30代の彼がヴェネツィアのゴシック建築について著した浩瀚な『ヴェネツィアの石』(第2巻、1853年)のなかに出てきます(第6章第22節)。彼自身「一見いかにも荒唐無稽な逆説」と書くように、少し戸惑わせる表現かもしれません。しかし「未完成な建築は高貴なものではありえない」というのではなく、「未完成なものこそ高貴だ」とするのは、ラスキンの人間の仕事一般についての考え方に根ざしています。モノを作る人間は本来は自由に活動します。しかし、ある時代(ラスキンの生きた19世紀のイギリスも含め)には、一方で自由な制作に携わる知的な人々、他方で奴隷的な仕事に携わる職人と、モノ作りが二極に分かれてしまう不幸な事態が生じてしまいます。そうなると、建築についても、いかに完璧な能力を持つ建築家がいたとしても、石を刻み、石を積んで貰うのは不自由で隷属的な職人たちに頼らざるをえません。彼が自分の仕事を完全に遂行できるとしたら、そのような職人たちの機械的な仕事の水準にあわせたかぎりでの仕事になります。しかし、ゴシック様式が代表するキリスト教建築では、職人たちはそのような与えられた機械的労働ではなく、自分たちの長所だけでなく短所もそのままに生かした自由な仕事を行います。その結果、建造物は隅から隅まで仕上がったもの(perfect)なものにはなりませんが、そのこと自体が建築を奴隷的労働の産物ではない、高貴なものにする、というわけです。また、後に続く節で言及されることになりますが、これは、より根本的なラスキンの自然観に呼応しています。生命とは常に変化し、生成するという考えです。完成した形というものは人間も含め、自然にはないのです。不完全な、あるいは不規則な形は、すべて変化を内包しており、逆に未完成な状態を禁じることは生命力を麻痺させることです(第25節)。
ゴティックの教会堂は長い年月、時には数世紀にわたって作られました。そのなかで次々に職人たちの手が加えられ、形を成長させていきます。これは近代の建築にはそぐわないやりかたです(そんな成り行き任せであれば建築許可がおりないでしょう)。しかし、すべてをひとりの建築家が最初から最後までコントロールした建造物が優れていて、多くの工人たちの手が加わる中で徐々に形を成してきた建造物が劣っているかというと、それは再考しなくてはならないでしょう。またこれは建築の問題だけではなく、私たちの身の回りの小さな制作物から、町や社会に至るまで、人間の作るものを反省する際に、心に留めておく必要があるように思います。
50年ほど前に、イギリスの美術史家ケネス・クラークが Ruskin Today (1964)という本を出しました。19世紀には広く読まれ、さらにはしばしば物議を醸したラスキンの著作が、20世紀半ばには書店の棚の上の方に埃をかぶっているのをクラーク卿が残念に思い、アンソロジーを出したのです。しかしまた50年ほど経って、依然としてラスキン全集は埃をかぶっているように思います。恰度2000年に、京都造形芸術大学でラスキン没後100周年の記念シンポジウムが催されました。そして今年また、同じく本学でラスキン生誕200周年記念シンポジウムが予定されています(https://kyoto.impacthub.net/event/john-ruskin200/)。あいにくすでに満席となってしまいましたが、報告書等でその内容は後日お知らせすることができると思います。関心のあるかたは是非そちらをご覧ください。
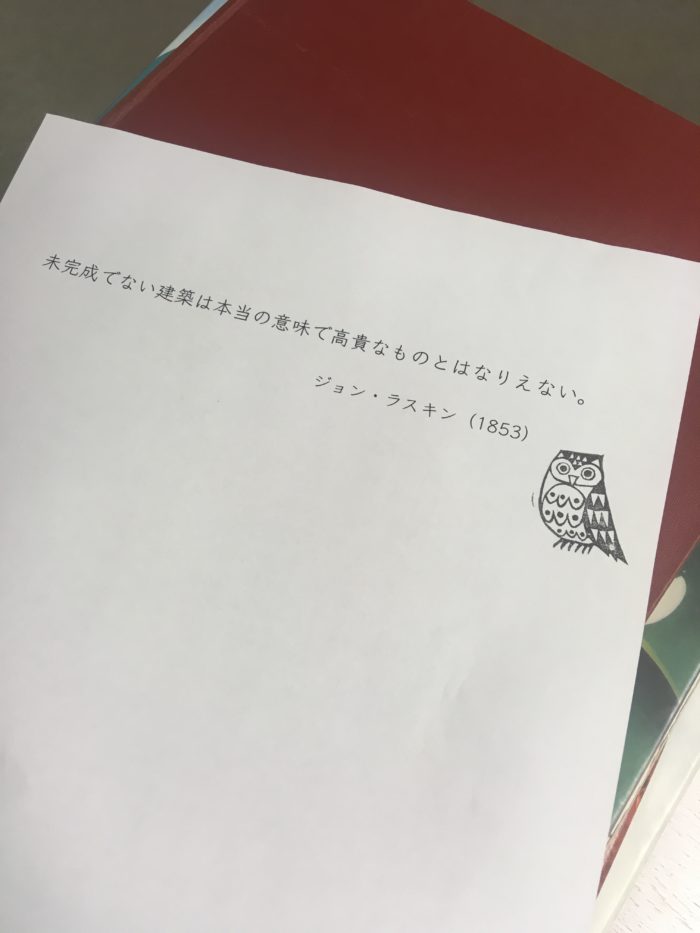
アートライティングコース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

アートライティングコース
2022年02月12日
【アートライティングコース】「完璧に仕上げることは、一種のフェティッシュでもある。」 バーナード・リーチ『作陶家の挑戦』1975年
みなさま、こんにちは。アートライティングコースの上村です。もう立春も過ぎて、年度末が近づいて来ました。アートライティングコースはまだ新しいコースで、卒業生を送り…
-

アートライティングコース
2023年10月18日
【アートライティングコース】「これはそれを殺すだろう」 ヴィクトル・ユーゴー『パリのノートル=ダム大聖堂』第8版、1832年
みなさま、急速に秋らしくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員、上村です。 「殺す」という言葉は、見た瞬間に目に強く飛び込…
-

アートライティングコース
2024年08月27日
【アートライティングコース】座学から野外へ アートライティングの身体性
こんにちは。アートライティングコース教員の大辻です。 毎年、8月16日の五山の送り火が済むと、少しは秋めいてくるものですが、今年の残暑は過酷という他ありません。…