

和の伝統文化コース
- 和の伝統文化コース 記事一覧
- 【和の伝統文化コース】鎌倉建長寺・四ツ頭茶会にて
2019年12月27日
【和の伝統文化コース】鎌倉建長寺・四ツ頭茶会にて
行く年を惜しみながらも、新しい年に希望を馳せるこの頃、お変わりありませんか?教員の雨宮です。本コースには「伝統文化実践Ⅱ-4(茶の文化)」というスクーリングがあります。茶会の発生や道具の歴史を理解し、茶道実習や道具作りを通し、幅広く茶文化を学ぶことを目標としています。
先日、「四ツ頭茶会」を体験するために令和元年十月二十四日、鎌倉の建長寺に行ってきましたので、ご報告いたします。
建長寺は、建長五年(一二五三年)に後深草天皇の勅により北条時頼が宋の高僧蘭渓道隆禅師を招いて開いた、日本で初めての禅の道場です。四ツ頭茶会は禅師の命日、七月二十四日(開山忌)に行われてきた茶会であり、二十年ほど前から禅師の遺徳を偲ぶ行事として、一般参加の日が設けられるようになりました。
茶会は、茶礼の解説を受けてから、叉手の姿勢(左手で右手を覆い、胸の上に重ねる)で龍王殿へ移動となります。叉手においては「こころがここにある」「こころを留める」ということを意識するようにと説明がありました。
四ツ頭とは、四人の正客と三十四人の相伴客をもてなすためのお茶会で、四人の供給僧の方がもてなして下さいます。
入室し着座すると、献香が焚かれます。禅師に献茶の後に、茶室の広間の四方に座った客の前に、抹茶の粉が入った天目茶碗と菓子盆が配られます。供給僧の方が、茶筅と浄瓶を持って入り、客に天目茶碗をささげ持たせ、湯を注いで点茶してまわります。茶菓のコンニャクは頂き、梵鐘の形の干菓子は懐紙に包んで持ち帰ります。本席である四ツ頭の他に、薄茶席が二席・中国茶席・点心席がありました。この茶会には、毎年全国から約五百名の茶人が参加します。
静寂な茶席で、供給僧の美しく流れるような所作に、茶のもてなしのこころが、禅宗寺院の儀礼の中で生まれ、現在に続いていることを実感しました。
その後、十一月に「建長まつり」が開催され、宝物風入れ見学と山門拝観の為に再び建長寺を訪れました。山門の楼上には釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢像が安置されていました。
山門の正面の「建長興国禅寺」と書かれた大扁額の下を歩いて見学しました。大扁額の下から参道に続く穏やかな景色を見た時、罹災から三門の再建に奔走しながらも、本人は山門の完成を見ることがなかった万拙碩誼の努力に胸が熱くなりました。建長寺を訪れた際には山門を見上げ、受け継がれた強い意志と普遍的な価値を感じて頂けたらと思います。
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

先日、「四ツ頭茶会」を体験するために令和元年十月二十四日、鎌倉の建長寺に行ってきましたので、ご報告いたします。
建長寺は、建長五年(一二五三年)に後深草天皇の勅により北条時頼が宋の高僧蘭渓道隆禅師を招いて開いた、日本で初めての禅の道場です。四ツ頭茶会は禅師の命日、七月二十四日(開山忌)に行われてきた茶会であり、二十年ほど前から禅師の遺徳を偲ぶ行事として、一般参加の日が設けられるようになりました。
茶会は、茶礼の解説を受けてから、叉手の姿勢(左手で右手を覆い、胸の上に重ねる)で龍王殿へ移動となります。叉手においては「こころがここにある」「こころを留める」ということを意識するようにと説明がありました。
四ツ頭とは、四人の正客と三十四人の相伴客をもてなすためのお茶会で、四人の供給僧の方がもてなして下さいます。
入室し着座すると、献香が焚かれます。禅師に献茶の後に、茶室の広間の四方に座った客の前に、抹茶の粉が入った天目茶碗と菓子盆が配られます。供給僧の方が、茶筅と浄瓶を持って入り、客に天目茶碗をささげ持たせ、湯を注いで点茶してまわります。茶菓のコンニャクは頂き、梵鐘の形の干菓子は懐紙に包んで持ち帰ります。本席である四ツ頭の他に、薄茶席が二席・中国茶席・点心席がありました。この茶会には、毎年全国から約五百名の茶人が参加します。
静寂な茶席で、供給僧の美しく流れるような所作に、茶のもてなしのこころが、禅宗寺院の儀礼の中で生まれ、現在に続いていることを実感しました。
その後、十一月に「建長まつり」が開催され、宝物風入れ見学と山門拝観の為に再び建長寺を訪れました。山門の楼上には釈迦如来・十六羅漢・五百羅漢像が安置されていました。
山門の正面の「建長興国禅寺」と書かれた大扁額の下を歩いて見学しました。大扁額の下から参道に続く穏やかな景色を見た時、罹災から三門の再建に奔走しながらも、本人は山門の完成を見ることがなかった万拙碩誼の努力に胸が熱くなりました。建長寺を訪れた際には山門を見上げ、受け継がれた強い意志と普遍的な価値を感じて頂けたらと思います。
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

和の伝統文化コース
2024年06月03日
【和の伝統文化】「利休忌月次(つきなみ)法要 於 大徳寺聚光院」
みなさま、こんにちは。和の伝統文化コース非常勤講師の青木です。 春から夏への変わり目、皆さまいかがお過ごしでしょうか? 今回は茶の湯文化にゆかりの深い大徳寺(注…
-

和の伝統文化コース
2023年12月21日
【和の伝統文化コース】「伝統文化実践II-4(茶の文化)」のご紹介
こんにちは。コース主任の野村です。 今回は和の伝統文化コースの授業の様子をお届けしたいと思います。 授業をご担当下さった中村幸先生からのレポートです。 11月4…
-
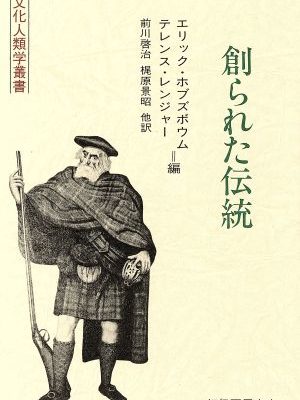
和の伝統文化コース
2022年03月01日
【和の伝統文化コース】伝統文化を学ぶ意味とは?
みなさんこんにちは、非常勤講師の黒河星子です。 本日は、伝統文化を学ぶ意味について、少し違った角度からお話ししたいと思います。 ★★★本ブログの末尾に、2021…




































