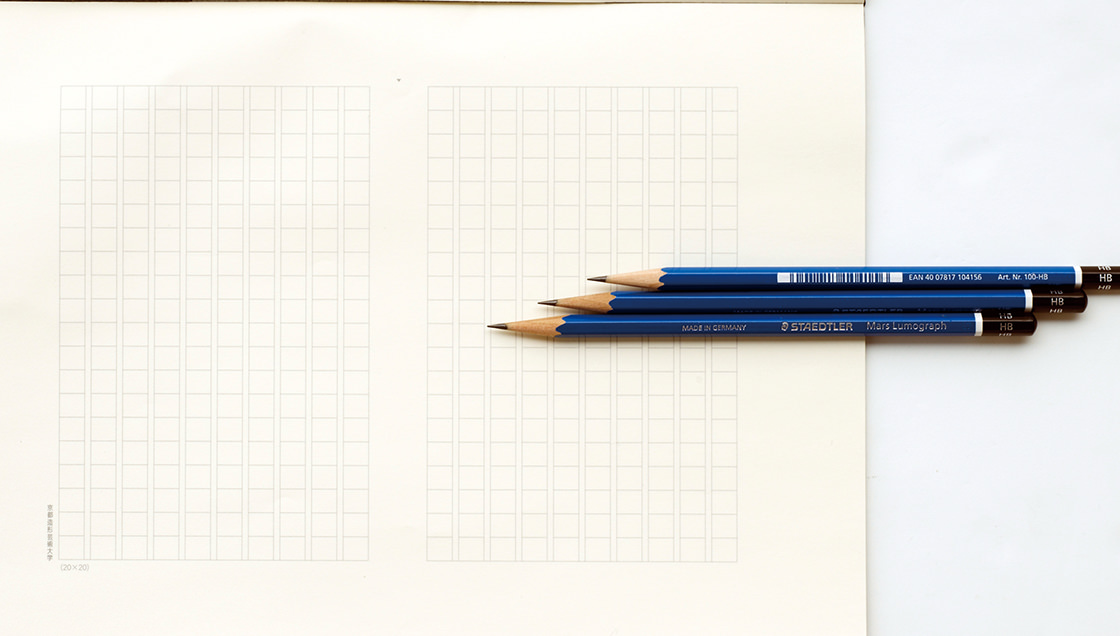

文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】 <日常> と <日乗> のあいだで
2020年06月22日
【文芸コース】 <日常> と <日乗> のあいだで

こんにちは。文芸コース教員の安藤善隆です。
<日常>という言葉に少し手が届きそうで、届かない。そんなもどかしさの中、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
まだ遠隔授業が中心となり、なかなかご一緒出来ませんが、お会い出来る日を楽しみにしながら、今日はそんな<日常>を文章で記す「日記」という文学について少し触れてみたいと思います。
ふっとお手を止める機会があれば、少しリラックスした気分で読んでみてください。
今年の4月、東京・下北沢に「日記を書くこと、読むこと、それぞれの魅力をひろめていく」ため『日記屋 月日』という店がオープンしました。新刊・古本問わず「日記本」を販売、「日記カード」などのオリジナルグッズなども扱い、日記が好きな人たちが集まり、その魅力を味わい、ひろく伝えていこうという集まりもあるこの書店は、ブック・コーディネーターの内沼晋太郎さんが運営しています。私も足を運んだことのある『本屋B&B』の共同経営者でもある方です。
■『日記屋 月日』
https://tsukihi.stores.jp/
その内沼さんは週刊文春の(2020年6月11日号)のインタビューの中で「今書店では、わかりやすく簡単にまとめられた自己啓発本や、今後の不安をあおって、未来に向かって焦らせる本がたくさん売られている。そういう本ばかりだと生きづらさを感じてしまいます」と現状を憂い、「いつまでも未来の準備をし続ける人生」でいいのか、だからこそ、自分を振り返る機能としての日記が必要で、道具としての日記の良さを広めていきたいと語っています。
「そうそう」と、様々な日記文学を読むことが大好きな私は大きく頷いていました。日記を読むことで「他人の人生を振り返ることもできるじゃないか」とも思いました。
でもそれだけじゃない……。
では、なぜ、私は日記を読むことがこんなに好きなんでしょうか。意識をしたことはありませんでしたが、少し考えてみました。

1976年11月24日水曜日から始まり、亡くなる5日前の1987年2月17日火曜日で終わるアンディ・ウォーホルの『ウォーホル日記』には数多くの著名人が登場します。ジョン・レノン、ジャクリーン・ケネディ、トルーマン・カポーティ、ジャン=ミシェル・バスキア、ウィリアム・バロウズ、ドナルド・トランプ……。
ポップアートの旗手の華やかな日常が描かれる一方で、純粋な視線で人々を観察し、彼らの姿、街の風景、そして時代を、ユーモラスな口調で切り取るこの日記に、ウォーホルの真髄を見たような気がしました。(因みにこの日記は、ウォーホルのスタジオでありサロンでもあった『ファクトリー』のタイピスト、パット・ハケットによってウォーホルが電話で話した内容を書き起こしたものです)。
このようなアーティストの日記を読む時には、もちろん華やかな世界を覗き見したいという気持ちはあります。他者の過去を体験してみたいという気持ちもあります。
でも、私が日記文学に惹かれるのは、そればかりではありません。日記は作家が書いたものであれ、画家が書いたものであれ、俳優が書いたものであれ(また普通の人々が書いたものであれ)、そこには、それぞれの視点で切り取られた<日常>の観察が書き込まれています。その上で彼らの記憶の積み重ね=<日乗>を追体験できる−そんな世界に私は魅了されているに違いありません。

『ウォーホル日記』にニューヨークという街の風を感じ、多和田葉子『言葉と歩く日記』で作家の観察眼の鋭さに驚き、伊丹十三『マルサの女日記』ではクリエーターの貪欲さを知り、柴崎友香『よう知らんけど日記』で大阪弁の素晴らしさを再認識し、吉行淳之介・編『酒中日記』を読み人々と杯を酌み交わす日々に思いを馳せる……。
<日常>が、<日乗>につながる瞬間がそこにはあるような気がします。
そして、それらを追体験することは、私に至福の時を与えてくれます。
 このコロナ禍の中で文芸誌はその誌面で様々な作家の日記を取り上げました。中原昌也「戒厳令の昼のフランス・ツアー日誌」、綿矢りさ「あの頃何してた?」(新潮6月号)や朝吹真理子「ビニールカーテンの美しさよ」、栗原康「俺たちのニライカナイーコロナ禍日記」、千葉雅也「非常時の日記」、そして本学でもかつて教鞭を執った新元良一「N Yロックダウン日記」(文学界7月号)などなど。
このコロナ禍の中で文芸誌はその誌面で様々な作家の日記を取り上げました。中原昌也「戒厳令の昼のフランス・ツアー日誌」、綿矢りさ「あの頃何してた?」(新潮6月号)や朝吹真理子「ビニールカーテンの美しさよ」、栗原康「俺たちのニライカナイーコロナ禍日記」、千葉雅也「非常時の日記」、そして本学でもかつて教鞭を執った新元良一「N Yロックダウン日記」(文学界7月号)などなど。それらを読んで今度は<日乗>から<日常>を意識するようになりました。
そこには(コロナ禍による未曾有の<日常>を通して)
「彼ら」の記憶と地続きになった「私たち」の記憶も息づいていたからです。
この3か月、いつもより少しだけ詳しく、その日の出来事をメモするようになりました。
私にとっての<日常>を取り戻すために<日乗>を書いてみようと。
この<日常>を知ることなく、今年1月に急逝した作家の<日乗>を読み返しながら、いま、そんなことを続けています。
文芸コース| 学科・コース紹介
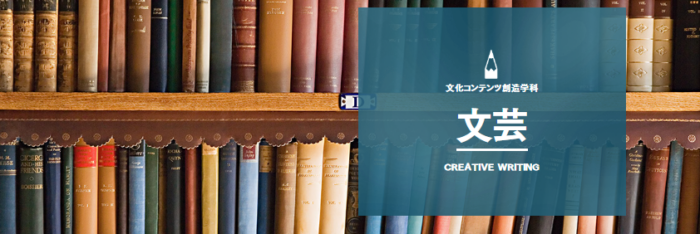
おすすめ記事
-

文芸コース
2019年04月18日
【文芸コース】入学ガイダンス始まる──有意義な大学生活を送るために。あわせて、読書会のご案内も。
みなさん、こんにちは。文芸コース教員の門崎です。 いよいよ新学期の始まりですね。 入学式が行われた4月7日の京都は少し肌寒い日でしたが、長持ちした桜の花が新入生…
-
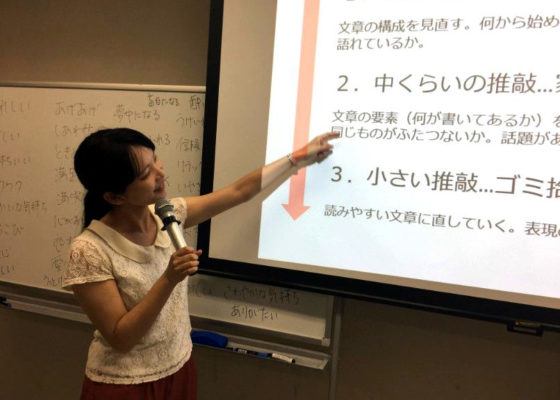
文芸コース
2018年07月23日
【文芸コース】自分の気持ちを言葉にする「エッセイ」の難しさと楽しさを知る
こんにちは。文芸コース教員の寒竹泉美です。6月30日~7月1日に瓜生山キャンパスで行ったスクーリング「文芸Ⅲ-1(エッセイ)」の様子をお伝えします。 みなさん、…
-
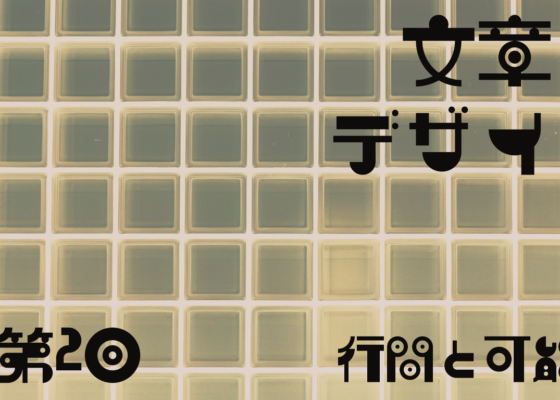
文芸コース
2024年05月27日
【文芸コース】文章とデザイン/第2回 行間と可能性
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 さあ「文章を書く上で、より深く読者をイメージするためのヒントを、デザインから学ぼう」という趣旨のテキスト、第…






























