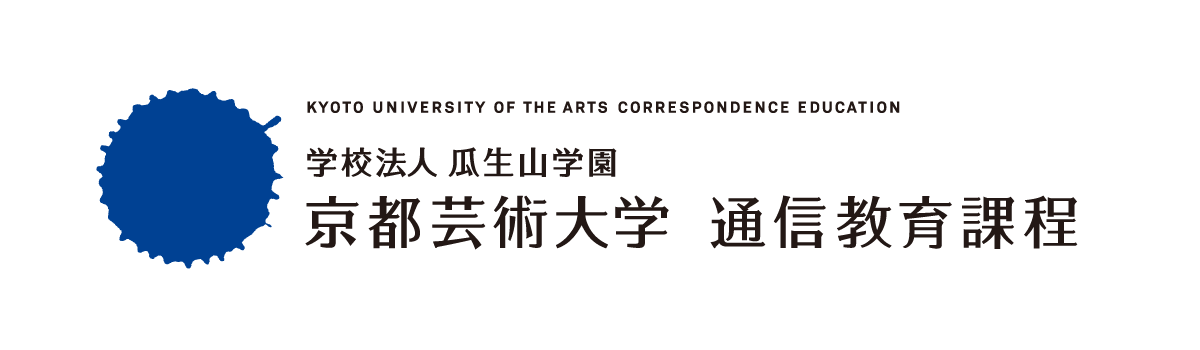芸術学コース
- 芸術学コース 記事一覧
- 【芸術学コース】感性のその先へ
2021年05月01日
【芸術学コース】感性のその先へ
風薫る季節、皆様いかがお過ごしでしょうか。芸術学コース教員の佐藤真理恵です。
私の研究分野は古代ギリシアなのですが、神話を主題とした芸術作品についての授業では、「意外にも現代の身近なところにギリシア神話のモティーフが使用されていて驚いた」という学生の声をよく耳にします。ギリシア神話は、キリスト教の物語と並び西洋美術における二大テーマの一角を成していますが、登場人物の多さ(と名前の長さ)や物語の多さのせいか、興味はあるものの手を出すのに躊躇する方も多いようです。しかし、ほんの少しでも神話をかじってみると、とくに西洋美術の作品における暗号めいた表象がスルスルと理解できるようになるばかりか、今日に至るまでさまざまにかたちを変えながら神話が上書きされ、語り直されてきている様が実感できるはずです。
そのようなわけで、今回は、ギリシア神話のとある登場人物の表象を例にとり、われわれに身近な形象に至るまでどのような変遷を辿ってきたのか、ごく簡単に紹介してみたいと思います。そのとは登場人物とは、セイレーンです。
まず、セイレーンとはどのような存在なのでしょうか。神話では、頭部は人間の女性、身体は鳥の姿をした半人半獣として伝えられています。図1は古代ギリシアのセイレーン彫像ですが、やはり鳥人間のような形象です。また、セイレーンは、岩場に棲み、通りかかった船の周りを飛翔し、美しい声で船乗りたちを惑わすとされています。ちなみに、セイレーンという語は、警笛などを意味するサイレンの語源にあたっています。魅惑的なセイレーンの声から警報音のサイレンへと語義が変遷しているようにもみえますが、いずれも注意を引き付けずにはおかないという意味では共通していますね。
なお、セイレーンは、紀元前8世紀の詩人ホメロスによる『オデュッセイア』にも登場します。オデュッセウス率いる船は、セイレーンらの住処を通過するにあたり、彼女らの声に惑わされて難破せぬよう、彼の部下たちは蜜蝋を捏ねたもので耳栓をし、いっぽう好奇心からセイレーンの歌を聴いてみたいオデュッセウスのみは耳を塞がぬものの身体を帆柱に縛り付けるという策をとります。図2の古代ギリシアの陶器画はこの場面を描いています。櫂船を漕ぐ部下たち、帆柱に括り付けられ顔を上げるオデュッセウス、左右の岩場から船へ向かってくる三羽のセイレーンたちが描かれています。
時代がかなり下って19世紀末においてもなお、『オデュッセウス』の記述や図2の陶器画に倣ったような古典的な表現でセイレーンを描いた芸術家たちもいます。その一例が、図3です。ここでも、船を囲むセイレーンたち、帆柱に縛られたオデュッセウス、布で耳を覆い、中にはさらに手でも耳を覆っている部下たちが描かれています。しかし、近代においていわば鳥人間としてセイレーンを描いている図3のような作品というのは、じつは稀有です。なぜなら、中世以降のセイレーン像は、鳥人間ではなく別様の形象をとってきたからです。
図4や図5のように、中世ヨーロッパのセイレーンの形象は、頭部は古代と同じく人間の女性ですが、下半身は鳥ではなく二股の魚の尾を伴っています。つまり、鳥人間から半魚人へと変化したのです。このように下半身が魚となったことで、船へのアプローチ方法も、岩場から船へ飛来するのではなく、海中から船に接近するという手段に変わります。なお、彼女らの半身が魚となり、棲み処も海に移った背景には、航海術の変化も影響しているという指摘があります。すなわち、従来は陸地や岩場を目印に進路を取っていましたが、中世に羅針盤が発明されたことにより、沖合での航海が可能となりました。それに伴い、セイレーンも沖合に棲む魚と結びつけられていったというわけです。
かようなセイレーンの表象は、近代の造形作品でも踏襲されています。例えば、図6は20世紀初頭の作品ですが、帆柱に縛り付けられ眼を見開いたオデュッセウスの船に、セイレーンたちが乗り込んで来る様子が描かれています。この作品は図3と制昨年が18年しか違わず、しかも同じく英国の画家ですが、一方では鳥人間、他方では人魚と、セイレーンの形象が異なっています。また、図6のうら若きセイレーンらは、歌声で船乗りを魅了するというよりは、船に乗り込んできて誘惑するという、なかなか身体を張った手段に出ているようす。しかも、彼女らのなかには下半身がすでに魚ではなく人間と化している者もあります。
セイレーンにはまた、船を難破させるというよりも、図7のように船乗りや漁夫ら男性を誘惑し水底へ引きずり込むという伝説も加えられていきます。図8は、画題をみても明確にセイレーンを描いたものとはいえませんが、セイレーンもまたここに描かれている人魚のような、男性を誘惑する者、悦楽へといざなう誘惑者として想像されていく経緯があるのです。ちなみに、ギリシア神話のセイレーンの物語と同様に、ドイツのローレライ伝説も、ライン川の急流地点で多発する船の事故をもとに、岩山に佇む美しい娘が船頭を惑わせると想像された物語です。いずれにせよ、造形作品を概観してみると、西洋近代におけるセイレーンは若く美しい人魚や水の精のイメージと重ねられてきたことが窺われます。
さらに、とりわけ19世紀以降、セイレーンはその誘惑者というイメージを色濃くし、妖婦や娼婦を彷彿させる姿で描かれるようにもなります。図8は、画題にセイレーンの名を冠してはいるものの、一見したところこれまで概観してきたような鳥人間も人魚も見当たりません。ただ、古代ギリシア風の建物の前で、頭髪を飾り並んで椅子に座っている若い女性たちの半身を覆う布は、見ようによっては人魚の尾のようでもあります。そして、女性たちが居並ぶ光景は、遊郭を想起させるかのようです。このように、とくに近代において、姿は違えど、セイレーンは男性を誘惑するエロティックな存在として表象されることが珍しくありません。
さて、最後にここで、われわれの身近にあるセイレーン像をご紹介いたしましょう。図4や図5のような二股の魚の尾をもつ中世のセイレーン像、どこか見覚えがありませんか。
ピンときた方もいらっしゃることと思いますが、そうです、ご存知スターバックスのロゴマークです。左側の白黒のものがオリジナルのロゴですが、これなどは先ほど見た中世のセイレーン像ときわめて似ています。右側の緑を加えた現行(2011年以前のものなので正確にはひとつ前の版)のロゴでは、図案がかなりデフォルメされているため、こちらを見ただけでは、スタバのロゴのモティーフがセイレーンであるとはなかなか気付かないかもしれません。しかしよく見ると、特徴的な二股の魚の尾もきちんと描きこまれています。スタバの創業者は、セイレーンが美しい歌声で船乗りを魅了したように、自分たちはコーヒーで人々を魅了したいとの思いをこのロゴマークに込めたそうです。このように、じつは今日においても、身近にギリシア神話の痕跡は数多く見出すことができます。

ちなみに、最近では、このスタバ版セイレーンとアマビエを合体させたキャラクターもインターネットを中心に登場しており、グッズも多数制作・販売されているようです。中には、図12のように、アマビエの特徴を踏襲し、頭上に尾を一本付け加えた三又の尾という形象も見受けられます。考えてみれば、アマビエは魚の特徴とともに嘴などには鳥のような特徴も見られ、セイレーンが纏ってきた諸特徴を併せ持った妖怪であるともいえます。セイレーンとアマビエのもつ意味合いは大きく異なるとは思いますが、少なくとも表象のうえでの類似点は興味深いところです。いずれにせよ、このような新たなキャラクターは、セイレーン像の刷新の一例、あるいは変種といってもよいかもしれません。このようにして、神話の表象は、さまざまな時代や文脈に応じて上書きされ、時として亜種を生み出しながら、脈々と継承されていくのではないでしょうか。
さて、とかく芸術作品の鑑賞においては、感性が重視される傾向があるように思います。むろん、感性によって捉えられる印象が作品の核心を突いていることもありますし、「白紙」の状態で感じ取ることの楽しさもありましょう。しかし、それとは別に、作品の背景を知ることではじめて見えてくる光景というものもあります。文化的・歴史的な文脈やさまざまな研究者の解釈に鑑みつつ、もう少し掘り下げて考察してみることで、作品をより多角的に、ときにはまったく新たな眼で眺める喜びは、なかなかの快感です。皆さんもぜひ、本学での学びをとおして、もう一歩、二歩、芸術に踏み込んでみませんか。
芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース|過去の記事はこちら
私の研究分野は古代ギリシアなのですが、神話を主題とした芸術作品についての授業では、「意外にも現代の身近なところにギリシア神話のモティーフが使用されていて驚いた」という学生の声をよく耳にします。ギリシア神話は、キリスト教の物語と並び西洋美術における二大テーマの一角を成していますが、登場人物の多さ(と名前の長さ)や物語の多さのせいか、興味はあるものの手を出すのに躊躇する方も多いようです。しかし、ほんの少しでも神話をかじってみると、とくに西洋美術の作品における暗号めいた表象がスルスルと理解できるようになるばかりか、今日に至るまでさまざまにかたちを変えながら神話が上書きされ、語り直されてきている様が実感できるはずです。
そのようなわけで、今回は、ギリシア神話のとある登場人物の表象を例にとり、われわれに身近な形象に至るまでどのような変遷を辿ってきたのか、ごく簡単に紹介してみたいと思います。そのとは登場人物とは、セイレーンです。
まず、セイレーンとはどのような存在なのでしょうか。神話では、頭部は人間の女性、身体は鳥の姿をした半人半獣として伝えられています。図1は古代ギリシアのセイレーン彫像ですが、やはり鳥人間のような形象です。また、セイレーンは、岩場に棲み、通りかかった船の周りを飛翔し、美しい声で船乗りたちを惑わすとされています。ちなみに、セイレーンという語は、警笛などを意味するサイレンの語源にあたっています。魅惑的なセイレーンの声から警報音のサイレンへと語義が変遷しているようにもみえますが、いずれも注意を引き付けずにはおかないという意味では共通していますね。
なお、セイレーンは、紀元前8世紀の詩人ホメロスによる『オデュッセイア』にも登場します。オデュッセウス率いる船は、セイレーンらの住処を通過するにあたり、彼女らの声に惑わされて難破せぬよう、彼の部下たちは蜜蝋を捏ねたもので耳栓をし、いっぽう好奇心からセイレーンの歌を聴いてみたいオデュッセウスのみは耳を塞がぬものの身体を帆柱に縛り付けるという策をとります。図2の古代ギリシアの陶器画はこの場面を描いています。櫂船を漕ぐ部下たち、帆柱に括り付けられ顔を上げるオデュッセウス、左右の岩場から船へ向かってくる三羽のセイレーンたちが描かれています。
時代がかなり下って19世紀末においてもなお、『オデュッセウス』の記述や図2の陶器画に倣ったような古典的な表現でセイレーンを描いた芸術家たちもいます。その一例が、図3です。ここでも、船を囲むセイレーンたち、帆柱に縛られたオデュッセウス、布で耳を覆い、中にはさらに手でも耳を覆っている部下たちが描かれています。しかし、近代においていわば鳥人間としてセイレーンを描いている図3のような作品というのは、じつは稀有です。なぜなら、中世以降のセイレーン像は、鳥人間ではなく別様の形象をとってきたからです。
図4や図5のように、中世ヨーロッパのセイレーンの形象は、頭部は古代と同じく人間の女性ですが、下半身は鳥ではなく二股の魚の尾を伴っています。つまり、鳥人間から半魚人へと変化したのです。このように下半身が魚となったことで、船へのアプローチ方法も、岩場から船へ飛来するのではなく、海中から船に接近するという手段に変わります。なお、彼女らの半身が魚となり、棲み処も海に移った背景には、航海術の変化も影響しているという指摘があります。すなわち、従来は陸地や岩場を目印に進路を取っていましたが、中世に羅針盤が発明されたことにより、沖合での航海が可能となりました。それに伴い、セイレーンも沖合に棲む魚と結びつけられていったというわけです。
かようなセイレーンの表象は、近代の造形作品でも踏襲されています。例えば、図6は20世紀初頭の作品ですが、帆柱に縛り付けられ眼を見開いたオデュッセウスの船に、セイレーンたちが乗り込んで来る様子が描かれています。この作品は図3と制昨年が18年しか違わず、しかも同じく英国の画家ですが、一方では鳥人間、他方では人魚と、セイレーンの形象が異なっています。また、図6のうら若きセイレーンらは、歌声で船乗りを魅了するというよりは、船に乗り込んできて誘惑するという、なかなか身体を張った手段に出ているようす。しかも、彼女らのなかには下半身がすでに魚ではなく人間と化している者もあります。
セイレーンにはまた、船を難破させるというよりも、図7のように船乗りや漁夫ら男性を誘惑し水底へ引きずり込むという伝説も加えられていきます。図8は、画題をみても明確にセイレーンを描いたものとはいえませんが、セイレーンもまたここに描かれている人魚のような、男性を誘惑する者、悦楽へといざなう誘惑者として想像されていく経緯があるのです。ちなみに、ギリシア神話のセイレーンの物語と同様に、ドイツのローレライ伝説も、ライン川の急流地点で多発する船の事故をもとに、岩山に佇む美しい娘が船頭を惑わせると想像された物語です。いずれにせよ、造形作品を概観してみると、西洋近代におけるセイレーンは若く美しい人魚や水の精のイメージと重ねられてきたことが窺われます。
さらに、とりわけ19世紀以降、セイレーンはその誘惑者というイメージを色濃くし、妖婦や娼婦を彷彿させる姿で描かれるようにもなります。図8は、画題にセイレーンの名を冠してはいるものの、一見したところこれまで概観してきたような鳥人間も人魚も見当たりません。ただ、古代ギリシア風の建物の前で、頭髪を飾り並んで椅子に座っている若い女性たちの半身を覆う布は、見ようによっては人魚の尾のようでもあります。そして、女性たちが居並ぶ光景は、遊郭を想起させるかのようです。このように、とくに近代において、姿は違えど、セイレーンは男性を誘惑するエロティックな存在として表象されることが珍しくありません。
さて、最後にここで、われわれの身近にあるセイレーン像をご紹介いたしましょう。図4や図5のような二股の魚の尾をもつ中世のセイレーン像、どこか見覚えがありませんか。
ピンときた方もいらっしゃることと思いますが、そうです、ご存知スターバックスのロゴマークです。左側の白黒のものがオリジナルのロゴですが、これなどは先ほど見た中世のセイレーン像ときわめて似ています。右側の緑を加えた現行(2011年以前のものなので正確にはひとつ前の版)のロゴでは、図案がかなりデフォルメされているため、こちらを見ただけでは、スタバのロゴのモティーフがセイレーンであるとはなかなか気付かないかもしれません。しかしよく見ると、特徴的な二股の魚の尾もきちんと描きこまれています。スタバの創業者は、セイレーンが美しい歌声で船乗りを魅了したように、自分たちはコーヒーで人々を魅了したいとの思いをこのロゴマークに込めたそうです。このように、じつは今日においても、身近にギリシア神話の痕跡は数多く見出すことができます。

ちなみに、最近では、このスタバ版セイレーンとアマビエを合体させたキャラクターもインターネットを中心に登場しており、グッズも多数制作・販売されているようです。中には、図12のように、アマビエの特徴を踏襲し、頭上に尾を一本付け加えた三又の尾という形象も見受けられます。考えてみれば、アマビエは魚の特徴とともに嘴などには鳥のような特徴も見られ、セイレーンが纏ってきた諸特徴を併せ持った妖怪であるともいえます。セイレーンとアマビエのもつ意味合いは大きく異なるとは思いますが、少なくとも表象のうえでの類似点は興味深いところです。いずれにせよ、このような新たなキャラクターは、セイレーン像の刷新の一例、あるいは変種といってもよいかもしれません。このようにして、神話の表象は、さまざまな時代や文脈に応じて上書きされ、時として亜種を生み出しながら、脈々と継承されていくのではないでしょうか。
さて、とかく芸術作品の鑑賞においては、感性が重視される傾向があるように思います。むろん、感性によって捉えられる印象が作品の核心を突いていることもありますし、「白紙」の状態で感じ取ることの楽しさもありましょう。しかし、それとは別に、作品の背景を知ることではじめて見えてくる光景というものもあります。文化的・歴史的な文脈やさまざまな研究者の解釈に鑑みつつ、もう少し掘り下げて考察してみることで、作品をより多角的に、ときにはまったく新たな眼で眺める喜びは、なかなかの快感です。皆さんもぜひ、本学での学びをとおして、もう一歩、二歩、芸術に踏み込んでみませんか。
芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース|過去の記事はこちら
おすすめ記事
-
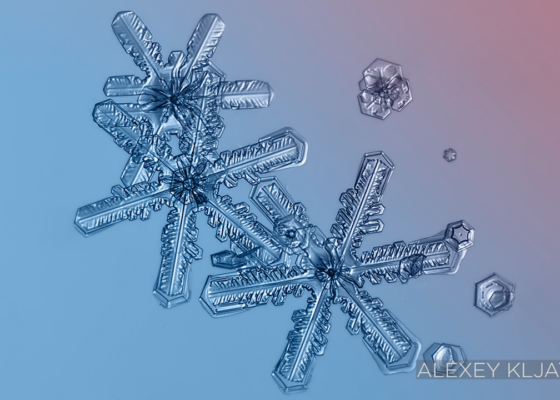
芸術学コース
2024年02月09日
【芸術学コース】雪を知る―芸術と科学の側面から
みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。暦の上ではそろそろ春、といえどもまだまだ寒い日が続いており、外出するのが億劫に感じる方もいらっし…
-

芸術学コース
2021年10月19日
【芸術学コース】トルチェッロ島、いくたびも
みなさん、こんにちは。芸術学コースの武井美砂です。秋も深まってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。今回は、美術史を長く続けていると、同じ作品に何度もめぐり会…
-

芸術学コース
2024年06月12日
【芸術学コース】音楽の「体験」を考える ―「ストップ・メイキング・センス」を例に
6月に入り近所では紫陽花が咲き始めました。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの田島です。 少し前になりますが、ライブ映画「ストップ・メイキ…