

芸術学コース
- 芸術学コース 記事一覧
- 【芸術学コース】通信教育で芸術学を学ぶということ
2023年05月10日
【芸術学コース】通信教育で芸術学を学ぶということ
こんにちは。そして、はじめまして。今年度から芸術学コースを担当することとなりました、教員の江本紫織です。
今回は「通信教育で美術史、芸術学を学ぶということ」の魅力を、「KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)2023」のレポートを交えてお伝えします。

みなさんは通信教育で芸術学(美術史や芸術理論)を学ぶということにどのようなイメージをお持ちでしょうか。
多くの方が思い描くのは、テキストや動画をもとに芸術の歴史や理論を学び、知識を身につける…というものかもしれません。
確かに、通信教育は遠隔の手法を用いた学習機会です。
ですが、それは通学(対面式の授業)による学びの「代わり」にすぎないのかというと、必ずしもそうではないようです。
それが一体何なのか、なかなか言語化することは難しかったのですが、今回「KYOTO GRAPHIE 2023」をめぐる中で「これだ」と思い至るものがありました。
それは(1)日々の生活や仕事(日常)が学びの助走となりうること、これによって(2)日常や芸術に対する新たな気づきが得られるということです。
どういうことか、「KYOTOGRAPHIE」での経験をもとに説明したいと思います。
KYOTOGRAPHIEとは、京都を舞台に開催される国際写真展です。
国内外の写真家の作品を、街中の展示会場をめぐりながら鑑賞します。
この期間、博物館やギャラリーはもちろん、寺院や町家、商店街まで——京都のあらゆるスポットが展示会場に様変わりします。
展示会場はあちこちに点在しているため、ある展示会場から別の展示会場に行く場合には街中を歩いて移動することになります。
一つの場所に展示されていれば、短時間で効率的に作品を見ることができるのかもしれません。
ですが、この移動の時間があるからこそ、一つの作品世界から別の作品世界を違和感なく行き来でき、それぞれの作品にじっくりと向き合うことができるのだと思います。
会場から会場への移動は新たな作品に出会い、没入するための「助走」期間でもあるのです。
通信教育で芸術学を学ぶということも同じです。
大学での学びは特定のキャンパスではなく、それぞれの日常の延長線上に置かれることとなります。
このことは、通信教育での学びがこれまでの経験(美術館に行くのが好き、もっと知りたいという興味関心など)という日常(助走)を基盤として成り立つものであることを意味します。
たとえば、本コースでは最終年度に卒業研究を行い、その成果として卒業論文を提出することが求められます。
この研究テーマを決める際、やはり活きてくるのがこれまでの経験、つまり日常です。
学生のみなさんのお話を伺っていると入学後はもちろん、入学前の経験を含めた「助走」があるからこそ出会えるテーマは少なくないと感じます。
話をKYOTOGRAPHIEに戻しましょう。
KYOTOGRAPHIEは「この会場に入ったら/出たら終わり」というものではありません。
日常と芸術の行き来は会場をめぐる間中続き、二つの経験の境界を曖昧にします。
このことがもたらすのは、ものの見方のわずかな変化です。
会場をめぐる中で体感する京都の街の様子はその一つと言えるでしょう。
単に生活の場として過ごす、あるいは観光地として訪れることでは気づかなかった街の様子は、「助走」のプロセスがあるからこそ得られるものです。
また、今回の出展作品の中には作品との物理的な距離を変えると、見え方が変わるというものがありました(ロジャー・エーベルハルト《Escapism》)。
コーヒーフレッシュの蓋に印刷された写真を再撮影し、大きく引き伸ばした作品です。
過度に引き伸ばされた写真は荒く、ドットによって構成されていることが明らかです。
大判の写真のため、作品に近づきすぎると印刷の網点が目立ち、単なる色の重なりにしか見えません。
遠くから見れば「山」や「サンゴ」のように判別できるものも、作品に近づきすぎるとたちまち何が描写されているのかがわからなくなってしまいます。
作品を「適切に」見るためには作品に近づいたり、遠ざかったりすることを繰り返さなければならないのです。
通信教育を通した芸術学の学びも、おそらくこのように視点の切り替えを促すきっかけとなるでしょう。
展覧会やデザインといった身近なものに対して、これまで気づかなかった「発見」があるかもしれません。
逆に、学びの外(日常)で経験したことが学びのヒントとなることもあるでしょう。
近すぎては見えないものが、遠ざかることではじめて捉えられるようになる、というわけですね。
このように通信制の大学で芸術学を学ぶことは、日常という身近な空間に質的に異なるものの見方や考え方を持ち込み、行き来することを可能にしてくれます。
「通信」というと物理的な距離を「なくす」ための手段のように思われるかもしれません。
ですが実際は遠くのものに近づくだけでなく、身近なものから遠ざかることもできるのです。
これは何かの「代わり」ではなく、「通信教育」だからこそ実現できるものと言えるでしょう。
気になる…と思われた方、日常を変える学びを一緒に始めてみませんか?
みなさんの入学によって新たな視点が持ち込まれることを、芸術学コース一同楽しみにお待ちしています。
資料請求|大学案内・募集要項

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)
芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識
次回の学生募集(入学のしかた)
■2023年度秋募集(10月入学生)※芸術教養学科のみ
詳細はこちらをご覧ください。
出願受付期間:2023年8月24日(木)10:00~10月7日(土)17:00
■2024年度春募集(4月入学生)※全学科コース/科目等履修生/通信制大学院
2023年12月に募集に関する情報公開予定(Webサイトにて告知)
入学のしかた
今回は「通信教育で美術史、芸術学を学ぶということ」の魅力を、「KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)2023」のレポートを交えてお伝えします。

通信教育×芸術学
みなさんは通信教育で芸術学(美術史や芸術理論)を学ぶということにどのようなイメージをお持ちでしょうか。
多くの方が思い描くのは、テキストや動画をもとに芸術の歴史や理論を学び、知識を身につける…というものかもしれません。
確かに、通信教育は遠隔の手法を用いた学習機会です。
ですが、それは通学(対面式の授業)による学びの「代わり」にすぎないのかというと、必ずしもそうではないようです。
それが一体何なのか、なかなか言語化することは難しかったのですが、今回「KYOTO GRAPHIE 2023」をめぐる中で「これだ」と思い至るものがありました。
それは(1)日々の生活や仕事(日常)が学びの助走となりうること、これによって(2)日常や芸術に対する新たな気づきが得られるということです。
(1)日々の生活や仕事(日常)が学びの助走となる
どういうことか、「KYOTOGRAPHIE」での経験をもとに説明したいと思います。
KYOTOGRAPHIEとは、京都を舞台に開催される国際写真展です。
国内外の写真家の作品を、街中の展示会場をめぐりながら鑑賞します。
この期間、博物館やギャラリーはもちろん、寺院や町家、商店街まで——京都のあらゆるスポットが展示会場に様変わりします。
展示会場はあちこちに点在しているため、ある展示会場から別の展示会場に行く場合には街中を歩いて移動することになります。
一つの場所に展示されていれば、短時間で効率的に作品を見ることができるのかもしれません。
ですが、この移動の時間があるからこそ、一つの作品世界から別の作品世界を違和感なく行き来でき、それぞれの作品にじっくりと向き合うことができるのだと思います。
会場から会場への移動は新たな作品に出会い、没入するための「助走」期間でもあるのです。
通信教育で芸術学を学ぶということも同じです。
大学での学びは特定のキャンパスではなく、それぞれの日常の延長線上に置かれることとなります。
このことは、通信教育での学びがこれまでの経験(美術館に行くのが好き、もっと知りたいという興味関心など)という日常(助走)を基盤として成り立つものであることを意味します。
たとえば、本コースでは最終年度に卒業研究を行い、その成果として卒業論文を提出することが求められます。
この研究テーマを決める際、やはり活きてくるのがこれまでの経験、つまり日常です。
学生のみなさんのお話を伺っていると入学後はもちろん、入学前の経験を含めた「助走」があるからこそ出会えるテーマは少なくないと感じます。
(2)日常や芸術に対する新たな気づき
話をKYOTOGRAPHIEに戻しましょう。
KYOTOGRAPHIEは「この会場に入ったら/出たら終わり」というものではありません。
日常と芸術の行き来は会場をめぐる間中続き、二つの経験の境界を曖昧にします。
このことがもたらすのは、ものの見方のわずかな変化です。
会場をめぐる中で体感する京都の街の様子はその一つと言えるでしょう。
単に生活の場として過ごす、あるいは観光地として訪れることでは気づかなかった街の様子は、「助走」のプロセスがあるからこそ得られるものです。
また、今回の出展作品の中には作品との物理的な距離を変えると、見え方が変わるというものがありました(ロジャー・エーベルハルト《Escapism》)。
コーヒーフレッシュの蓋に印刷された写真を再撮影し、大きく引き伸ばした作品です。
過度に引き伸ばされた写真は荒く、ドットによって構成されていることが明らかです。
大判の写真のため、作品に近づきすぎると印刷の網点が目立ち、単なる色の重なりにしか見えません。
遠くから見れば「山」や「サンゴ」のように判別できるものも、作品に近づきすぎるとたちまち何が描写されているのかがわからなくなってしまいます。
作品を「適切に」見るためには作品に近づいたり、遠ざかったりすることを繰り返さなければならないのです。
通信教育を通した芸術学の学びも、おそらくこのように視点の切り替えを促すきっかけとなるでしょう。
展覧会やデザインといった身近なものに対して、これまで気づかなかった「発見」があるかもしれません。
逆に、学びの外(日常)で経験したことが学びのヒントとなることもあるでしょう。
近すぎては見えないものが、遠ざかることではじめて捉えられるようになる、というわけですね。
このように通信制の大学で芸術学を学ぶことは、日常という身近な空間に質的に異なるものの見方や考え方を持ち込み、行き来することを可能にしてくれます。
「通信」というと物理的な距離を「なくす」ための手段のように思われるかもしれません。
ですが実際は遠くのものに近づくだけでなく、身近なものから遠ざかることもできるのです。
これは何かの「代わり」ではなく、「通信教育」だからこそ実現できるものと言えるでしょう。
気になる…と思われた方、日常を変える学びを一緒に始めてみませんか?
みなさんの入学によって新たな視点が持ち込まれることを、芸術学コース一同楽しみにお待ちしています。
資料請求|大学案内・募集要項

芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース紹介動画(教員インタビュー)
芸術学コースコースサイト Lo Gai Saber|愉快な知識
次回の学生募集(入学のしかた)
■2023年度秋募集(10月入学生)※芸術教養学科のみ
詳細はこちらをご覧ください。
出願受付期間:2023年8月24日(木)10:00~10月7日(土)17:00
■2024年度春募集(4月入学生)※全学科コース/科目等履修生/通信制大学院
2023年12月に募集に関する情報公開予定(Webサイトにて告知)
入学のしかた
おすすめ記事
-
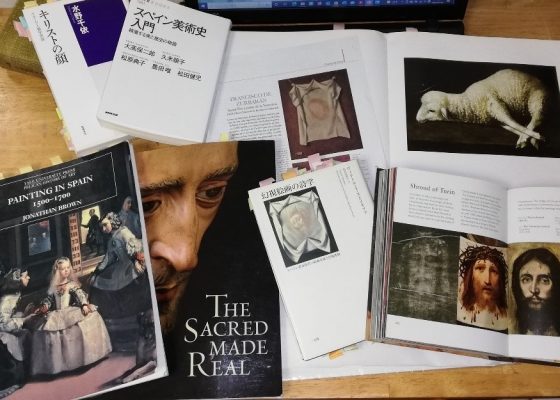
芸術学コース
2022年07月10日
【芸術学コース】「好き」よりも「なぜ?」-研究テーマを決められないときに
みなさま、こんにちは。芸術学コースの田島です。 早々に梅雨が明けてしまい猛暑日が続いております。何かとお忙しいかとは思いますが、くれぐれも無理をなさらないようお…
-

芸術学コース
2021年06月08日
【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地①ルンビニー
みなさん、こんにちは。芸術学コース教員の金子典正です。今回は2020年2月にインドの仏跡を旅した時の様子を、前回に引き続き、ご紹介します。 ▼前回のコラムはこち…
-

通信教育課程 入学課
2025年10月25日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …


































