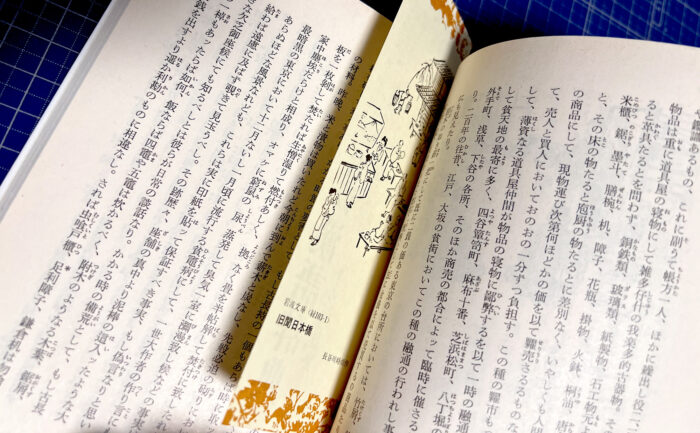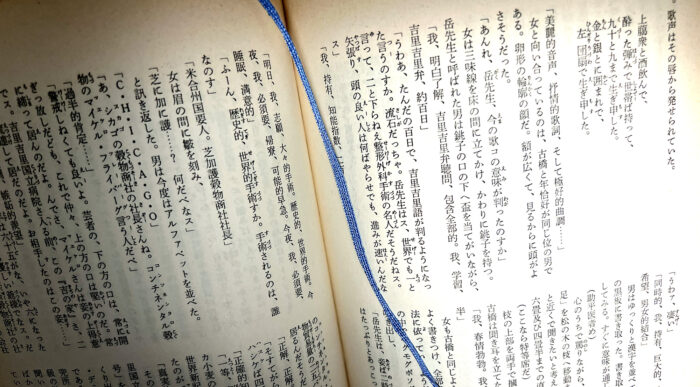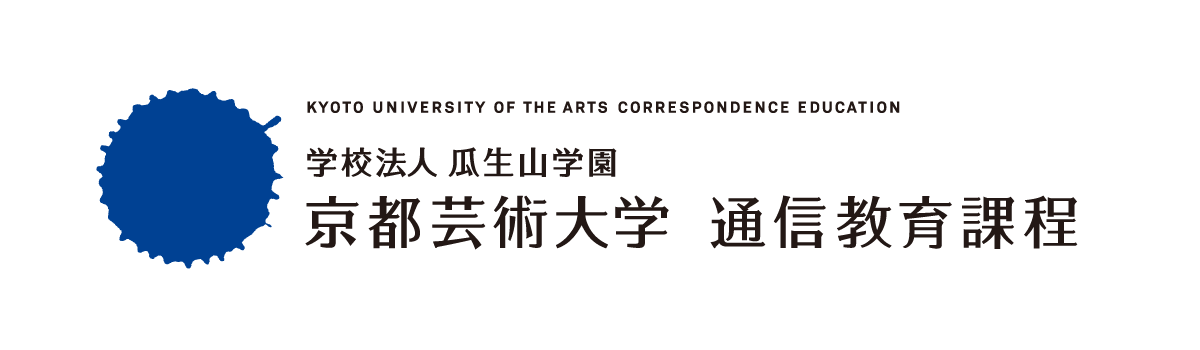文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】本を読むということ 1/しおりを使わずに読む。
2023年05月26日
【文芸コース】本を読むということ 1/しおりを使わずに読む。
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。
これから文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方から、私がよく受ける質問のひとつに、「何を読めばよいか?」というものがあります。文芸コースでは、「読むこと」と「書くこと」を学びの両輪ととらえており、たくさん書くことと同時に、たくさん読むことも奨励しているわけですから、「たくさん読めって言われても……何を読んだらいいんだろう?」という質問には、かなりの必然性があると言えるでしょう。
しかしながら……私は特にこの質問に対する明確な答えを持っていないのです。私がおもしろいと思う本、私の人生において強い影響をもたらした本、読むことで私に力をもたらした本……などであれば、いくらも列挙することができます。でも、それはあくまでも私の主体的な価値観に基づく本との出会いに過ぎず、もっと言えば私の個人的な趣味嗜好に左右される種類の本たちでもあり、そうした矮小な視点を押し付けるような姿勢が、果たして文芸を学びたいと願う人々の未来に資するかどうかを自問すると、甚だ怪しいところがあります。学問領域を区切るならば、体系的に学ぶためのテキストを紹介することは可能でしょう。
例えば「儒教についてゼロから学んでみたいんですが、何から読めばいいでしょうか? やっぱり論語ですか?」と問われたら、口角泡を飛ばして「いや、論語は重要ですが、あえて後回しにしましょう、特に学而第一を最初から読むのはやめなさい。四書五経において最初に触れるべきは、何と言っても易経。その中でも繋辞伝から紐解きましょう。繋辞伝を穴が空くほど読み返したら、次はいよいよ……」と語るところですが(ごめんなさい、私は単なる漢文好きであって、別に儒教の専門家でもなんでもないので、これもやっぱり個人的な体験に由来する主張に過ぎません)、そうでないのなら、ふわっとした「何を読めばよいか?」といった質問には、個々人の社会的背景や主義主張、性格嗜好などがあると思ってしまい、サラッと乱暴に答えを提示するわけにはいかないと、躊躇してしまうわけです。
が、文芸コースの主任という立場にある人間が「何を読めばいいか? そんなの、好きなものを読んだらいいじゃないの」では、やっぱりあまりにも無責任というか、それこそ文芸を学びたいという方の意欲をくじくような態度と受け止められかねませんし、私自身、そうした放任の姿勢を是とはしない主義なので、折角の機会ですから、ここでしっかり「読む」ことについて、言語化したいと思います。
無論、上に書いたように、個人的な読書体験に基づく古今の名作の押し付けはしません。そうではなく、私が「読む」という行為性においてより重要であると思うのは、あるいは「読む」について私に語ることが可能な部分があるとすれば……私はこう考えました。私の役目は、文芸を学びたいと考える人々に対して「何を読むか」ではなく「どう読むか」を伝えることではないか、と。
この「どう読むか」という視点は、簡単に言えば、日常における本との接し方についての論点です。とりわけ、身体性という部分に着目して、「どう読むか」について私は語りたいと思います。誰もが知っているように、時間は有限です。忙しなく進む現代という時間軸において、読書に避ける時間は、誰もがふんだんに持っているわけではありません。そうした状況下において、「よりよく本を読むためには、どうするべきか」を、私なりの観点から論じたい……それがこれからお届けするテキストの狙いです。
しおりを使わずに読む
ということで、まずは「どう読むか」の第一回として、上記の提案をしてみたいと思います。
しおりは、本を読まれたことのある方ならば、誰もが一度ならず手にしたことのあるアイテムでしょう。書店で文庫を買うと、しおりが既に挟まれていたり、景品として添えられていたりするものです。単なる小さな厚手の紙に過ぎませんが、本にまつわる蘊蓄が書いてあったり、作中のキャラクターのビジュアルが印刷されていたり、いろいろと各版元が工夫を凝らしている部分でもあって、本を楽しむ魅力のひとつであると言えるでしょう。
本によっては、栞紐というものもあります。本の背側からヒョイと伸びている、平織りされた数ミリメートル程度の幅を持つ紐のことです。スピンと呼ぶ場合もあります(英語だとBookmark)。
しおりや栞紐、スピンと呼ばれる存在の意義は、別に難しくありません。本を読んでいる途中、何らかの事情で本を閉じなければならなくなったとき、自分がどこまで読んでいたかを物理的に示してくれる役割をそれらは有しています。本は、たっぷりと時間があれば、最初から最後まで一息に読むこともできますが、忙しい現代においては、誰もがそうした時間を確保できるとは限りません。私も、半ば職業的に読書をする場面があるとは言え、なおかつ本がもたらす芳醇な世界に没入しやすい性格でもありますが、それでも一気に本を読み切る体験は、そう滅多にはありません。
となると、「どこまで読んだか」を認識する必要性は読書という行為において不可避であるとも言えます。
しかしながら、本を読むとき、私は、しおりやそれに類するアイテムに頼らないようにしています。理由は私が編集者であり、職業病か、視界に入ったノンブルを瞬間的に記憶する能力があるから……ではありません。私もたいがい老齢に差し掛かっていますし、悲しいかな、記憶力も年を追うごとに頼りなくなっていますから、そんな芸当はできっこないのです。
そうではなく、私がしおりを使わない最大の理由は……「同じ箇所を繰り返し読むため」です。
印刷された紙を束ねた、コーデックスと呼ばれる種類の(現代の紙の本における最もスタンダードなスタイルの)本は、当然ですが物理的に紙の束分の厚みを持ちます。数百枚の紙が重なっているわけですから、まさか私がその厚みを指先に感じながら「む。ここがさっきまで読んでいた180〜181ページの見開きだな」とピタリ該当ページを当てるような真似、できるわけがありません。どんな愛書家であっても不可能でしょう、きっと。もっとも、ある程度であれば推量することはできます。仮に320ページの本だとして、200ページ付近で読むのを中断したとして、あるとき、その本を手にして読むことを再開しようと思ったとき、近いページを開くこと自体は、そこまで難しくはないかもしれません。
ですが、その「だいたいこの辺まで読んだっけ?」と思って開いたページが、どんぴしゃり先程まで読んでいた部分である可能性は、かなり低いはずです。私はそうして開いたページにチラチラと目を落とし、「あら、まだ読んでない部分だ。途中まで読んだところは、もう少し前だな」と思えば、パラパラとページを戻します。たいてい、戻しすぎて「あ、ここはさっき読んだところだ」というあたりまで遡ってしまいます。逆に開いたページが「うん、ここはもう読んだところだな。本を閉じたのはもう少し先のページだ」となったら、私はページを先に進めたりせず、たまたま開いたそのページから改めて読むことをします。
どちらの方法を選ぶにせよ、この態度ですと、当たり前ですが「以前に読んだ箇所」を再度読み返すことになります。
そして、この体験を、私は「本を読む」という営みにおいて、非常に重要視しています。
なぜならば、同じ箇所を読み返す私は、過去の私とは既にして別人であるからです。本を読むことを中断したのが仮に五分前だとしても、五分後の私は違う人間です。五分間が……例えば電車を乗り換える時間であったならば、私は「なんとかして次に来る電車に乗らなければ、保育園のお迎えの時間に間に合わない!」と焦っていたかもしれず、そうして目的の電車に無事間に合っていれば五分後の私は安堵に包まれており、対して間に合っていなければ五分後の私は失意と絶望に打ち拉がれているかもしれません。どちらにせよ、その私は少なくとも精神状態の点においては、五分前の私とは異なる私のはずです。
あるいは五分間において、何らかの生理的欲求の奴隷となった私は、それが空腹という欲望であれば立ち食い蕎麦のひとつでもかっ食らったかもしれません。それが排泄という欲求であればトイレに駆け込み出すものを出したでしょう。いずれにせよ、五分前の私と五分後の私は、その身体的状況において明確な変化を遂げています。
その変化を、私は本を読むことに活かします。どのような些細なものであれ、変化した事実を持つ私が、同じ本の同じ箇所を読み直す。すると……不思議なことに、同じ文章であるはずなのに、同じようには読めないのです。まるっきり違うものとして読める、というわけでもありませんが、微細な変化には鋭く思考が反応します。あるいは最初に読んだつもりでいた文章でも、変化した自分の目を通して改めて読むと、見落としていた表現性や、味わいそこねていた言葉たち、読めていなかった文間……そうしたものと出会えることが、多々あるのです。
この、「意図しない読み直し」を可能とするのは、しおりに頼らない、自分がどこまで読んだかを決して記録しようとしない、非合理的な再読行為です。ですが、その非合理性が、読書において「最初に読んだときには、意識できなかった部分の発見」をもたらしてくれるとしたら、どうでしょう? 遅々として物語を先に読み進められない状態にいらいらする? まさか。やってみるとわかります。いかに私たちが「急いで読む」ことをしたせいで、どれほどたくさんの「文章の奥底に眠っていた深い表現」を見落としていたかを。
この「しおりを使わずに本を読む」方法、実は非効率的でもなんでもありません。「そんなまどろっこしい読み方をして、時間を使うよりは、まず一度読み終えて、それからもう一度読んだらいいじゃないか」とする意見があれば私は否定しません。私も好きな本、愛するタイトルは最初から最後まで読むことを、何度となく繰り返します。が、あらゆる本を最初から愛せるわけではありません。初回の読み方が雜だったせいで、その本の本質に踏み込めないまま、でも「読んだ」という事実に満足してしまい、二度と紐解かなかった……経験、皆さんもあるでしょう? 私にもたくさんあります(そうして、本棚の本がドンドン溢れかえっていくわけです)。なかなか「ふう、読み終えた。あまりおもしろく感じなかったが、私の目が節穴だった可能性も捨てきれない。改めて最初から読み返そう」なんて姿勢を選ぶのは、相当の根性、あるいは精神的余裕がないと、実現できない気がします。それよりは「えーっと、どこまで読んだかな。ここかな。いや、もうここは読んだな……あー、でもいいや、もう一度読み直してみよう。最初に読んだとき、ちょっと分かりにくく感じた気もするし」というふうに、本の途中途中で、読み返す作業を重ねながら、ちょっとずつ最終ページに近づいたほうが、一冊の本を深く読むことにつながりますし、日常において小さな変化を小刻みに重ねていった、異なるたくさんの自分たちの力を借りることができるゆえに、勢い任せで読んだときには出会えなかった表現たちを、効率よく発見できる可能性がだいぶ高くなるのです。
最後に蛇足を。この「しおりを使わずに本を読む」という方法論が一番有効な作家は、これは完全に私の個人的意見ですが、大江健三郎だと思います。とりわけ一九六四年以降の作品群は、私のような浅学非才の人間にとっては、どれ一つとしてスムーズに読めるものではなく、ゆえに私はかえって全力で「しおりを使わずに本を読む」ことで出会える再読性(re-readability)に期待し、そこに縋り付けば、私のような愚鈍な人間であっても、大江健三郎の作品の真髄……とまでは行かずとも、深淵な魅力の一端にどうにか触れられるのではないかと願い、何度も何度も同じ箇所を読み返しました。『ピンチランナー調書』なんて、もう十五年以上昔の話ですが、読み終えるのに半年かかりました。中盤からは、わざと読み返さざるをえないようなページの開き方をしていたように記憶しています。でもまあ、その甲斐あってか、四十歳も過ぎ、ここ最近は、堂々と「好きな作家? 大江健三郎です」と人前で放言できるようになりました。
さて、長々書き連ねてしまいましたが、みなさんもぜひ、一度でよいですから「しおりを使わずに本を読む」ことをしてみてください。きっといつもとは少し違う、読書体験を味わえるはずですから。
文芸コース主任 川﨑昌平
文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事
-

文芸コース
2022年12月01日
【文芸コース】「観察」で語彙を増やそう
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 文芸コースで講師をしていると、時折「語彙を増やすにはどうすればよいか」といった種類の質問を受けることがありま…
-

文芸コース
2021年01月17日
【文芸コース】卒業生紹介「文芸のある風景」
通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸…
-

通信教育課程 入学課
2025年10月25日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …