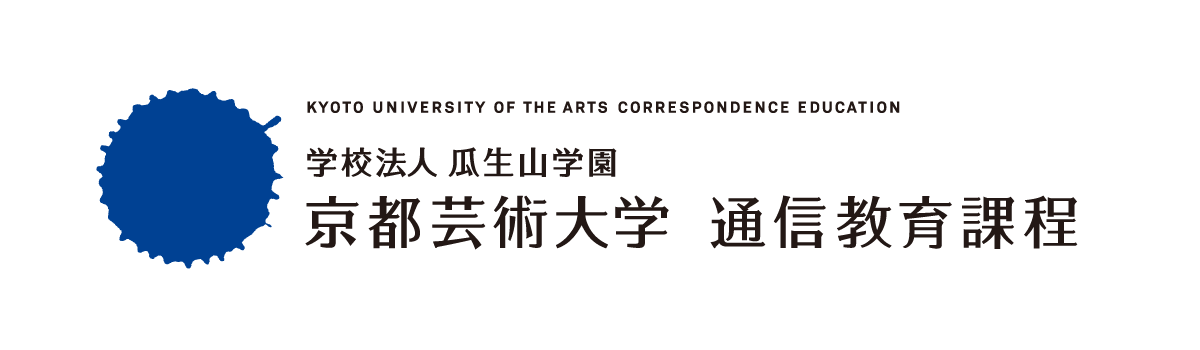文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】本を読むということ 3/立って読む。
2023年07月31日
【文芸コース】本を読むということ 3/立って読む。

結局のところ、書くことも読むことも、身体性の延長にある行為なのだと私(川﨑昌平)は思う。
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。
文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方のために、「本の読み方」あるいは「本を読むということ」の意味を、もっと言ってしまえば「よりよく本を読むためには、どうするべきか」を、私なりの観点から論じようと思い、この連載のような原稿をスタートしてみました。
特に「本はこう読めばよい!」といった正解のようなものを、読者の皆さんに押し付ける腹積もりはないので、「読書におけるひとつの(風変わりな?)視点」のようなものを、提供できればと思っています。では、第3回目をスタートしましょう。
立って読む。
ヘミングウェイは、立ちながら原稿を書いたそうです。強靭な下半身が要求されそうな(同じレベルで腰から上の筋肉についても相当量が必要とされそうな)書き方ですが、ある意味では頷けなくもありません。スタンディング・デスクなんて言葉があるらしいのですが、立ったまま仕事をすると、肉体が自然と作業効率をあげようと動き出し、結果として時間効率がよいのだとか。「文章を書く上での時間効率とは、いったい何を指すのか」という疑問も湧き上がりますが、おそらくは言葉を生み出し文章を編み出そうとする上で……ひとつには表現の冗長性を削ることができる点は強調できるかもしれません。
実際にヘミングウェイにインタビューしたわけでもないので、御本人の思惑は知る由もありませんが、『老人と海』のような短編を読むと、その叙述の鋭さ、無駄な言葉を用いず、しかし端的に状況や心情を言語化しきる筆勢に気が付きます。もしそこに立って書くこととの因果関係があるのだとすれば、座ることによる長時間の執筆を避ける姿勢が、すなわち短時間で書こうとする思考が、自ずと言葉を吟味させ、文章に贅肉をつけないような意識をもたらしたのかもしれません。
あるいは……これまた想像でしかありませんが、立って書くことで生じる肉体への負荷を利用して、ヘミングウェイは身体が緩慢になるのを予め防ごうとしているのかもしれません。
リラックスという概念がありますが、心身ともにストレスがない状態は必ずしも創作に好影響ばかりもたらすというわけではありません。私は長らくサラリーマンをしながら作家活動をしていたのですが、「明日のプレゼンの準備全然できてないよ、どうしよう……」といったような焦燥に駆られ不安に苛まれる夜のほうが、かえって自分の作品に没頭できたように記憶しています。もっと若い頃には温泉宿を一週間ほど逗留して書き下ろしの単行本の執筆に専念しようとしたこともあったのですが、広い和室のゆったりとした空間やいつでも温泉に入れるシチュエーション下ではさして筆が走らず、むしろ宿から帰る途上の電車の中で、座席に腰掛けてキュッと身を縮めて膝の上に置いたノートパソコンでカタカタやっていたときのほうが捗りました。ひょっとするとヘミングウェイも肉体に適度な負荷を与えることで、精神に隙が生まれることを避け、もって執筆に集中しようとする狙いがあったのかもしれません……というか、話を進めるためにも、一旦この仮説を前提として、本論に入りたいと思います。
さて、書くというアウトプットではなく、読むというインプットにおいても、適度なストレスは有効でしょうか? 私はおおいに可能性があると思っています。実際に、人体を想定しながら「立って読む」ことの具体を考えてみましょう。
第一に、手および腕について考えてみましょう。紙に印刷された書籍を読む場合、私は両手を使います。右手は本を開く作業に、左手はページをめくる(送る)動作にそれぞれ費やします。うつむいたままだと首が疲れるので、ある程度は目線を下げはするものの、そこまで落とさずに済むように両腕は軽く持ち上げて、本自体が大胸筋上部ぐらいの高さに来るよう調節します。
第二に、腰から下の下半身について考えてみましょう。両手両腕は上述のように本の固定およびページ操作に専従しますから、「立って読む」ためには全身を支える動作を下半身に任せなければなりません。電車などの揺れる構造物を想定すると、ある程度シビアに肉体をコントロールする必要性があります。フラフラしてしまうようでは、結果的に上半身も揺れてしまい、必然、読むことに難儀します。踵や脹脛でしっかり地面に根ざすように意識しつつ、膝を柔らかく使って不意の振動にも対処できるよう構え、それらの動きを大腿部および腰周りの筋肉を総動員して支配しなければなりません。
第三に、背骨から頚椎、そして頭部へと至る肉体の部分について考えてみましょう。私の場合、読む際には目という器官を用いるわけですが、他の部位はさておき、目への過度なストレスは避けなければ、一定時間以上の読書はままなりません。現実問題としてどうしたって目も疲弊するわけですが、そのスピードは極力他の部位で緩和したい。そこで重要になるのが首、そして首を引っ張り上げる背骨および背筋たちの動きです。背を丸めてしまうと、立っているがゆえに避けられない重力の魔手に簡単に堕ちます。ですから背筋に力を込めて、頭部を持ち上げるような意識を注ぐ必要があります。本を読むときぐらい、頭を下げたくはないですからね。
第四に、脳そのものについて考えてみましょう。当然ですが読むという行為の根幹を司るのは(まあ、私も専門家ではないのでよくわからずに書いてしまっていますが)脳です。文字情報を処理し、思考可能な対象として、言葉に置き換える作業をしてくれるのは、私の脳以外にありえません。実際に内部でどのような処理がなされているのかは本論とはかけ離れる内容となりますし、また私にそこを語る能力もないためよしておきましょう。問題は、「立って読む」行為がもたらす読書体験の質的変化です。
第一から第三までの考察でうっすら想像できるように、「立って読む」際には、かなりの身体的拘束が発生することがわかります。簡単に言えば、肉体の自由度が極めて減るわけです。椅子に座っていれば脚を組もうがプラプラさせようが地団駄踏もうがご随意にという具合ですが、立つ場合はそんな自由は消し去ります。立つことにまず肉体が専念しなければならないからです。
この肉体の不自由性は、読書体験においてある視点をもたらしてくれるかもしれません。当然ですが、立つことに肉体が専念せざるを得ないため、私のボディは他に余計なことができなくなります。ある意味では、集中できているという見方もできるかもしれません。「立って読む」ことをする私の肉体は、本来ならば生じたであろう各種の身体的反応もまた制限されるのですから。
具体的には感情の発露を身体を経て表現することがほぼ不可能になります。例えば読書を通じて興奮したとき、ベッドに寝転びながらその本を読んでいたのならば、私はブサイクな尻を持ち上げて膝から下の脚を激しく上下させつつ「ビッタンバッタン」をしたかもしれませんが、立っている以上、そんなマネはできません。「悶絶」という感情の起伏に伴う身体性はいくつかのパターンが考えられますが、いかなる些細な動作にも「立って読む」読書体勢はシビアな制約をもたらします。身悶えだってできないし、四肢を震わせることも無理、もっとシンプルに手に汗握ることだって本を持つことに専念しなければならない両手たちからクレームが来る動作になってしまいますから、やはり不可能なのです。
因果が逆だと指摘する方もいらっしゃるでしょうが、やってみるとわかります。「立って読む」以上、過度の心理の動きを肉体が自ずと抑制するために、結果として非常に冷静に文章を目で追うようになるのです。いつ何時でも私の心を震わせてやまない、私の愛するタイトルたちで「立って読む」実験をしてみましたが、ドストエフスキーの『賭博者』も『貧しき人々』も、太宰治の『津軽』も、白鳥士郎の『りゅうおうのおしごと!第5巻』も、北杜夫の『さびしい王様』も、バルトの『表徴の帝国』も、石川啄木の『喰うべき詩』も、従来の読みごたえと比較してみると、幾分以上に冷静に読めてしまいました。
無論、おもしろくなかった、ということはありません。それらを私はやはり楽しく読みましたし、愛すべきテキストたちへの愛を再確認する作業において遜色はなかったと断言します。一方で肉体の反応はやはり露骨に異なった事実も否定できません。わかりやすい例ですと、涙が出ませんでした。確かに感動はするのですが、そして私は『賭博者』でおばあさんが大損するシーンや『津軽』でタケと出会った直後の場面などでは何度読み返しても涙腺が緩んできた人間なのですが、「立って読む」とどうにかこうにか涙が瀬戸際で押しとどまり、私の目やにで汚れたシワだらけの目尻を湿らせることは、ついにありませんでした。
立っている以上、肉体の制御はかなりの部分で視覚に委ねられるわけですが、涙は視覚の精度を著しく下げるでしょうから、私の身体がそれを危険と判断し、ギリギリのところで落涙に至らせなかったのかもしれません。
その上で得た発見……というと大げさに聞こえるかもしれませんが、冷静にならざるを得ない私の身体は、それまで私が決して丁寧には読んでいなかった箇所への、新たな視座をもたらすこともしてくれました。肉体の反応をシャットアウトできるため、記された文字たちに集中できたからかもしれません。『津軽』で言えば、クライマックスよりもむしろ津軽到着直後の場面における小さな叙述たちの意味や、『賭博者』で言えば、主人公の目線で乱暴に語られる脇役たちのささいな言動の価値などに、私の意識が向くようになりました。無論それらを私は決して読み飛ばしていたわけではないのですが、「立って読む」ことで、思考を切り替えて読んだはずの文章たちに改めて向かい合うことができた、という意味になるでしょうか。
というわけで長くなりましたが、要するに「立って読む」による肉体への制約は、思考に新たな視点を呼び込む可能性もある、という話でした。文芸表現に興味がある方や、本が好きだという方は、ぜひとも実践してみてください。上述のように既読の書籍で実験してみると、発見の有無をよりクリアに確認できるでしょう。また、私の実験中に用いた書籍は、すべて判型は文庫本サイズです。A5判の上製本で「立って読む」を体現するのはあまりにも身体への負荷が大きすぎると判断したからですが……あえて肉体への枷を強めたいと狙うならば、大きい本をどうにか両手で持ち上げながら、立ち尽くしつつ読んでみるというのも、何か新しい出会いを生むかもしれません。
本を読むという行為は、単に目で文字を追いかけるという意味ではないのです。読書は身体がするのです。全身全霊を賭して言葉に挑むアクション、それが読書なのです……という真実を、一度実体験するためにも「立って読む」を私はおすすめします。もちろん、無理のない範囲で、怪我の危険などを排除した上で、かつ周囲に迷惑をかけることがないように。
文芸コース主任 川﨑昌平
文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事
-

文芸コース
2022年06月27日
【文芸コース】「一人称」と「三人称」ってどう違うの!
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、文芸コースに在籍する方、あるいは文芸コースに興味があってこのブログを呼んでくださっている方……どうです? …
-

文芸コース
2021年01月17日
【文芸コース】卒業生紹介「文芸のある風景」
通信教育部のパンフレットでは、毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のエピソードなどをお聞きしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸…
-

通信教育課程 入学課
2025年10月25日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …