

芸術教養学科
- 芸術教養学科 記事一覧
- 【芸術教養学科】「で、何を教えるの?」
2023年08月08日
【芸術教養学科】「で、何を教えるの?」
みなさん、こんにちは。芸術教養学科の岩元です。この4月に着任して、初めてのブログ投稿です。どうぞよろしくお願いします。

写真は都内在住の私が在籍する、外苑キャンパスの入り口です。ここ数ヶ月、友人に「京都芸術大学に着任した」と告げると、「え!じゃあ今度京都行くよ!」といった前のめりな返しがあり、「いや、東京にいるのよ」と答えると若干がっかりされる、というやりとりが頻発しております。
ひょんなところから京都の持つ「人を惹きつける力」を感じるとともに、少々複雑な気持ちになります。
■「で、何を教えるの?」
そして、おおよそ次に聞かれるのが、「で、何を教えるの?」という質問。当然です。「教員」として着任する人に、何を教えるのかを尋ねることはごくごく自然なことです。しかし、この質問の回答に窮してしまうのです。
大雑把にいえば「デザイン思考を教えるよ」と言っても間違いではありません。ただ、この芸術教養学科はフルオンラインの芸術大学。教えるといっても、私が直接教壇に立って講義を行うわけではありません。講義は動画教材として豊富に用意されていますし、通学不要のコースですから、学生のみなさんと実際にお会いする機会も極めて限られています。
ですから、「いや、講義もしないし、学生の方と直接会うこともほぼ無いんだよ」と説明するのですが、より困惑させてしまう一方。「え?どういうこと?」「じゃあ、何してるの?」と、いうことになります。
では、実際のところ、主に何をしているのか?
■「じゃあ、何してるの?」
まずはレポートの講評・採点業務です。着任前に過去のブログを見て「採点の祭典」(https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=98742) と称される怒涛のレポート添削の日々に戦々恐々としておりました。そして早速5月、そしてこの8月と洗礼を受けています。
1年早く着任された宮先生が「血まなこで読んでいる」とおっしゃっていたのですが、そのとおりでした。なかなかの数かつ分量のレポートなのですが、先輩方は一つ一つとても真剣かつ丁寧に講評されており、新参者の私には神業のようにも感じてしまいます。負けじと目をこらして、何より学生のみなさんの綴る熱量のこもった言葉を味わいながら、講評させていただいています。(このブログを執筆している今日もまさに、時折外苑の緑に包まれて、一息ついては、採点にも取り組んでいます。)

そしてもう一つは学生のみなさんとのオンラインコミュニケーションです。月に一度のオンライン学習相談会「フライング・カフェ」の企画・運営や、在学生・卒業生・教員をつなぐSNS「airUコミュニティ」を通じた情報発信・日記投稿&閲覧、質問対応など、直接会えないからこそ様々なかたちでのやりとりを行なっています。また担当している「芸術教養演習1」「芸術教養演習2」の授業では、近しいテーマで取り組む少人数グループに分かれて、サイト上の掲示板でのテキスト投稿によるディスカッションも行われます。
■着任して驚いたこと
ちなみに着任して驚いたことの1つに、学生のみなさんのあたたかくて積極的な交流姿勢があります。
「airUコミュニティ」で、どなたかからの質問やお悩み、そして「初投稿です」といった書き込みがあると、学生の方や卒業生コーチの方々から、すかさずコメントや「いいね」がつきます。また「フライング・カフェ」で、相互交流のブレイクアウトセッションを行うと、緊張しつつもあっという間に打ち解けて、自己紹介の時間が足りなくなる、といったグループにもたくさん遭遇しました。「芸術教養演習1」「芸術教養演習2」のディスカッションでは、お互いの調査に対して質問や感想を伝え合ったり、自分が知っている情報を提供したりすることによって相手の調査に貢献する様子がとてもよく見受けられます。
私はよりよい関係構築のためには「レスポンス」や「リアクション」といった「反応を示すこと」がとても大切であると考えています。オンラインのコミュニケーションであれば尚更です。そのようなやり取りが其処彼処で見られることに感動してしまいました。
聞けば、このような風土は早川先生が旗振り役として立ちながら、1期の学生のみなさんの頃から主体的に紡がれてきたものであるとのこと。「フルオンラインでも豊かな大学生活は送れるものである」と、なかば確信めいた気持ちにさせてもらえる体験でした。
■今年は「芸術教養学科設立10周年」
他にも大学としての委員会業務やフルオンラインでの学習支援施策の検討、ワークショップやコンテンツの開発などに取り組んでいます。
中でも今年度は記念すべき「芸術教養学科設立10周年」ということもあり、通常業務と並行して学科一丸となって様々な記念イベントの企画にも取り組んでいます。こちらについては、またあらためてご紹介させていただく機会があるかと思います。
■「で、何を教えるの?」
さて、つらつらとこの4ヶ月のお仕事状況を紹介させていただきました。ひるがえって冒頭の「で、何を教えるの?」という質問に対する私の答え。それは、「何かを教えるというより、広く芸術やデザインについて学びたいと思って踏み出した人を、全力で後方支援する仕事なんだ」ということです。少し長い説明ですが、そう表現するのが今最もしっくりきています。
私がこれまで一貫して仕事の軸としてきたこと。それは「本領発揮の支援」です。ここでもそのような貢献をしていけたらと考えています。これからどうぞよろしくお願いいたします。
\祝・開設10周年/
2013年「手のひら芸大」第一号として開設された芸術教養学科の10周年記念イベントの様子を公開いたします。是非ご視聴ください。
芸術教養学科|学科・コース紹介


写真は都内在住の私が在籍する、外苑キャンパスの入り口です。ここ数ヶ月、友人に「京都芸術大学に着任した」と告げると、「え!じゃあ今度京都行くよ!」といった前のめりな返しがあり、「いや、東京にいるのよ」と答えると若干がっかりされる、というやりとりが頻発しております。
ひょんなところから京都の持つ「人を惹きつける力」を感じるとともに、少々複雑な気持ちになります。
■「で、何を教えるの?」
そして、おおよそ次に聞かれるのが、「で、何を教えるの?」という質問。当然です。「教員」として着任する人に、何を教えるのかを尋ねることはごくごく自然なことです。しかし、この質問の回答に窮してしまうのです。
大雑把にいえば「デザイン思考を教えるよ」と言っても間違いではありません。ただ、この芸術教養学科はフルオンラインの芸術大学。教えるといっても、私が直接教壇に立って講義を行うわけではありません。講義は動画教材として豊富に用意されていますし、通学不要のコースですから、学生のみなさんと実際にお会いする機会も極めて限られています。
ですから、「いや、講義もしないし、学生の方と直接会うこともほぼ無いんだよ」と説明するのですが、より困惑させてしまう一方。「え?どういうこと?」「じゃあ、何してるの?」と、いうことになります。
では、実際のところ、主に何をしているのか?
■「じゃあ、何してるの?」
まずはレポートの講評・採点業務です。着任前に過去のブログを見て「採点の祭典」(https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=98742) と称される怒涛のレポート添削の日々に戦々恐々としておりました。そして早速5月、そしてこの8月と洗礼を受けています。
1年早く着任された宮先生が「血まなこで読んでいる」とおっしゃっていたのですが、そのとおりでした。なかなかの数かつ分量のレポートなのですが、先輩方は一つ一つとても真剣かつ丁寧に講評されており、新参者の私には神業のようにも感じてしまいます。負けじと目をこらして、何より学生のみなさんの綴る熱量のこもった言葉を味わいながら、講評させていただいています。(このブログを執筆している今日もまさに、時折外苑の緑に包まれて、一息ついては、採点にも取り組んでいます。)

そしてもう一つは学生のみなさんとのオンラインコミュニケーションです。月に一度のオンライン学習相談会「フライング・カフェ」の企画・運営や、在学生・卒業生・教員をつなぐSNS「airUコミュニティ」を通じた情報発信・日記投稿&閲覧、質問対応など、直接会えないからこそ様々なかたちでのやりとりを行なっています。また担当している「芸術教養演習1」「芸術教養演習2」の授業では、近しいテーマで取り組む少人数グループに分かれて、サイト上の掲示板でのテキスト投稿によるディスカッションも行われます。
■着任して驚いたこと
ちなみに着任して驚いたことの1つに、学生のみなさんのあたたかくて積極的な交流姿勢があります。
「airUコミュニティ」で、どなたかからの質問やお悩み、そして「初投稿です」といった書き込みがあると、学生の方や卒業生コーチの方々から、すかさずコメントや「いいね」がつきます。また「フライング・カフェ」で、相互交流のブレイクアウトセッションを行うと、緊張しつつもあっという間に打ち解けて、自己紹介の時間が足りなくなる、といったグループにもたくさん遭遇しました。「芸術教養演習1」「芸術教養演習2」のディスカッションでは、お互いの調査に対して質問や感想を伝え合ったり、自分が知っている情報を提供したりすることによって相手の調査に貢献する様子がとてもよく見受けられます。
私はよりよい関係構築のためには「レスポンス」や「リアクション」といった「反応を示すこと」がとても大切であると考えています。オンラインのコミュニケーションであれば尚更です。そのようなやり取りが其処彼処で見られることに感動してしまいました。
聞けば、このような風土は早川先生が旗振り役として立ちながら、1期の学生のみなさんの頃から主体的に紡がれてきたものであるとのこと。「フルオンラインでも豊かな大学生活は送れるものである」と、なかば確信めいた気持ちにさせてもらえる体験でした。
■今年は「芸術教養学科設立10周年」
他にも大学としての委員会業務やフルオンラインでの学習支援施策の検討、ワークショップやコンテンツの開発などに取り組んでいます。
中でも今年度は記念すべき「芸術教養学科設立10周年」ということもあり、通常業務と並行して学科一丸となって様々な記念イベントの企画にも取り組んでいます。こちらについては、またあらためてご紹介させていただく機会があるかと思います。
■「で、何を教えるの?」
さて、つらつらとこの4ヶ月のお仕事状況を紹介させていただきました。ひるがえって冒頭の「で、何を教えるの?」という質問に対する私の答え。それは、「何かを教えるというより、広く芸術やデザインについて学びたいと思って踏み出した人を、全力で後方支援する仕事なんだ」ということです。少し長い説明ですが、そう表現するのが今最もしっくりきています。
私がこれまで一貫して仕事の軸としてきたこと。それは「本領発揮の支援」です。ここでもそのような貢献をしていけたらと考えています。これからどうぞよろしくお願いいたします。
\祝・開設10周年/
2013年「手のひら芸大」第一号として開設された芸術教養学科の10周年記念イベントの様子を公開いたします。是非ご視聴ください。
芸術教養学科|学科・コース紹介

おすすめ記事
-

芸術教養学科
2022年09月05日
【芸術教養学科】新入生のリアルな声から迫る!芸術教養学科とは?
今回は、客観的な数値データや新入生のリアルな声から、「芸術教養学科(手のひら芸大)」の本質に迫りたいと思います。 まず、新入生のみなさんに以下の質…
-
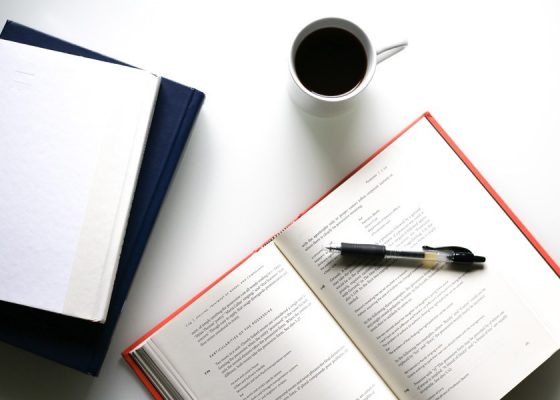
芸術教養学科
2023年07月25日
【芸術教養学科】社会人が学ぶということ〜自負と謙虚
芸術教養学科 早川克美 人生、30年、40年、50年、60年、70年、生きた時間だけ様々な経験を積み、それが生きた証であり、その人の自負となります。自負の「自」…
-

芸術教養学科
2023年06月20日
【芸術教養学科】アートを学びたい人にとっての「デザイン思考」
こんにちは、芸術教養学科教員の下村です。 今これを書いているのは、6月の中旬。入学や異動のどたばたも一段落し、嵐のようだった春期の添削もちょうど先ほど終わったと…






























