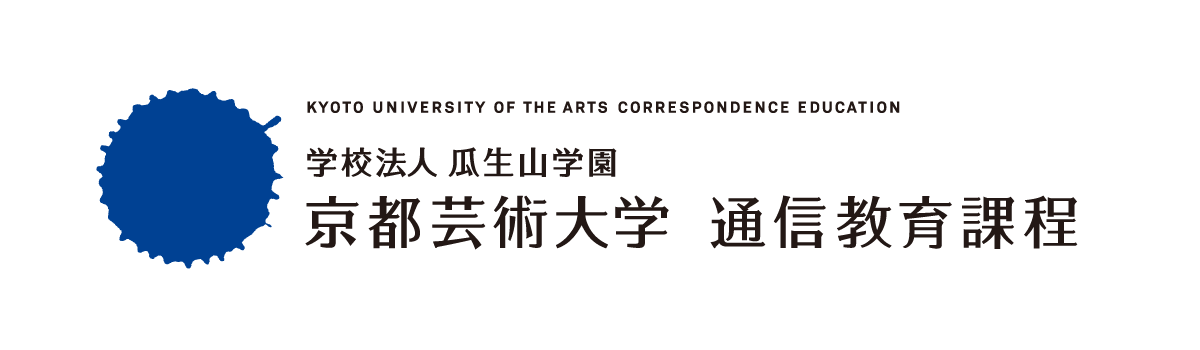文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】本を読むということ 4/なぜ本を読むのか。
2023年09月02日
【文芸コース】本を読むということ 4/なぜ本を読むのか。
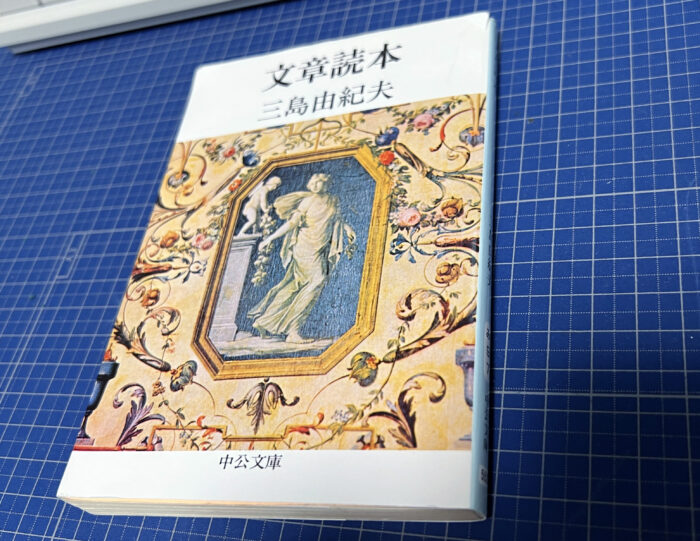
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。
文芸を学びたいという方、あるいは本学文芸コースに在籍する学生の方のために、「本の読み方」あるいは「本を読むということ」の意味を、もっと言ってしまえば「よりよく本を読むためには、どうするべきか」を、私なりの観点から論じようと思い、この連載のような原稿をスタートしてみました。
特に「本はこう読めばよい!」といった正解のようなものを、読者の皆さんに押し付ける腹積もりはないので、「読書におけるひとつの(風変わりな?)視点」のようなものを、提供できればと思っています……という前口上で毎度拙稿を披露させてもらいましたが、今回は、まだ述べていなかった「なぜ読むのか」という部分、すなわち文芸を学ぶ上での「読むこと」の根本的な意義や価値について、可能な限りわかりやすく語りたいと思います。
なぜ本を読むのか。
文芸コースでは「書くこと」と「読むこと」の双方を重視しています。どちらか一方ではダメなのです。読まずに書くだけではいずれ語彙もアイデアも枯渇します。書かずに読むだけではあなたの価値と可能性を誰も知らないまま終わってしまいます。両者は文芸という学びにおいては切っても切れない間柄、ですから「書くこと」と「読むこと」はどちらも大切にしましょう……といった内容をしょっちゅう話しているのですが、つい最近、学生のひとりからこんな質問を受けました。
「書くことも読むことも大切だというのはよくわかりましたが、書きながら読むことはできませんし、読みながら書くことも難しいですよね? 順番というものはあるんですか?」
鋭い質問だと思いました。確かに人間、ページに目を落としながらペンは握るのはなかなか難儀しますし、猛然とキータイプしつつブラウザで電子書籍をスクロールするのもそこそこ苦労するものです……とお茶を濁すようでは、主任の重責はつとまりません。私は間髪を置かずに解答しました。
「書くことです。まず、書く。読むのはそれからです」
私があまりにも堂々と答えすぎたせいか、あるいは一を聴いて十を知る方だったのか、学生は「……わかりました。ありがとうございます」と神妙に返事をするのみで、それ以上の会話が生まれることはありませんでした(あまりにも解答として不足であることは明白なので、それが原因となって今回の文章を書いている側面もあります)。
が、しかしながら、よく考えればわかるように、この流れは本来的には逆であるようにも思えます。「まず、読むことが先じゃないのか。読むことへの学びを深めてこそ、書くということをよりよく学べるのでは?」とする意見が呈されれば、私は正直、全力で首肯するでしょう。全くその通りだと思うからです。
紺屋の白袴というぐらいですから、なるほど、自分の着衣に無頓着なファッション・デザイナーはこの世に存在するかもしれません。誰かが着る服をクリエイションする創造性と、自身が必要に応じて纏う衣類への意識とが、おびただしい乖離を見せる事例は、ひょっとすると探せばあるかもしれません。
しかし、例えば食事なら? 一流の料理人がいたとして、お客に料理を提供して喜ばせる技術に長けた人間がいたとして、さて当人が食に無頓着ということがあるでしょうか?
日本各地、四季折々の食材に精通し、古今東西の調理法を遍く修め、日夜多くの食通を唸らせる凄腕の料理人がいたとして、その人物が口にするものといったら味も素っ気もないジャンクフードばかり、あるいは栄養が摂れさえすればよいとばかりにサプリメントのような食品ばかり……ということがあるでしょうか? 私はないと思います。優れたアウトプットをする人間は、やはり秀でたインプットを平素から実践しているものです。
同じように、優れた文章を書く人間は、私の経験から断言させてもらえば、やはり秀でたインプット、すなわちこの場合で言えば、文章を読むという行為において、秀逸な態度を示すものです。ですから、読むという行為は、まず間違いなく書くという表現において不可欠であり、あるいは相互補完的に両者の重要性を当人にとって意識させるものであると、私は考えています。
しかしながら、読むという行為は、実はそれほど簡単な作業ではありません。単に文字が読めるとか、言葉の理解に難がないとか、そういったレベルの話だけでは、太刀打ちできない部分が、読むという行為には存在します。そのあたりの、読むことの難しさについて、言及している過去の名文を参照してみましょう。
チボーデは小説の読者を二種類に分けております。一つはレクトゥールであり、「普通読者」と訳され、他の一つはリズールであり、「精読者」と訳されます。チボーデによれば、「小説のレクトゥールとは、小説でいえばなんでも手当たり次第に読み、『趣味』という言葉のなかに包含される内的、外的のいかなる要素によっても導かれていない人」という定義をされます。新聞小説の読者の大部分はこのレクトゥールであります。一方、リズールとは、「その人のために小説世界が実在するその人」であり、また「文学というものが仮の娯楽としてではなく本質的な目的として実在する世界の住人」であります。リズールは食通や狩猟家や、その他の教養によって得られた趣味人の最高に位し、「いわば小説の生活者」と言われるべきものであって、ほんとうに小説の世界を実在するものとして生きていくほど、小説を深く味わう読者のことであります。私はこの「文章読本」を、いままでレクトゥールであったことに満足していた人を、リズールに導きたいと思ってはじめるのであります。これはまったく一作家にすぎぬ私にとって僭越な言葉でありますが、作家たることはまたリズールたることから出発するので、リズールの段階を経なければ文学そのものを味わうことができず、また味わうことができなければ、自分も作家となることができません。
『文章読本』(三島由紀夫著、中央公論新社、一九九五年、改訂版)より引用
文中のチボーデとは『小説の美学』(生島遼一訳、白水社、一九四〇年)や『スタンダール伝』(大岡昇平訳、青木書店、一九四二年)など、フランス文学に関連する著作を多数持つ、フランスの文芸批評家であったアルベール・ティボーデ(一八七四〜一九三六年)のこと。三島由紀夫は自身の『文章読本』を書く上で、ティボーデの言葉を引いて、果敢に読書のあり方そのものを問おうとします。
ちなみにこの三島由紀夫の『文章読本』、本当におもしろい一冊で、文芸を学ぼうとする人であれば天地がひっくり返っても目を通しておいてほしい文献のひとつなのですが、特にそのおもしろさを私なりにここで説明させてもらうとすると、簡単に言えば、三島由紀夫は明快に、「誰でも書ける文章」のようなものを批判しているのです。
1970年代当時にあった表現上の潮流、作中の三島由紀夫の言葉を借りるならば「素人文学」に対する、強い拒絶の意志が三島由紀夫の『文章読本』にはあります(読めばわかりますが、三島由紀夫は素人が書くことを否定しているのではありません。定型化された文体のようなものを未来の書き手に押し付けんとする簡便な形式主義のようなものを嫌っているのだと……私は思います)。
全編を通じて噎せ返るほど濃厚に香り漂う三島由紀夫の文章哲学、あるいは文章表現における美学のようなものは、読むだけでも楽しいですし、これから文章を書こう、なかんずく「凡百の作家志望者とはもう根っこから異なる自分だけの文章をモノしたい!」という野望に燃えている人にとっては、まさにバイブルになりかねない書物と言うことができます。それくらい強烈な表現意識が、堅牢な美意識が、お腹が苦しくなるぐらい味わえる、名著なのです。私はとてもじゃないですが、三島由紀夫の説く鮮烈な文章軌範に倣う覚悟がないため、読むだけにとどめてはいますが……書いたり読んだりする自分自身を顧みるための教科書として、時々読み返します。発見をもたらしてくれたり、あるいは警告として働いてくれたり……こんな言い方は憚られますが、まったく、便利な一冊なのです。
さて、その『文章読本』の冒頭部分において、三島由紀夫がなぜティボーデの言葉を引いたかと言えば、理由は書いてある通りで、「いままでレクトゥールであったことに満足していた人を、リズールに導きたいと思ってはじめるのであります。」とあることからもわかるように、読者への啓蒙としての意欲がきっぱりと立ち現れているためです。ですから、三島由紀夫の立場に我が身を重ねるのであれば、三島由紀夫の『文章読本』は文字通り、文章を読むための本、本を読む読者のための本であるということができます。
一方で、三島由紀夫自身が書いているように「作家たることはまたリズールたることから出発するので、リズールの段階を経なければ文学そのものを味わうことができず、また味わうことができなければ、自分も作家となることができません。」ということですから、読者の立場からすれば、レクトゥール(普通読者)からリズール(精読者)を経て、作家にならんとする観点が読み手の思惑にあったとしても道を外してはいないわけです。
ここで私は冒頭の問題に話を戻したいと思います。私はなぜ「書くことが先である」のように述べたのか。どちらも大切であると言うくせに、「書くこと」が「読むこと」より先に来る順序とした理由はどこにあるのか。
結論はシンプルで「書くことをするためには、読むことが必要だが、しかし、まず書かなければ、読むこともままならないから」です。あくまでも私の考えに準拠した学びの流れではあるのですから、これが正解とは思いません。しかし、三島由紀夫(が引用したティボーデ)の言葉を借りるならば、誰もが順序立ててレクトゥールを経てリズールに至り、ようやく作家としての基礎を固める……という道筋を歩めるとは限らないと私は思います。
まず、やっぱり、書きたいという欲望があるならば、書いてみるのが、書いてしまうのが、表現を志した人間の性というものでしょう。その上で失敗したり挫折したり、うまくいかない経験をたっぷりと味わった後、改めて読むことをする。然る後、読書体験から自分の表現の未熟さを嫌というほど理解してから、再度筆を執る……こういった流れも、表現を学ぶルートには確かにあると思うわけです。
書く→うまく書けない→たくさん読む→たくさん書く
ルートを視覚化するとこんな具合です。迂遠と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは私の個人的感慨ですが、表現に近道はないと信じています。否、むしろ遠回りするぐらいが、表現を楽しみ、表現を能動的に実践する上では、かえって効率的なのではないかとすら、ここ最近は考えています。
近節流行りの言葉にタイパという用語があるようですが、整備された時間的効果が高いとされる方法論をなぞったところで、自分自身の理想とする表現がそこにあるとは、私には到底思えません。用意された表現のアウトプットに自身を適合させることに抵抗がないならば、既存のフォーマットを選ぶだけの学びにも価値はあるかもしれませんが……そこから生まれる表現が持つ(であろう)既視感は、少なくとも私にはおもしろいものには感じられないのです。
ですから、本稿を読んでくださった皆さんが、皆さん個々人の表現を体現しようとするのであれば、これと定められた道筋を歩むのではなく、皆さん自身で、独自の学びを開拓してほしいと私は願っています。書いてみたが、なかなか思うように書けなかった……そうした実感を経てこそ、ここまで書いてきた読むという行為への私からのいくつかの提案が、皆さんにとって価値を持つであろうと、私は信じています。
それに、よくよく考えれば当たり前のことかもしれませんが、要するに、誰だって自分がレクトゥールであるかリズールであるかなんて、すぐには自覚的に判別できっこないわけです。自身の読書体験を振り返って、「うん、俺はまだまだレクトゥールだな」とか「私はそろそろリズールの域に達しているかも」とか、そんな自己分析は、少なくとも客観的公平性を有するレベルにおいては(まあ、そんなもの持たなくてもよいとは思いますが)誰もが言及できないはずのもので、私だって職業的に本を読むことをしていますが、さて自分が素人読者か精読者かと自問したところで、答えは出せません。
謙遜気味に「いやあ、私の読書量なんて全然でして……まだまだレクトゥールですよ」と薄ら笑いを浮かべることは簡単にできますが、「いや、お前、謙譲の美徳の精神の発露のつもりでしゃべっているかもしれんが、本当に読書量、不足しているぞ?」と碩学たちに指弾されたら恥ずかしくなって貝のように押し黙ってしまうでしょうし、編集者からお世辞混じりに「さすが、よく読んでいらっしゃいますね」と煽てられれば、「まあねえ、僕もこの世界、長いですから、ha,ha」と臆面もなく得意になってしまうかもしれません。
つまり、読書家であるか否かなど、自分ではわからないことであり、特段わかる必要もないわけですが、しかし、書くという行為を経ると、自分には真剣に読書量が不足していると理解できたり、あるいは特定の領域においては効力のある読書体験を記憶していると発見できたり……いずれにせよ何らかの示準を手にすることができるわけです。
もちろんこんなふうに偉そうに書いている私ですが、いつだって「もっと読まないとダメだなあ」と我が身を省みて思うことばかりです。ゆえに、書くことをしつつ、いつも読むことをしています。もう少し若い頃は向こう見ずというか、無鉄砲というか、ろくに読むことをせずに、無我夢中で筆を走らせてしまったものですが、齢四十を過ぎ、文字通り馬齢重ねてしまった身としては、正直リズールたる素質が自分にあるかどうかも疑わしく思いつつも、しかし、リズールたらんと志さない限りは、もうにっちもさっちもいかねえなと自分に悪態吐きたくなる日々でしたので、心を入れ替えて、まずはリズールになろうと心機一転、ここ最近は本を読み耽ることをしているわけです。
無論、心を入れ替えたとしても、即座に立派な読書家になれるわけでもありません。読むという行為は、一見単純そうに思えて、しかし、その実、かなりの思考するべき余地を持つ、複雑で有機的で感情的でありながら人間工学的でもあり……そして、おもしろい活動なのです。そのおもしろさを、これからもゆっくり考えていくことにしましょう。
文芸コース主任 川﨑昌平
文芸コース| 学科・コース紹介

おすすめ記事
-

文芸コース
2022年06月27日
【文芸コース】「一人称」と「三人称」ってどう違うの!
皆さん、こんにちは。文芸コースの川﨑昌平です。 さて、文芸コースに在籍する方、あるいは文芸コースに興味があってこのブログを呼んでくださっている方……どうです? …
-

文芸コース
2022年12月01日
【文芸コース】「観察」で語彙を増やそう
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 文芸コースで講師をしていると、時折「語彙を増やすにはどうすればよいか」といった種類の質問を受けることがありま…
-

通信教育課程 入学課
2024年01月02日
【初心者でも大丈夫!】基礎から学べる通信教育部のカリキュラムとは?
これから出願するかどうか検討をはじめるといった方に向けて、ぜひ知っていただきたい初心者でもイチから芸術を学ぶことができる本学の特長をいくつかご紹介いたします。 …