

染織コース
- 染織コース 記事一覧
- 【染織コース】草津の青花を摘んで花びら染めをしました
2023年09月28日
【染織コース】草津の青花を摘んで花びら染めをしました
皆様、こんにちは。染織コースの繁田真樹子です。
染織コースの皆さんには大変馴染みのある青花ペン、水に濡れると流れて消えますので印付けや下絵に大変便利です。このペンには青花の抽出液は入っていませんが、名前の由来となっている「青花」がどんな姿なのかをご存知でしょうか?

滋賀県草津市周辺に今でもこの「青花」を栽培しているところがあります。
青花というのは通称で、学名を大帽子花(オオボウシバナ)と言います。露草の栽培変種です。
露草に比べるととても大きな花で、早朝に(この日は朝7時撮影)花が開き、正午にはしぼんでしまいます。


花弁を絞り液を和紙に幾重も染み込ませてできた「青花紙」は手描き友禅の下絵を描くのになくてはならない存在でした。青花の青い液で描いた線は水で流れて残らないので表舞台には出ない裏方の存在です。着物(手書き友禅)需要の減少や代替え品の登場で青花紙を作るために栽培する農家は現在2軒となりました。
今回私は青花を主とする農産物の生産、加工、販売、あおばな観光農園の運営、企画をされていますNPO 法人青花製彩の峯松さんにお話をうかがい青花摘み体験をするために青花畑にまいりました。

峯松さん
「かつての青花の産業というのは家族単位でお花を集めて青花紙を作るという形で成り立っていましたが今やそれは難しくなっています。新しい需要を作って地域の皆さんと共に青花の産業の新しい形をアプローチしていく事を目指してこの畑を運営しています。畑で皆さんに摘んでもらった青い花弁は食用の着色料になる予定です。そういった事で青花が皆さんに知られるようになったらと思います。」
花弁摘みは7月~8月の花が咲く時期です。詳しくはHP をご覧ください。
https://www.big-advance.site/c/135/1814
昼には萎みますので急いで花弁を摘みます。この青花は摘み取ったものを持ち帰る事もできますし、その場で重さを量り、量によっては買い取ってもらう事もできます。私はこの花弁を使って染めたかったので持ち帰ります。

絞るととても美しい青色の液が出ます。


青花を摘み、量ってもらうと80g ほど、これを持ち帰り、花びら染めをします。

先に述べました通り、水に流れますのでこのまま布を青い絞り液につけたところで色は流れます。青花の青い色素はコンメリニンというアントシアン系のもので、花びら染めはアントシアン系色素で染める方法です。チューリップやバラなどの赤や紫の花弁や葡萄(の皮)などの果実に含まれています。ですのでそう言ったものでも染められますので皆さんもお試しください。
摘み取った青花の花弁をまず酸性の水溶液に入れ色素を取り出します。

できた抽出液に絹の風呂敷を浸して色を吸収させます。
 次に色を定着させるために媒染液に浸します。これは酢酸アルミの媒染液です。浸すと赤紫色だったものが青に変化し布に定着します。
次に色を定着させるために媒染液に浸します。これは酢酸アルミの媒染液です。浸すと赤紫色だったものが青に変化し布に定着します。



青花の花びら染めで夏の空のような素敵な風呂敷ができました。

制作の様子を動画で紹介しています。
消えるという用途で使われてきた青花、これからは美しい青も活かせることを願っております。
道端に咲く露草、その変種である青花(学術名:大帽子花)の青い色は布に付いても水で流れて残りません。その性質を利用して江戸時代から糸目友禅の下絵描きに使われてきました。
今回はこの青花のお話しと、水で流れてしまうこの青花でスカーフを染めるというデモンストレーションをいたします。工程それぞれで変わる色を通して染色が化学とつながっているということをお伝えします。後半には実際の授業の様子や卒業生の現在の活動をご紹介します。
染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから
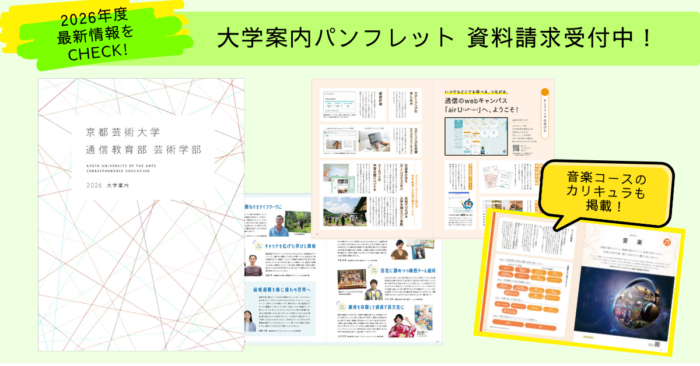
京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ
研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。
染織コースの皆さんには大変馴染みのある青花ペン、水に濡れると流れて消えますので印付けや下絵に大変便利です。このペンには青花の抽出液は入っていませんが、名前の由来となっている「青花」がどんな姿なのかをご存知でしょうか?

青花ペン(主成分はヨウ素とデンプン)
滋賀県草津市周辺に今でもこの「青花」を栽培しているところがあります。
青花というのは通称で、学名を大帽子花(オオボウシバナ)と言います。露草の栽培変種です。
露草に比べるととても大きな花で、早朝に(この日は朝7時撮影)花が開き、正午にはしぼんでしまいます。

青花(大帽子花)

露草
花弁を絞り液を和紙に幾重も染み込ませてできた「青花紙」は手描き友禅の下絵を描くのになくてはならない存在でした。青花の青い液で描いた線は水で流れて残らないので表舞台には出ない裏方の存在です。着物(手書き友禅)需要の減少や代替え品の登場で青花紙を作るために栽培する農家は現在2軒となりました。
今回私は青花を主とする農産物の生産、加工、販売、あおばな観光農園の運営、企画をされていますNPO 法人青花製彩の峯松さんにお話をうかがい青花摘み体験をするために青花畑にまいりました。

峯松孝好さん
峯松さん
「かつての青花の産業というのは家族単位でお花を集めて青花紙を作るという形で成り立っていましたが今やそれは難しくなっています。新しい需要を作って地域の皆さんと共に青花の産業の新しい形をアプローチしていく事を目指してこの畑を運営しています。畑で皆さんに摘んでもらった青い花弁は食用の着色料になる予定です。そういった事で青花が皆さんに知られるようになったらと思います。」
花弁摘みは7月~8月の花が咲く時期です。詳しくはHP をご覧ください。
https://www.big-advance.site/c/135/1814
昼には萎みますので急いで花弁を摘みます。この青花は摘み取ったものを持ち帰る事もできますし、その場で重さを量り、量によっては買い取ってもらう事もできます。私はこの花弁を使って染めたかったので持ち帰ります。

摘み方のレクチャーを受けて花弁を摘みます
絞るととても美しい青色の液が出ます。

花弁を手ですりつぶすと

たくさんの青色抽出液が
青花を摘み、量ってもらうと80g ほど、これを持ち帰り、花びら染めをします。

ふるいにかけて花弁だけにしています
先に述べました通り、水に流れますのでこのまま布を青い絞り液につけたところで色は流れます。青花の青い色素はコンメリニンというアントシアン系のもので、花びら染めはアントシアン系色素で染める方法です。チューリップやバラなどの赤や紫の花弁や葡萄(の皮)などの果実に含まれています。ですのでそう言ったものでも染められますので皆さんもお試しください。
摘み取った青花の花弁をまず酸性の水溶液に入れ色素を取り出します。

抽出液は青から赤紫色に変化します
できた抽出液に絹の風呂敷を浸して色を吸収させます。
 次に色を定着させるために媒染液に浸します。これは酢酸アルミの媒染液です。浸すと赤紫色だったものが青に変化し布に定着します。
次に色を定着させるために媒染液に浸します。これは酢酸アルミの媒染液です。浸すと赤紫色だったものが青に変化し布に定着します。
酢酸アルミ水溶液を作る

色素を吸収した風呂敷を浸す

赤紫色だった風呂敷が青に変化して定着する
青花の花びら染めで夏の空のような素敵な風呂敷ができました。

制作の様子を動画で紹介しています。
消えるという用途で使われてきた青花、これからは美しい青も活かせることを願っております。
道端に咲く露草、その変種である青花(学術名:大帽子花)の青い色は布に付いても水で流れて残りません。その性質を利用して江戸時代から糸目友禅の下絵描きに使われてきました。
今回はこの青花のお話しと、水で流れてしまうこの青花でスカーフを染めるというデモンストレーションをいたします。工程それぞれで変わる色を通して染色が化学とつながっているということをお伝えします。後半には実際の授業の様子や卒業生の現在の活動をご紹介します。
染織コース | 学科・コース紹介

大学パンフレット資料請求はこちらから
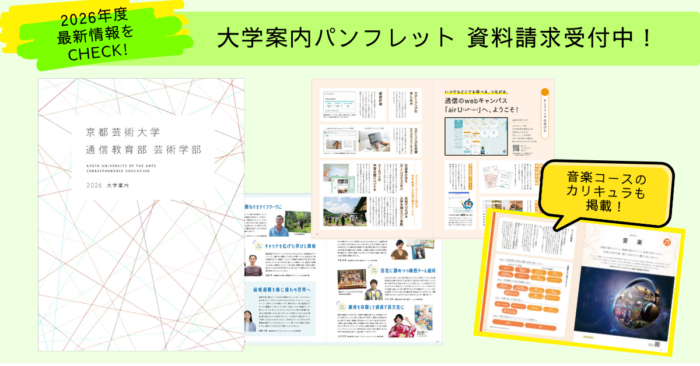
京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ
研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。
おすすめ記事
-

染織コース
2022年06月22日
【染織コース】「自由に描く・蠟染の世界」
皆様こんにちは。通信染織研究室の梅崎由起子です。 関西は梅雨に入り、乾きにくく染物がちょっとしにくい季節となりました。 しかし、季節の移ろいにも負けず、カラフル…
-

染織コース
2018年10月12日
【染織コース】いろいろな織機
みなさんこんにちは。染織コースの久田多恵です。学部の織に関する授業や大学院ではさまざまな織機を使って基本的な織り方から高度な技法まで、多種多様な織物に取り組んで…
-

通信教育課程 入学課
2020年02月20日
3人の卒業生に聞く「芸術を学ぶことで変わる、私たちの暮らし」
こんにちは。通信教育部 入学課です。 本学の入学説明会では例年卒業生をお招きし、芸大での学びの本音を語っていただく「ゲストトーク」も行っています。本学で学ぶこと…






























