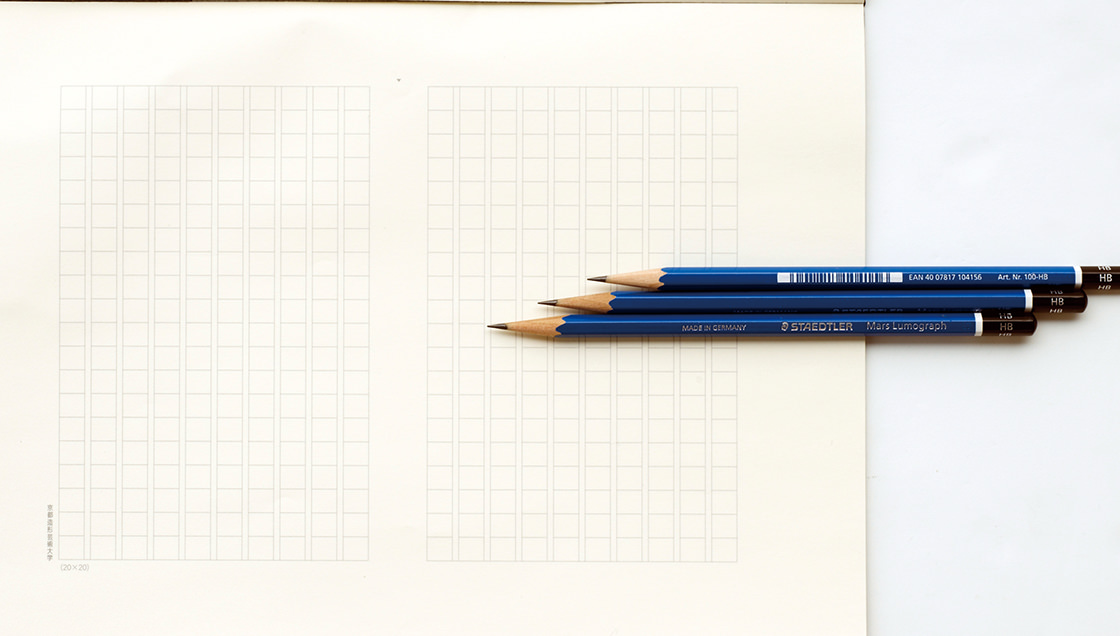

文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】文章とデザイン/第3回 行長と可能性
2024年06月26日
【文芸コース】文章とデザイン/第3回 行長と可能性

皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。
では「文章を書く上で、より深く読者をイメージするためのヒントを、デザインから学ぼう」という趣旨のテキスト、第3回目に参りましょう。
まずは図1を見てください。

フォントは筑紫Aオールド明朝(L)、文字サイズは13Q、1行40文字
私の書いた文章を、文字組みしてみたものになります。例によって面妖な内容が書かれていますが……今を去ること13年前に、河出書房新社の主催する第48回文藝賞で最終選考まで残った私の小説の、冒頭部分です。今読むと恥ずかしいのを通り越して、いっそ胸がすくような泥臭さがあって、なんだか悪くない気もしてくるから不思議です。
まあ内容は無視して、注目してもらいたいのは1行の長さです。これを専門用語で行長と呼び、意味は「1行における行頭から行末までの長さ」のことですが、言葉尻ほど単純な要素ではありません。理想的な文字組みを目指すのであれば、「文字組みアキ量設定」などを始め括弧類(「、“、〈……など)、終わり括弧類(」、”、〉……など)、読点類、句点類、中点類、連続役物、和文、欧文、縦中横表記……等々、実にさまざまな文字記号に対して、個別に設定しなければならないからです。したがって、実際の多くの書籍において、各行の行長は均一ではないことを、皆さんも体験的にご存知のはず。横組などで欧文が混じるようなケースにおいては、アルファベットは各文字の字幅が異なるため、ますます難しいものになります。そうした場合における、絶対値として固定された行の長さを、行長と呼ぶこともあります。
いずれにせよエディトリアルデザインの観点から行長を解説しようとすると、なかなかに難事業となりますから、ここでは単に最もシンプルな定義である「1行における行頭から行末までの長さ」に着目し、かつ文字数で判断する態度で見ていきましょう。図1は、縦40字です。特に文字組みアキ量設定などはいじっていません。ほぼベタです。新書などはこのぐらいの行長かもしれませんね。
それでは次に、図2を見てください。

フォントは筑紫Aオールド明朝(L)、文字サイズは13Q、1行47文字
どうでしょう? 図1と比べるとだいぶ行長が長く感じられるかもしれません。A5判型の上製本などに多そうな組み方と言えるでしょうか。
続けざまに図3を。

フォントは筑紫Aオールド明朝(L)、文字サイズは13Q、1行55文字
こうなってくると、さすがに13Qでは厳しいでしょうね。A5判上製本だとしても文字を並べすぎ……まあ、実際に私の書棚にはそれぐらい文字数を1行に詰め込んだ本もありましたが(『アートフル・サイエンス 啓蒙時代の娯楽と凋落する資格教育』バーバラ・M・スタフォード著、高山宏訳、1997年、産業図書)、図版などを多めにインサートしないとキツイというか、可読性においてやや心配になる版面になるでしょう。文字しかないのであれば、私なら2段組にします。
さて、いろいろと見てみましたが、皆さんに考えてほしいのは、「適切な行長」などではないのです。第1回からの繰り返しになりますが、本連載のテーマはエディトリアルデザインの基礎について語ることではありません。デザインの側面から、文芸表現における新たなアイデアを模索することにこそ、本懐があるのです。
と、前置きを再度確認した上で、今回皆さんに向き合ってほしいのは……「行長って逆にどこまで伸びるんだろう?」という問いかけです。

フォントは筑紫Aオールド明朝(L)、文字サイズは10.3pt
はい、ということでつくってみました。行長、もう文字数ではカウントする気になれませんね。マージン含めた可読範囲の行長という意味では、1200mmです。1メートル超え! 1ページの長辺がそんな長さだったら、もう勘弁してくれという気持ちになるはずです。刺さる本棚がそもそもなさそうですし、めくるのだって一苦労……と安直に書いてしまいましたが、本当にそうですか? 皆さんご自身の読書体験、否、「文字を読む体験」を思い起こしてください。行長1200mmって……珍しいですか?
答えはNoですよね。書籍にはコデックス(綴じた本)とスクロール(巻いた本)があるわけで、歴史的にはもちろんスクロールのほうが遥かに長く、その上で印刷技術の発展過程においてスクロールよりもコデックスのほうが支配的になったわけですが、現代はスクロール復権の時代です。だってそうでしょう? 皆さん、いつだってスクロールを読んでいますよね? Webで、インターネットで、日々スクロールしちゃっているでしょう? 正確にカウントしたことはありませんが、間違いなく私に限れば、ここ10年で、コデックスによる文字数インプット総量は、スクロールのそれに凌駕された観があります。
となれば、行長ももっとスクロールを意識してみるのはどうでしょう? 漫画だってWebToonとやらでスクロールで読ませる形態が増えてきていることですし、文芸だってスクロールして悪いわけがない。なろうやカクヨムを思い起こしてください。アレと同じです。スクロールして読ませるフィールドをつくって、その1行あたりの文字数を、1字にすれば、はい、図4のできあがり。
こうなるともう、文章そのものの質も変わりそうな気がします。私なんかは修飾節を延々と肥大化させる悪癖が文章術においてあるわけですが、それって結局、書籍ベースの行長に依存した考えた方に過ぎないんです。1行45文字とかで考えるから、「長いよ、もっと細かく文章を区切っていこう?」みたいなアドバイスをされちゃうわけで、図4のように延々長々書き続ける形態が是とされるならば、そこまで気になりません。
私の好きな絵本に『の』(Junaida著、福音館書店、2019年)というものがありますが、まさにあんな感じ。たった1行しかない、でも長大な文章を編むことができるかもしれません、行長の可能性をとことんまで広く論じ考えようとするならば。
さあ、皆さん、1行の行長をどこまでも長くしてみましょう。ページって概念そのものがコデックスというメディア特性の奴隷でしかないわけです。その呪縛から思考を解き放ち、自由な表現を実践してみてください。「ページをめくって読む? いつの時代の話をしてるんだ。アナクロもいい加減にしてくれ!」と叫びましょう。あなたの文章は改行なんてしなくていい。延々書き続けてください、どこまでも文芸表現の新たな未来目指して伸長し続けてください。その先に見えるものは、きっとあなた自身ですら出会ったことのなかった、新鮮な表現形態であるはずです。
川崎昌平
文芸コース| 学科・コース紹介
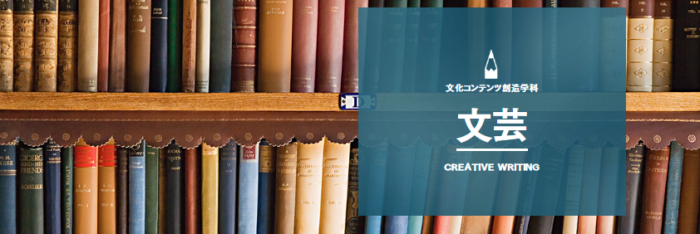
おすすめ記事
-
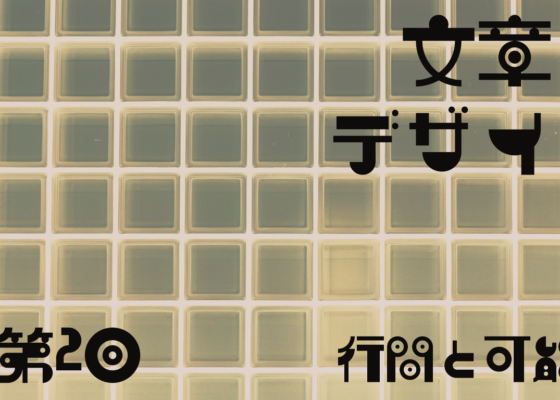
文芸コース
2024年05月27日
【文芸コース】文章とデザイン/第2回 行間と可能性
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 さあ「文章を書く上で、より深く読者をイメージするためのヒントを、デザインから学ぼう」という趣旨のテキスト、第…
-

文芸コース
2024年04月26日
【文芸コース】文章とデザイン/第1回 文章とフォント
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 早速ですが、まずは下の図1を見てください。 私の書いた2行の文章を、それぞれ4パターンの書体(フォント)によ…
-
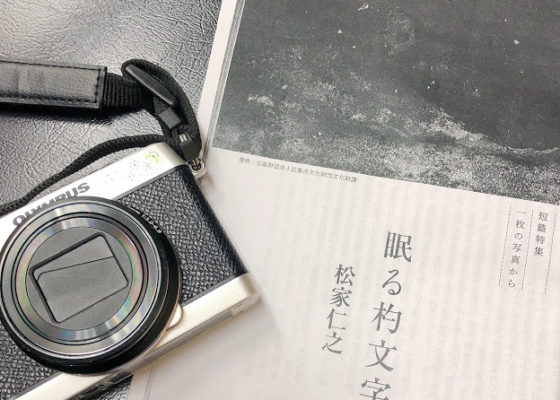
文芸コース
2019年02月08日
【文芸コース】特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」
文芸コース主催の特別講義「現実と小説のあいだにあるもの」が1月19日(土)の午後5時30分から、東京・外苑キャンパスで開かれました。講師は、作家で季刊総合誌『考…






























