

アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「飾りすぎてはいけない。素っ気無くてもいけない。意味がなくてはならず、意味深すぎてはならない。」──宮部みゆき
2024年07月22日
【アートライティングコース】「飾りすぎてはいけない。素っ気無くてもいけない。意味がなくてはならず、意味深すぎてはならない。」──宮部みゆき
 みなさん、こんにちは。
みなさん、こんにちは。アートライティングコース非常勤の青木由美子です。
怖いような暑い日が続いていますね。気温が38℃に達した昼日中、外に出た瞬間、『湯を沸かすほどの熱い愛』(1)という映画のタイトルが頭に浮かびました。ストーリーとは関係なく「沸かす」「熱い」に連想が発動したようです。映画に限らず書名や楽曲名が記憶に刻まれていて、ふとした拍子に思い出されることが、私にはあります。子供のころ愛読したケストナーの代表作『点子ちゃんとアントン』(2)はそのひとつで、何の脈絡もなく数年に一度くらいの頻度で思い浮かび、不思議な気持ちになります。映画も小説も心に響いた好きな作品ですが、ベストワンという訳ではありません。それでも強い印象が続くのは、風変りな言葉が感性の普段とは異なる部分に触れるのでしょうか。タイトルが読者に働きかける力は、出会った時に感じる以上に大きいのかもしれません。
さて、私はアートライティングコースの演習科目「ディスクリプション」を担当し、学生のみなさんの課題作品を添削・講評しています。本コースの演習科目は他に「クリティカル・エッセイ」「インタビューの方法論」「書評を書く」「ノンフィクションを書く」など。実践的な書く力をつけるカリキュラムが充実しています。どの演習科目も小論文ではなく文章作品を書くことを課題としているのがアートライティングコースの特長です。ここで言う文章作品とは、美術、建築、写真、映像、書籍、音楽、食文化、ファッション、パフォーミングアーツなど、広くとらえたアートを対象に、それぞれの価値を発見し読者に提示するテキスト、つまりアートライティングを指しています。※作品ですからもちろんタイトルが必要ですが、その制作に苦心している受講生は少なくないようです。作品にぴったりなタイトルをつけることは、プロのライターや作家、あらゆる書き手にとっても容易ではないでしょう。エッセイやインタビューに答えて悩ましさを語っているのを目にしたことがあります。
さて、どうしたら魅力的なタイトルを作れるのでしょう。
ヒントとなる本を探してみました。
※アートライティングとは何か?4月掲載、大辻都先生のブログ記事に丁寧な解説があります。ぜひご覧ください。
https://www.kyoto-art.ac.jp/t-blog/?p=116907
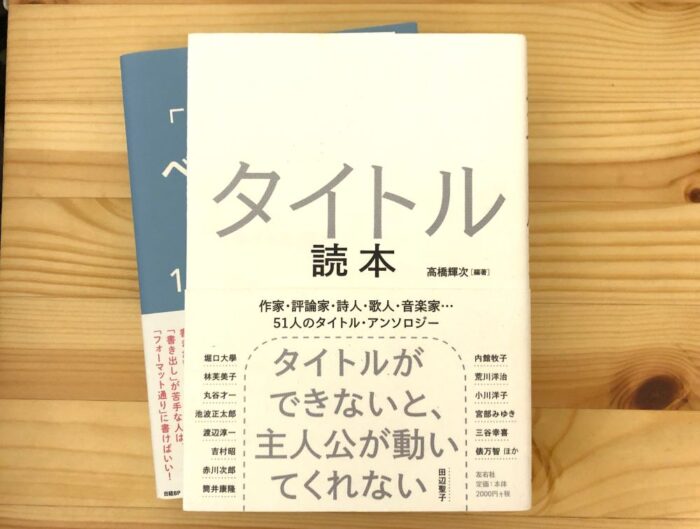
冒頭に掲げた言葉は、作家 宮部みゆきが小説のタイトルについて語ったものです。51人の作家が自著のタイトルをどのように考案し、どうつけたか、作品完成までのエピソードを明かした一冊、『タイトル読本』(3)から引用しました。このアンソロジーからは小説家、詩人、評論家、歌人、脚本家、翻訳家などベストセラー作家たちがタイトルに悩み、知恵を絞り、さまざまにアプローチを試みている姿が浮かび上がってきます。その一端がうかがえる目次「発想とヒント」は、見るだけで楽しくなります。(以下『タイトル読本』より一部抜粋)
II 発想とヒント
映画のポスターをイメージする│タイトルの付け方 恩田陸
名曲のタイトルを使う│タイトルについて 赤川次郎
テーマソングの一節を│タイトルについて 浅田次郎
気に入ったセリフをタイトルにする│タイトルをめぐる迷想 倉橋由美子
二百以上のタイトルを書き並べる│題名のつけかた 野呂邦暢
会話の中で決める│六脚の椅子と十七羽の色とり鳥 新井満
店の人に聞いてみる│小説の題 古山高麗雄
他人に任せる│「愉快」と「おいしい」の関係 林望
酒を飲む│小説の題名 吉村昭
詩人になる│題をつける 北村太郎
時代の感覚に合わせる│小説の題名 円地文子
題と内容のすきまを作らない│作品の顔 山田稔
内容に密接に結び付けない│小説の題名 阿刀田高
一度見たら永遠に忘れないタイトルを│私はタイトル(だけ)作家 山本夏彦
耳もとでささやくようにつける│背表紙たちの秘密 小川洋子
練達の書き手が揃ったエッセイ集。本のタイトルという同じお題を、実にそのひとらしく、かつ楽しげに語っています。タイトルを考えるのが大好きという恩田陸、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』を微妙な言い回しで誉める渡辺淳一、おせいさん節が炸裂してお腹が痛くなるほど笑わせてくれる田辺聖子、とまあまあ贅沢なアンソロジーです。自身のタイトルのつけ方を丁寧に解説する川本三郎、他の作家のタイトルを次々と挙げて称える荒川洋治。タイトル考案のヒントがいっぱいです。行き詰ったらご一読を。
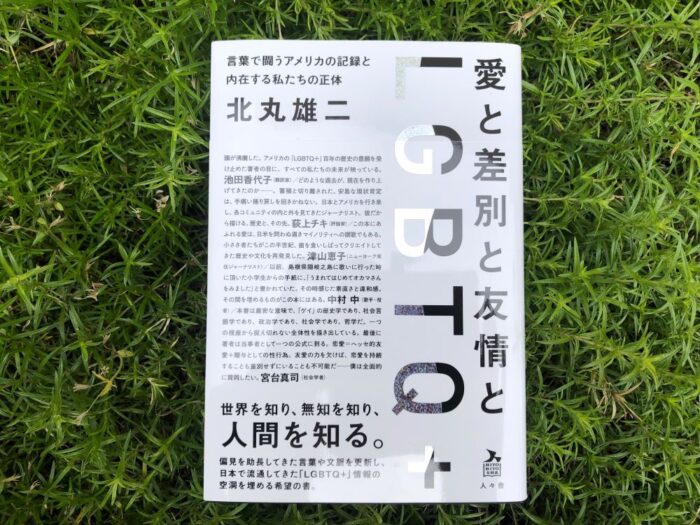
ネット書店で「文章の書き方」を検索するとおよそ1000件がヒットします。それが「タイトルのつけ方」だと4件から10件。あまりの少なさに驚きました。『 すごいタイトル㊙法則 』(4)はその数少ない中の一冊。書籍、映画、音楽、テレビ番組などヒットしたコンテンツの膨大な数のタイトルを集めて分類・分析し、鑑賞者を惹きつけるタイトルの「13の法則」を見出した力作です。
読みたくなる、観たくなる、「すごいタイトル」13の法則
① 「いちご大福」の法則 ──合わないふたつを組合せる
② 「の」の法則 ───言葉を重ねて深みをます
③ 「もしドラ」の法則 ─長い長いタイトル
④ 「プレバト」の法則──短縮形にしてヒットを狙う
⑤ 「パワーワード」の法則──インパクトのある言葉を入れる
⑥ 「なったらいいな」の法則 ──ベネフィットをタイトルに
⑦ 「数字は奇数」の法則 ──奇数を使う
⑧ 「さおだけ屋」の法則──疑問形にする
⑨ 「しなさいするな」の法則 ──命令形にする
⑩ 「お名前+α」の法則──主人公の名前入れる
⑪ 「ん」の法則 ──「ん」が入ると当たる
⑫ 「ゴロリズム」の法則 ──言葉を選び語感を整える
⑬ 「色キュン」の法則──タイトルに色を入れる(5)
『 すごいタイトル㊙法則 』が、世に溢れている文章指南書から一歩抜け出ているのは、コンテンツの種類を細かく分けている点です。書籍なら小説・エッセイを文芸とし、ビジネス書、自己啓発書、マネー本、ライフ本、ノンフィクションと分けています。TV番組もドラマ、バラエティ、朝ドラなど、細かくセグメントしてデータを解析。提唱している法則の精度を上げています。たとえば歴代本屋大賞ベスト3受賞作48作品の調査では10タイトルが①の「いちご大福の法則」に、20タイトルが②の「の」の法則に当てはまっていました。なんという確率!ただし、③以降の法則に該当する小説は全くありませんでした。
一方でビジネス書、自己啓発本、生活実用書、教養新書などの文芸・コミック以外の書籍のタイトル分析では⑤「パワーワード」の法則、⑥「なったらいいな」の法則、⑦「数字は奇数」の法則、⑧「さおだけ屋」の法則、⑨「しなさいするな」の法則が多数みられました。考えてみれば当然の結果ではあるのですが……。
著者の川上徹也氏が自ら述べているように、この本の手法は「後だしジャンケン」です。数多くの成功例にならったフォーマットに乗ったからといって必ず成功するわけではありません。それでもヒットしたタイトル分析には意味があると川上氏は言います。たった数文字の組み合わせが人を動かし、強い印象を残し、社会に波を起こす力があるなら、その仕組みを明らかにし読者に伝えたい、と。それは、私も知りたいです。
このコラムを書くために、文章の書き方指南書を何冊か集中的に読んでみました。これまでほとんど無縁だったハウツー本を熟読して、新鮮に感じること、改めて気づいたこともありました。困ったのは創作物の評価基準が、売れる、バズる、ヒットするに偏っていることでした。そういう価値観の薄い私の戸惑いは別にして、アートライティングを学ぶ人にフィットしない方法論ではないかと思いました。バズるアートライティング!それは可能なのでしょうか。
気を取り直して「すごいタイトル13の法則」を眺めてみれば、アイディア出しのチェックシートに悪くないかもしれませんね。
最後に私の本棚から、「タイトル買い」をした本を3冊ご紹介します。
〇『読めよ、さらば憂いなし』松田青子/河出書房新社、2015年。
〇『絵のうら側に言葉の糸をとおす』鴻池朋子、大竹昭子、堀江敏幸、
カタリココ文庫、2022年
〇『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』小原 晩/自費出版、2022年
参考文献
(1)『湯を沸かすほどの熱い愛』監督中野量太、2016年、日本。
(2)エーリッヒ・ケストナー著/池田代子訳『点子ちゃんとアントン』岩波文庫、2022年。
(3)高橋輝次編著『タイトル読本』左右社、2019年。https://sayusha.com/books/-/isbn9784865282450
(4)川上徹也.著 『すごいタイトル㊙法則』青春出版社. Kindle 版.
アートライティングコース|学科・コース紹介
 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
おすすめ記事
-

アートライティングコース
2022年12月21日
【アートライティングコース】アートの基礎体力を鍛えて書く
こんにちは。アートライティングコース担当教員の大辻都です。 2022年もあとわずか。今年一年あったことをふり返るとともに、来年は何をしてどう過ごそ…
-

アートライティングコース
2023年10月18日
【アートライティングコース】「これはそれを殺すだろう」 ヴィクトル・ユーゴー『パリのノートル=ダム大聖堂』第8版、1832年
みなさま、急速に秋らしくなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。アートライティングコースの教員、上村です。 「殺す」という言葉は、見た瞬間に目に強く飛び込…
-

アートライティングコース
2024年06月18日
【アートライティングコース】少しでも自分の内部に向ける時間があることが大切なのである(『海からの贈物』A・M・リンドバーグ)
こんにちは。アートライティングコース非常勤教員のかなもりです。自然も生活も何もかもが忙しく動き回る春を終え、おもむろに夏へと向かっていくこの時期、私たちには雨季…






























