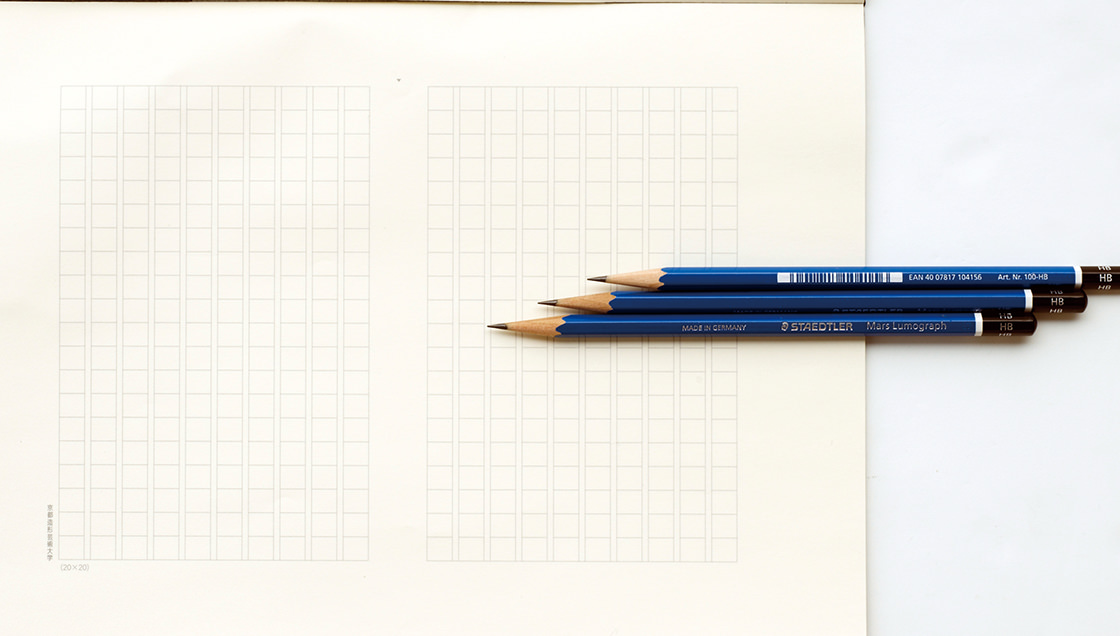

文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】フィクションは、基本的に何を書いてもいい──それなのに、なぜ私は自由に書けないのか?
2025年07月16日
【文芸コース】フィクションは、基本的に何を書いてもいい──それなのに、なぜ私は自由に書けないのか?
 文芸コースの麻宮ゆり子です。
文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は、フィクション(小説)を書く上で私が直面した “無意識の心理的抵抗” について、お話したいと思います。
まず、ノンフィクションと違って小説(フィクション)は、基本的に「何を書いてもいい」という前提がベースになっています。舞台も事件も、どんなに突飛でも構いません。物語として整合性があり、登場人物同士のバランスが取れていれば、何1つ問題はない。もちろんモラル的に不快感を及ぼすキャラクターを登場させれば読者にめちゃくちゃ嫌われることもありますが、たとえ嫌われたとしても、その人物がやはり物語の流れに必要不可欠なのであれば、どんな人を書いたっていいんです。描かれる事件についても、作者のエゴがそこに混じっていなければ(敏感な読者は作者のエゴを鋭く嗅ぎ取ります)、つまり「その事件を描く必然性」があれば、どれほど凄惨な出来事であっても、描いていいのです。
それなのに私は一時期、創作において自由に人物を創ったり動かしたりができず、大きな壁にぶつかったことがありました。
私は麻宮ゆり子名義で小説家デビューを果たしたあと、主に男性を主人公にした作品を書く、ということをやってきました。そもそもなぜ男性のキャラクターを主人公にしたかといえば、「女性が書いた男性キャラは嘘っぽい」とか「何だか女っぽい」と言われるのが嫌だったし、単純に、人物を書く幅を広げるという練習の意味でも挑戦してみようと思ったからです。
で、その結果書いた作品が賞を獲り、なぜか読者にも自然に受け入れられたので、何だか変だな~と思いながらも嬉しかったのを覚えています。私が書いた男性キャラは意外や意外、男性にも評判がいいようでした。人は、自分のことを自分がいちばんわかっているようで、実はまったくわかっていない──それが人間なのだと、私は思います。ですから、やはり自分ではよくわからないのですが、この件をきっかけに、私の中で男性キャラを描くことはけっして難しくはない、という自信のようなものが生まれました。
実際、男性に取材をして書いたので、そのへんも功を奏したのかもしれません。ただ今感じるのは、私自身が、私の中にある「男性性」や「男性的な弱さ」を否定していないし、むしろその「男性的な弱さ」に魅力を感じる傾向があったから書けたのではないかということです。
誰の中にも基本的に「男性性」や「女性性」など、さまざまな性の感覚は潜んでいると私は思っています。だからこそ女性の心理を描くのがうまい男性作家がいたり、男性読者を夢中にさせるBL小説が書ける女性作家がいたりする。逆に、男性であっても、自分の中の「男性性」に自信がないと、必要以上に「男性性」を誇示してしまいセクハラに発展してしまうのではないでしょうか。
では、自分の中の「女性性」に自信がない女性の場合、どういった現象が起きるでしょうか。一つの例は、私の体験から語ることができます。
 女性の登場人物が複数出てくる小説を書いてください。という依頼を受けて少し書いてみたところ、編集者から意外な感想をもらいました。
女性の登場人物が複数出てくる小説を書いてください。という依頼を受けて少し書いてみたところ、編集者から意外な感想をもらいました。「女性が何だかみんな似ているので、もう少し、いろいろ変えてもらえませんか?」
・・・・・・似てる? なぜ? その瞬間、冷や汗がにじみました。
「どの人物も真面目すぎて、何というか、ダメなところを見せないっていうか」
気を遣っていたようでしたが要するに、男性キャラほど魅力的に書けていない。頑張り屋だが弱点を見せず、強がってばかりで、その上似たような女性キャラばかり出てくるからおもしろくない、と編集者の方は言っていたのだろうと思っています。
私としては女性キャラは書いていても、何かこう、燃え上がるものを感じない。アクセルを踏んでいるつもりが、どこか知らぬところでブレーキが強くかかっていて前へ進まず、ただ消耗する感じだけがある。なぜ?
結論から言いますと、原因は、私の生い立ちにありました。私の生家は、「条件つきの愛」しか許されない、いわば典型的で昭和的な機能不全家族でした。
家の中の支配を一手に握っていたのは、私の母親でした。子供の頃、私は母の目線や些細な行動、含みのある言葉などから、まさに「生きる上での条件」のようなものを感じ取っていました。たとえば、「女の子らしくあってはいけない」「可愛く装ってはいけない」「異性にモテるなんてもってのほか」「勉強で私を超えたら許さない」「友達と親しくするより、家族を優先しなさい」「でもお父さん(夫)と仲良くしすぎたらダメ」・・・・・・といった具合に。
もちろんそんなことを正面から言われたわけではありません。でも、幼い頃からのやり取りの中で、私は何となく“そうしなければ生かしてもらえない空気”を感じていました。
学生時代は周囲の誰よりも成績がよかったことを誇りにしていた母親は、おそらくもっと外の世界へ出て活躍したかったのだろうと私は思っています。けれど昭和という時代や、両親からの「こうあるべき」という価値観(=条件、暗示)に抗えず、飲み込んでしまった。そして、本来自分に向けるべきだったエネルギーを私に「条件」を課すかたちでぶつけてしまったのかもしれません。
しかし無意識だろうと何だろうと、生殺与奪を握られている母親から長い期間にわたってこんな暗示を入れられたら、子供は震え上がって「死んだふり」をするしかありません。そう、私の、さまざまな「女性らしい豊かさ」は子供の頃に殺され、凍りついたままだったのです。
その結果、私の創作に現れる女性たちは、強くあらねばとどこか強迫的になっている、生真面目な人物ばかりになってしまっていたのです。
確かに、小さい頃、母親から問答無用で髪を短く切られていた私は、髪(女性性の象徴)を伸ばすことにずっと抵抗があり、ときには髪を刈り上げて「あの子は男の子?」と言われたりしていました。女なのに、女である自分が嫌いで、私は女性であってはならないと思い込んでいたんです(そんな無茶な!)。
みなさんも、「こんな人物が書きたいのになぜか書けない」「いろいろ書いてみたい、でも怖い」と感じているのであれば、もしかしたら私のような “見えないブレーキ” がかかっているのかもしれません。そのときは、勇気を出して向き合ってみてください。気づくことで、凍りついた氷は、確実に、少しずつ溶けていきます。本当は、どんな人物を書いてもいいし、どんな物語を創ってもいい。それが、フィクションの世界なのです。
文芸コース| 学科・コース紹介
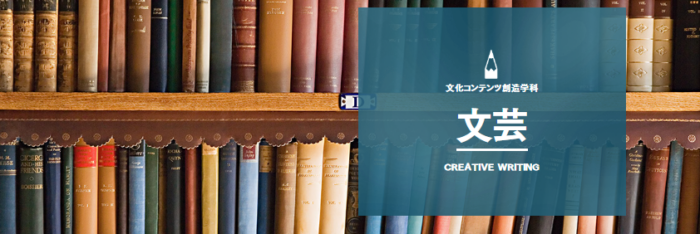 大学パンフレット資料請求はこちらから
大学パンフレット資料請求はこちらから
おすすめ記事
-
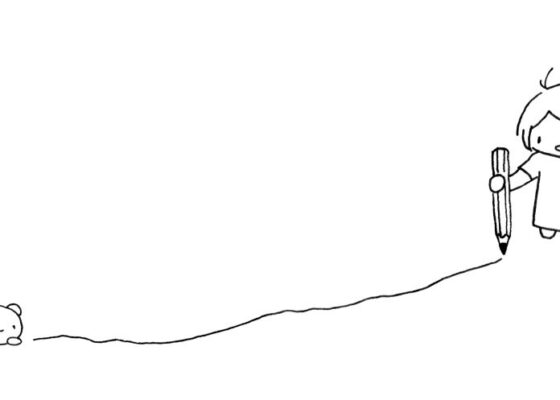
文芸コース
2025年01月27日
【文芸コース】「書き直す技術」を学ぶ場として
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 つい先日、文芸コースも入学説明会を実施しました。入学を検討している方、本学に興味を持ってくださった方に向けて…
-

文芸コース
2025年05月22日
【文芸コース】食べものを描写する
文芸コースの麻宮ゆり子です。今回は学生さんによく伝えている「描写」について書いていこうと思います。 かつて私が「小説の学校」へ通っていた頃、いつも言われていたの…
-

文芸コース
2023年03月19日
【文芸コース】書き続けるコツ
皆さん、こんにちは。文芸コース主任の川﨑昌平です。 丸1年間、この面妖なブログにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。2022年度の締めということで、…






























