

歴史遺産コース
- 歴史遺産コース 記事一覧
- 【歴史遺産コース】テキスト科目「歴史遺産学基礎講義(京都学)」で学ぶ、新しい京都の風景
2020年06月09日
【歴史遺産コース】テキスト科目「歴史遺産学基礎講義(京都学)」で学ぶ、新しい京都の風景

東山、平安神宮
その歴史は意外と新しく、明治28年(1895)に、平安遷都1100年を記念して造られました。平安京を造営した桓武天皇を祭神とします(後に孝明天皇も合祀)。近代京都をしのばせるモニュメントです。
みなさん、こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。
本当に少しずつ、日常生活に戻りつつあるこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、私が担当する「テキスト科目」の魅力と特徴とをご紹介したいと思います。「テキスト科目」は、自宅でテキストや文献にあたりながら課題に取り組む科目です。「なんだか難しそう…。」と思われる方もおられるでしょう。
でも、そんなことはないのですよ。

大文字から眺める京都市内
変貌を遂げてゆく京都の歴史を、この山はずっと見守ってきたのでしょう。写真の右が北、手前が東です。北・東西と三方を山に囲まれているのがわかります。左奥の木々の生い茂った空間は現在の京都御苑です。
歴史遺産コースでは、京都の歴史について学ぶ「スクーリング科目」や「テキスト科目」がいくつも用意されています。今回ご紹介する「歴史遺産学基礎講義(京都学)」はその中の「テキスト科目」の一つです。
■2020年度歴史遺産コース:開講予定の授業はこちらからご覧いただけます。
https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/history/pdf/kamoku.pdf
日本史の教科書や概説書では、その時代の政権を中心に書かれることが多く、鎌倉時代以後、政治の舞台が京都を離れてしまうと、京都に関する記述は少なくなります。歴史の表舞台に出た時の京都しか知らないという方々も多いと思いますが、京都には古代から近現代まで、たくさんの出来事があり、多くの歴史が積み重ねられています。
本科目では、この通史では見えにくい、京都を主人公にした歴史を学ぶことができます。

鷹ヶ峰御土居
豊臣秀吉が京都の周囲に築かせた土塁で、一部が現存しています。この時代、京都は巨大な城壁に囲まれており、開放的な現在の京都市の空間とは随分と異なっていました。秀吉の権力の一端がうかがえます。
本科目では、テキスト『京都学』を用いますが、このテキストがよくできているのです。
政治や文化だけにとどまらず、図をふんだんに使用し、京都の都市空間がどのように変化したのかを丁寧に書いています。平安京成立後、碁盤の目状に道路が整備された空間がそのまま現代まで保存されてきたわけではありません。そこで暮らす人々が生きていくために、碁盤の目の外に居住地を拡大したり、堀や塀で空間を囲んだり、支配者が住人の立ち退きを伴う大掛かりな町の整備を行ったりします。
京都の空間の変化という視点で読んでいくと、これまで知らなかった京都の姿が浮かび上がります。時代によって、相当、町の風景が違っていたことに気づくでしょう。
このテキストは、テキスト科目『京都学入門』でも使用しており、二つの科目を通じて、京都の歴史に関する知識が豊かになる仕組みになっています。

鴨川”デルタ”
出町柳にある三角洲です。ここで高野川と賀茂川が合流し、鴨川となります。穏やかな川面がまぶしい、市民の憩いの場です。しかし、平安時代から都の人々は、鴨川の水害に幾度となく苦しめられてきました。
テキストを読むだけで、いろいろと新しい知識を得ることができて楽しいのですが、本科目では、京都の歴史が大きく変化する転換期に注目して、レポートを書いてもらいます。ダイナミックに変化する京都の歴史を捉えることを学び、また、特定の時代の歴史に関する知識を深めます。具体的には、古代から近現代までの8課題のうちから2つ選びます。
でも、レポートをどうやって書くの、何を書いたらよいの…と不安に思われる方もおられるでしょう。
安心してください。この科目にはもう一つ目的があるのです。
それはレポートを作成する方法を学ぶということです。
そのために、基礎的事実の確認や、先行研究の内容の比較、自分の考えのとりまとめという、レポートを書くのに必要な作業をしてもらい、その作業の過程を文字化してレポートにして提出してもらいます。各課題ともステージ1~4を設けて、行う作業を細かく指示しています。指示通りに作業を順番に行い、それを文章化すれば、レポートが出来上がるという仕組みです。この作業を通して、レポートを書く際に行う作業が身に着くことになります。レポートは提出後、教員の添削・コメント付きで戻ってくるので、客観的に自分の書いたレポートを振り返り、次に生かすことができます。

仁和寺
平安時代、光孝天皇の遺志を継いで子の宇多天皇が完成させ、譲位後に出家し、ここを御在所とします。親王の子として生まれ、一度は源姓を賜り皇室を離れ、その後天皇となるという、波乱万丈の人生を送りました。
本科目は、京都の歴史について知識を深め、レポートの作成方法も身に着く一石二鳥の科目です。
京都の歴史の全貌が見えた時、点と点だけであった事実がつながり、これまでとは違った京都の風景が見えることでしょう。
最後に、下記の写真は京都御所の南側、建礼門のあたりの風景です。天皇の居所であった内裏は、平安時代には現在地よりずっと西の千本通付近にありました。御所の歴史を紐解くだけで、様々なドラマが浮かびあります。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら
おすすめ記事
-
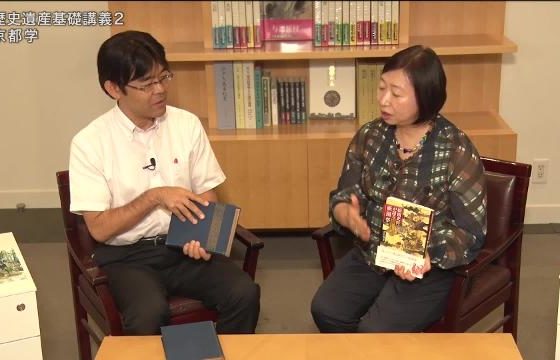
歴史遺産コース
2019年08月06日
【歴史遺産コース】“歴史研究” の方法を知る授業。「歴史遺産学基礎講義(京都学)」
みなさん、こんにちは。 今回は、歴史遺産コースの授業「歴史遺産学基礎講義(京都学)」をご紹介します。 こちらの授業は、京都を基にした「歴史研究」の方法を知る必修…
-

歴史遺産コース
2021年05月07日
【歴史遺産コース】京都の歴史を学ぶ―テキスト科目「歴史遺産学講義(京都)」のご紹介―
みなさん、こんにちは。 歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田です。青葉の美しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 今回は私の担当する、今年度から内…
-

歴史遺産コース
2022年07月15日
【歴史遺産コース】京都の大学で京都の歴史を学ぶ
みなさん、こんにちは。業務担当非常勤講師の岩田です。7月に入り、真夏日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。 このブログでは、これまで、歴史遺産コースの様々…






























