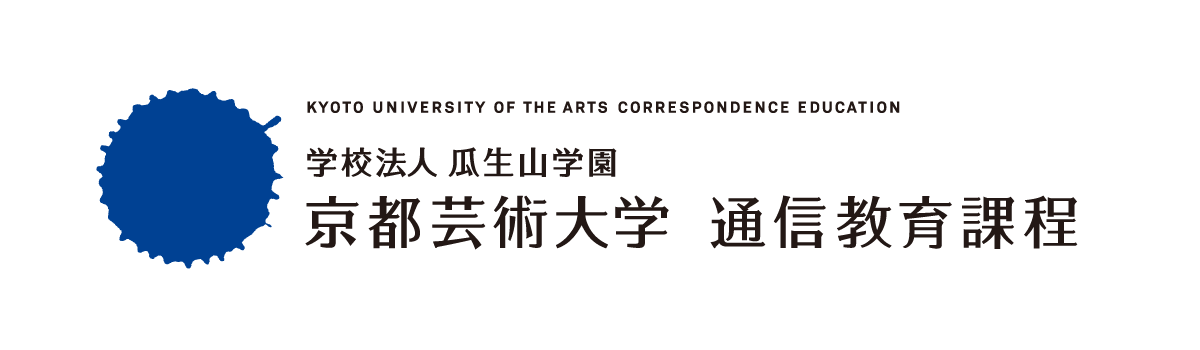文芸コース
- 文芸コース 記事一覧
- 【文芸コース】「うたい文句」は七五調
2020年07月29日
【文芸コース】「うたい文句」は七五調

こんにちは。文芸コース教員の安藤善隆です。なかなか思い切って外出できない日々が続いておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
皆さんとお会い出来る日を楽しみにしながら、今日は「文」の「芸」をつなぐ話をしてみたいと思います。
ふっとお手を止める機会があれば、少しリラックスした気分で読んでみてください。
わたしは四半世紀近く、編集という仕事に携わってきました。その中で様々な出会いがあったのですが、演劇というエンタテイメントとの出会いは大きな財産になっています。
そして演劇との出会いは、それらに携わる人々との出会いでもありました。劇作家、演出家、また劇場やプロデューサーや新聞社の方々…。数多くの人たちとの出会いが、演劇の楽しさをわたしに教えてくれました。
でも、コロナ禍でその出会いの場=劇場には、いつものように足を運ぶことはままならない状態です。(少しずつ再開されてきていますが……。私が最後に劇場に足を運んだのは3月20日。本学・春秋座で上演された地点『罪と罰』でした。もう4ヶ月近く演劇を観ていないことになります)。
そんな時、ふと「演劇は観るだけじゃない。読む演劇もある」ということを思い出しました。
「戯曲を読むことも、面白いよ!」とシアターコクーンで舞台を観たあと、渋谷の蕎麦屋で教えてくれたのはある評論家でした。
戯曲を読むことは、最初は取っ付きにくいのですが、慣れてくると作品の中にある台詞がどんどん自分の身体の中に入ってくる感じがして、頁をめくる手が止まらなくなってきます。そこにある台詞の数々は、劇作家が観客に直接届けるのではなく、役者がアウトプットすることを前提に書かれたものであるためか、つい声に出したくなったりもします。(そういえば村上春樹さんがその創作の秘密を明かしたインタビューの中で「耳で聞いてわからない言葉は、使う時に慎重にならなきゃいけない(中略)言葉の響きって大事なんです」とおっしゃっていました)。
もしかすると文学賞の受賞者に劇作家や脚本家が名を連ねているのは、そのあたりに秘密があるのかも知れませんね。
そんなことを考えているうちに歌舞伎の中の台詞のことを思い出しました。
特に河竹黙阿弥の。
それはある雑誌の編集者と話していた時のこと。「キャッチの書き方のコツ、知ってる?」と聞かれました。そんなのがあれば、もちろん聞きたい。キャッチとはキャッチコピーの略。誌面の中で読者の関心を呼び、注目を集めるための言葉です。いわゆる「うたい文句」のこと。その後、編集者は続けてこう言いました。
「歌舞伎の台本を読んでみろよ、特に黙阿弥を」

河竹黙阿弥は1816(文化13)年に生まれ、江戸と明治、二つの時代で活躍した狂言作家です。『三人吉三廓初賈』『青砥稿花紅彩画(弁天小僧)』『網模様燈籠菊桐(小猿七之助)』など江戸末期の世情を写し取った白浪狂言=盗賊ものを多く生み出し活躍しました。その後明治に入り、『高時』など史実に忠実な演出をとりいれた活歴物や文明開化の世相や風俗を映した散切狂言も多数発表。1893(明治26)年76歳で死去しています。
そんな黙阿弥は編集者のあいだでは、キャッチコピーの名手としても知られていたのです。「白波もの」と呼ばれる作品の中で書かれた台詞は、観る者、聞く者を「心地いい」気分にしてくれます。それは、わたしにとってまさに「うたい文句」でした。
「黙阿弥を読んで、いいキャッチを書いてやろう」と邪な気持ちで、私は東京創元社発行『名作歌舞伎全集』の中の河竹黙阿弥の巻を読みふけりました(因みにこの全集を選んだのは、青山二郎のその見事な装丁に惹かれたからでもあります)。
聞いたことのある台詞もその中にはありました。例えば
知らざあ言って聞かせやしょう。
浜の真砂と五右衛門が
歌に残せし盗人の
種は尽きねえ七里ヶ浜、
その白波の夜働き、
以前を言やぁ江の島で
年季勤めの稚児ヶ渕、
百味で散らす蒔銭を
当に小皿の一文子、
百が二百と賽銭の
くすね銭せえだんだんに
悪事はのぼる上の宮、
(中略)
名さえ由縁の弁天小僧
菊之助たぁおれがことだ。
(松竹(株)・歌舞伎美人HPより)
「青砥稿花紅彩画(白浪五人男)」の中の弁天小僧菊之助の台詞です。
また(季節は、少しズレてしまいますが)
月も朧に白魚の
篝も霞む春の空、
冷てえ風もほろ酔に
心持よくうかうかと、
浮かれ烏のただ一羽
塒へ帰る川端で、
棹の雫か濡れ手で泡、
思いがけなく手に入る百両、
ほんに今夜は節分か、
西の海より川のなか
落ちた夜鷹は厄落とし、
豆沢山に一文の銭と違って金包み、
こいつぁ春から延喜がいいわえ
(名作歌舞伎全集第十巻 東京創元新社より)
などなど……。

最初はキャッチに使えそうな台詞を探すように読んでいたのですが、そのうちに台詞が紡ぎ出す物語世界自体に引き込まれていました。そしていつの間にか十八代目中村勘三郎らの声が聞こえはじめ、そこは3階席から観た南座の舞台になっていました……。
なかなか舞台に接することができない今、わたしは京都の風景を友に戯曲を読みながら「観劇」を続けています。
皆さんも、もし機会がありましたら演劇を「読んで」みてください。きっとあなただけの舞台を観劇できるはずです。
文芸コース| 学科・コース紹介

過去の記事はこちら
おすすめ記事
-

文芸コース
2020年12月24日
【文芸コース】2020年、印象に残った文芸ジャンル本3冊
こんにちは。文芸コースの教員、 安藤善隆です。 ウイルスとの戦いの中、世界中の人々が様々な思いを巡らせながら2020年が過ぎていこうとしています。 「巣ごもり」…
-

文芸コース
2019年01月25日
【文芸コース】卒業生紹介 文芸が開いた新しい扉
通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は文芸コース。文芸…
-

文芸コース
2021年10月26日
【文芸コース】見てから読むか!読んでから見るか!
皆さん、こんにちは。コロナ禍は少し落ち着きをみせてきていますが お元気でお過ごしでしょうか。文芸コース教員の安藤です。 前回の本欄でもご紹介させて…