

アートライティングコース
- アートライティングコース 記事一覧
- 【アートライティングコース】「人と書とは、ともに老いる」孫過庭『書譜』(七世紀)
2021年05月20日
【アートライティングコース】「人と書とは、ともに老いる」孫過庭『書譜』(七世紀)
早々と梅雨入りを迎えたようですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
アートライティングコースの教員、上村博です。
先日、本コースではオンラインの新入生ガイダンスと、それに引き続きこれまたオンラインでの懇親会を行いました。昨年来、すっかりオンラインの催しが普通になりました。昨年も最初の頃こそ「今度は直接顔を合わせてお話しできたらいいですね!」などと言っておりましたが、いまや、慣れてしまったのか、あるいはちょっとあきらめ気分といいますか、そんなことすらあまり言わないようになってしまいました。しかし、画面越しにでも、新入生のみなさんとお話しができるのは幸せなことです。実際、当日は70名超のかたが参加されて大賑わいでした。そして3〜4名の小グループに分かれての自己紹介や贔屓の作家紹介の時間では、みなさんお互いに初対面同士ですが、そこはやはり大人の集まりですね、穏やかながら活発にお話が弾んでおりました。文化とは、価値を共有することです。芸術に関心を持ち、芸術について著述しようという意欲あるみなさんが集うさまを見て、いままさに芽吹きつつある新たな文化芸術の勢いが感じられました。それぞれのお人柄、考え方、キャリアなどが実にさまざまですし、若い方も年配の方も、それぞれの経験を持つ方が芸術に接されることで、芸術もそれぞれの仕方で新たに生かされるように思います。
ところで、タイトルに掲げましたのは、唐代に活躍した書家の孫過庭の言葉です。
彼の著した『書譜』(687)は、それ自体が書の傑作として讃えられ、台北故宮博物院の至宝のひとつですが、そこで彼は過去の書の大家たちの逸話を述べつつ、書の理論を示しています。
そのなかで、書が人となりと密接に関わっていることを語りながら、「人書倶老」、つまり人が老いると書も一緒に老いていくと言います。彼によれば、書の学習と人生の段階とは対応しています。
書を学ぶ者は、最初はきっちりと整った「平正」を学びますが、やがて複雑で表現性の高い「険絶」を追求するようになります。しかし、それを経たのち、ふたたび「平正」へと戻ることで、完成する、というのです。人間の老成は書の習熟と並行します。書というジャンルそのものが人間の成熟の度合いを反映しやすいのかもしれませんが、そもそも芸術や学問ということ自体、単なる技術や知識の獲得には終わらないものがあります。たとえ技術を身につけるとしても、その技術は自分におまけのように継ぎ足されるものというよりも、同時に自分自身を変え、成長させるものです。
とはいえ、芸術のような人生ばかりとは限りませんし、実際、作品は素晴らしいのに「お人柄はちょっと」という芸術家もいるかもしれません。まったく人と芸術が重なることはないでしょう。十九世紀の西欧では芸術の世界は人間の世界とは別物だという考え方もありました。しかし、それでも芸術は人間の資質をある程度反映しますし、そしてまた人間が変わろうとする際には、技術や知識は大きなきっかけとなります。
アートライティングもひとつの芸術です。それを学びつつ、また自分を変え、手に入れた芸術とともに立派に老いていきましょう。
アートライティングコース|学科・コース紹介

▼アートライティングコース:おすすめ記事
アートライティングコースの教員、上村博です。
先日、本コースではオンラインの新入生ガイダンスと、それに引き続きこれまたオンラインでの懇親会を行いました。昨年来、すっかりオンラインの催しが普通になりました。昨年も最初の頃こそ「今度は直接顔を合わせてお話しできたらいいですね!」などと言っておりましたが、いまや、慣れてしまったのか、あるいはちょっとあきらめ気分といいますか、そんなことすらあまり言わないようになってしまいました。しかし、画面越しにでも、新入生のみなさんとお話しができるのは幸せなことです。実際、当日は70名超のかたが参加されて大賑わいでした。そして3〜4名の小グループに分かれての自己紹介や贔屓の作家紹介の時間では、みなさんお互いに初対面同士ですが、そこはやはり大人の集まりですね、穏やかながら活発にお話が弾んでおりました。文化とは、価値を共有することです。芸術に関心を持ち、芸術について著述しようという意欲あるみなさんが集うさまを見て、いままさに芽吹きつつある新たな文化芸術の勢いが感じられました。それぞれのお人柄、考え方、キャリアなどが実にさまざまですし、若い方も年配の方も、それぞれの経験を持つ方が芸術に接されることで、芸術もそれぞれの仕方で新たに生かされるように思います。
ところで、タイトルに掲げましたのは、唐代に活躍した書家の孫過庭の言葉です。
彼の著した『書譜』(687)は、それ自体が書の傑作として讃えられ、台北故宮博物院の至宝のひとつですが、そこで彼は過去の書の大家たちの逸話を述べつつ、書の理論を示しています。
そのなかで、書が人となりと密接に関わっていることを語りながら、「人書倶老」、つまり人が老いると書も一緒に老いていくと言います。彼によれば、書の学習と人生の段階とは対応しています。
書を学ぶ者は、最初はきっちりと整った「平正」を学びますが、やがて複雑で表現性の高い「険絶」を追求するようになります。しかし、それを経たのち、ふたたび「平正」へと戻ることで、完成する、というのです。人間の老成は書の習熟と並行します。書というジャンルそのものが人間の成熟の度合いを反映しやすいのかもしれませんが、そもそも芸術や学問ということ自体、単なる技術や知識の獲得には終わらないものがあります。たとえ技術を身につけるとしても、その技術は自分におまけのように継ぎ足されるものというよりも、同時に自分自身を変え、成長させるものです。
とはいえ、芸術のような人生ばかりとは限りませんし、実際、作品は素晴らしいのに「お人柄はちょっと」という芸術家もいるかもしれません。まったく人と芸術が重なることはないでしょう。十九世紀の西欧では芸術の世界は人間の世界とは別物だという考え方もありました。しかし、それでも芸術は人間の資質をある程度反映しますし、そしてまた人間が変わろうとする際には、技術や知識は大きなきっかけとなります。
アートライティングもひとつの芸術です。それを学びつつ、また自分を変え、手に入れた芸術とともに立派に老いていきましょう。
アートライティングコース|学科・コース紹介

▼アートライティングコース:おすすめ記事
【アートライティングコース】教えるとは共に希望を語ること、学ぶとは真実を胸に刻むこと(ルイ・アラゴン)
【アートライティングコース】「味覚表現は共通のボキャブラリーを見つける作業」(続木義也)
おすすめ記事
-
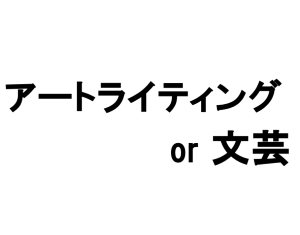
アートライティングコース
2025年06月04日
【アートライティングコース】アートライティングと文芸のあわい
こんにちは。アートライティングコース非常勤講師の小柏裕俊です。今年度からアートライティングコースのブログを定期的に執筆します。 筆者は文芸コースにも長く関わって…
-
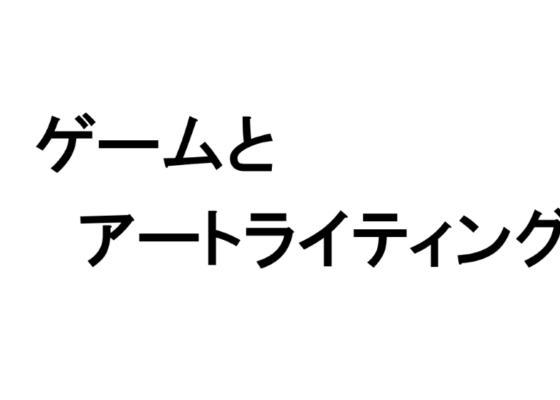
アートライティングコース
2026年02月03日
【アートライティングコース】ゲームをめぐるアートライティング
こんにちは。アートライティングコース教員の小柏裕俊です。 アートライティングとは、芸術や文化をめぐる文章を書くこと、そうしてできあがった文章作品のことです。ここ…
-

アートライティングコース
2021年04月07日
【アートライティングコース】教えるとは共に希望を語ること、学ぶとは真実を胸に刻むこと(ルイ・アラゴン)
こんにちは。アートライティングコースの大辻都です。 いつになく開花の早かった桜が見頃を終え、名残の花吹雪が舞い散ったこの週末、京都芸術大学瓜生山キャンパスでは入…































