

和の伝統文化コース
- 和の伝統文化コース 記事一覧
- 【和の伝統文化コース】初夏を彩る山法師(ヤマボウシ)と和洋折衷の美
2021年05月31日
【和の伝統文化コース】初夏を彩る山法師(ヤマボウシ)と和洋折衷の美
皆さん、こんにちは。
和の伝統文化コース非常勤講師の黒河星子です。
今回は季節と花にまつわるお話をひとつしたいと思います。
今年は梅雨入りが例年よりなんと3週間も早く、五月晴れの陽気をゆっくり楽しむ間もなく紫陽花が色づき始めています。
思い返せば今春は桜の開花も早く、入学式の頃にはすでに散っていましたし、躑躅も例年より早く終わったような気がします。頭の中で季節と花のズレを感じて、なんとなく落ち着かない気持ちになります。温暖化の影響があるのかはわかりませんが、季節という概念も曖昧なもので、暦に合わせてぴったり進むわけではなく移ろいゆくものなのだなと気づかされます。
それと同時に、いかに人は無意識に草木を見て、季節を感じ取っているのかということも実感しました。
春には梅や桜、初夏には躑躅や藤、紫陽花というように、とくに草木に詳しい人でなくとも誰しも花を見て自然と季節を意識していると思います。
近年では、桜が散ると次に街路を彩るのはハナミズキというイメージが定着してきました。ハナミズキは白か薄紅の花が、初夏に相応しいさわやかな印象を与えてくれますが、ご存じのとおり外来種で、別名を「アメリカヤマボウシ」といいます。
ちなみに、花にみえるのは実際には葉の一部で、葉が変形した「総苞」と呼ばれるものだそうですが、分かりやすくするためにここでは「花」と書かせていただきます。
ところで、在来種のヤマボウシはどんな樹で、どんな花を咲かせるのかご存じでしょうか。
先日近所を散歩していると、ふとある民家の庭木に目が留まりました。最初はハナミズキかなと思ったのですが、花の感じや葉の付き方が微妙に違います。
家に帰って図鑑で確認してみると、これがヤマボウシであることがわかりました。
ハナミズキとの違いの分かりやすい点をいくつか挙げると、まずは開花時期です。
4月の下旬から5月の上旬にかけて咲くハナミズキに対し、ヤマボウシは5月下旬から7月の始めにかけて比較的遅く、長い間咲きます。見た目の上でわかりやすいのは、花弁の形です。ハナミズキの花弁は丸みがありますが、ヤマボウシの花弁は先がとがっています。さらに、樹全体を見た時に印象が異なるのは、葉と花のバランスでしょう。ハナミズキは葉が出る前に花が咲くので樹がすっきりした状態で花が目立ちやすいのに対し、ヤマボウシは葉が先に出るため緑に茂った樹の中に白い花(薄紅色のものもある)が混じって、コントラストが映えるのが特徴です。
意識して見てみると、街のあちらこちらでヤマボウシを見かけます。外来種にすっかり慣れてしまって、もともと日本にある樹の方に馴染みがなくなっているということに気づかされました。


「ヤマボウシ」という名前の由来は、一説には花の様子が白い頭巾をかぶった比叡山の僧兵を連想させるところから来ているとされています。
元々山の谷筋に自生している樹ですが、園芸用として品種改良されて様々な見た目のものがあります。中にはハナミズキにそっくりのものもあるので、ますますややこしいですね。
ヤマボウシの歴史を辿ると、いくつか興味深い事実が浮かび上がります。ヤマボウシは日本で古くから親しまれている植物ですが、かつては園芸用というよりはむしろ木材に使用されていたようです。一方で、茶花としては利休好みの花として古くから珍重されてきました。
また面白いことに、江戸時代には海外に輸出されて観賞用の樹木として栽培されたといいます。反対に日本にハナミズキがやって来たのは、1912年にアメリカのワシントンに桜を寄贈した返礼として送られたのが初めとされています。この時の原木は日比谷公園などに移植されたものの、第二次世界大戦中にほとんど伐採されて残っていないそうです。
庭木や街路樹としてハナミズキが定着したのは平成に入ってからで、歴史はまだ浅いといえるでしょう。
ここでもう一つ興味深い事実があります。それはハナミズキの流行を追うように、近年マンションや公園などのシンボルツリーとして、ヤマボウシの人気が上がってきているということです。ヤマボウシはハナミズキに比べて野趣があり落ち着いた雰囲気なので、現代的な和洋折衷の住宅にも向いています。
ヤマボウシはまた、ハナミズキに比べて病害虫に強く、手がかかりにくいという利点もあるそうです。

このように、外来のもの流入が結果として在来のものを見直す機会になるという事例は、少なくないように思います。
長い年月を経て気候風土や文化習慣も徐々に変わっていきますが、文化の継承という問題を考える上では、「外」のものと「内」のもの、古いものと新しいものを調和させながら今の世に合った形にしていくという姿勢こそが重要なのかもしれません。
=======
<新入生のみなさんへ>
新学期が始まり2ヵ月が過ぎました。新入生の皆さんは、通信教育部での学びに慣れて来られた頃と思います。通信教育部ではairUを使った学習が中心になりますから、まずは学習用Webサイト「airU(エアー・ユー)」をよく使いこなせるようになりましょう。
学生生活で分からないことがあるときは、airU学習ガイドのページを開いてください。airUの使い方から教育課程、学習方法など、学生生活における基本的な事柄はここで調べることができます。
また、和の伝統文化コースでの学習の進め方の詳細は、学習ガイドのページから「コースガイド・ハンドブック」の項目を選択すると、コースごとの説明がPDFファイルで読めるようになっています。
今年度はコロナ禍の影響で、初めて対面と配信のハイブリッド形式で新入生ガイダンスを行いました。4月と5月の二回にわたって実施されましたが、皆さん参加されましたでしょうか?もし参加できなかった方がいらっしゃれば、airUマイページの「教材box」から、左のメニュー「補助教材」を選択するとガイダンスの動画が見られます。
テキスト科目とスクーリング科目の申し込み方法、レポートの提出や試験の受け方を始め、1年次に取るべき科目の紹介などかなり具体的に説明していますので、新入生の方は是非ご覧になってください。
=======
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

▼和の伝統文化コース;おすすめ記事
過去の記事はこちら
和の伝統文化コース非常勤講師の黒河星子です。
今回は季節と花にまつわるお話をひとつしたいと思います。
今年は梅雨入りが例年よりなんと3週間も早く、五月晴れの陽気をゆっくり楽しむ間もなく紫陽花が色づき始めています。
思い返せば今春は桜の開花も早く、入学式の頃にはすでに散っていましたし、躑躅も例年より早く終わったような気がします。頭の中で季節と花のズレを感じて、なんとなく落ち着かない気持ちになります。温暖化の影響があるのかはわかりませんが、季節という概念も曖昧なもので、暦に合わせてぴったり進むわけではなく移ろいゆくものなのだなと気づかされます。
それと同時に、いかに人は無意識に草木を見て、季節を感じ取っているのかということも実感しました。
春には梅や桜、初夏には躑躅や藤、紫陽花というように、とくに草木に詳しい人でなくとも誰しも花を見て自然と季節を意識していると思います。
近年では、桜が散ると次に街路を彩るのはハナミズキというイメージが定着してきました。ハナミズキは白か薄紅の花が、初夏に相応しいさわやかな印象を与えてくれますが、ご存じのとおり外来種で、別名を「アメリカヤマボウシ」といいます。
ちなみに、花にみえるのは実際には葉の一部で、葉が変形した「総苞」と呼ばれるものだそうですが、分かりやすくするためにここでは「花」と書かせていただきます。
ところで、在来種のヤマボウシはどんな樹で、どんな花を咲かせるのかご存じでしょうか。
先日近所を散歩していると、ふとある民家の庭木に目が留まりました。最初はハナミズキかなと思ったのですが、花の感じや葉の付き方が微妙に違います。
家に帰って図鑑で確認してみると、これがヤマボウシであることがわかりました。
ハナミズキとの違いの分かりやすい点をいくつか挙げると、まずは開花時期です。
4月の下旬から5月の上旬にかけて咲くハナミズキに対し、ヤマボウシは5月下旬から7月の始めにかけて比較的遅く、長い間咲きます。見た目の上でわかりやすいのは、花弁の形です。ハナミズキの花弁は丸みがありますが、ヤマボウシの花弁は先がとがっています。さらに、樹全体を見た時に印象が異なるのは、葉と花のバランスでしょう。ハナミズキは葉が出る前に花が咲くので樹がすっきりした状態で花が目立ちやすいのに対し、ヤマボウシは葉が先に出るため緑に茂った樹の中に白い花(薄紅色のものもある)が混じって、コントラストが映えるのが特徴です。
意識して見てみると、街のあちらこちらでヤマボウシを見かけます。外来種にすっかり慣れてしまって、もともと日本にある樹の方に馴染みがなくなっているということに気づかされました。


「ヤマボウシ」という名前の由来は、一説には花の様子が白い頭巾をかぶった比叡山の僧兵を連想させるところから来ているとされています。
元々山の谷筋に自生している樹ですが、園芸用として品種改良されて様々な見た目のものがあります。中にはハナミズキにそっくりのものもあるので、ますますややこしいですね。
ヤマボウシの歴史を辿ると、いくつか興味深い事実が浮かび上がります。ヤマボウシは日本で古くから親しまれている植物ですが、かつては園芸用というよりはむしろ木材に使用されていたようです。一方で、茶花としては利休好みの花として古くから珍重されてきました。
また面白いことに、江戸時代には海外に輸出されて観賞用の樹木として栽培されたといいます。反対に日本にハナミズキがやって来たのは、1912年にアメリカのワシントンに桜を寄贈した返礼として送られたのが初めとされています。この時の原木は日比谷公園などに移植されたものの、第二次世界大戦中にほとんど伐採されて残っていないそうです。
庭木や街路樹としてハナミズキが定着したのは平成に入ってからで、歴史はまだ浅いといえるでしょう。
ここでもう一つ興味深い事実があります。それはハナミズキの流行を追うように、近年マンションや公園などのシンボルツリーとして、ヤマボウシの人気が上がってきているということです。ヤマボウシはハナミズキに比べて野趣があり落ち着いた雰囲気なので、現代的な和洋折衷の住宅にも向いています。
ヤマボウシはまた、ハナミズキに比べて病害虫に強く、手がかかりにくいという利点もあるそうです。

このように、外来のもの流入が結果として在来のものを見直す機会になるという事例は、少なくないように思います。
長い年月を経て気候風土や文化習慣も徐々に変わっていきますが、文化の継承という問題を考える上では、「外」のものと「内」のもの、古いものと新しいものを調和させながら今の世に合った形にしていくという姿勢こそが重要なのかもしれません。
=======
<新入生のみなさんへ>
新学期が始まり2ヵ月が過ぎました。新入生の皆さんは、通信教育部での学びに慣れて来られた頃と思います。通信教育部ではairUを使った学習が中心になりますから、まずは学習用Webサイト「airU(エアー・ユー)」をよく使いこなせるようになりましょう。
学生生活で分からないことがあるときは、airU学習ガイドのページを開いてください。airUの使い方から教育課程、学習方法など、学生生活における基本的な事柄はここで調べることができます。
また、和の伝統文化コースでの学習の進め方の詳細は、学習ガイドのページから「コースガイド・ハンドブック」の項目を選択すると、コースごとの説明がPDFファイルで読めるようになっています。
今年度はコロナ禍の影響で、初めて対面と配信のハイブリッド形式で新入生ガイダンスを行いました。4月と5月の二回にわたって実施されましたが、皆さん参加されましたでしょうか?もし参加できなかった方がいらっしゃれば、airUマイページの「教材box」から、左のメニュー「補助教材」を選択するとガイダンスの動画が見られます。
テキスト科目とスクーリング科目の申し込み方法、レポートの提出や試験の受け方を始め、1年次に取るべき科目の紹介などかなり具体的に説明していますので、新入生の方は是非ご覧になってください。
=======
和の伝統文化コース|学科・コース紹介

▼和の伝統文化コース;おすすめ記事
【和の伝統文化コース】こんな時こそ、おうちで学ぼう!
【和の伝統文化コース】行けば何かがわかる。中国庭園における現地の学びの大切さ
過去の記事はこちら
おすすめ記事
-
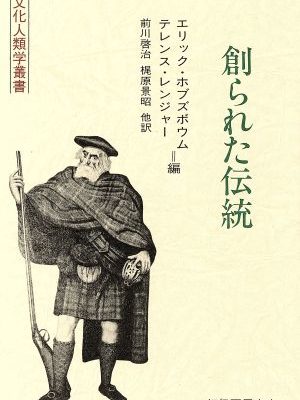
和の伝統文化コース
2022年03月01日
【和の伝統文化コース】伝統文化を学ぶ意味とは?
みなさんこんにちは、非常勤講師の黒河星子です。 本日は、伝統文化を学ぶ意味について、少し違った角度からお話ししたいと思います。 ★★★本ブログの末尾に、2021…
-

和の伝統文化コース
2019年10月21日
【和の伝統文化コース】和歌の美意識の概要と特色を探る。秋の一日体験授業「伝統文化と和歌」のご案内
みなさん、こんにちは。 今回は、11/9(土)に開催する「秋の一日体験入学」をご紹介します。 和の伝統文化コースでは「伝統文化と和歌」という授業を開催。 日本文…
-

和の伝統文化コース
2021年12月17日
【和の伝統文化コース】大覚寺での伝統文化研修
皆さん、こんにちは。 和の伝統文化コース教員、井上治です。 今回は本学通信教育課程「和の伝統文化コース」から「伝統文化研修」という授業を紹介したいと思います。 …






























