

芸術学コース
- 芸術学コース 記事一覧
- 【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地②ブッダガヤ
2021年09月02日
【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地②ブッダガヤ
みなさん、こんにちは。お元気ですか?芸術学コースの金子典正です。まだまだ暑さが続きますが、夜になると虫の音が心地よい季節となってきました。
さて、前回はお釈迦さまの誕生の地であるルンビニーをご紹介しましたが、今回は悟りを開かれた成道の地、四大聖地の二番目にあたるブッダガヤについてお話しします。
▼前回のコラムはこちら
では早速ですが、まずは本題に入る前に、前回の復習も兼ねて、誕生後のお釈迦さまの生涯を確認しておきたいと思います。その内容については、原始仏教聖典と呼ばれる阿含経などの最初期の経典や、お釈迦さまの伝記をつづった『過去現在因果経』『仏本行集経』などの仏伝経典によってかなり詳しく知ることが出来ます。記された内容には多少の違いはありますが、以下では、コルカタ・インド博物館が所蔵する《四相図》の浮彫を見ながら説明します。
 本浮彫は高さ92㎝、砂岩、初転法輪の地として知られるサールナートから出土し、グプタ朝の5世紀後半に制作されたものと考えられています。上下四段に場面が区切られており、下から誕生、成道、初転法輪、涅槃の場面が造形化され、まさに四大聖地の出来事があらわされている《四相図》です。こうした四相図、あるいはさらに四つの場面を加えた八相図がサールナートから多数出土しており、5世紀頃後半にはこうした仏伝の特定の場面が定着していたことがうかがわれます。では早速、最下段の誕生の場面の拡大写真をご覧ください。
本浮彫は高さ92㎝、砂岩、初転法輪の地として知られるサールナートから出土し、グプタ朝の5世紀後半に制作されたものと考えられています。上下四段に場面が区切られており、下から誕生、成道、初転法輪、涅槃の場面が造形化され、まさに四大聖地の出来事があらわされている《四相図》です。こうした四相図、あるいはさらに四つの場面を加えた八相図がサールナートから多数出土しており、5世紀頃後半にはこうした仏伝の特定の場面が定着していたことがうかがわれます。では早速、最下段の誕生の場面の拡大写真をご覧ください。
 経典の記述を参照すると、画面右側にはルンビニーの園で手を上げて木の枝を掴んでいるお母さまの摩耶夫人の姿。その右腰の辺りに右脇から生まれたばかり(えっ!右脇から?はい、そうです)のお釈迦さまがあらわされ、それを帝釈天が受け止めています。帝釈天の背中側には誕生後に七歩あるいて「天上天下唯我独尊」といった同じくお釈迦さまの姿が異時同図法であらわされ、頭上には灌頂をする九龍の龍王が二人あらわされています。
経典の記述を参照すると、画面右側にはルンビニーの園で手を上げて木の枝を掴んでいるお母さまの摩耶夫人の姿。その右腰の辺りに右脇から生まれたばかり(えっ!右脇から?はい、そうです)のお釈迦さまがあらわされ、それを帝釈天が受け止めています。帝釈天の背中側には誕生後に七歩あるいて「天上天下唯我独尊」といった同じくお釈迦さまの姿が異時同図法であらわされ、頭上には灌頂をする九龍の龍王が二人あらわされています。
そして、誕生後のお釈迦さまは王子として王宮で不自由なく暮らしますが、やがて四苦八苦を経験し、29歳で出家します。その際に愛馬カンタカに乗って城から出る様子が画面左下にあらわされ、さらに画面左上には苦行林について自ら剃髪している様子がみえます。
キリスト教美術もそうですが、作品中に文字による説明がなくとも、聖書や経典などのテキストを参照すると、それが何の場面かがたちまち分かります。つまり、勉強すればするほど作品の理解が深まり、どんどん面白くなっていくのが、こうした美術作品を研究する美術史学の醍醐味なのです。
では続いて、下から二段目の成道の場面を見てみましょう。
 まず中央には悟りを開いた証として右手を大地に触れる降魔触地印を結んだお釈迦さまがひと際大きくあらわされています。その向かって左側には、少し摩滅していますが、悟りを妨げる魔王マーラの姿と娘が一人、向かって右側にも二人の娘が立ち、お釈迦さまを誘惑した魔王マーラの美しい三人娘の姿があります。
まず中央には悟りを開いた証として右手を大地に触れる降魔触地印を結んだお釈迦さまがひと際大きくあらわされています。その向かって左側には、少し摩滅していますが、悟りを妨げる魔王マーラの姿と娘が一人、向かって右側にも二人の娘が立ち、お釈迦さまを誘惑した魔王マーラの美しい三人娘の姿があります。
さらに画面上方の左右には武器を持った怪物たちがみえますが、内側の怪物の腹部をよくみると腹踊りのように大きな顔があらわされています。この腹踊り型の怪物の作例は、インドのみならず中国にもみられ、大学院生だった頃にこれについて調べたことがあるのですが、経典にそのような怪物が記されていることを確認して感心したことがあります。経典の記述にもとづき、かなり忠実に図像化していることが分かります。
さらに、お釈迦さまの頭上には、こちらも少し摩滅しているようですが、菩提樹があらわされており、その菩提樹の末裔こそが以前にブログでご紹介した下記の写真のブッダガヤの菩提樹です。
 写真中央にみえる菩提樹と画面左側の大菩提寺の大塔の間(石の柵の内側)に、悟りを開かれた金剛宝座があります。このブッダガヤの大精舎とよばれるこの大菩提寺は、19世紀末、イギリス人の考古学者アレキサンダー・カニンガムによって発見、修理されて現在の姿になりました。
写真中央にみえる菩提樹と画面左側の大菩提寺の大塔の間(石の柵の内側)に、悟りを開かれた金剛宝座があります。このブッダガヤの大精舎とよばれるこの大菩提寺は、19世紀末、イギリス人の考古学者アレキサンダー・カニンガムによって発見、修理されて現在の姿になりました。
それと、前々回のブログでは、この菩提樹はスリランカのスリー・マハー菩提樹から育てられたものと記しましたが、実は19世紀末に古木が台風で倒壊していまい、現在のものはそれから新たに芽をふいた菩提樹であるというカニンガムの記録も残っています。直系か否かの問題はあるにせよ、いずれにせよブッダガヤの菩提樹ですので、何らかの繋がりがあることは間違いないでしょう。
▼前々回のコラムはこちら
では最後に、ここから徒歩数分のところにあるブッダガヤ考古博物館の所蔵作品を1点紹介します。大菩提寺は欄楣と呼ばれる巨大な石の柵で囲まれていますが、創建期に遡る紀元前1世紀の欄楣が現存しており、そのほとんどが博物館で展示されています。なかでも美術全集などで必ず取り上げられる作例がこちらです。
 砂岩の欄楣の上部、直径35㎝ほどの円形のなかに三人の人物像があらわされています。一見すると、地面にタイルを敷いている職人さんのようにみえます。何も知らないと「大菩提寺を建てるときの工事の様子かな?」なんて勝手に想像してしまいがちですが、これは祇園精舎建立の物語にもとづくもので、給孤独長者が精舎を建てる際、その土地をジェーダ太子から買い取るために地面に金貨を敷き詰めている場面であることが、従来の研究によって指摘されています。布金買地とも呼ばれる場面です。手塚治虫の『ブッダ』を読んだことがあれは、その場面を覚えている方もいらっしゃるでしょう。さらに専門的なことですが、この物語は奈良・西ノ京にある薬師寺の東塔檫銘にも関係してきます。
砂岩の欄楣の上部、直径35㎝ほどの円形のなかに三人の人物像があらわされています。一見すると、地面にタイルを敷いている職人さんのようにみえます。何も知らないと「大菩提寺を建てるときの工事の様子かな?」なんて勝手に想像してしまいがちですが、これは祇園精舎建立の物語にもとづくもので、給孤独長者が精舎を建てる際、その土地をジェーダ太子から買い取るために地面に金貨を敷き詰めている場面であることが、従来の研究によって指摘されています。布金買地とも呼ばれる場面です。手塚治虫の『ブッダ』を読んだことがあれは、その場面を覚えている方もいらっしゃるでしょう。さらに専門的なことですが、この物語は奈良・西ノ京にある薬師寺の東塔檫銘にも関係してきます。
ところで、京都の祇園って、なぜ祇園というのでしょうか。調べてみるとすぐに分かりますので、調べてみてください。仏教美術の面白さをもっと味わうことが出来るでしょう。それでは、続きはまた次回に!
芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース|過去の記事はこちら
さて、前回はお釈迦さまの誕生の地であるルンビニーをご紹介しましたが、今回は悟りを開かれた成道の地、四大聖地の二番目にあたるブッダガヤについてお話しします。
▼前回のコラムはこちら
【芸術学コース】お釈迦さまの四大聖地①ルンビニー
では早速ですが、まずは本題に入る前に、前回の復習も兼ねて、誕生後のお釈迦さまの生涯を確認しておきたいと思います。その内容については、原始仏教聖典と呼ばれる阿含経などの最初期の経典や、お釈迦さまの伝記をつづった『過去現在因果経』『仏本行集経』などの仏伝経典によってかなり詳しく知ることが出来ます。記された内容には多少の違いはありますが、以下では、コルカタ・インド博物館が所蔵する《四相図》の浮彫を見ながら説明します。
 本浮彫は高さ92㎝、砂岩、初転法輪の地として知られるサールナートから出土し、グプタ朝の5世紀後半に制作されたものと考えられています。上下四段に場面が区切られており、下から誕生、成道、初転法輪、涅槃の場面が造形化され、まさに四大聖地の出来事があらわされている《四相図》です。こうした四相図、あるいはさらに四つの場面を加えた八相図がサールナートから多数出土しており、5世紀頃後半にはこうした仏伝の特定の場面が定着していたことがうかがわれます。では早速、最下段の誕生の場面の拡大写真をご覧ください。
本浮彫は高さ92㎝、砂岩、初転法輪の地として知られるサールナートから出土し、グプタ朝の5世紀後半に制作されたものと考えられています。上下四段に場面が区切られており、下から誕生、成道、初転法輪、涅槃の場面が造形化され、まさに四大聖地の出来事があらわされている《四相図》です。こうした四相図、あるいはさらに四つの場面を加えた八相図がサールナートから多数出土しており、5世紀頃後半にはこうした仏伝の特定の場面が定着していたことがうかがわれます。では早速、最下段の誕生の場面の拡大写真をご覧ください。 経典の記述を参照すると、画面右側にはルンビニーの園で手を上げて木の枝を掴んでいるお母さまの摩耶夫人の姿。その右腰の辺りに右脇から生まれたばかり(えっ!右脇から?はい、そうです)のお釈迦さまがあらわされ、それを帝釈天が受け止めています。帝釈天の背中側には誕生後に七歩あるいて「天上天下唯我独尊」といった同じくお釈迦さまの姿が異時同図法であらわされ、頭上には灌頂をする九龍の龍王が二人あらわされています。
経典の記述を参照すると、画面右側にはルンビニーの園で手を上げて木の枝を掴んでいるお母さまの摩耶夫人の姿。その右腰の辺りに右脇から生まれたばかり(えっ!右脇から?はい、そうです)のお釈迦さまがあらわされ、それを帝釈天が受け止めています。帝釈天の背中側には誕生後に七歩あるいて「天上天下唯我独尊」といった同じくお釈迦さまの姿が異時同図法であらわされ、頭上には灌頂をする九龍の龍王が二人あらわされています。そして、誕生後のお釈迦さまは王子として王宮で不自由なく暮らしますが、やがて四苦八苦を経験し、29歳で出家します。その際に愛馬カンタカに乗って城から出る様子が画面左下にあらわされ、さらに画面左上には苦行林について自ら剃髪している様子がみえます。
キリスト教美術もそうですが、作品中に文字による説明がなくとも、聖書や経典などのテキストを参照すると、それが何の場面かがたちまち分かります。つまり、勉強すればするほど作品の理解が深まり、どんどん面白くなっていくのが、こうした美術作品を研究する美術史学の醍醐味なのです。
では続いて、下から二段目の成道の場面を見てみましょう。
 まず中央には悟りを開いた証として右手を大地に触れる降魔触地印を結んだお釈迦さまがひと際大きくあらわされています。その向かって左側には、少し摩滅していますが、悟りを妨げる魔王マーラの姿と娘が一人、向かって右側にも二人の娘が立ち、お釈迦さまを誘惑した魔王マーラの美しい三人娘の姿があります。
まず中央には悟りを開いた証として右手を大地に触れる降魔触地印を結んだお釈迦さまがひと際大きくあらわされています。その向かって左側には、少し摩滅していますが、悟りを妨げる魔王マーラの姿と娘が一人、向かって右側にも二人の娘が立ち、お釈迦さまを誘惑した魔王マーラの美しい三人娘の姿があります。さらに画面上方の左右には武器を持った怪物たちがみえますが、内側の怪物の腹部をよくみると腹踊りのように大きな顔があらわされています。この腹踊り型の怪物の作例は、インドのみならず中国にもみられ、大学院生だった頃にこれについて調べたことがあるのですが、経典にそのような怪物が記されていることを確認して感心したことがあります。経典の記述にもとづき、かなり忠実に図像化していることが分かります。
さらに、お釈迦さまの頭上には、こちらも少し摩滅しているようですが、菩提樹があらわされており、その菩提樹の末裔こそが以前にブログでご紹介した下記の写真のブッダガヤの菩提樹です。
 写真中央にみえる菩提樹と画面左側の大菩提寺の大塔の間(石の柵の内側)に、悟りを開かれた金剛宝座があります。このブッダガヤの大精舎とよばれるこの大菩提寺は、19世紀末、イギリス人の考古学者アレキサンダー・カニンガムによって発見、修理されて現在の姿になりました。
写真中央にみえる菩提樹と画面左側の大菩提寺の大塔の間(石の柵の内側)に、悟りを開かれた金剛宝座があります。このブッダガヤの大精舎とよばれるこの大菩提寺は、19世紀末、イギリス人の考古学者アレキサンダー・カニンガムによって発見、修理されて現在の姿になりました。それと、前々回のブログでは、この菩提樹はスリランカのスリー・マハー菩提樹から育てられたものと記しましたが、実は19世紀末に古木が台風で倒壊していまい、現在のものはそれから新たに芽をふいた菩提樹であるというカニンガムの記録も残っています。直系か否かの問題はあるにせよ、いずれにせよブッダガヤの菩提樹ですので、何らかの繋がりがあることは間違いないでしょう。
▼前々回のコラムはこちら
【芸術学コース】ちいさな大きな喜び
では最後に、ここから徒歩数分のところにあるブッダガヤ考古博物館の所蔵作品を1点紹介します。大菩提寺は欄楣と呼ばれる巨大な石の柵で囲まれていますが、創建期に遡る紀元前1世紀の欄楣が現存しており、そのほとんどが博物館で展示されています。なかでも美術全集などで必ず取り上げられる作例がこちらです。
 砂岩の欄楣の上部、直径35㎝ほどの円形のなかに三人の人物像があらわされています。一見すると、地面にタイルを敷いている職人さんのようにみえます。何も知らないと「大菩提寺を建てるときの工事の様子かな?」なんて勝手に想像してしまいがちですが、これは祇園精舎建立の物語にもとづくもので、給孤独長者が精舎を建てる際、その土地をジェーダ太子から買い取るために地面に金貨を敷き詰めている場面であることが、従来の研究によって指摘されています。布金買地とも呼ばれる場面です。手塚治虫の『ブッダ』を読んだことがあれは、その場面を覚えている方もいらっしゃるでしょう。さらに専門的なことですが、この物語は奈良・西ノ京にある薬師寺の東塔檫銘にも関係してきます。
砂岩の欄楣の上部、直径35㎝ほどの円形のなかに三人の人物像があらわされています。一見すると、地面にタイルを敷いている職人さんのようにみえます。何も知らないと「大菩提寺を建てるときの工事の様子かな?」なんて勝手に想像してしまいがちですが、これは祇園精舎建立の物語にもとづくもので、給孤独長者が精舎を建てる際、その土地をジェーダ太子から買い取るために地面に金貨を敷き詰めている場面であることが、従来の研究によって指摘されています。布金買地とも呼ばれる場面です。手塚治虫の『ブッダ』を読んだことがあれは、その場面を覚えている方もいらっしゃるでしょう。さらに専門的なことですが、この物語は奈良・西ノ京にある薬師寺の東塔檫銘にも関係してきます。ところで、京都の祇園って、なぜ祇園というのでしょうか。調べてみるとすぐに分かりますので、調べてみてください。仏教美術の面白さをもっと味わうことが出来るでしょう。それでは、続きはまた次回に!
芸術学コース|学科・コース紹介

芸術学コース|過去の記事はこちら
おすすめ記事
-

芸術学コース
2020年09月23日
【芸術学コース】儚き肉体の栄光
こんにちは。芸術学コースの佐藤真理恵です。時おり秋の気配を感じるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。 本来ならば、この時期、巷にはまだ東京オリン…
-
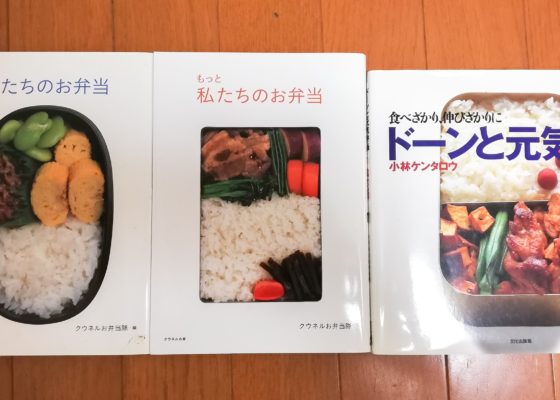
芸術学コース
2020年10月28日
【芸術学コース】日常・お弁当・芸術
10月も半ばを過ぎ、めっきり秋めいてきました。いかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの田島恵美子です。「新しい日常」が定着しつつあるこの頃、皆さんの毎日の生活に…
-

通信教育課程 入学課
2020年07月27日
流動的で複雑な時代に求められる「芸術のチカラ」とは?
みなさん、こんにちは。通信教育部事務局です。 近年よく言われている「VUCA(ブーカ)」という言葉をご存知でしょうか? 特にビジネスシーンなどで市場や社会状況全…






























