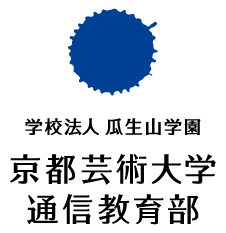文化コンテンツ創造学科
食文化デザイン
FOOD CULTURE DESIGN
食を文化芸術ととらえ、
食に関わる幅広い知識と豊かな感性を学ぶ。
座学によって食の幅広い知識を得るとともに、さまざまな食の現場や人とつながるリアルな学びにふれ、
自宅のキッチンや食卓をアトリエとして自らの手で試みる。
日常の中で学びと実践を繰り返し、食を通じて人や自分を幸せにする企画力や創造力を育んでいきます。
食文化デザインコースの特長
01. 食を文化芸術として学び、食文化の担い手を育成。
食やおいしさを「技術」としてだけでなく、フードデザインを軸に、文化人類学、科学、美学、地域デザインなどのさまざまな視点から「文化芸術」として学びます。食と「ライフデザイン」「ビジネスデザイン」「体験デザイン」を切り口に、食の楽しみ方や伝え方にも焦点を当て、社会に多様な展開ができる食文化の担い手を育成します。
02. 国内外で活躍する食に関わるスペシャリストから学べる。
講師陣は国内外の第一線で活躍する、食に関わるプロフェッショナル。研究者・表現者をはじめツーリズム、メディア、ビジネス、フードテックなど幅広い分野からスペシャリストが集結。
03. バスク・カリナリー・センター(BCC)から提供される講義も。
カリキュラムのうち2単位分の講義内容は、スペイン・バスク地方にある世界最高峰のガストロノミー教育機関であり、料理界のパイオニアである、「バスク・カリナリー・センター(BCC)」から提供されます。

食文化デザインコース
入学~卒業までのステップ
| ライフデザイン | ビジネスデザイン | 体験デザイン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 食と文化 | 食と社会 | 食とプランニング | 食とプロデュース | 食と理論 | 食と感性 |
step1 食と文化を理解し、おいしさをつくる基礎知識を身につける。 |
|||||
| 食べるということ | 世界の食探究 | 食文化デザイン入門 | おいしさの科学 | ||
| 日本の食らしさとは | 食卓の民俗学 | フードデザイン基礎 | 味覚の科学 | ||
step2 食の魅力や価値を見出し、実践的な食体験デザインに挑戦する。 |
|||||
| 食の器と道具 | 持続可能な 食との関係 |
フードデザイン実践 | 日本の食と知恵 | 食の鑑賞法 | |
| おいしさの 食体験デザイン |
食美学 | ||||
step3 食と様々な領域の関係性を探り、食体験の活用法を広げる。 |
|||||
| 食の未来ビジョン | フードメディア | フードビジネス構築 | |||
| ガストロノミー ツーリズム |
食の地域価値共創 | ||||
step4 「わたし」の視点で、 人や社会の喜びを育む食文化デザインを提案する。 |
|||||
| プレゼンテーション | 卒業制作 | ||||
食文化デザインコース
1年間の学習ペース
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ▲ 美学概論 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ★ 食文化デザイン基礎 1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||
| ★ 食文化デザイン演習Ⅰ-1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||
| ★ 食文化デザインⅠ-1、2 | 動画視聴 ×2 |
作品 ×2 |
講評視聴 ×2 |
|||||||||
| ★ 食文化デザインⅡ-1、2 | 動画視聴 | 作品 | 講評視聴 | 動画視聴 | 作品 | 講評視聴 | ||||||
- これに加え、総合教育科目などを8〜10科目、自由に選択し履修
- この履修スケジュール例は、1年次入学生が4年間での最短卒業をめざす場合の1年目の参考例です。
| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| ● 論述基礎 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ▲ 美学概論 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ▲ 芸術理論 1 | レポート | 試験 | ||||||||||
| ▲ 芸術史講義(日本)1 | 動画視聴 | レポート | 講評視聴 | |||||||||
| ▲ 芸術史講義(ヨーロッパ)1 | 動画視聴 | レポート | 講評視聴 | |||||||||
| ★ 食文化デザイン基礎1〜4 | 作品 | 作品 | 作品 | 作品 | ||||||||
| ★ 食文化デザイン演習Ⅰ-1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||
| ★ 食文化デザイン演習Ⅱ-1、2 | 作品×2 | |||||||||||
| ★ 食文化デザインⅠ-1、2 | 動画視聴 ×2 |
作品 ×2 |
講評視聴 ×2 |
|||||||||
| ★ 食文化デザインⅡ-1、2 | 動画視聴 ×2 |
作品 ×2 |
講評視聴 ×2 |
|||||||||
| ★ 食文化デザインⅢ-1 | 動画視聴 | 作品 | 講評視聴 | |||||||||
| ★ 食文化デザインⅣ-1、2 | 動画視聴 ×2 |
作品 ×2 |
講評視聴 ×2 |
|||||||||
- これに加え、学部共通専門教育科目などを2~3科目、自由に選択し履修
- この履修スケジュール例は、3年次編入生が2年間での最短卒業をめざす場合の1年目の参考例です。
食文化デザインコース
学費の目安
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 355,000円 × 4年間 = 1,420,000円 |
|
卒業までの合計⾦額(4年間) |
|
|
|
| 入学選考料 | 20,000円 |
|---|---|
| 入学金 | 30,000円 |
| 保険料 | 140円 |
| 授業料 | 355,000円 × 2年間 = 710,000円 |
|
卒業までの合計⾦額(2年間) |
|
|
|
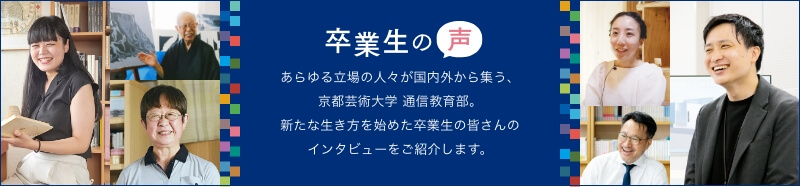
おすすめブログ記事