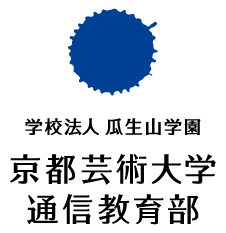2025年01月20日
2/14(金) 書くことへのアプローチを語るトークセッション 「時代の文化を育むアートライティング」
2/14(金)19:00-20:30 オンライン開催
書くことへのアプローチを語るトークセッション 「時代の文化を育むアートライティング」
無名のアーティストに新たな時代の兆しを感じる。熟達した職人の手に留めておきたい技を認める。なにげない散歩の途中に受け継がれた土地の記憶を聞きとる——
その時だけで霧消しがちな発見に輪郭を与えてくれるのがことばだ。新しいもの、古いもの、身近なもの、遠くのもの、あらゆるアートや文化対象の世界における意味を読み取り、言語化して他者と分かち合う契機は至るところに待ち構えている。
このトークセッションでは、インタビュー、ノンフィクション、書評、小説、翻訳など、登壇者たちがこれまでのキャリアで試みてきた書くことへのアプローチ法を語るとともに、それぞれの視点で選んだアートライティングの実践例を紹介する。
開催概要
【日時】2025年2月14日(金)19:00-20:30
【参加費】無料
【開催形態】Zoomウェビナー
※定員1,000名(先着順・参加無料)
【お申込はこちら】
https://cc.kyoto-art.ac.jp/webapp/form/19365_vqcb_355/index.do
【登壇者】
山家悠平(やんべ ゆうへい):歴史学、特に日本の近代女性史研究。
小説家・青波杏としての顔も持ち、2022年、第35回小説すばる文学賞受賞。
著書に『遊廓のストライキ: 女性たちの二十世紀・序説』(共和国)、『生き延びるための女性史:遊廓に響く〈声〉をたどって』(青土社)、編著に松村喬子『地獄の反逆者 松村喬子遊郭関係作品集』(こはく文庫)、青波杏名義では、『揚花の歌』『日月潭の朱い花』(ともに集英社)がある。
「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」担当。

木村俊介(きむら しゅんすけ):インタビュアー。京都芸術大学准教授。
『奇抜の人』(平凡社)でデビュー。「働く人」「作る人」へのインタビュー取材を軸に執筆活動を展開。著書に『インタビュー』(ミシマ社)、『漫画編集者』(フィルムアート社)、『善き書店員』(ミシマ社)、『料理狂』(幻冬舎文庫)、聞き書きに『調理場という戦場』(斉須政雄/幻冬舎文庫)、『バンド』(クリープハイプ/ミシマ社)、『デザインの仕事』(寄藤文平/講談社)、書籍の取材構成に『西尾維新対談集 本題』(講談社)、『海馬』(池谷裕二・糸井重里/新潮文庫)などがある。
「アートライティング演習4 インタビューの方法論」担当。

大辻都(おおつじ みやこ):文学研究、京都芸術大学教授、アートライティングコース主任(司会)。
編集ライターの経験を経てから大学院に進学、文学研究の道に入る。専門はフランス語圏文学。京都芸術大学では2019年の開講時よりアートライティングコースを担当。
著書に『渡りの文学』(法政大学出版局)、『アートとしての論述入門』、『アートを書く、文化を編む』(ともに京都芸術大学出版局)、訳書にドミニク・レステル『肉食の哲学』、マリーズ・コンデ『料理と人生』(ともに左右社)などがある。「アートライティング特講1 アートを書く・文化を編む」「アートライティング演習1 ディスクリプション」「アートライティング演習2 クリティカル・エッセイ」「アートライティング演習5 書評を書く」「卒業制作準備」「卒業制作」担当。

■京都芸術大学通信教育部アートライティングコースとは
https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/art_writing/京都芸術大学通信教育課程のコースとして、2019年に開講したアートライティングコース。芸術作品の実践そのものではなく、芸術・文化について書くためのスキルを磨くことを目的としています。 美術や舞台などあらゆる芸術ジャンルの批評はもちろん、新しく芽生えつつあるアートの潮流や文化動向を取材し記事にまとめたり、訪ねた土地の文化的価値を見出したりと、その範囲はかなりの広がりを持っています。
学生はアートが趣味の社会人からセミプロのライターまでさまざま。またクリエイター、アーティストの立場から「自分の作品を言語化してよりよく伝えたい!」と門を叩く学生も増えています。 在学生は、芸術史や美学などの基礎を体系的に学ぶと同時に、書くことの方法論に関する講義を受け、ジャンルの異なるライティングの実践にも取り組みます。 文章力の向上がプロフェッショナルなスキルに結びつくのはもちろんですが、思考の流れがクリアになり発想が豊かになるのはさらに大きな価値と言えます。限りある人生の時間、一瞬ごとの密度を今よりもっと高めてみませんか。
卒業生の声
■「自力で学ぶ方法はいくらでもありますが、大学に籍を置き、再び学生となって学ぶ経験は、想像以上に自分の視野と活動の幅を広げてくれました。 “ライター”という職業は門戸が広い反面、どんな人間が何を書くか、いかに選ばれるような仕事ができるか、が問われる世界です。
“社会人の芸大生”は、きっかけをつかむための“武器”になり、“個性”にもなり得ましたし、書き続けたことが実績の一つとなって、外部での執筆につながったと思います」
(東京都、40代)
■「それまで学んでいたコースで、書くことで学びが深まるということに気付きました。次はアウトプットする方法を学びたいと思ったので入学を決めました。書くために知っておかないといけない基本の芸術史、美学などに取り組みました。感覚だけでなくきちんと裏付けがあるライティングを、という目標がもてました。
書いたものを批評しあう授業は、自分の文章を客観的に読み直せるよい機会です。他の方の文章やアイデアからも学びました」
(大阪府、60代)
■「アートライティングコースで学んだことは、身近な対象にも目を向け、その中に何かを見出すこと。それは結局、その対象を好きになるということです。つまり私は、何かを見出して書くたびに、好きなものが増えていくわけです。それって、人生にとって豊かなことなんじゃないでしょうか」
(滋賀県、40代)