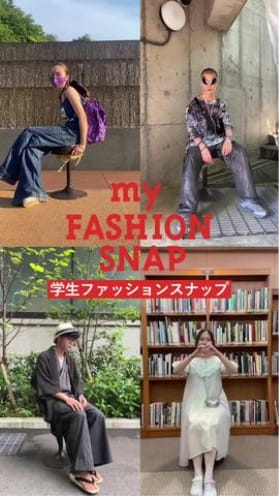企業や自治体との仕事に取り組む
社会実装
プロジェクト

企業や自治体から
“仕事”の依頼を受け、
アートやデザインの力で商品開発や
まちづくりに取り組む名物プログラム。
年間100件以上の依頼が届く。
- 対象
-
全学科/全学年
- 目標
-
企業・自治体から依頼いただく実際の「仕事」を通じて、社会に出て行く時に必要となる力=「社会人基礎力」を身につけます。
- アートやデザインを社会の課題解決につなげるプロセスを学ぶ。
- コースの専門性を実社会の課題解決に応用する為の考え方を身につける。
- クライアントのニーズをとらえ、課題発見から企画立案、ものづくりまでの実践力を身につける。
- 予算やスケジュールなど、仕事としての進行管理を行い責任感を身につける。
- チームで企画を実行・推進する中で自分の得意分野やスキル発見を行う。
プロジェクトの種類
領域横断プロジェクト
- 自身の専門分野に関わらず、受講ができる
- 一定の条件を満たしたプロジェクトは単位認定が可能
- 学科・学年を越えたプロジェクトチームで取り組むため、領域を越えた仲間ができる
ウルトラプロジェクト

-
 写真:KENJI YANOBE Archive Project
写真:KENJI YANOBE Archive Project
- 自身の専門分野に関わらず、受講ができる
- 第一線で活躍するアーティストなどプロの現場を体験。制作スキルや社会で通用する実践力を身につける
- 一定の条件を満たしたプロジェクトは単位認定が可能
プロジェクトの流れ参加~完了までの例
-
STEP
興味のあるプロジェクトを見つける。
前期・後期にそれぞれ説明会を実施。
内容を確認し、気になるプロジェクトへ参加エントリーを行う。例
歴史遺産学科1年○○君の場合プロジェクト例はこちら伝統文化&大きな制作物に興味→粟田神社と取り組む「粟田大燈呂プロジェクト」へ参加。

-
STEP
プロジェクトの始動
複数の学科・コースから学生が集まり、チームが編成される。
メンバーやクライアントとの顔合わせを経て、課題リサーチから企画立案、制作へ取り組んでいく。
-
STEP
クライアントへのプレゼン
企業や自治体が抱える課題を理解し、ミーティングを重ね、具体的な企画案を検討する。クライアント(企業や自治体)に向けプレゼンテーションをおこなう。

-
STEP
プロジェクトの完了/納品
企画案の通過後、役割分担など仲間どうしで協力し合い、納期に間に合う様に制作を進める。
完成した作品をクライアントへ納品する。例
ホスピタルアートプロジェクトデザイン採用→病院の壁面へ施工。完成→納品完了。
粟田大燈呂プロジェクト企画案採用→学内で大燈呂制作→完成後、粟田神社へ納品し完了。

-
STEP
着地や効果
一定の条件を満たしたプロジェクトは単位認定が可能。
領域を横断し、専門分野以外の事にも挑戦する事で新しい仲間や可能性を得る事が出来る。
また、プロジェクトでの成果を就職活動に活かすなど、その後の活動へ活用できる。
納品後、反響の大きなものはメディア掲載なども。例
プロジェクトの参加経験から自分の得意分野を見つけ、進路を決めることに活かせた。
プロジェクト例

HAPii+ ホスピタルアートプロジェクト
病気や怪我の治療に励む子どもたち・ご家族・医療スタッフのための空間づくりに取り組むプロジェクト。図案構想、病院へのプレゼンテーション、作業計画の策定等を経て、アート・デザインの力がどのように貢献できるかを考えカタチにしていきます。

UHA味覚糖×京都芸術大学商品開発プロジェクト
e-maのど飴、ぷっちょで知られるUHA味覚糖と商品開発に取り組んだプロジェクト。「京都」「お土産としても買っていただける商品」をテーマに、京都の老舗漬物店「西利」の漬物を配合した「ぷっちょしば漬味」の企画・デザインの策定を担当し、発売されました。

松尾スズキ・リアルワークプロジェクト
劇団「大人計画」を主宰し、作家・演出家・映画監督として活躍する松尾スズキ教授とともに舞台芸術作品を創作するプロジェクト。2023年度は学科・学年の垣根を越えた9名の学生とともに「命、ギガ長スzzz」を制作し、発表公演を行いました。

粟田大燈呂プロジェクト
京都東山の粟田神社で行われる「夜渡り神事」行列の色鮮やかな大燈呂を制作するプロジェクト。単なる制作だけでなく、神社や周辺地域の歴史・伝承等を調査、京都の歴史・芸術・文化を掘り下げ、モノづくりの真髄を学びます。

京都南座看板制作プロジェクト
歌舞伎発祥とされる京都南座。そこで行われる公演のために看板を制作するプロジェクト。
横幅10メートルを超えるダイナミックな一文字看板は注目度抜群。京都市の景観条例に対する知識・経験を身につけながら、デザインスキルを磨きます。

フコクアトリウム空間プロデュースプロジェクト
大阪駅前にある大阪富国生命ビルの地下1階アトリウム空間「フコク生命(いのち)の森」をアートでプロデュースするプロジェクト。昨年は夏に巨大壁画、冬には本格的な立体オブジェの制作を行い、多くの人が行き交う空間を彩りました。
\ 動画もチェック/

産学連携・地域連携に関するご意見募集
京都芸術大学では、アート・デザインの力を活かして、企業や自治体が抱える課題に取り組む社会実装プロジェクトを展開しており、学生ならではの視点から誘発される、既存の概念にとらわれない新たな価値を創出します。今後の産学連携・地域連携活動の参考にさせていただきたく、地域の皆さまからのご意見を広く募集いたします。
実施期間
令和7年9月1日~令和8年8月31日
本学の産学連携・地域連携に係る活動について、ご意見を下記フォームよりお寄せください。
アンケートフォーム
ご参考
ご回答いただいた個人情報は、アンケートの集計・分析のみに利用し、その他の目的で使用することはありません。また、個人を特定できる形で公開することはありません。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。
技術シーズについて
本学は、研究を通じて社会課題の解決に貢献することを目指しており、その基盤となるのが、教員が持つ「技術シーズ」です。ここでは、産学連携・地域連携プロジェクトへの活用が期待される、本学の教員が持つ技術シーズの一部をご紹介します。
日本庭園・歴史遺産研究センター:仲隆裕 NAKA, Takahiro
仲教授は、日本庭園史、文化財庭園保存修復を専門としており、特に以下の分野での研究を進めています。
- 日本庭園史: 古代から現代までの日本庭園の変遷、様式、思想、文化などに関する研究
- 文化財庭園保存修復: 文化財として指定されている庭園の保存、修復に関する研究、技術開発
これらの専門分野に基づき、以下のような技術シーズを創出できる可能性がございます。またこれらの技術シーズは、文化財保護、観光、地域活性化など、様々な分野での活用が期待されます。
- 伝統的な日本庭園の復元・修復技術: 古文献や発掘調査に基づいた、伝統的な日本庭園の復元・修復技術の開発。現代の技術と伝統的な技術を融合させることで、より精度の高い復元や、持続可能な修復方法の確立が期待できます。
- 文化財庭園の維持管理技術: 近年の気候変動や都市化により、文化財庭園の維持管理が困難になっています。教授の研究成果を活かし、環境負荷を低減し、持続可能な維持管理を行うための技術開発。
- 日本庭園の文化的価値の可視化: 日本庭園が持つ文化的価値を、映像やVRなどのデジタル技術を用いて可視化する技術開発。これにより、日本庭園の魅力を国内外に発信し、観光資源としての活用や、文化財保護への意識向上に貢献。
- 日本庭園を活用した地域活性化: 日本庭園を核とした地域活性化のための企画・デザイン提案。歴史的建造物や周辺の景観と調和した庭園整備、庭園を活かしたイベント企画など、地域の魅力を高めるための総合的な提案。
ご参考
ACOP アート・コミュニケーション研究センター:伊達隆洋 DATE, Takahiro
伊達隆洋教授は、主に以下の分野で研究・活動しており、これらの内容が技術シーズとして考えられます。
専門分野
- 臨床心理学: 臨床心理の知見をアート鑑賞やファシリテーションに応用し、人々の学びや変化を促進する研究。
- コミュニケーション論: アート作品を通じた対話やコミュニケーションのあり方を探求。
- 鑑賞教育: 美術館における教育プログラムの開発・実践、特に「対話型鑑賞」という手法の研究と実践。
主な技術シーズと考えられる内容
- 対話型鑑賞 (Art Communication Project, ACOP) の手法開発・実践:
- 「みる・考える・話す・聴く」というプロセスを通じて、知識偏重ではない作品鑑賞体験を提供し、鑑賞の基礎となるスキルやリテラシーを養う。
- 鑑賞者間の協同学習を重視し、多様な解釈や意見を検討することで、主体的な学びや批判的思考を育む。
- 美術館・博物館だけでなく、教育機関、企業の人材育成、組織開発、医療・福祉など幅広い分野に応用。
- 対話型鑑賞の実施者となるファシリテーター養成プログラムの開発・実施。
- 対話型鑑賞の効果測定・研究
- 日本における対話型鑑賞の受容史と手法の研究。
- 対話型鑑賞が鑑賞者に与える心理的な影響(認知の変化、コミュニケーション能力の向上など)を研究。
- エビデンスに基づいた対話型鑑賞の質の向上や、新たな応用分野の開拓に貢献。
- アートを通じたコミュニケーション促進
- アート作品を媒介とした、参加者間の対話や学習を促進するプログラムやワークショップの開発。
- 地域社会におけるコミュニケーション活性化や、多様な背景を持つ人々の相互理解促進に貢献。
- 企業向け人材育成・組織開発プログラム
- 対話型鑑賞の手法を応用し、ビジネスパーソンのコミュニケーション能力、観察力、多角的な視点を養う研修プログラムの開発・提供。
- 組織内のコミュニケーション改善やチームビルディングに貢献。
技術シーズの活用例
- 美術館・博物館における鑑賞体験の提供、および教育普及の人材育成。
- 学校教育における主体的な学びを促す教材やプログラムの開発。
- 企業における社員研修プログラムの開発。
- 地域イベントにおける参加者間の対話促進。
- 医療・福祉分野におけるコミュニケーションスキル向上のための研修。