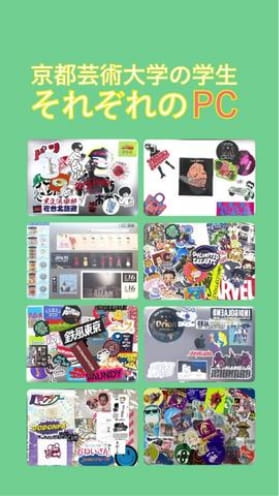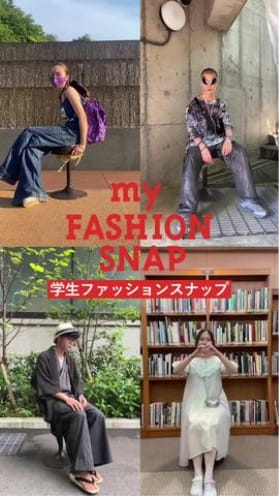学長・副学長メッセージ
学長 - 佐藤 卓
学長就任にあたってのメッセージ
京都芸術大学の学長に就任した佐藤卓です。私は長年デザインの仕事をしてきて、現在もさまざまな仕事に携わっています。そしてデザインとは何か、アートとの違いは何かを考え続けてきました。「芸術」という言葉は、京都芸術大学にアートのコースもあればデザインのコースがあるように、その全てを包含する大きな概念と定義していいと思います。アートの力、そしてアーティスティックな思考や生き方に無限の可能性と憧れを抱きながら、私自身はデザインを起点に社会を見てきました。
アートやデザインの世界に「作品」という言葉が流布していますが、私はこの「作品」という言葉に敏感にならざるを得ませんでした。アートは「作品」ですが、デザインは「作品」なのか。デザインとは何かを問うていくとこれを曖昧にできなくなります。「作品」という言葉の定義にもよりますが、私は今、デザインに「作品」という言葉は使いません。デザインの本質は「作ること」ではなく「繋ぐこと」だからです。アートとデザインが混ざり合うことはあってもその中心は同じではなく、デザインをあらゆる物事の間を繋ぐ媒介、例えば経済、医療、福祉そして教育の間と考えれば、アートもデザインが社会との間を繋いでいるといえます。空間も照明も、映像メディアも音響システムも絵の具や筆でさえデザインされています。このように考えれば、アートとデザインの関係、あるいはそれぞれの役割の中心がどこにあるのかが理解できると思います。
巷でデザインとは何かと問えば、カッコいいもの、洗練されているものなど、そのほとんどが見た目からくる印象でしょう。デザインは「見た目」と捉えられがちです。しかし見た目の意匠とともに設計も機能もデザインですから、デザインという言葉が一般的にはこのように誤解され続けています。デザインの本質は、生み出すことではなく繋ぐこと。それに対してアートは明らかに主体があり、生み出すことに意味があります。この“生み出すこと”と“繋ぐこと”で実は社会の全ての営みは流れている。その全ての営みに芸術、そして芸術的な感性が必要であると説いたのが本学創設者 德山詳直であり、掲げた理念が“藝術立国”であると私は理解しています。
全ての人に芸術的な感性もデザインマインドも、実は宿っているはずで、そこに蓋をしているのが現代社会なのではないか。それを解決するために遡るとやはり教育に至ることがよく理解できます。本当の豊かさとは何か。それが今、最も求められる問いだと思います。芸術に年齢も性別も国籍も立場も関係ありません。あらゆる人が芸術的感性を育むことのできる時代、みなさんとともに芸術の可能性を探りたいと思っています。

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年独立。株式会社TSDO代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)、『Just Enough Design』(Chronicle Books)など。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。
副学長 - 荒川 朱美
新型コロナウィルスの影響で中止となった展覧会が開催されると聞き、美術館に出かけました。ニューヨークが生んだ伝説の写真家、ソール・ライター(Saul Leiter 1923-2013)の作品展です。
雨のしずくをまとったガラス窓の向こうに立つハンチングの男性、降りしきる雪の中あしばやに立ち去る赤い傘の女性、ショーウィンドウに映る曖昧な輪郭の町並みに重なる横顔・・・。ストリート・スナップはもちろん、ファッション写真や広告写真にも豊かな芸術性が溢れる作品に、心が震える展覧会でした。
雨の日や雪の日、あるいは刻々と変化する光の中で、人と風景が溶けあう一瞬を切り取ったソール・ライターの作品は、人もまた風景の一部にすぎないのだと教えてくれました。
「私は単純なものの美を信じている。もっともつまらないと思われているものに、興味深いものが潜んでいると信じているのだ。」
「私の好きな写真は何も写っていないように見えて、片隅で謎が起きている写真だ。」
ソール・ライターの言葉が、私の胸にすとんと飛び込んできました。
そのことに気づいたとき、芸術の専門分野が異なる私がなぜライターの写真に共感するのか、その理由がわかりました。身近な町とそこで暮らす人々への真摯なまなざし、それが同じだと感じたのです。
私の専門は環境デザイン、おもに住宅と町並みのデザインを研究・制作してきました。
ゼミの学生たちと一緒に中国やトルコの歴史都市を訪れ、現地の研究者や学生たちと協働し、地域に根差した生活のあり方と伝統的な住まいや町並みの様相を調査しました。
フィールド調査では時間が許す限り、町や自然の風景と人々の生活を観察します。写真を撮り、実測し、スケッチし、ヒアリングします。民家の中庭の片隅に陣取り、一日中暮らしぶりを眺めたりもします。
それらをまとめ、分類し、図面を起こし、模型をつくります。そこで見つけた小さな気づきが、住まいや町並みを再生するためのコンセプトへと発展し、大きな成果につながることもありました。
必要なのは、風景と人々への真摯なまなざしでした。
京都芸術大学には、さまざまな分野の芸術を志す皆さんと、皆さんの学びを支えるたくさんの教職員がいます。いつもどこかで展覧会やイベントが開催され、皆さんに出会いと発見をもたらす場となっています。
京都芸術大学で、分野や立場や年齢を越えて、同じまなざしを持つ生涯の友を見つけ、実り多い学生生活を送られることを願っています。

奈良女子大学、東京工業大学篠原一男研究室を経て、奈良女子大学大学院博士課程単位取得退学。1988年から10年に亘る中国歴史都市での町並み保存再生調査研究により、2001年度都市計画学会石川賞を受賞(グループ受賞)。トルコをはじめアジアの伝統的な町並みや住空間の研究に取り組む。また京町家の再生や、NPOと共同した永代供養墓などの設計も手がける。著書に『住まいの解剖学』(角川 美と創作シリーズ・共著)、『中国の歴史都市-これからの景観保存と町並みの再生へ』(鹿島出版会・共著)など。
副学長 - 上田 篤
皆さんの人生とともに歩む大学、芸術を心から楽しみ学び続けられる場へ
通信教育担当副学長への就任にあたって掲げた私の目標です。
本学での学びをもとにこれからの社会の変革を担うであろう通学課程の学生とともに、顔を合わせることは少なくとも仕事や家事と両立しながら全国各地で一緒に学び、時に京都や外苑のキャンパスに集う通信教育課程の学生も日々切磋琢磨しています。我々は日々現場でその両方の熱量を感じ刺激を受けています。大学に求められる要素も多様化し、社会人の「学び直し」という言葉を耳にすることが多くなりましたが、全ての人にとって大切なのは「学び重ねる」ことであり、キャリアを単に上書きするのではなく、化学変化させることにあると実感しています。通学課程の皆さんが驚くべき速さで学びを吸収する姿を見るのと同じく、様々なキャリアを持つ社会人が自分の可能性をどんどん広げていく姿を見ることが本学教職員の楽しみなのです。
藝術とは全ての人類に開かれた学問であり、元来の意味は、自らの環境に豊かさを付与するための視点や知識、技芸というものです。世界がその重要性を再認識し、それを取り戻すべく動き始めています。デザイン思考や芸術的思考と謳われて久しいですが、それらは巷に溢れた本で身に付くものではなく、実践を繰り返しながら身体に浸透していくものでしょう。異なる背景や価値観を持つ多様な学生が集うこの壮大な学び場で、自らを生涯更新し続けていきましょう。豊かさとは笑顔が増えることによって可視化されるものだと私は思っています。その状況を生み出そうとする皆さんこそが笑顔に溢れ、心から藝術・デザインを楽しみ、学び続けられる場として進化を重ねていくことをここにお約束したいと思います。
本学の理念「藝術立国」も途方もなく大きな動きに捉えられがちですが、ここで藝術を学んだひとりひとりがそれぞれの環境を少しずつ豊かに、良くしていく成果の積み重ねによってこそなし得る世界だと私は信じています。
通学課程3,700名、通信教育課程10,000名を超える学生が集う大学となった今、お互いの刺激とそこから生じる化学変化をより活性化させながら、本学だからこそ実現できる学びの世界の構築を目指していきたいと思っています。
さあ一緒に、藝術を、デザインを、楽しもう。

大阪府岸和田市にて生まれだんじり囃子を聞きながら成長し大学入学とともに上洛。京都工芸繊維大学大学院修了、建設会社勤務後、建築家・デザイナーとして独立。2005年京都芸術大学教員となり現在に至る。その間に、京都工芸繊維大学院博士後期課程単位取得退学。
人の集う場のデザイン、空間演出デザインを専門とする。最新の手掛けた空間は、研究室や卒業生と取り組んだ亀岡市「開かれたアトリエ」。滋賀県甲賀市信楽地区の芸術祭「シガラキマニア」の監修も務める。著書に『図形ドリル』(学芸出版社・単著)。普段は通信教育部のありとあらゆるところで奮闘中。
副学長 - 小山 薫堂
京都に京都芸術大学があって良かった・・・
一人でも多くの人にそう言わせたいと強く思いながら私は着任しました。
京都芸術大学の姉妹校である東北芸術工科大学のデザイン工学部内に企画構想学科が新設されたのは2009年。私はその初代学科長として教鞭を執ってきました。学生たちに教えてきたのは「企画」という学問。企画とは解決する知恵であり、価値を生み出す計画です。芸術とデザインの境界線が曖昧になっている今だからこそ、芸術にも企画の力が必要だと痛感しています。
優れた芸術性によって生み落とされた作品は、どんな形で誰と出会い、どう扱われるか、によってその価値を大きく変えます。作品にとっての最良の出会いを創造することこそ、企画の真骨頂でもあります。
本学の学生たちの才能を開花させるため、どんな機会を創出し、どんなゴールを目指せば良いのか?自分のネットワークと企画力をつなぎ合わせ、“学生にとっての利”を最大化することが、社会連携担当副学長としての私の使命です。
幸いにも、京都芸術大学には二つの強みがあります。まず、各ジャンルの第一線で現役として活躍している教授陣です。彼らの人生を特等席で見つめ、たくさんの刺激を受けながら自らの創造性を磨くことができる本学の学生たちは本当に幸せです。
そしてもう一つの強みは、京都に存在しているということ。当たり前のように聞こえますが、この価値を忘れてはいけません。世界的視野に立って見つめれば、京都という都市は、東京以上に日本を印象づける強いブランド力を持っています。しかも京都市は、人口の10人に1人が大学生というまさに学生の街。さらに文化庁の移転も決まり、これほど文化芸術の学びにふさわしい地はありません。
素晴らしい教授陣と千年の都・京都のブランド力・・・どちらにも強力な「磁力」があります。事象を誘い、人を引き寄せ、注目を集める、という磁力です。本学の磁力が導く無数のチャンスに、まず学生たちは気づくべきです。そして圧倒的努力によってそれを生かすのです。
センスは知識と経験を重ねることで作られてゆきます。そしてそれが作品の魂となります。あらゆる方法で最良の環境を整え、学生たちのセンスと魂を磨いてみせます。 本学には、学生たちの芸術的創造力と人間力によって、社会を少しでも良くしたいという揺るぎなき理念があります。京都芸術大学で生み出されてゆく作品、そして人間が、京都の価値向上、ひいてはこの国の輝かしい未来につながるであろうことを私は信じています。

日本大学藝術学部在学中に放送作家として活動を開始し、数多くの番組を企画・構成。『料理の鉄人』『トリセツ』では、国際エミー賞を受賞。さらに脚本を手掛けた映画『おくりびと』で2009年に第81回米国アカデミー賞外国語映画賞を受賞し、国内外で高い評価を受けた。エッセイ連載、作詞など幅広く活動する他、下鴨茶寮主人、京都館館長、経済産業省「JAPAN DAY PROJECT」総合プロデューサー、文化庁「日本遺産審査委員会」委員など、多くの政府・地域・企業のアドバイザー等を務める。また熊本県地域プロジェクトアドバイザーを務め、人気キャラクターくまモンの生みの親でもある。さらに、2009年4月から2017年3月まで東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長を務めた。