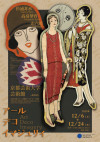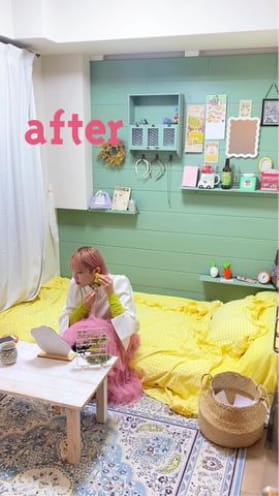2014.06.18
- 展覧会
- 近畿圏
震災前に写真におさめられた飯舘村の美しい暮らしの風景
「飯舘村の暮らし~管野千代子写真展~」
2014. 06/17 (火)
2014. 06/23 (月)
10:00
18:00
瓜生山キャンパス 瓜生館1F
2014年6月17日(火)より、瓜生山キャンパス瓜生館で震災前に福島県・飯舘村で繰り広げられていた美しい暮らしの風景を伝える写真展「飯舘村の暮らし~管野千代子写真展~」が開催されます。
この写真展は、福島県浪江町の看護師で写真家の管野千代子さんが、東日本大震災の前年に隣接する飯舘村に足を運び、小川で水遊びを楽しむ子どもたちや農家の人々の生き生きとした表情を捉えた写真作品を紹介しようというもの。
震災から3年が経過しても、13万人を上回る人々が未だ自宅に戻れない現状がある一方、被災地以外では震災や原発事故の記憶が風化しつつある今、この悲劇の重みを見つめなおす機会にして欲しいと、京都出身で現在南相馬市在住の有志によって企画されました。
展覧会では写真作品40点が、震災後に撮影された写真のデジタルスライドショーとともに紹介されます。
また、展示写真のポストカードも販売されます。
◆ギャラリートーク
日 時:2014年6月17日(火)13:00~
会 場:京都造形芸術大学 瓜生山キャンパス 瓜生館1F
ト ー ク:管野千代子(写真家)
参 加 費:無料
申 込:不要
【管野千代子(かんのちよこ)プロフィール】
1946年生まれ、宮城県角田市出身。福島県立医大附属看護学校卒業、ニッコールクラブ会員。
全日写連福島支部所属。全日本山岳写真協会会員。各種フォトコンテストなどで入賞多数。
福島県浪江町に住み看護師として働きながら、折に触れて飯舘村に通い、山里の暮らしを撮り続けてきた。
自身も原発事故被災者となりながらも、現在は仮設住宅などを訪れ撮影をしている。
*********************************************************************************************************************::**************
【失われた日本の原風景】(展示会場 メッセージボードより)
カメラマンにとって、飯舘村はシャッターチャンスの宝庫であった。村は標高400 ~ 600メートルの高原地帯にあり、日本の原風景ともいえる景色、家並みが数多く見られ、四季を通じて訪れる者に安らぎを与えてくれた。
村民が外来者に親切で、カメラを向けても断られた記憶がない。おまけに、農作物をたくさん頂戴して、その優しさとおいしさに感激した。全国の美しい村連合に加盟しているが、美しい村は単に景色のみならず、人づくりが結実したものだと実感した。
また、村の精神でもある「までい(注)」の心は、モノにあふれた現代の社会に警鐘を鳴らしてくれた。
夏の子どもたちの川遊び。はしゃぐ声が聞こえてきそうである。70歳近い私が子どもだった頃、田んぼの水路で川魚を獲った記憶が蘇るが、今の日本でそうたやすく見られる景色ではない。
豊かな自然を利用して、山羊、猪、牛、馬なども飼育されていた。写真のおばあちゃんは小遣いで山羊を買ったが孫のようにかわいいと言った。そのあとつがいにして子どもまで生れたが、原発避難の時に、泣く泣く手放したそうである。
冬の飯舘村は標高があるため、真っ白の銀世界となり、厳しい寒さの中でも特産の干し大根を地域ごとに作り出荷していた。お袋の味を好む人にはこたえられない食べ物である。広い庭一面に干された大根は飯舘村の自然風景に良くマッチしていた。村は高冷地であるため、以前は農作物が実らず、現在の農業形態になるまでは大変な苦労をしたという。やっと高冷地ならではの村づくりができ、これからだという時に、福島第一原発の爆発事故により、30キロメートルも離れているにもかかわらず、風向きによって村が放射能で汚染され、全村警戒区域となった。
写真に映された一人ひとりの笑顔が今は悲しい。突然村の暮らしを奪われてしまった憤り、怒り、悔しさ、無念さ、不安、悲しみが見えてくる。村を追われて家族がバラバラになり、今どこにどうしているだろうと思うと怒りで胸が震える。原発事故は平穏な村の暮らしを一気に奪い去った。
美しい村の自然、人びとの暮らしを奪う権利など、国であれ企業であれ、あっていいものであろうか。心の拠りどころとなる美しい日本の自然を消失させた責任は大きい。
狭い日本の各地に原子力発電所はある。福島の二の舞がどこになるかわからない。次代を担う子どもたちに、安全で美しい自然を残す責任がわれわれ大人たちにはある。全国の子どもたちに同じ苦しみを絶対に味わわせてはいけない。
(注)「真手」を語源とした、真心を持って、手間を惜しまず、つつましくという意味の東北地方で使われる言葉。
(DAYS JAPAN 2013年7月号掲載記事より転載)
****************************************************************************************************************************************
この写真展は、福島県浪江町の看護師で写真家の管野千代子さんが、東日本大震災の前年に隣接する飯舘村に足を運び、小川で水遊びを楽しむ子どもたちや農家の人々の生き生きとした表情を捉えた写真作品を紹介しようというもの。
震災から3年が経過しても、13万人を上回る人々が未だ自宅に戻れない現状がある一方、被災地以外では震災や原発事故の記憶が風化しつつある今、この悲劇の重みを見つめなおす機会にして欲しいと、京都出身で現在南相馬市在住の有志によって企画されました。
展覧会では写真作品40点が、震災後に撮影された写真のデジタルスライドショーとともに紹介されます。
また、展示写真のポストカードも販売されます。
◆ギャラリートーク
日 時:2014年6月17日(火)13:00~
会 場:京都造形芸術大学 瓜生山キャンパス 瓜生館1F
ト ー ク:管野千代子(写真家)
参 加 費:無料
申 込:不要
【管野千代子(かんのちよこ)プロフィール】
1946年生まれ、宮城県角田市出身。福島県立医大附属看護学校卒業、ニッコールクラブ会員。
全日写連福島支部所属。全日本山岳写真協会会員。各種フォトコンテストなどで入賞多数。
福島県浪江町に住み看護師として働きながら、折に触れて飯舘村に通い、山里の暮らしを撮り続けてきた。
自身も原発事故被災者となりながらも、現在は仮設住宅などを訪れ撮影をしている。
*********************************************************************************************************************::**************
【失われた日本の原風景】(展示会場 メッセージボードより)
カメラマンにとって、飯舘村はシャッターチャンスの宝庫であった。村は標高400 ~ 600メートルの高原地帯にあり、日本の原風景ともいえる景色、家並みが数多く見られ、四季を通じて訪れる者に安らぎを与えてくれた。
村民が外来者に親切で、カメラを向けても断られた記憶がない。おまけに、農作物をたくさん頂戴して、その優しさとおいしさに感激した。全国の美しい村連合に加盟しているが、美しい村は単に景色のみならず、人づくりが結実したものだと実感した。
また、村の精神でもある「までい(注)」の心は、モノにあふれた現代の社会に警鐘を鳴らしてくれた。
夏の子どもたちの川遊び。はしゃぐ声が聞こえてきそうである。70歳近い私が子どもだった頃、田んぼの水路で川魚を獲った記憶が蘇るが、今の日本でそうたやすく見られる景色ではない。
豊かな自然を利用して、山羊、猪、牛、馬なども飼育されていた。写真のおばあちゃんは小遣いで山羊を買ったが孫のようにかわいいと言った。そのあとつがいにして子どもまで生れたが、原発避難の時に、泣く泣く手放したそうである。
冬の飯舘村は標高があるため、真っ白の銀世界となり、厳しい寒さの中でも特産の干し大根を地域ごとに作り出荷していた。お袋の味を好む人にはこたえられない食べ物である。広い庭一面に干された大根は飯舘村の自然風景に良くマッチしていた。村は高冷地であるため、以前は農作物が実らず、現在の農業形態になるまでは大変な苦労をしたという。やっと高冷地ならではの村づくりができ、これからだという時に、福島第一原発の爆発事故により、30キロメートルも離れているにもかかわらず、風向きによって村が放射能で汚染され、全村警戒区域となった。
写真に映された一人ひとりの笑顔が今は悲しい。突然村の暮らしを奪われてしまった憤り、怒り、悔しさ、無念さ、不安、悲しみが見えてくる。村を追われて家族がバラバラになり、今どこにどうしているだろうと思うと怒りで胸が震える。原発事故は平穏な村の暮らしを一気に奪い去った。
美しい村の自然、人びとの暮らしを奪う権利など、国であれ企業であれ、あっていいものであろうか。心の拠りどころとなる美しい日本の自然を消失させた責任は大きい。
狭い日本の各地に原子力発電所はある。福島の二の舞がどこになるかわからない。次代を担う子どもたちに、安全で美しい自然を残す責任がわれわれ大人たちにはある。全国の子どもたちに同じ苦しみを絶対に味わわせてはいけない。
(注)「真手」を語源とした、真心を持って、手間を惜しまず、つつましくという意味の東北地方で使われる言葉。
(DAYS JAPAN 2013年7月号掲載記事より転載)
****************************************************************************************************************************************
| 費用 | - |
|---|---|
| 定員 | - |
| 申込方法 | - |
| 主催 | 飯舘村の暮らし・管野千代子写真展 実行委員会 |
| お問合せ | 京都造形芸術大学 広報室 (Tel: 075-791-9122) |