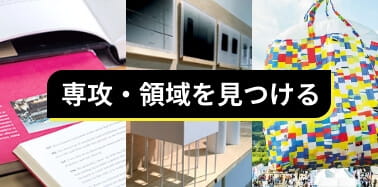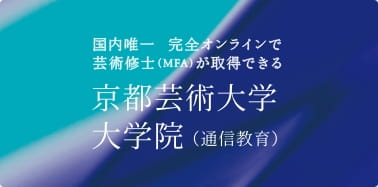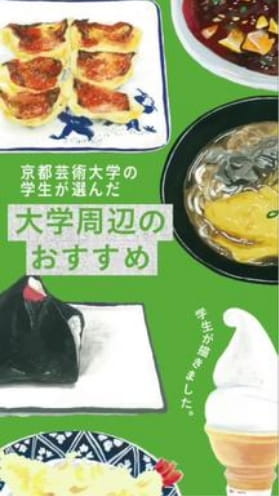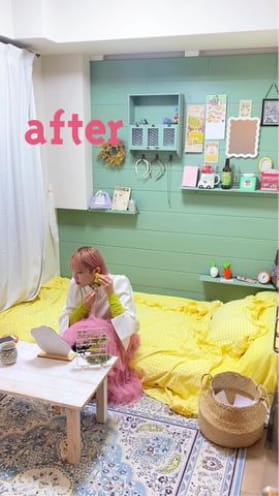博士課程 芸術専攻
「理論」のみ、あるいは「理論」と「制作」の研究により、博士号取得を目指す
京都芸術大学大学院の博士課程は、小規模のゼミ指導により論文執筆や作品制作を進め、博士(芸術または学術)の取得を目指します。
京都・瓜生山キャンパスでのゼミ指導を受けながら研究・制作を進めることを基本としますが、専門分野によっては京都に居住せずに指導を受けることも可能です。

専攻長メッセージ
博士課程では、理論研究のみの人も、制作研究を伴う人も、3年間で博士学位申請論文が完成できるように、綿密な学修スケジュールが立てられています。例えば1年目は前期に本学大学院紀要への論文投稿、後期は学内展覧会「D#展」に向けて制作を進めます。2年目以降は学術雑誌への論文投稿、学会等での口頭発表、ギャラリー等での個展開催、公募展への出品など、各自の成果を世に問いつつ実績を積み上げながら学位取得を目指します。 教員は現役の研究者や制作者であり、皆さんの良きアドバイザーです。研究・制作を深め、学友と共に切磋琢磨し、博士課程で自身を大きく成長させて下さい。

仏教美術史・東洋美術史専攻。博士(文学)。早稲田大学大学院博士課程満期退学、同大学文学部助手、講師、京都造形芸術大学准教授を経て現職。論文に「唐招提寺『金亀舎利塔』について」「中国仏教初伝期に於ける仏像受容の実態に関する一考察」など多数。共編著に『芸術教養シリーズ3 中国の美術と工芸 アジアの芸術史 造形篇I』(藝術学舎、2013)『芸術学基礎 研究のアプローチ』(藝術学舎、2025)ほか。