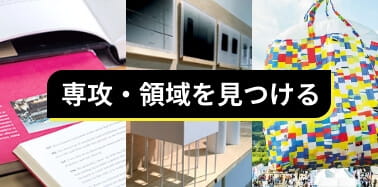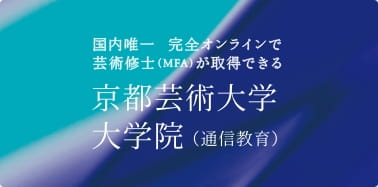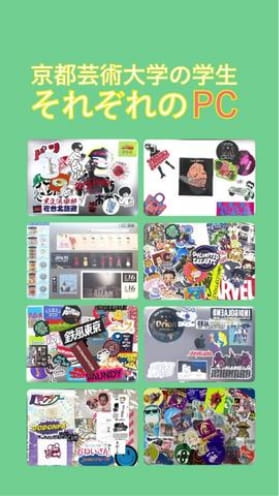建築・環境デザインを探究するには、都市や生態、地域性といった「私たちが生きる環境」をどのように考えるかが重要になります。本領域では、専門分野と周縁分野の制作・研究に取り組むなかで、環境デザインにおける実践知を獲得。修了後は建築家やランドスケープデザイナー、あるいは都市や地域のスペシャリストへ。世の中にある既存の価値や信念を再考するきっかけとなる問いを投げかけ、建築・環境デザインの境界を広げながら、その未来像を提起できる人材の育成をめざします。
特長
-
対面学習+オンライン学習
実践の中で知性を鍛える
半期ごとに1つ、2年間で4つのスタジオに所属して、建築設計や環境デザインに取り組みます。指導にあたるのは、第一線で活躍する建築家やランドスケープデザイナー。各スタジオで1つ、4つの実践的な課題に向き合い、互いに議論を交わすなかで、建築や環境デザイン、その周縁の知性を研鑽。新たな建築・環境デザインを生むための想像力と個性を伸ばします。
-
多彩なスタジオ群を横断して学びを組み立てる
複数あるスタジオは、「建築・都市・くらし」「風景・庭園・生態」「ローカル・越境・マルチモーダル」の3つのカテゴリーに分かれており、自身の研究テーマを軸に選択します。各自の研究テーマの視点からスタジオでの学びに取り組むことで、学際的な学びを構築することが狙いです。スタジオごとに作品と小論文を完成させ、最終的には4つの作品と小論文をひとつのテーマでまとめて修了制作・修了論文に。スタジオは対面とオンラインを交互に実施するので、社会人や遠隔地の方もライフスタイルに合わせた学びが可能です。
-
2025年度スタジオ担当教員
教員メッセージ-
カテゴリーA 「建築・都市・くらし」
建築・都市 スタジオ | 前田 茂樹 + 大坪 良樹
住環境デザイン スタジオ | 小杉 宰子 + 太田 雄太郎
再生デザイン スタジオ | 吉村 理 + 大坪 良樹
アーキ・フォーミング スタジオ | 丹羽 隆志 + 大坪 良樹 -
カテゴリーB 「風景・庭園・生態」
日本庭園デザイン スタジオ | 加藤 友規 + 熊倉 早苗
リジェネラティブ・デザイン スタジオ | 鈴木 卓 + 熊倉 早苗
URBAN PLACE デザイン スタジオ | 河合 健 + 熊倉 早苗
エコロジカル ランド+アーキ スタジオ | 渡辺 美緒 + 太田 雄太郎 -
カテゴリーC 「ローカル・越境・マルチモーダル」
循環デザイン スタジオ | 松本 尚子 + 寺田 英史
ヘリテージデザイン スタジオ | 橋本 健史 + 寺田 英史
リサーチ&キュラトリアル スタジオ | 川勝 真一 + 寺田 英史
「遊びと場」のデザインスタジオ | 遠藤 幹子 + 寺田 英史
-

学習環境について
- スタジオは、京都・瓜生山キャンパスと東京・外苑キャンパスのいずれかで開講します。
- スタジオは、原則、対面授業と遠隔授業を2週間おきに実施します。
- 土曜日に開講するスタジオもありますので、社会人の方は働きながらも学ぶことが可能です。
- 個別の研究・制作は基本的に自宅で行いますが、必要に応じて大学院生専用スペースやその他の施設を利用できます。
- 学修環境の確保のためにスタジオの受講者数を調整しますので、希望するスタジオに所属できない場合があります。
履修スケジュール例
領域週間スケジュールイメージ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1週 |
午前 | スタジオ (火曜開催) |
スタジオ (土曜開催) |
|||||
| 午後 | (基盤科目) | (原論) | 分野特論4 (M1/前期) |
|||||
|
第2週 |
午前 | |||||||
| 午後 | (基盤科目) | 分野特論3 (M2/通年) |
(原論) | 分野特論4 (M1/前期) |
||||
|
第3週 |
午前 | スタジオ (火曜開催) |
スタジオ (土曜開催) |
|||||
| 午後 | (基盤科目) | (原論) | 分野特論4 (M1/前期) |
|||||
|
第4週 |
午前 | |||||||
| 午後 | (基盤科目) | 分野特論3 (M2/通年) |
(原論) | 分野特論4 (M1/前期) |
1年次
| 科目名 | 学び方 | 単位数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
基盤科目 必修 |
前期・平⽇毎週1講時×14回 |
2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
基盤科目 必修 |
後期・平⽇毎週1講時×7回 |
2 | ● | ● | ||||||||||
|
原論5 選択必修 |
平⽇集中講義+レポート等 |
2 | ● | ● | ● | |||||||||
|
分野特論4 選択必修 |
平⽇毎週2講時×15回 |
4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
演習1 必修 |
対⾯のみ・オンラインのみ交互・2週間ごと |
4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
演習2 必修 |
4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| その他 |
オンライン可 |
ガイダンス |
ガイダンス |
2年次
| 科目名 | 学び方 | 単位数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
原論2 選択必修 |
集中講義+レポート等 |
2 | ● | ● | ● | |||||||||
|
分野特論3 必修 |
平⽇隔週2講時×15回 |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
|
研究1 必修 |
対⾯のみ・オンラインのみ交互・2週間ごと |
4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
研究2 必修 |
4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| その他 |
オンライン可 |
ガイダンス |
⼝頭試問 |
- 入学に際して「留学」の在留資格を取得される外国人留学生の方は、留学生コース(International Students Track) の対象となり、各自の専攻科目の他に「日本文化・日本語理解科目(修了要件:16単位)」の受講が必要です。
詳細はカリキュラムページをご確認ください。
2025年度スタジオ開講予定日程
前期
| 京都 | 東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火曜 | 土曜 | 火曜 | 土曜 | ||
| A |
スタジオ名 |
建築・都市 | − | 住環境デザイン | − |
|
担当教員 |
前田茂樹・大坪良樹 | − | 小杉宰子・太田雄太郎 | − | |
| B |
スタジオ名 |
リジェネラティブデザイン | 日本庭園デザイン | − | − |
|
担当教員 |
鈴木卓・熊倉早苗 | 加藤友規・熊倉早苗 | − | − | |
| C |
スタジオ名 |
循環デザイン | − | − | − |
|
担当教員 |
松本尚子・寺田英史 | − | − | − | |
|
スタジオ名 |
ヘリテージデザイン | − | − | − | |
|
担当教員 |
橋本健史・寺田英史 | − | − | − | |
| 2025 授業日 |
対面 |
04/22, 05/20, 06/17, 07/15, 07/29, 08/02※ | 04/19, 05/17, 06/14, 07/12, 07/26, 08/03※ | 04/22, 05/20, 06/17, 07/15, 07/29, 08/03※ | − |
|
遠隔 |
04/29, 06/03, 07/01 08/02(土) 京都 合評 ※ |
05/03, 05/31, 06/28 08/02(土) 京都 合評 ※ |
04/29, 06/03, 07/01 08/02(土) 京都 合評 ※ |
− | |
| 備考 | − | − | − | − | |
後期
| 京都 | 東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火曜 | 土曜 | 火曜 | 土曜 | ||
| A |
スタジオ名 |
− | 再生デザイン | − | − |
|
担当教員 |
− | 吉村理・大坪良樹 | − | − | |
|
スタジオ名 |
− | アーキ・フォーミング | − | − | |
|
担当教員 |
− | 丹羽隆志・大坪良樹 | − | − | |
| B |
スタジオ名 |
URBAN PLACE デザイン | − | − | エコロジカル ランド+アーキ |
|
担当教員 |
河合健・熊倉早苗 | − | − | 渡辺美緒・太田雄太郎 | |
| C |
スタジオ名 |
リサーチ&キュラトリアル | − | − | − |
|
担当教員 |
川勝真一・寺田英史 | − | − | − | |
|
スタジオ名 |
「遊びと場」のデザイン | − | − | − | |
|
担当教員 |
遠藤幹子・寺田英史 | − | − | − | |
| 2025 授業日 |
対面 |
09/23, 10/21, 11/11, 12/09, 12/23, 2026/01/10※ | 09/27, 10/25, 11/08, 12/13, 12/20, 2026/01/10※ | − | 09/27, 10/25, 11/08, 12/13, 12/20, 2026/01/10※ |
|
遠隔 |
10/07, 11/04, 11/25 2026/01/10(土) 京都 合評 ※ |
09/27, 10/11, 11/08, 11/29, 12/13 2026/01/10(土) 京都 合評 ※ |
− | 10/11, 11/08, 11/29 2026/01/10(土) 京都 合評 ※ |
|
| 備考 | − | アーキフォーミングスタジオは、ベトナムへの渡航(2−3日)とオンライン授業を中心に実施します。 | − | − | |
- スタジオは、2025年度の実績に基づくものです。
- スタジオ名や教員、また、訪問先等の都合で日程が変更になる場合があります。
- 2026年度の日程はお問い合わせください。
動画もチェック


教員メッセージ
「建築・都市・くらし」

カテゴリーAのスタジオ群は、建築や空間の設計に実践的に取り組みます。わたしたちを取り巻く社会状況や既存の枠組みを正しく認識することからスタートし、都市や建築を介して発生する人々の交流や自然、物との関係について考え、それらのより良い関係を空間の力を用いてデザインすることで、都市や建築、居住空間を次の世代へと受け渡す提案や問題提起を目指します。
「風景・庭園・生態」

カテゴリーBのスタジオ群では、地球規模で連鎖する自然生態系への知見を持ちながら、京都でこそ学べる日本庭園の探求。エコロジカルなライフスタイルを育てるガーデンデザイン。まちの歴史・文化の文脈を改めて問い、環境工学や材料から都市環境を再編するようなランドスケープデザインなど、これらの専門性を深化させ、包括し、超えてゆく設計力と論理構築力を獲得します。
「ローカル・越境・マルチモーダル」

私たちのくらしは、固有の地域性、そして生物/非生物との多様な関係の上に成り立っています。カテゴリーCのスタジオ群では、専門的な知識を元に、社会的/文化的/技術的文脈から新たな眼差しを向け、身のまわりを深く知ると共に、これからの人や生物が生きるための環境とより良い持続性について想像力を広げ、スケールと分野を超えて活動します。
- 上記の教員陣を中心に、チームで領域を担当します。
教員一覧
担当教員(2025年度)
-
 領域長 小杉 宰子 教授 建築デザイン
領域長 小杉 宰子 教授 建築デザイン -
 荒川 朱美 教授 住宅設計、都市景観デザイン
荒川 朱美 教授 住宅設計、都市景観デザイン -
 浦田 友博 専任講師 建築設計
浦田 友博 専任講師 建築設計 -
 遠藤 幹子 教授 遊び・学び・育ちの場のデザイン、参加型場づくり、参加型アートインスタレーション
遠藤 幹子 教授 遊び・学び・育ちの場のデザイン、参加型場づくり、参加型アートインスタレーション -
 太田 雄太郎 専任講師 建築設計、インテリアデザイン、プロダクトデザイン
太田 雄太郎 専任講師 建築設計、インテリアデザイン、プロダクトデザイン -
 大坪 良樹 専任講師 建築設計
大坪 良樹 専任講師 建築設計 -
 小野 暁彦 教授 建築設計
小野 暁彦 教授 建築設計 -
 加藤 友規 教授 日本庭園史、日本庭園の作庭・育成管理、文化財庭園の保存と活用
加藤 友規 教授 日本庭園史、日本庭園の作庭・育成管理、文化財庭園の保存と活用 -
 河合 健 教授 ランドスケープデザイン
河合 健 教授 ランドスケープデザイン -
 川勝 真一 教授 建築リサーチ、建築史、建築キュレーション
川勝 真一 教授 建築リサーチ、建築史、建築キュレーション -
 熊倉 早苗 准教授 造園学、海外の日本庭園、ランドスケープデザイン
熊倉 早苗 准教授 造園学、海外の日本庭園、ランドスケープデザイン -
 鈴木 卓 教授 ランドスケープ設計
鈴木 卓 教授 ランドスケープ設計 -
 寺田 英史 専任講師 建築設計
寺田 英史 専任講師 建築設計 -
 丹羽 隆志 教授 建築設計、プロダクトデザイン、土木デザイン
丹羽 隆志 教授 建築設計、プロダクトデザイン、土木デザイン -
 橋本 健史 教授 建築設計
橋本 健史 教授 建築設計 -
 写真:Didier Boy de la Tour坂 茂 教授 建築
写真:Didier Boy de la Tour坂 茂 教授 建築 -
 前田 茂樹 教授 建築設計
前田 茂樹 教授 建築設計 -
 町田 香 准教授 日本庭園史、日本文化史
町田 香 准教授 日本庭園史、日本文化史 -
 松本 尚子 准教授 建築設計
松本 尚子 准教授 建築設計 -
 吉田 裕枝 教授 建築空間設計、地域文化デザイン
吉田 裕枝 教授 建築空間設計、地域文化デザイン -
 吉村 理 教授 建築設計
吉村 理 教授 建築設計 -
 渡辺 美緒 教授 ランドスケープデザイン
渡辺 美緒 教授 ランドスケープデザイン
大学院客員教員(2025年度)
- 尼﨑 博正|日本庭園
- 堀部 安嗣|建築デザイン
修了後の進路
2024年度実績
- 千葉大学大学院園芸学研究科(進学)
- 青木あすなろ建設株式会社
- 株式会社ADワークスグループ
- 株式会社アルモ設計(鹿島グループ)
- 株式会社E-design
- 株式会社ウッディホーム
- 株式会社オリバー
- ケイシンネット株式会社
- 株式会社キノアーキテクツ
- 合肥奥祥新材料科技有限公司
- 株式会社彩ユニオン
- JLLリテールマネジメント株式会社
- 株式会社ジーク
- 住協建設株式会社
- 株式会社 石勝エクステリア
- 株式会社生和コーポレーション
- 須賀工業株式会社
- ダイダン株式会社
- 大和ハウス工業株式会社
- 中国創新発展研究院大阪支社
- 株式会社戸田芳樹風景計画
- 日産緑化株式会社
- 日本建設株式会社 (清水建設グループ)
- バンク・オブ・イノベーション
- 株式会社博報堂プロダクツ
- 株式会社URリンケージ
- RooMoo Design Studio