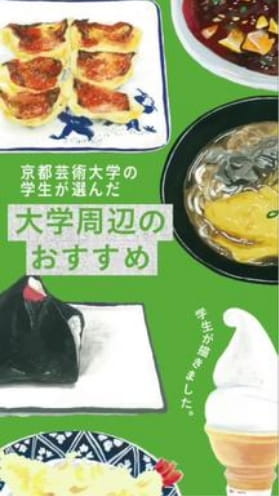藝術立国− 平和を希求する大学を目指して −
「藝術立国―平和を希求する大学をめざして―」(2007年)の全文をお読みいただけます。
PDFダウンロード
京都文藝復興
「京都文藝復興」(2000年)の全文をお読みいただけます。
PDFダウンロード
まだ見ぬわかものたちに
「まだ見ぬわかものたちに―瓜生山学園設立の趣旨―」(1976年)の全文をお読みいただけます。
PDFダウンロード
通信による芸術教育の開学にあたって
「通信による芸術教育の開学にあたって」(1998年)の全文をお読みいただけます。
PDFダウンロード
創設者・德山詳直について

1930年5月13日、隠岐の島(島根県隠岐郡海士町)生まれ。戦後間もない1948年に同志社外事専門学校に入学、1950年に同志社大学法学部政治学科へ進学するも、隣国で勃発した朝鮮動乱に抗議する運動に身を投じたことから、数回にわたり逮捕・拘留されることとなった。拘置中に差し入れられた奈良本辰也著『吉田松陰』に感銘し、吉田松陰が終生にわたって德山の思想的な礎になる。近代西欧文明が行き詰まることを早くより看破し、松陰や岡倉天心に深く傾倒しながら、藝術の力による国づくり「藝術立国」を志して、東洋の思想を基盤にした藝術教育に生涯を捧げた。1977年に京都造形芸術大学の前身である京都芸術短期大学、1991年に京都造形芸術大学、1992年に東北芸術工科大学(山形市)、1993年に財団法人日本文化藝術財団(東京)を創設。また、1998年に芸術大学で初めてとなる通信教育課程を設置し、2005年には「こどもこそ未来」を掲げて幼児保育機関「こども芸術大学」を、2010年には東京・明治神宮外苑に藝術の生涯学習機関「東京藝術学舎」を開設した。現在、これらの学び舎で藝術教育を受けた人々が、さまざまな分野で活躍している。2014年10月20日逝去。著書に『藝術立国』がある。
検索結果:0
思い出・エピソード
70代 / 女性
京都造形芸術大学(通信) / 卒業生
また、2010年の卒業式では、少し老けられた姿で、杖を持参で壇上の椅子に腰かけられていましたが、いざ挨拶となると杖もなしに壇上で立ってやはり熱弁を振るわれました。
ご冥福をお祈りするとともに創設者の意思のもと学園の発展をお祈りします。
故人へのメッセージ(弔辞)
30代 / 女性
京都造形芸術大学(通信) / 在学生
この言葉が忘れられません。
常に「闘い」「血の一滴まで」というお話の中に芸術家魂だけが成し遂げられる「何か」を予感したものです。
後世に残る化石、そしてその御意志は永遠に生き続けていきます。
ありがとうございました。
思い出・エピソード
60代 / 男性
京都芸術短期大学 / 教職員(元・現)
ぼくは単なるお伴だったし、実はその時何もよいことが言えたわけでもなかったのに、それから3日ほどして、突然、徳山先生がまだ海のものとも山のものともわからないぼくの伏見の公団アパートの一室に、夜、クラウンを自分で運転して、酒をもってきてくださった。今日はじっくり君と話そうやないかと言われ、壱岐の島の生い立ちから、学生運動で追われて瓜生山に立てこもったこと、そしてそこに学園を開こうと決意したいきさつなど、感動することばかりだった。そして、そのまま、「俺は今日はここに泊まるぞ」と言われて、せまいアパートに布団も引かないで寝込んでしまわれた。これはショックだった。
翌朝になって、君は弟のやっているシンクタンクで働いてこいと言われて故・田中貞夫さんにその場で電話してもらった。それからほどなくして田中さんが芸短大の常務理事として着任することになり、ぼくはまずもとの専門学校の専任教員として、新たに京都国際文化専門学校の設立をし、次に芸短大に雇用されて芸術文化研究所、さらに映像学科(当初、日本初のコンピュータグラフィックスの専門教育機関をめざした)の設立に関わらせてもらった。
この間に息子が生まれたら、すぐにまた来てくださって、自分の子供のように喜んで、君はまず借金しても家を買えと言いながら、息子を抱きかかえて、あの笑顔でにこっと微笑まれたのが忘れられない。
こういう過程で、徳山先生は、大学のありかた、経営の仕方だけでなく、人間の生き方を自然に教えてくださった。あの頃ねつっぽく語っておられた、芸術・学術の大学の夢を、一代で本当に実現されるとは、実はぼくはその時には思っていなかった。亡くなられる前に、もう一度、お話しがしたかった。生き方を教えてくださった恩人として心から感謝するとともに、ご冥福をお祈りしています。
関西学院大学総合図書館長・社会学部教授 奥野卓司